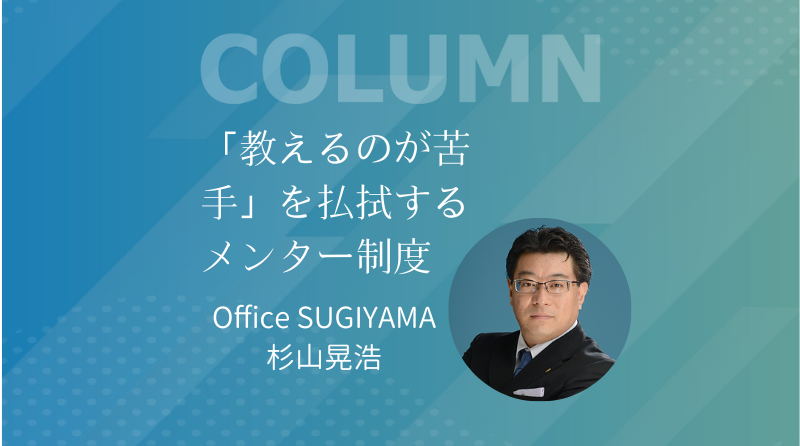前回までは訪問看護ステーションの管理者さんの悩みにフォーカスして、ステーション運営に役立つ理論をご紹介してきました。今回からは、特に訪問看護ステーションを新事業として立ち上げられる事業者の方々のお悩みに着目していきます。
他事業と訪問看護ステーションのシナジーを生んでいくためのヒントとなり、かつ訪問看護ステーションの課題解決にもつながる理論のご紹介等をしていこうと考えています。
新規事業としての訪問看護ステーション運営
訪問看護ステーションを新規事業として立ち上げようとしていらっしゃる事業者の多くは、既に介護事業や他の事業をされており、訪問看護ステーションを立ち上げることでそれらの既存事業とのシナジーを期待されてのことと考えられます。
しかし、実際には、期待した既存事業とのシナジーが発揮できず、そもそも訪問看護ステーション単体の運営にも苦戦していると悩まれているというお話をよく伺います。
シナジーとは何か?
そもそもシナジーとはどう言った意味なのでしょうか?オックスフォード現代英英辞典第10版によると、the extra energy, power, success, etc. that is achieved by two or more people, companies or elements working together, instead of on their ownとあります。日本語に訳すと、複数の何かが一緒に働くことで、一つ一つで得られる結果以上の結果、つまり相乗効果が得られるといった意味のようです。
介護事業と訪問看護事業で得られるシナジーとは
介護事業と訪問看護事業の間に期待するシナジーといえば、例えば訪問介護事業所や居宅介護事業所、通所介護事業を持っている事業者さんが利用者獲得の窓口を広げるほか、自社事業のラインナップを増やすことで利用者を囲い込み、売上を増やすといったことが考えられます。第7次医療計画等においても医療機関の機能分化等を進めることにより2025年までに14万床を削減し、新たに30万人分の患者を介護施設や在宅医療等において受け入れることが見込まれています。つまり、今後もますます在宅サービスでは医療が必要な利用者が増えるということです。
訪問看護事業を自社内に持ち医療との連携を強めることで、介護事業を含め利用者獲得面での強みになると期待できます。また、職員同士が交流することで介護職と看護職の相互理解が深まり、連携がスムーズになるかもしれません。さらに、包括的で質の高いケアの提供が実現できれば、利用者の満足や外部連携先からの信頼向上にもつながります。
しかし、既存介護事業と訪問看護ステーションとのシナジーが発揮できていない事業者さんでは、介護事業と相互に流入を増やすことができず、新規に立ち上げた訪問看護ステーションの赤字が続き、逆にマイナスになっているといったお悩みを伺います。
何故シナジーが発揮できないのか?
それでは何故、今まで他事業では成功してきたにもかかわらず訪問看護ステーションの運営が上手くいかないのでしょうか。
ここでは、介護事業を手掛けていた事業者さんが、新たに訪問看護事業を始めるという場合について考えてみます。
まずは、介護事業と看護事業の位置づけを簡単な図に表してみました。

両者の間には、何よりも介護サービスであることと医療サービスであることの違いがあります。それぞれで働く人々の違いも大きいように感じます。また、利用者さんを自施設に受け入れて介護を提供するようなサービスであったり、利用者宅へスタッフが訪問してサービスを提供するデリバリー型であったりとそれぞれの領域で様々なサービス形態があります。
これらの違いを踏まえ、現場オペレーションだけでなく、現場に従事する人々に対する支援についても違いを意識する必要があります。
例えば介護職員として働く人と、看護師として働く人とでは受けてきた教育課程も専門性も異なるため、キャリアに関する考えも異なってきます。一般的には、看護師の方がより専門性の高い教育を受け、専門職としてのキャリアアップに対する意欲も高いと考えられます。そのため、働くうえで会社に求めるものも異なってくる可能性があります。
また、受け入れ型のサービスとデリバリー型のサービスでは費用構造が異なるだけではなく現場のオペレーションや必要なマネジメントも自ずと異なってきます。情報共有一つをとっても、受け入れ型であれば職員同士が膝を突き合わせて話し合うという機会も取りやすいでしょう。しかし、デリバリー型であれば直行直帰の職員もいるかもしれませんし、ICT等を活用した情報共有がメインになるかもしれません。情報共有の方法に違いがあれば、自ずと管理職のマネジメントスタイルにも違いが出てきます。
このように、一口に介護業界の事業と言っても上記の切り口では4象限の領域があり、それぞれに異なるマネジメントや組織作りが必要になってきます。
あくまで私の経験の範囲のお話ですが、既存事業と訪問看護事業の間のシナジー創出がうまくいっていない会社さんでは、「介護も看護も同じようなもの」「場所は関係ない」と全てを一括りに考え、既存事業で成功したやり方で訪問看護も同じようにマネジメントしようとしている事が往々にしてありました。
異なる性質の事業間でどうやってシナジーを創出していくか
以上のように、他事業と訪問看護ステーションのシナジーを生み、かつ訪問看護ステーション運営単体でも軌道に乗せていくためには、異なる性質のものをまとめてマネジメントを行なって結果を出す必要があります。
こうした場面のヒントとなる理論として、次回はサービスプロフィットチェーン(以下、SPC)という考え方をご紹介します。
SPCは従業員満足度と顧客満足度が利益と連鎖関係にあるという考え方で、訪問看護ステーション運営における人材と売上という二つの課題を同時に解決し、かつ介護事業と看護事業のような異なる事業を複数まとめる際にもとても有用な考え方です。