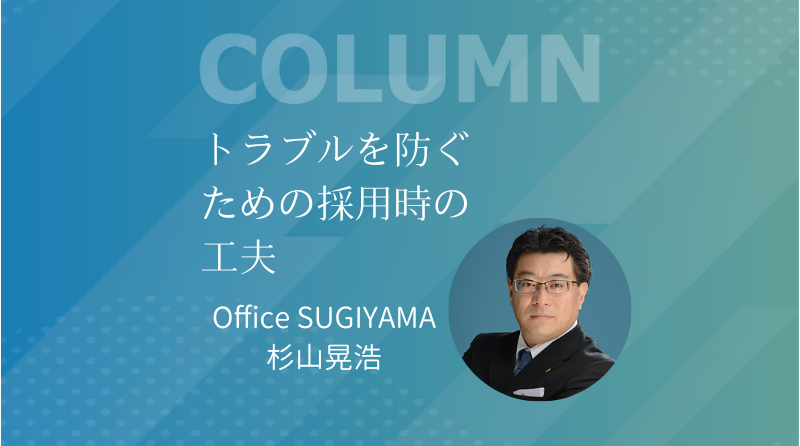1.慢性的な人手不足がもたらす『いいなり採用』とは
厚生労働省が毎月発表している一般職業紹介状況から産業別新規求人数をグラフ化してみると、医療・福祉業界の人材不足は他産業と比べて慢性的に深刻な状態にあることが見てとれます。
医療・福祉業界の求人数は全産業の25%を占めています。つまり、4件に1件が医療・福祉業界の求人ということになります。さらに、医療・福祉業界の求人の内訳は、社会保険・社会福祉・介護事業が約7割で、医療が3割です。
すなわち、介護事業における人手不足が非常に深刻であることが分かります。

(出典:一般職業紹介状況)
また、介護労働安定センター令和3年度「介護労働実態調査」結果の概要からは、介護事業所全体の人材の不足感は事業所全体で6割、訪問介護員では8割と高止まりしていることが分かります。
このような状態が続くと、多くの経営者や採用担当者は、『応募がないから来た人を雇わざるを得ない』と考え、どのような人が応募してきたとしても採用してしまう状況を肯定するようになります。

(出典:令和3年度「介護労働実態調査」結果の概要について )
一方、売り手市場にあることを理解している応募者は、自身に有利になるようにさまざまな条件を介護事業所に伝えてくることがあります。
このようなときに、応募者の言いなりになってその応募者のみに有利な労働条件を決めてしまうのは将来のトラブルの原因となります。筆者は、これを『いいなり採用』と呼んでいます。
ひとつでも自分に有利な条件を引き出すことができると、応募者が入社した後も、次々に自分の要求をぶつけてくるようになります。賃金や諸手当、勤務シフトや休日・休暇などの特別待遇の要求が多いようです。特に、勤務シフトや休日・休暇などをその職員の好き勝手にされてしまうと、職場のチームワークにも乱れが出てきてしまいます。
いいなり採用はこのように、介護事業所内にトラブルメーカーを生み出してしまいます。『会社が●●までしてくれると言っていた。なぜしてくれないんですか』『いま私が辞めたら、介護報酬が減額されるでしょう。だったら×してくれたっていいじゃないんですか?』などと詰め寄ってくる強者もいるようです。
いわばモンスター化した職員は、合同労組に入って条件闘争してくることもありました。他の職員を巻き込んで労働組合を結成して条件闘争してきたこともありました。
いずれにしろ、トラブルメーカーが動き回ることで職場の秩序は乱れ、会社は多くの時間とお金を浪費してしまうことになります。
初めから、『いいなり採用』をしないことで、介護事業所内にトラブルメーカーの発生を防ぎましょう。
求人をしても応募がないということは当たり前の現実です。人材不足感が高いために求人数は増え続けていくのに対し、失業者や転職希望者はそうそう増えないため、応募が集まらないのです。
なお、令和3年度「介護労働実態調査」の事業所調査の結果報告書からは、ハローワークからの紹介とリファラル採用がメインの採用ルートとなっています。採用ルートを工夫することは応募者の増加につながるため、いろいろとPDCAをまわすことが大切です。
【無期雇用職員の採用において利用した手段・媒体(複数回答)】

(出典:令和3年度介護労働実態調査 事業所における介護労働実態調査結果報告書)
2.採用面談時の条件交渉と事前対策が大切に
『いいなり採用』を回避するためには、あらかじめ介護事業所として飲める条件と飲めない条件を明確にしておくことが重要です。そのうえで、応募者からの個別の要望について判断し、飲めない条件であれば、丁寧に理由を添えてお断りすることが最も大切です。
例えば、賃金・手当などの収入に関することと休日・休暇などの労働時間に関することの条件を明確にしておくと良いでしょう。介護事業所によっては、個別の事情があるかもしれません。過去に労働条件等で労使トラブルがあった介護事業所については、その時の争点を洗い出しておきます。
このように、雇用条件のうち自社として譲ることのできないボーダーラインを文字として書き出しておくことで、条件交渉の際にブレずに対応できるようになります。併せて、応募者からの質問に面接官がすぐに回答できるようにQ&A方式のマニュアルを整備しておくことも重要です。当然、面接官トレーニングは必須です。事前にトレーニングしておかないと、予期しない質問を受けた際などに本来すべきではない回答をしてしまうリスクが高まります。しかし、私の知る限り、面接官トレーニングを実施している介護事業所はほんの一握りしかありません。
3.採用と不採用のボーダーラインを明確化する
条件面談時に採用と不採用を決定するためのボーダーラインを明確化しておくことは、人事担当者の大切な仕事です。
なお、チェック項目の整備とともに、就業規則や人事制度と相違していないか最終的なチェックが必要です。相違があるときは、就業規則の変更や人事制度の改定を適切に行ってください。
それでは、主なチェックポイントをお伝えします。
賃金・手当に関するボーダーラインのチェックポイント
主なチェックポイントは以下のとおりです。
①基本給の決定根拠
②処遇改善加算の取り扱い
③各種手当の支給基準
④賞与の支給基準
⑤退職金制度の支給基準
①基本給の決定根拠
応募者の技術スキルを明確化するためには、スキルマップの活用が有効です。
応募者の配属に伴う役割、期待を明確化し、伝えるべきことを伝え、復唱させるなどして、理解度も把握しておくことが必要です。
②処遇改善加算の取り扱い
自社の処遇改善加算振り分けのルールと応募者が通常に勤務した際に期待される金額の目安などを明確化しておきます。
③各種手当の支給基準
役割に関する手当については、そのポジションに期待している働きを明確に伝えられるようにしておきます。
家族手当や住宅手当については、支給対象者および支給基準を明確化しておきます。
通勤手当については、金額の算出方法や想定される例外的取り扱いなどを明確化しておきます。
そのほかの手当についても、対象者と対象基準を明確化しておくことが重要です。なぜなら、手当は介護事業所が自由に決定できる仕組みである分、抜け漏れが発生し易く、労使での見解の相違が出やすいためです。同一労働同一賃金も念頭において整理する必要があります。
④賞与の支給基準
賞与制度の有無を明確化しておきます。原則として賞与を支給するのか、原則として賞与は支給しないが介護事業所の環境を総合的に鑑みて支給するのかといった違いを明確にしておく必要があります。
非正規雇用者には、労働条件通知書への記載事項となっています。
⑤退職金の支給基準
退職金制度の有無を明確化しておきます。いつから支給対象となるのか、どれぐらいもらえる可能性があるのかは、あらかじめモデル退職金支給額のグラフを作成しておくと応募者からの理解も得られやすいでしょう。
最近では、選択制401Kを退職金制度として活用している介護事業所も増えています。応募者が理解しやすい説明資料を準備しておくと良いでしょう。
(参考記事:退職金制度の存在が介護事業の経営に与える大きな影響)
休日・休暇に関するボーダーラインのチェックポイント
主なチェックポイントは次の通りです。
①休日の決定方法
②休暇の種類
①休日の決定方法
全社的に休日が同一でしたら特にトラブルは発生しないと考えられます。
休日でトラブルが発生し易いのが、休日シフト制を採用しているときです。勤務シフトは、誰がどのように決めているのか、シフトの変更はどのようなルールに基づいて行われているのかなどを明確にしておきましょう。
現場任せにしている場合にありがちなのは、休日シフトの決定権者の機嫌を損ねてしまい、嫌がらせされるなどのハラスメント発生のきっかけになることです。過去にそのような例があれば、なおさら公平なルールを決めておきましょう。
②休暇の種類
介護事業所では、休暇を増やす工夫をしている事例が増えてきています。
休暇というのは、労働日に何らかの要因で労働免除にする仕組みのことです。最近では妊活のための休暇制度を設ける介護事業所が増えてきました。
また、年次有給休暇を申請する際のルールを明確にしておきます。年次有給休暇の利用に関しては自由なのですが、事業の正常な運営を妨げるような事は防がなければなりません。公平で組織運営上のモラルを保てるようなルールにしておきましょう。
4.正しい内定通知の方法
選考が終了し、条件面談が終わったら、初めて内定となります。
内定通知にあたっては、内定通知書を交付するとともに、労働条件通知書による労働条件の文書明示も行ってください。
なお、内定通知書には内定取消事由の記載を忘れないようにしてください。内定者が、内定取消事由を確認した証拠も残すようにしておきましょう。
労働条件通知書の交付にあたっては、内容を読み上げながら1項目ずつ確認していきます。疑義があるようでしたら、丁寧に説明を繰り返してください。最後に説明を受け、内容に了承したことへの署名を求めましょう。
『いいなり採用』によるトラブルの発生は、多くの場合が正しい内定通知をしていないことに起因します。
とりあえず入社日だけ決めて、『●●については、あなたの悪いようにしないから…』などと雇用契約をスタートさせてしまうと、後日『あのとき、●●してくれると言っていましたよね』などと要求を受けることになります。
労働基準法第15条には、所定の労働条件を記載した書面を交付する義務が定められていますが、単に書面を渡すだけでは不十分です。しっかりと説明し、納得の上で入社してもらう努力をすることが、トラブルメーカーを生み出さない仕組みとなるのです。
入社後に自分勝手な都合を介護事業所に要求してきたとしても、事前にできることとできないことを伝えているのが明確であれば、自信を持って要求を断ることができます。
今後ますます採用環境は厳しくなります。あまりにも応募が少なければ、採用基準を下げてしまいたくなるでしょう。それでも、そのような行為が、後々組織内に混乱を引き込んでしまうことを意識しておきましょう。
◆「正しい内定通知ができる内定通知書ひな形」のプレゼント◆
最後までお読みいただきありがとうございます。
「正しい内定通知ができる内定通知書ひな形」を希望者全員に無料プレゼントします。
お気軽に下記からお申し込みください。