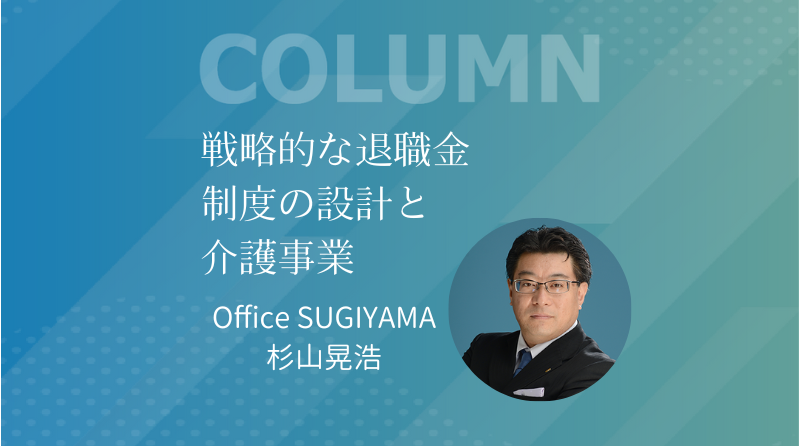1.退職金制度の導入の検討が増えている理由
最近、経営者や人事担当者から退職金制度に関するお問合せが増えています。背景として、次の3つの点が大きいように感じます。
【1】キャリアアップ助成金の受給を目指すための退職金制度導入ニーズ
【2】スタッフを確保(採用・定着)するための退職金制度導入ニーズ
【3】401K(確定拠出年金)などの広がりに伴う退職金制度見直しニーズ
キャリアアップ助成金の受給を目指すための退職金制度導入ニーズ
最初にキャリアアップ助成金の受給を目指すための退職金制度導入ニーズについて解説します。
これまで多くの事業所で利用されてきたキャリアアップ助成金の正社員化コース・障害者正社員化コースの受給要件が大きく変わりました。具体的には、2022(令和4)年10月1日以降に非正規スタッフが正社員転換したときに「賞与制度または退職金制度」のいずれかの制度の適用がなければ、助成金対象とはならなくなりました。
また、同一労働同一賃金への対策として、昨年度はキャリアアップ助成金の諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成が廃止され、賞与・退職金制度導入コースへと変更されました。これまで助成金の対象とされていた、家族手当、住宅手当、健康診断制度の3つの制度よりも、賞与・退職金制度を政府が重視しているという考えの表れだと捉えています。
ところで、業績の良し悪しやキャッシュフローの多寡を参考にして賞与額を決定したいと考える介護事業の経営者は少なくありません。目先の資金繰りが心配な経営者は、原則支給の賞与制度の導入を嫌う傾向にあります。一方で、資金準備期間が長い退職金制度の導入には好意的な経営者も多いものです。その結果、賞与制度の導入より、退職金制度の導入を望む声が増えているように感じます。
参考までに、就業規則における賞与の規定例を列記しました。
このうち、原則支給の規定例のみ賞与制度があると判断されます。
●原則支給の規定例
「賞与は原則として支給する。ただし、業績によっては支給しないことがある」
●原則不支給の規定例 「賞与は支給しない。ただし、業績によっては支給することがある」
●原則として賞与を支給することが明瞭でない規定例 「賞与の支給は会社業績による」
なお、賞与を支給する場合、就業規則に支給対象時期、賞与の算定基準、査定期間、支払方法等を明確にしておくことが必要です。
【参考】 キャリアアップ助成金が変わります ~ 令和4年4月1日以降 変更点の概要~(厚生労働省リーフレット)
スタッフを確保するための退職金制度導入ニーズ
続いて、スタッフを確保するための退職金制度導入ニーズについて解説します。
介護事業所において、スタッフの確保はとても重要な課題です。スタッフを確保するには、「採用すること」と「退職させないこと」のいずれの対策も手を抜くことができません。
まず、採用について考えてみます。
公共交通機関の混雑や繁華街の賑わいを見ると、既にコロナは過去のものとなっているように感じます。厚労省の一般職業紹介状況の有効求人倍率は毎月右肩上がりに上がり続けています。コロナ前の有効求人倍率を抜くのも時間の問題だと考えています。
【参考】厚生労働省 一般職業紹介状況(令和4年4月分)について

【画像】上記リンク先より抜粋
有効求人倍率が高くなるほどに、介護事業所における求人応募者の獲得が難しくなってきます。求職者から応募してもらうためには、雇用条件を他社より良くする必要があります。
ニッセイビジネスインサイトが厚労省「平成30年就労条件総合調査」を基に作成した退職金制度の有無に関する資料からは、100人以下の企業では2割以上の企業が退職金制度を導入していないことが分かります。例えばハローワークの求人票では、「退職金制度の有無」を明示する欄があります。すなわち、退職金制度のない会社は10社中2社しかありません。だから、求職者の目には「この介護事業所は退職金制度すらない介護事業所である」と簡単に認知されてしまいます。
【参考】ニッセイビジネスインサイト

【画像】上記リンク先より抜粋
「退職金制度がある介護事業所」と「退職金制度がない介護事業所」のどちらの介護事業所に応募が集まると考えますか。もちろん、「退職金制度がある介護事業所」のほうが就職先として魅力的に感じますね。反対に「退職金制度がない介護事業所」は求職者の応募を集めることに苦労することになります。退職金制度のニーズが高まるのは、当然のことですね。
介護スタッフにとって、「退職金制度がある介護事業所」であれば将来設計(老後設計)がし易くなるので、定着の効果は高まるでしょう。
さらに退職金制度は、退職の意思表示をしたスタッフに対して、退職を思いとどまらせるためのツールとなることもあります。
勤務していた期間に応じ、10年間、20年間と節目で大きく退職金額が跳ね上がる制度設計をされた退職金制度を例にとって説明します。
このような制度の下で、勤続9年目のスタッフが退職しそうになったときに、『退職を1年遅らせることで退職金がかなり増えますよ。だから今辞めるのは得策じゃありませんよ。』と伝え、退職防止に利用することができます。
401K(確定拠出年金)などの広がりに伴う退職金制度見直しニーズ
最後に、401Kなどの広がりに伴う退職金制度見直しニーズについて説明します。
厚労省発表の企業型確定拠出年金の加入者数、実施事業所数は共に年を追って増加傾向です。特に実施事業所数は2017年から急激に増加しています。
確定給付型退職金制度が内在するリスクを回避するために、確定拠出型退職金制度である日本版401Kを導入する企業が増えているためです。
また、岸田文雄政権では、国民が貯蓄から投資へ意識を変えるような政策を考えています。今後401Kの導入が増えると考える根拠にもなると考えられます。

【参考】厚生労働省 確定拠出年金の施行状況 https://www.mhlw.go.jp/content/000520816.pdf
2.退職金制度に内在するトラブルの火種
退職金制度にまつわる2つのトラブルケースをご紹介します。
最初にご紹介するのは、最も大きなリスクとなる、退職者が発生したときに退職金の準備ができないケースです。
基本給〇倍のように計算する確定給付型の退職金制度があります。このような制度では、あらかじめ退職金準備資金を積み立てていることが多いのですが、稀に退職金の積み立てをしていない会社もあります。また、予定よりも早期に多くの退職者が発生してしまい、積立金額を超える退職金の準備をしなければならなくなることがあります。
これらの状況は、資金繰りを悪化させます。最悪のケースでは、資金ショートから倒産も考えなければなりません。
だれがいつ退職するかは予測不可能です。急な退職金の発生に対応できる体力がない介護事業所が、これから退職金制度の導入を検討するのなら、急な資金準備の必要がない確定拠出型の退職金制度をお勧めします。ただし、退職金規程を見直す場合には、現に雇用しているスタッフの既得権を侵害しないようにする必要がありますのでご注意ください。
次に、退職金制度が規程化されていないケースのトラブルをご紹介します。
退職金制度は退職金規程として明文化されていなくても、退職者に退職金を支払っている事実があれば、慣習法としてスタッフに退職金請求権が発生することがあります。
スタッフとしては、退職金規程がなくても、退職金がもらえるのならば文句はいいません。トラブルになるのは、問題社員の退職に伴い、退職金を不支給にするケースです。自分だけ退職金がもらえないのは不当だとして、労働基準監督署や裁判所に訴えるケースは意外と多いものです。
このようなトラブルを回避するためには、退職金規程を明文化することです。規程を作成する際のポイントは、不支給事由を明確化することです。不支給事由の内容に合わせて、事由発生後の手続きプロセスなども規定中に明示すべきです。
ちなみに、私は、退職金の支給をめぐる裁判に関わったことがあります。
当初は退職したスタッフが労働基準監督署に訴え、労働基準監督官から、これまでのスタッフと同様の計算方法により、退職金を100%の金額で支給するように伝えられました。会社が不服に感じ、退職金を支払わなかったところ、訴訟となりました。私は、社会保険労務士なので弁護士のように法廷に立つことはできません。私ができる最大限の支援をしたところ、裁判官の判断は退職金額の50%を支払うことに落ち着きました。労働基準監督署では100%支払うべき、裁判所では50%支払うべきと判断が分かれました。もっとも、当該退職スタッフの非行が、社会通念上許される程度を明らかに超えていました。会社が、不支給事由が明確化された退職金規程を作成し、周知していれば、無駄なお金と時間を失うことはなかったと考えます。
3.介護事業所がすぐに取り組める退職金制度
退職金制度は、退職金の額の算定基準によって、さまざまな制度設計ができます。
オリジナルの退職金制度を設計するには、勤続年数、在職中の会社への貢献度など、何を価値とするかを決めるところからスタートします。退職金規程の文言、退職金額のシミュレーションなど、しなければならないことは多岐にわたるため、退職金制度導入まで相当の時間を要します。
すぐに退職金制度を導入したいのならば、次にご紹介する共済制度のうちどちらかの利用をお勧めします。
最初に、中小企業退職金共済をご紹介します。この制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営しています。月額掛金は、1人あたり5,000円から3万円まで積み立てることができます。パートタイマーなら2,000円から積み立てることができます。加入手続きは銀行などでお手軽にできます。
お得なポイントは、新しく中退共制度に加入する事業主や、掛金月額を増額する事業主に、掛金の一部を国が助成してくれる点です。
次に、特定退職金共済をご紹介します。こちらは、全国の商工会議所や商工会で申込みが可能です。月額掛金が1人1,000円から3万円までです。1,000円から積み立てられるので、資金繰りに大きな影響を与えることなく退職金制度を導入できるのが大きなメリットです。
どちらの共済制度も、掛金は全額損金となります。
いずれの共済制度も、退職者に直接支払われるため、退職時に会社の現金が流出することはありません。資金繰りに影響がないから、安心して経営ができます。
まだ、退職金制度の導入がない介護事業所であれば、この機会に検討されることをお勧めします。
◆「退職金診断」のプレゼントとアンケート◆
最後までお読みいただきありがとうございます。
また、簡単なアンケートにお答えいただくだけで退職金制度の現状課題が見える化できる「退職金診断」をOffice SUGIYAMA グループから無料プレゼントします。
お気軽に下記からお申し込みください。