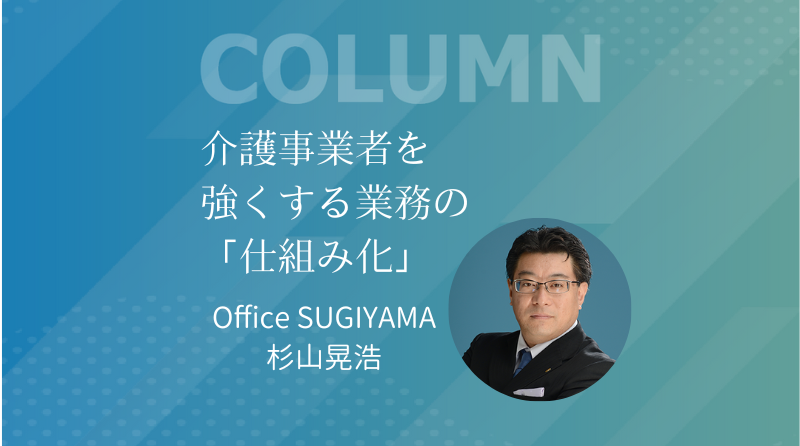2024年6月7日、東京商工リサーチがセンセーショナルな記事を公表しました。『2024年1‐5月の「介護事業者」の倒産 72件に急増 上半期の過去最高を上回る、深刻な人手不足と物価高』
概要は以下の通りです。
- 2024年1月から5月にかけて、介護事業者の倒産件数が急増し72件に達した。
- 増加率は前年同期比で75.6%で過去最高を記録。主な要因は人手不足と物価高騰。
- サービス別では訪問介護事業者が34件、通所・短期入所事業者が22件、有料老人ホームが9件と上半期では過去最多の倒産数を5月時点で更新。

(【画像】「2024年1‐5月の「介護事業者」の倒産 72件に急増 上半期の過去最高を上回る、深刻な人手不足と物価高」東京商工リサーチ2024/06/07より)
同社の記事では、介護事業者の経営環境が悪化している要因が複数指摘されています。
今回は、介護事業者が現在直面している課題を整理し、その課題を乗り越えて経営を安定させるための”仕組み化”のポイントと手順についてご提案します。
1.介護事業所が直面する8つの課題
介護事業所が直面する課題の背景には、複雑で多岐にわたる要因が絡み合っています。それらを8つにまとめました。

まず、「人手不足」についての異論はないでしょう。
日本の高齢化が進む中で、介護職員の需要は急増していますが、供給はそれに追いついていません。介護職員の確保が難しく、既存の職員に対する負担が増加し、離職率が高まる悪循環が生じています。
また、昨今では「物価高騰」が介護事業所の経営を圧迫しています。
光熱費や消耗品の価格が上昇する中で、多くの事業所はコスト削減に苦慮しています。特に小規模な事業所では、こうしたコスト増加が直ちに経営に深刻な影響を及ぼします。事業所が自主的にサービス価格を調整できないことも、経営を圧迫する要因となっています。
他業界と比較したときの「賃金格差」の問題も重要です。
介護職は社会的に重要な役割を担っていますが、その労働条件や賃金は他の職種に比べて低いことが多いです。この賃金格差が介護職員のモチベーションを低下させ、長期的なキャリア形成を困難にしています。賃金が低いままでは、優秀な人材が他の職種に流出してしまい、結果として人手不足がさらに深刻化します。
「過重な業務負担」も介護職員にとって大きな課題です。
介護現場は常に人手不足に悩まされており、一人当たりの労働負担が過剰になりがちです。これにより、職員の疲労が蓄積し、離職率が高まります。過重労働はサービスの質を低下させる原因ともなり、利用者の満足度や安全性にも影響を及ぼします。
「報酬改定」の影響も見逃せません。
介護報酬が引き下げられると、事業所の収入が減少し、経営が厳しくなります。特に小規模事業所では、報酬改定の影響が大きく、経営の安定が揺らぎやすくなります。
「小規模事業者の脆弱性」は、経営基盤の弱さから来ています。介護事業者の多くを占める小規模事業所は、十分な資本を持たずに運営されており、経済的なショックに対する耐性が低いです。こうした事業所は、少しの収益減やコスト増で倒産リスクが高まるため、持続的な経営が難しいのが現状です。
「サービスの質低下」も深刻な課題です。
人手不足や過重労働が続くと、職員の疲労が増し、結果として提供されるサービスの質が低下します。こうなると利用者からの信頼が損われ、ひいては事業所の評判にも影響を与えます。サービスの質が低下すると、新たな利用者の獲得が難しくなり、経営の安定がさらに難しくなるでしょう。
最後に「競争激化」についてです。
介護事業は競争が激しく、多くの事業者が限られた市場でシェアを争っています。特に、同一地域内での競争が激化すると、利用者の獲得が難しくなり、価格競争も激化します。これにより、収益性が低下し、経営が厳しくなる事業所が増加します。
現在、介護事業所はこれらの課題が複合的に絡み合うことで厳しい経営環境に置かれています。持続可能な経営を実現するためには、これらの課題に対して総合的に対策することが求められます。
2.介護事業所における仕組化のポイント
こうした課題の対策として、取り組んでいただきたいのが業務の仕組み化です。
ここでいう仕組化とは、再現性のある仕事のやり方を確立し、それを標準化することを指します。具体的には、自社独自の仕事の方法をマニュアル化し、誰が実行しても一定の品質と効率性を保つことができる体制を作ることです。仕組み化を進めることで、社員はより付加価値の高い業務に集中できます。結果として、社員のやりがいや成長機会が増え、組織全体の生産性が向上することが期待できるでしょう。
例えば、介護事業所においては、リクルートメントプロセスの標準化やシフト管理システムの導入、請求ソフトの利用などが仕組化しやすい部分でしょう。
仕組化の恩恵は、業務の省力化に留まらず、組織全体のパフォーマンス向上にも寄与します。
仕組化された業務プロセスは、新人教育の負担を軽減し、迅速な戦力化を可能にします。また、標準化された手順により、業務のミスやトラブルが減少し、安定した運営が実現するでしょう。
さらに、仕組み化は競争力の強化にも寄与します。市場環境の変化に柔軟に対応できる組織は、競争優位性を維持しやすくなります。業務プロセスの見直しや改善を継続的に行うことで、常に最適な状態を保つことができます。
総じて、仕組み化は組織の持続的な成長と発展に不可欠な要素です。効率的で再現性のある業務プロセスを確立することで、組織全体の生産性と競争力を高め、社員の満足度や成長を促進することができるのです。
3.8つの課題に対する仕組化の提案
仕組み化を実現するためには、先述した8つの課題に対して具体的な対応策を講じることが重要です。それぞれの課題に対応するアイデアを以下に提案します。
1.人手不足への対応
仕組化アイデア: リクルートメントプロセスの標準化と効率化。職員募集から採用、研修、定着までのプロセスを明確にし、効果的な採用戦略を策定する。特に、新人研修プログラムを充実させ、早期定着を図る。
2.物価高騰への対応
仕組化アイデア: コスト管理システムの導入。物品管理と在庫管理を効率化し、無駄な経費を削減する。定期的な経費見直しを行い、節約できるポイントを明確にする。
3.賃金格差への対応
仕組化アイデア: 賃金体系の透明化とインセンティブプランの導入。評価制度を見直し、成果に応じた報酬を提供することで、職員のモチベーションを向上させる。特に、チームでの成果を評価する仕組みを作る。
4.業務の過重への対応
仕組化アイデア: 業務プロセスの自動化とタスク分担の明確化。ルーチン業務を自動化することで、職員の負担を軽減し、重要な業務に集中できる環境を整える。シフト管理システムを活用し、労働時間の適正化を図る。
5.報酬改定への対応
仕組化アイデア: 収益管理の強化と多様な収入源の確保。介護報酬に依存しすぎない経営モデルを構築するため、新たなサービスや商品の開発、地域社会との連携を強化する。
6.小規模事業者の脆弱性への対応
仕組化アイデア: 財務管理の強化とリスクマネジメントの徹底。定期的な財務状況のチェックと、リスクに対する対策を講じることで、経営の安定を図る。また、地域の他の事業者との連携を強化し、リソースを共有する。
7.サービスの質低下への対応
仕組化アイデア: サービス品質管理システムの導入。利用者からのフィードバックを定期的に収集し、サービス改善に役立てる。職員の継続的な教育と研修を実施し、サービスの質を維持・向上させる。
8.競争激化への対応
仕組化アイデア: 差別化戦略の確立とマーケティングの強化。他の事業所と差別化できる独自のサービスや特徴を打ち出し、地域での存在感を高める。オンラインマーケティングや地域イベントを通じて、利用者の認知度を向上させる。
いかがでしょうか。自社独自の再現性のある仕事のやり方を確立し、組織全体で共有することで、長期的な成長と発展を促進することができるようになります。
あとは、経営者が本気で取り組むだけです。
ただしそれぞれの介護事業所には、強み、弱みがあります。したがって、課題の大きさや優先順位も異なります。いかに自社独自の仕組みを作り上げ、浸透させるかがポイントとなります。
もしも「私にはムリだ!」と感じたら、ぜひオフィススギヤマグループにご相談ください。先ずは、御社の課題を見えるようにするところからお手伝いをさせていただきます。
4.人手不足に対する仕組み化をすすめる7つのステップ
さて、ここで介護事業者を最も悩ませているであろう人材不足への対応(リクルートメントプロセスの標準化と効率化)について詳述します。
仕組化を進めるには、先ず選考フローを見える化することから始めます。介護事業所ごとに選考プロセスは異なるため、それぞれが自社のフローを一つ一つを見える化する必要があります。以下の選考フローは、その一例だと考えてください。
1. 現状分析と目標設定
現状分析: 現在の採用プロセスを詳細に分析し、問題点や改善点を洗い出す。
目標設定: 具体的な目標(例:採用期間の短縮、採用コストの削減、優秀な人材の獲得)を設定する。
2. プロセスの標準化
採用フローの文書化: 採用プロセスの各ステップを明確にし、文書化する。これには、求人広告の作成、応募者の選考、面接、内定通知のプロセスが含まれる。
チェックリストの作成: 各ステップのチェックリストを作成し、必要なタスクが漏れなく実行されるようにする。
3. 自動化とシステム導入
応募者管理システム(ATS)の導入: 応募者情報を一元管理し、応募から採用までの進捗を可視化する。
自動化ツールの活用: 自動返信メールや面接スケジュールの自動調整など、手間のかかる作業を自動化する。
4. トレーニングと教育
担当者の教育: 採用担当者に対して、標準化されたプロセスとシステムの使い方を教育する。
継続的なトレーニング: 定期的なトレーニングを実施し、新しい手法やツールの導入に対応する。
5. 継続的な改善
フィードバック収集: 採用プロセスに参加した応募者や面接官からフィードバックを収集し、プロセスの改善に役立てる。
KPIのモニタリング: 採用活動の成果を測定するためのKPIを設定し、定期的にモニタリングして改善点を見つける。
6. ドキュメントとガイドラインの整備
プロセスガイドラインの作成: 採用プロセスの各ステップに関する詳細なガイドラインを作成し、関係者全員に共有する。
マニュアルの更新: 新しいツールやプロセスの導入に合わせて、マニュアルを更新する。
7. コミュニケーションと協力
チーム内の連携強化: 採用チーム内での情報共有とコミュニケーションを強化し、連携をスムーズにする。
他部門との協力: 採用プロセスの改善には他部門の協力も必要な場合があるため、部門横断的な協力体制を整える。
ぜひこのように自社のステップを見える化し、リクルートメントプロセスの再現性を高めてください。なお、再現性を高めるには、プロセスフローチャートを作成し、関係者間で情報共有することが必要です。
また、これを実効性あるものにするためには、プロセスを守らないスタッフに対して人事考課で減点するなど何らかの防止策をしておく必要があります。
5.採用プロセスを効率化するプロセスフローチャートの作成方法
最後に、採用フローのプロセスフローチャートを作成するための手順をお伝えします。
◆フローチャート作成の手順◆
1.フローチャートツールの選定
Lucidchart、Microsoft Visioなどのフローチャート作成ツールを選定します。
2.主要ステップのリストアップ
採用プロセスの主要なステップをリストアップします。
以下はリストの例です。
☑求人ニーズの確認
☑求人広告の作成と公開
☑応募者の受付と管理
☑書類選考
☑一次面接
☑二次面接(決定権者面接)
☑内定通知と条件交渉
☑入社手続き
☑各ステップの詳細化
主要プロセスがリストアップできたら、各ステップごとの具体的なタスクやアクションを詳細化します。
例えば、書類選考では「履歴書の受領」「選考基準に基づく評価」「選考結果の通知」などが考えられます。
3.フローチャートの作成
フローチャートツールを使い、各ステップをボックスとして描画し、それらを矢印でつなげます。
開始: フローチャートの始点(求人ニーズの確認)を描く。
プロセス: 各ステップを順次描き、次のステップへの流れを示す矢印を追加。
判断: 判断が必要なポイント(例:書類選考の結果が合否)をダイヤモンド形で描き、Yes/Noの矢印で分岐。
終了: 最終ステップ(入社手続き完了)を描く。
完成したフローチャートを関係者と共有し、求職者の対応をするごとにレビューをおこないます。
フィードバックを基に修正しながら実効性を高めていきます。
オフィススギヤマグループでは、このような介護事業所の仕事の仕組み化をお手伝いをしています。
お気軽にお問合せください。
◆『採用プロセスフローチャート例』プレゼント◆
最後までお読みいただきありがとうございます。
今月は、記事中でも紹介した『採用プロセスフローチャート例』を希望者全員に無料プレゼントします。
ご希望の方はお気軽に下記からお申し込みください。