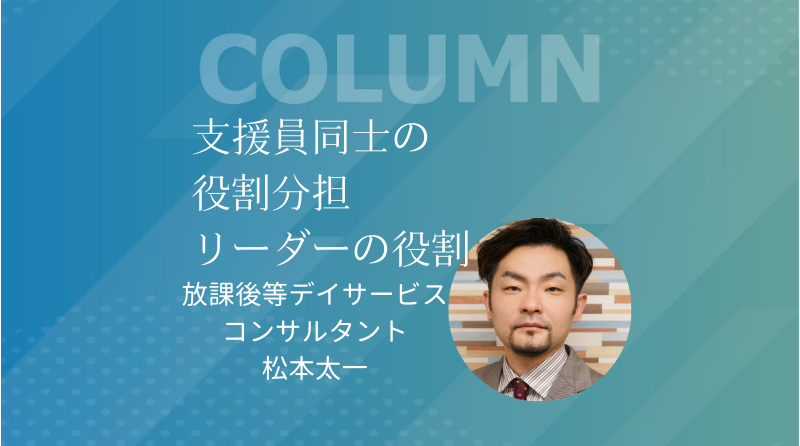放課後等デイサービスコンサルタントの松本太一です。
療育の現場にあまり関わったことのない方などを対象に、事業参入を検討される前に知っておきたいこと、事業所運営のポイントなどを紹介しております。
今回は、普段からアドバイスする機会が多い、支援員同士の役割分担について取り上げます。
放課後等デイサービス事業所の開所時から役割分担を明確にしておこう
開業前、もしくは直後の事業者様にアドバイスする機会が多いテーマとして「支援員の役割分担の明確化」があります。
開業当初の利用児が少ない状況では、支援員が子どもに一対一でつくことができるので役割分担をする必要性がそれほど意識されません。しかし、定員近くまで子どもが増えた段階で起こりがちなのが、役割分担が不明確であることによって、支援をスムーズに行えないばかりか、コミュニケーションが上手く行かずに支援員同士の不和につながってしまうということです。
子どもが増えてから仕組みを変えるのは大変ですので、開業当初の時間に余裕のあるうちから支援員同士の役割を明確にしておくことが大切です。
支援員の役割を「リーダー」と「サブ」に分ける
私は、支援員の役割について、1人「リーダー」を決めることとその他のメンバーを「サブ」に充てることをお薦めしています。今回はリーダーの役割に焦点を当てて解説していきます。
リーダーの主な役割は以下の通りです。
- タイムキープ
- 集団活動時の全体司会
- 状況にあわせたタイムスケジュールの変更
- 状況にあわせたサブメンバーへの役割指示
リーダーの役割【1.タイムキープ】
以前のコラムで、事業所のタイムスケジュールを設定する重要性を説明しました。このタイムスケジュール通りに支援プログラムを進めることが、リーダーの重要な役割の1つです。具体的には、スケジュールにある次の活動が始まる前に「あと5分で◯◯を始めます。準備を始めてください」というイメージで、事業所全体に声掛けをします。
タイムキープが必要である理由は、発達障害のある子どもは注意の切り替えが難しい傾向にあることと関係します。例えば自由時間にブロック遊びに熱中していた子に、突然「今から運動を始めます」と言っても、上手く切り替えることができず、無理に参加を促そうとすると怒ったりパニックになってしまうことが多いのです。そこで、リーダーが事前に全体にアナウンスすることで子どもも次の活動への見通しがつき、同時にその子についている支援員も「もうすぐ運動が始まるからそろそろ片付けよう」と言葉をかけることで、スムーズな注意の切り替えを促すことができます。
リーダーの役割【2.集団活動時の全体司会】
集団で活動を行う際、子どもたちの前に立って、課題の説明を行います。放デイに通うお子さんは周囲の状況を理解することが困難だったり、多動である子が多いため、以下のようなポイントに気をつけて司会する必要があります。
言葉の説明は最小限にとどめ、見せる、やってみせる
発達障害の中でもADHD(注意欠如多動症)のあるお子さんは、集中を維持するのが難しく、長い説明をじっと聞いていることが苦手です。またASD(自閉症スペクトラム症)の子の多くは言葉よりも目でみたものに影響されやすいという特徴があります。そのため、言葉の説明は必要最低限にとどめ、できるだけ物を見せたり、実際にやって見せることでしっかり理解できるようになります。例えば、「だるまさんがころんだ」であれば「鬼が振り向いたら止まって、動いてしまったら鬼のところへ行って・・」と言葉だけで説明するのではなく、実際に支援員が鬼と子ども役に分かれて実演してみせることが大切です。
個別対応はサブに任せる
リーダーが全体に向けて課題の説明をしているときに、離席をしたり、だしぬけに関係のない話を始めたりする子がいます。それをリーダーが動いて席に戻そうとしたり、話に答えていたりすると、全体の説明が滞り、他の子どもたちが置いてきぼりになります。そうなると、退屈になった他の子たちがさらに席を離れたり関係のない話をして集団が崩壊してしまいます。
こうした子への対応はサブメンバーに任せ、リーダーは常に全体への説明に徹することを意識しましょう。
リーダーの役割【3.状況にあわせたタイムスケジュールの変更】
タイムスケジュール通りに支援を進めることは大切ですが、子どもの来所時間のズレや急なトラブルによってスケジュール通りに進まないことは当たり前に起きます。このとき、状況にあわせてタイムスケジュールを変更する責任と権限を持つのがリーダーです。
リーダーが決まっていない現場では、各々の支援員が独断で動いてしまい、全体のスケジュールが崩れてしまうということが起こりがちです。そうならないために、リーダーは常に全体の流れを把握して、スケジュール変更が必要だと判断すれば、それを他の支援員に伝えます。他の支援員も、スケジュールの変更の必要があることに気づいたら独断で動くのではなく、リーダーにその旨を伝え、判断を仰ぎます。
リーダーの役割【4.状況にあわせたサブ支援員への役割指示】
「◯◯さん、□□くんの対応に入ってください」「△△さん、工作の準備をしてください」といったように、サブの支援員に役割を指示するのもリーダーの役割です。2でも述べたように、リーダーは全体の進行を行うため、個別の対応はサブに任せるのが基本です。積極的にサブの支援員に役割を振っていきましょう。それを実行するためにも、リーダーはあまり特定のお子さんと関わりすぎず、部屋の中で全体を見渡せる位置に立っていることが望ましいといえます。
リーダーはスタッフ全員が持ち回りで担当するのが望ましい
それでは、誰がリーダーを担当するのがよいでしょうか?支援員の状況にもよりますが、基本はパートタイマーさんも含めてスタッフ全員の持ち回りで行うことをお勧めします。
リーダーというとベテランしかできないように思われるかもしれませんが、タイムスケジュールと課題の構成がしっかりできていれば、計画通りに支援を進めればよいだけですから、経験の浅い人にもできます。むしろ、子どもごとに臨機応変な対応が求められるサブの方が、経験値が必要です。
普段から支援員全員がリーダーとサブを両方経験していることで、お互いがお互いにどう動いてもらえるとありがたいのか、意識できるようになります。スケジュールと課題の内容は経験あるスタッフがしっかり計画したうえで、リーダーは経験の浅い人にも積極的に勤めてもらうのがよいでしょう。
次回は、このリーダーの進行のもとで動くサブの役割について解説します。