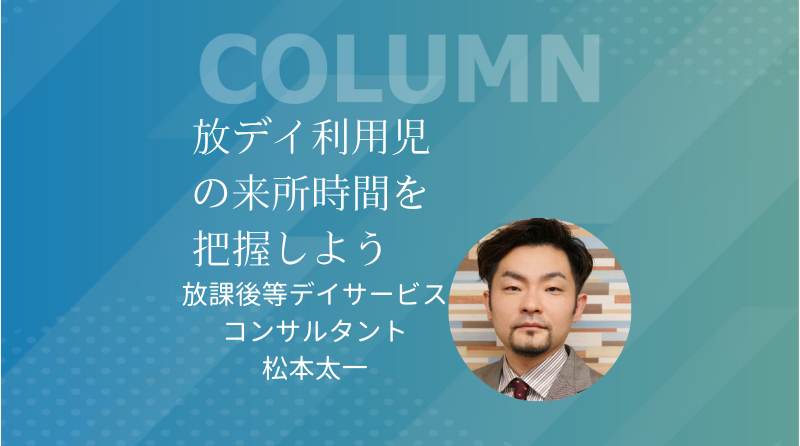放課後等デイサービスコンサルタントの松本太一です。介護経営ドットコムでは、この事業への参入に関心を持っていらっしゃる介護事業者様にぜひ知っていていただきたい、運営のポイントをご紹介しております。
すでに放デイ事業を運営されていらっしゃる方におかれても、是非、運営状況の見直しにお役立てください。
*過去に取り上げたテーマ:①「療育」「預かり」2種類のニーズの理解と両立、②幅広い年代のお子さんに対応できるプログラム
今回から2回に分けて、放デイ運営の重要なポイントである「タイムテーブルの作成」について解説します。前半は、その準備に当たる「来所時間の明確化」についてお伝えします。
最新の放デイサービスガイドラインでも求められている「タイムテーブルの作成」
タイムテーブルとは、子どもたちに事業所での一日をどのように過ごしてもらうか示した計画のことです。2024年7月に国が改定した 「放課後等デイサービスガイドライン」では、その必要性について下記の通りに記載されています。
事業所における時間をどのようにして過ごすかについて、一人一人の放課後等デイサービス計画を考慮し、一日の時間と活動プログラムを組み合わせたタイムテーブルを作成する。タイムテーブルは、こどもの生活リズムを大切にし、日常生活動作の習得や、こどもが見通しを持って自発的に活動できるよう促されることが期待される。(p39)
荒れる事業所の共通点「タイムテーブルが作成されていない」
このように、最新のガイドラインでも作成が求められているタイムテーブルですが、他児とのトラブルや物の破損が絶えない荒れた事業所に訪れると、それが作られていないことが多いのです。
タイムテーブルが作られていない事業所では、大抵の場合、子どもが来所した後それぞれのペースでおやつを食べ、宿題に取り組み、あとは帰りの時間まで自由に過ごすだけになってしまっていることが少なくありません。
すると、自由時間に暇になった子どもたちが走り回ったりプロレスごっこのような危険な遊びを初めてしまい、それがエスカレートして喧嘩になったり怪我をしたりしてしまいがちです。支援員が注意しても、代わりに子どもたちが取り組める活動が計画されていなければ、やはり子どもたちは手持ち無沙汰になってしまい危険な遊びを再開してしまいます。
こうした事例からもわかるように、タイムテーブルを作り、その日どのように過ごしてもらうかを明確にしておくことは、子どもたちが安全に、安心して過ごせる事業所を作るための最低限の条件なのです。
タイムテーブルが作られない原因は「来所時間がバラバラであること」
ところが、このタイムテーブルを作るのがなかなか難しいという現状があります。子どもが放デイ事業所に来所する時間がバラバラだからです。
放課後等デイサービスはその名の通り、学校が終わったあとの時間に活動します。学校の終業時間は、子どもの学年や曜日によって異なり、また学校から施設までの移動時間も関係します。そのため、どのお子さんがいつやってくるかは、毎日変わるのです。
また、支援員が車で送迎を行っている事業所の場合、子どもだけでなく支援員が事業所に戻って来る時間もばらついてしまいます。
そのため、何の対策もしなければ、支援員はその日利用するお子さんたちがそれぞれ何時に来所するのか、そのとき事業所には何人の支援員がいるのか把握できないまま支援に臨むことになります。そのような状況では、タイムテーブルの作りようがありません。結果として、先ほど述べたような無計画な過ごし方が生まれてしまうのです。
計画的なプログラム提供への第1歩は「子どもたちの来所時間を表に書き出す」こと
きちんと機能するタイムスケジュールを作るには、まずお子さんの来所時間を正確に把握する必要があります。具体的な必要な対応は、その日の来所時間を毎日表に書き出し、事業所に掲示することで、各支援員が子どもたちの来所時間(=運転する支援員が事業所に到着する時間)を把握できるようにすることです。
実際の運用例について、以下にイメージをお示しします(利用児名・職員名は個人情報のため伏せてあります)。

このデイでは、1日の間に6便も送迎車が出入りしています。(6台車があるわけでなく、同じ車が2回送迎に出ていることもあります)。
この表は、その日デイを利用する予定のお子さんの学校への迎えについて、右から
- 「発」 事業所から車が出立する時間
- 「下校時間」 子どもが下校する=車が学校に到着する時間
- 「着」 車が事業所に到着する時間
- が書いてあります。
右から3列目の「着」時間に着目すると、この日は15時10分から16時までの間に子どもたちが断続的に来所する予定であることがわかります。
また、全体を眺めると大まかに「15時20分までに到着するグループ」「16時に到着するグループ」があることも見えてきます。
そこまでわかれば、タイムテーブルは、
- 15時20分までにやってくる前半グループの16時までの過ごし方
- 16時以降全員が揃ってからの過ごし方
ここまでわかって、初めてその日のタイムテーブルを作ることができるようになります。
「毎日表を作る」―習慣化の大変さを乗り越え、先を見通した支援を
先ほど触れたように、放デイに子どもたちが来所する時間は毎日変わります。ですから、先の表も毎日書かなれればなりません。しかし、忙しい支援員さんには最初のうち中々受け入れていただけないこともあります。新しい習慣を定着させるための支援に入る際、私は実際に来所する時間を聞き取りながら一緒に表を作っていくことにしています。
一旦表ができ、これに基づいてタイムスケジュールが組めるようになると、支援員さんたちも見通しを持って活動を計画することができ、子どもたちの意欲的な活動への参加にもつながります。すると、支援員にかかるストレスも大幅に減って支援全体の負担は減るのです。
実際に、「最初、松本さんに来所時間を表に書くように言われたときは面倒だと思ったけれど、今は書いた方がラクだということがよくわかりました」とよく言われます。最初は少し億劫かもしれませんが、手間を掛けるだけの価値はありますので、ぜひ試してみてください。
次回はいよいよ、タイムテーブルそのものの作成についてお話させていただきます。