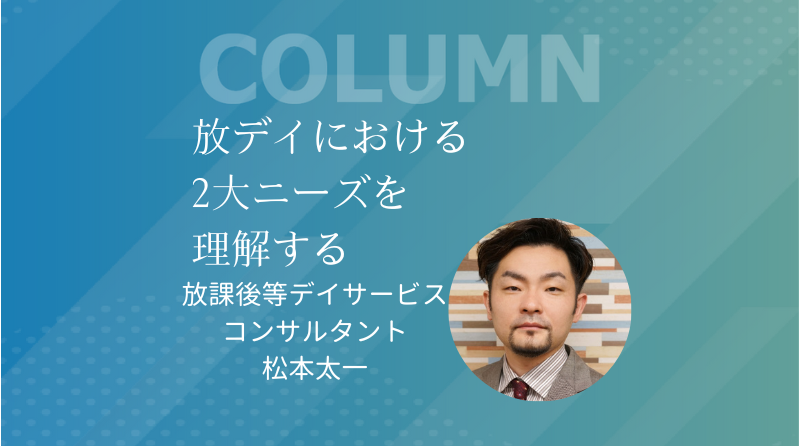初めまして、私は松本太一と申します。これまで、放課後等デイサービスなど療育に関わる現場に100カ所以上お伺いして、事業運営をご支援してきました。
介護経営ドットコムではこれから、この事業への参入に関心を持っていらっしゃる介護事業者様にぜひ知っていていただきたいポイントをご紹介してまいります。
放課後等デイサービス運営特有の難しさ
障害のある学齢期のお子さんが通う放課後等デイサービスは、学校・家庭に次ぐ第3の居場所として、お子さんの発達に大変重要な役割を果たしています。
しかし、これまで研修やコンサルティングを行ってきたなかで「放デイの運営は難しい・・・」と嘆かれる経営者さんには数多く出会ってきました。その中には他業種で1億円以上の売上になるまで会社を大きくしてきた方もいれば、介護保険事業で成功された方もおられます。
そんな方でも放デイの運営が難しいのはなぜでしょうか。それは、放デイの事業には未経験の方にとって想像しにくい特殊な性質があるからです。
この性質を踏まえた事業の目的や理念の設定、組織のルール作りを行わないと、たとえ熱い思いや経営手腕があったとしても経営者とスタッフが同じ方向を向いて事業に取り組むことは難しいでしょう。
そこで、今回は、放デイ特有の性質や運営上の難しさにスポットを当てつつ、どうすれば、経営者とスタッフが一丸になって安定的な運営ができるのかについて、わかりやすく解説していきます。
放デイには「療育ニーズ」「預かりニーズ」の2つがある
放課後等デイサービスを経営される方、そして働くスタッフの皆さんから共通して多く聞かれるのが「放課後等デイの目的はなんなのか?」という問いです。現に放デイで仕事をしている人にとってさえ、この事業の目的がはっきりとはわかりにくい部分があるのです。
その理由は、この事業が満たしていくべきニーズが、「療育ニーズ」「預かりニーズ」の2つに分かれていることにあります。このことを理解しておかないと、後で述べるように、自分たちの事業の目的が何なのかはっきりしないまま、バラバラの方向を向いて仕事をせざるを得なくなってしまいます。
以下、詳しく説明していきましょう。
まず、放デイの目的について、法律では下のように規定されています。
就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与すること
(児童福祉法第六条の二の二より)
この条文で規定されているのが、一般に「療育ニーズ」と言われているものです。
このニーズに対応するため、事業所ではお子さんの発達段階や障害特性にあわせた療育目標、課題を設定し、その達成を通じて発達を支援していくことになります。ここで想定されているサービスの受益者は障害のあるお子さんです。
しかし、実際に放デイを運営してみると、もう一つ別の大きなニーズがあることに気づきます。それが「預かりニーズ」です。具体的には「保護者が仕事から帰ってくるまで施設で預かってほしい」「休日や長期休み中に子どもを預かってほしい」「学校から自宅までの送迎を担ってほしい」といったニーズで、その受益者は保護者さんです。
| 療育ニーズ | 預かりニーズ | |
|---|---|---|
| 受益者 | 障害のあるお子さん | 保護者 |
| 目的 | お子さんの発達支援、生活能力の向上 | 保護者の就労支援、レスパイトケア |
| 支援内容 | 発達段階や障害特性に応じた訓練、社会との交流促進 | 長時間預かり、送迎サービス、休日や長期休暇中の受け入れ |
| 法的根拠 | 児童福祉法に明記 | 明確な規定なし(実際のニーズに基づく) |
放課後等デイサービス事業者が直面する保護者の「預かりニーズ」
経営者の多くは、法律でも規定された事業目的である「療育ニーズ」を念頭に置き、お子さんの発達のためにどういう関わりを提供すればよいかを考える一方、「預かりニーズ」についてはそれほど重く見ていません。
しかし、いざ運営が始まると
「朝8時から預かってもらえますか」
「遠方ですが送迎してもらえますか」
「日曜日も預かってもらえますか」
といった「預かりニーズ」の強さに直面することになります。
背景にある事情として、障害のあるお子さんを育てているご家庭は共働きが多いことがあります。療育にはお金がかかりますし、お子さんが将来自分でお金を稼げるとは限らないので貯金も必要です。その場合、自分が帰宅するまで、あるいは、休日家事を行うために預かってくれる施設はどうしても必要です。また子育てのストレスから、保護者さん自身が精神障害と診断され、デイへの送り迎えが難しい場合も多くあります。こうした理由から、保護者さんの預かりニーズは極めて切実なものがあります。
「預かりニーズ」に振り回されるリスク
強い「預かりニーズ」に直面した経営者は、売上を挙げる必要からそのニーズに応えようとします。しかし、長時間のお預かりを実施することで陥りがちなのが、スタッフが支援内容を振り返る時間が取れなくなったり、送迎に時間がかかりすぎたりしてお子さんが事業所に滞在できる時間が短くなってしまい、「療育ニーズ」に充分応えられなくなるという事態です。
その結果、経営者もスタッフも、「何を目的にしてこの仕事をしているのかがよくわからない」という状態におちいり、一枚岩になって日々の事業所運営に励むことが難しくなってしまいます。スタッフの離職という形となってその影響が現れ、ついには経営が困難な状態に陥ってしまうことも少なくありません。
「療育ニーズ」対応への特化は危険
それならいっそのこと預かりニーズを切り捨てて療育ニーズ対応に特化するのはどうでしょうか。実際そうした事業所もあります。
たとえば、送迎や長時間の預かりを廃し、一回の利用を1時間以内にとどめて1対1で専門性の高い個別指導を行うような事業所があり、これは俗に「療育特化型」と呼ばれたりします。
しかし、この形は経営者自身、または採用の決まっている幹部スタッフが極めて経験豊富な療育者でない限りはリスクが高いでしょう。
なぜなら、他の事業所が長時間預かりや送迎を通じて預かりニーズに応えている中、保護者さんに「長時間預かってももらえなくても、自分が送迎してでも、この事業所の療育を受けさせたい」と思ってもらえない限り、契約してもらえないからです。
「療育ニーズ」「預かりニーズ」の両立を目指す
未経験の状態から放デイの運営に乗り出す場合、療育ニーズと預かりニーズの両立を目指すことが、放デイの制度の趣旨を尊重しつつ、安定的な施設経営を確立するうえの現実的かつスタンダードな選択になります。
この際重要なことは、まず経営者自身が「放デイの目的は、お子さんに質の高い療育を提供してその発達を促すだけでなく、保護者さんが安心してお子さんを預けられ、仕事をしたり休んだりできることである」と認識し、それをスタッフにも事あるごとに伝えることです。その上でどうしても両立が難しい場合は、話し合いの機会を持ち、自分たちの施設がどちらのニーズを優先するのかについて合意形成をしっかり行うことが大切です。
いかがでしたでしょうか。今回は、放課後等デイサービス運営の基礎となる「療育ニーズ」と「預かりニーズ」についてお話ししました。
次回は、運営のもう一つのポイントである「幅広い年代のお子さんへの対応」について解説していきます。