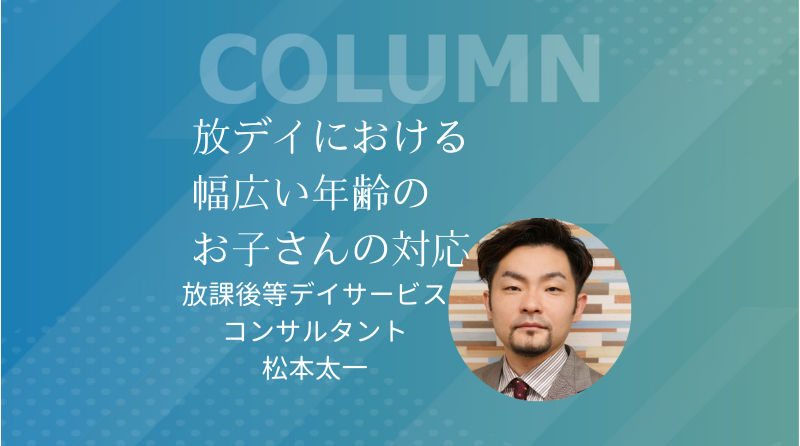放課後等デイサービスコンサルタントの松本太一です。
介護経営ドットコムでは現在、この事業への参入に関心を持っていらっしゃる事業者様にぜひ知っていていただきたい準備や運営のポイントをご紹介しております。
2回目となる今回は「幅広い年代のお子さんへの対応」をテーマにお伝えします。
※前回記事: 「療育」「預かり」2種類のニーズを両立する―放課後等デイ事業参入前に知っておくべきポイント①
幅広い年齢・発達段階の子どもが対象となる放課後等デイサービス
放課後等デイサービスの対象となるのは小・中・高校生で、年齢で言うと6歳から18歳までのお子さんが利用します。この中には、発達の遅れがある子もいて、一般的な成長の過程に当てはめると、まだ言葉の意味がわからない0歳代の認知発達段階にあるお子さんから、知能が高すぎるために同年代の子どもと話が合わずに不登校になっているようなお子さんまでいらっしゃいます。
このことからもわかるように、放課後等デイサービスの運営にあたっては、幅広い年齢と、さらに幅広い発達段階のお子さんに対応できる支援体制を用意する必要があります。しかし、特に新規参入された経営者の場合、その用意が不十分なまま開業してしまい、後々困ってしまうケースが少なくありません。
「差別化戦略」の罠とは?
幅広い年齢や個人の発達段階に合わせた支援が困難になってしまう原因の一つとして、新たに放デイを立ち上げる経営者の多くが、「他の事業所にはない特色を打ち出さなければ集客できない」と考え、新奇性の高いプログラムで差別化しようと考えることがあります。最近は、英語・プログラミング・運動などが人気のコンセプトで、福祉施設向けに調整された特殊な機械を使ったり、PC・タブレットのようなIT機器を使ったりした魅力的なサービスが多数展開されています。
しかし、こうしたテーマやツールの多くは、放デイにやってくる幅広い年代の子どもたちの一部にしか対応できず、そのことが事業所の舵取りを難しくしていることが少なくないのです。
たとえば英語やプログラミングは、言葉や数に対する一定の理解が必要であり、「物の名前を言えるようになった」、「1から5までの数を数えられるようになった」、といった段階のお子さんにとっては難しすぎます。
逆に、運動プログラムとして音楽に合わせて手足を動かすようなサービスを提供する場合、小学校低学年くらいまでのお子さんは楽しくても、中学生や高校生からすると退屈だったり子どもっぽくて恥ずかしかったりして、参加を拒否されてしまうことがあります。
こうした理由でプログラムに参加しない子が一定数出てしまうと、その子たちが走り回ったり、プロレスごっこのような危険な遊びをはじめたりしてしまいます。
はてはプログラムに参加している子にちょっかいを出してしまい、プログラム全体が成立しなくなってしまうこともあります。
「今更やめるわけにもいかず・・・」
経営者としては、せっかく費用と時間をかけて用意したプログラムを無駄にはできませんし、またそこに魅力を感じて契約した保護者の存在を考慮すると、簡単にやめるわけにいきません。
そこで支援員に無理にでも採用したプログラムを実施するよう求めると、今度は子どもに合わないプログラムを実施しなければならない支援員の不満が募ります。そこから経営者との関係が悪くなって、離職につながってしまうことも少なくありません。
発達段階にあわせたグループ分けとプログラムがカギ
新奇性のあるプログラムを導入すること自体が悪いのではありません。問題は、子ども全員を一つのプログラムに参加させようとすることにあります。よほどお子さんの年齢や発達段階が揃っている事業所でない限り、日々の活動は最低でも2グループに分かれて計画・実施することを考えるべきでしょう。
たとえば、運動の中でダンスを特色として打ち出すのであれば、低学年及び知的な遅れのある子向けのグループには、アブラハム体操のような先生の動きを忠実に再現するような課題を設定し、高学年の子には創作ダンスを教えるといったことが考えられます。
あるいは、小学生低学年のグループはダンスをするが、小学校高学年・中高生はプログラミングを学ぶ、といった具合に、活動のテーマそのものを変えていくことも考えられます。
プログラム以外の時間を組み合わせる
上でお伝えした方法の他に、私がよく提案させていただくのは、一つのグループが「おやつ」「宿題」「自由時間」といったプログラム以外の時間を過ごしている間、もう一つのグループがプログラムを行い、途中で交代する形です。
【放課後等デイサービス:運動プログラムの日のタイムテーブル例】
| 時間帯 | 低学年グループ | 高学年グループ |
|---|---|---|
| 15:15-16:00 | 体操プログラム | おやつ・宿題・自由時間 |
| 16:00-16:45 | おやつ・宿題・自由時間 | 創作ダンス |
| 16:45-17:00 | 帰りの会 | |
この方法のメリットは、おやつ・宿題・自由時間は比較的少ないスタッフで対応できるため、プログラムに重点的に人員を割くことができる点にあります。ただし、プログラムの時間が短くなるため効率的な進行が求められます。
多様な子どもに対応できるアナログゲーム

多様な発達段階に対応できるプログラムの一例として、私が放デイ事業者様にご紹介しているアナログゲーム療育を紹介させていただきます。放デイの実践の中から生まれたこの技法は、市販されている数多くのカードゲームやボードゲームを用いて、2歳から大人までの幅広い発達段階において、コミュニケーションや社会性の発達を促すものです。
具体的にどんなゲームを使うのか、またどんな関わり方をすればよいのかは、私が出演しているYoutube「遊びと育ちチャンネル」にて解説していますので、アナログゲーム療育の公式サイトとあわせて、ぜひ一度ご覧ください。
まとめ
今回は、放課後等デイサービスに通うお子さんの幅広い年齢や発達段階にどう対応するかについてお話しました。
次回は、こうしたプログラムを円滑に実施するうえで必要なタイムテーブルの作成について解説していきたいと思います。どうぞご期待ください。