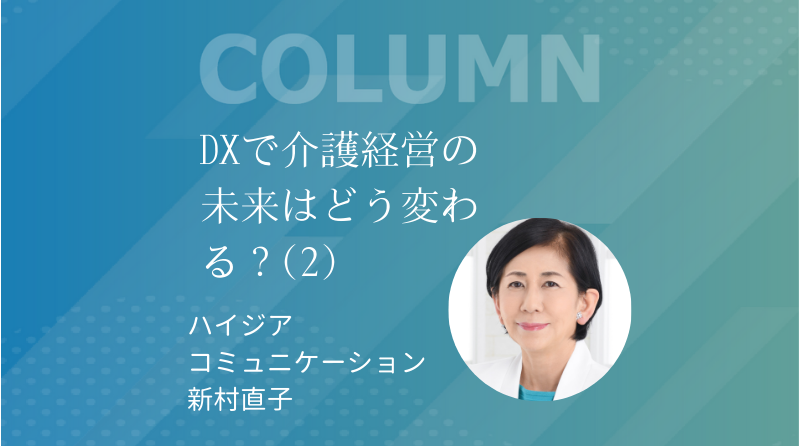昨年12月、クラウド型の介護ロボット連携プラットフォーム「Smart Care Operating Platform(略称SCOP)」を開発した功績から、内閣官房主催の「第5回日本医療研究開発大賞AMED理事長賞」を受賞。「介護DX」のキーパーソンとして今、業界内外で大きな注目を集めているのが、社会福祉法人善光会の理事・最高執行責任者(COO)・統括施設局長の宮本隆史さんです。
施設内に介護ロボットの研究拠点を設置。様々なセンサー機器や、これらを連携する自社開発プラットフォームを駆使することで、巡回・見守り、記録・申し送りなどの介護業務を大幅に省力化しました。現場主導によるDX介護の先端事例をご紹介します。
*前回記事:介護業界のDXを推進するキーパーソンたちに聞く─ DXで介護経営の未来はどう変わる?(1)
介護ロボットの研究拠点を自ら備える社会福祉法人

【画像】宮本隆史氏
介護施設を運営する社会福祉法人でありながら、ICT機器の開発にも自ら取り組む善光会とは一体どんな法人なのでしょうか。
善光会は2005年、「オペレーションの模範となる/業界の行く末を担う先導者になる」ことを理念に掲げ、創立しました。東京都大田区(6拠点)と葛飾区(1拠点)に拠点をもち、本部がある複合福祉施設サンタフェ ガーデンヒルズでは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、障害者支援施設、デイサービス、通所リハビリテーション、ショートステイを運営しています。「諦めない介護」、「先端技術と科学的方法を用いたオペレーション」をビジョンに掲げ、これまで様々な介護ロボット※1を評価・導入、介護業務の効率化、DXに取り組んできました。
※1:厚生労働省によると、介護ロボットとは、情報を感知(センサー系)、判断し(知能・制御系)、動作する(駆動系)という3つの要素技術を有する、知能化した機械システムのこと。装着型のパワーアシスト、歩行アシストカート、自動排泄処理装置、各種見守りセンサーなどが具体例。
DXの旗振り役はCOOの宮本隆史さん。介護ロボットの研究拠点としているのが、「サンタフェ総合研究所」です。ロボットスーツ「HAL」を皮切りに、これまで善光会で導入・評価してきた介護ロボット機器は実に150種類以上。「どこの介護施設よりも導入実績が豊富」と自負する介護ロボットの実証から得た知見を、福祉業界全体で広く活用してもらおうとの狙いから、同研究所を2017年に設立しました。
センサー機器を駆使した最先端ユニット型特養とは
DXの実証舞台となっているのが、善光会が運営するユニット型の特別養護老人ホーム「フロース東糀谷」(定員160名)です。フロアの一角には、多様な機器類の管制塔のようなブースがあり、呼吸・心拍・睡眠といった利用者のバイタル情報を集約する大型のコントロールパネルやタブレットPCなどが置かれています。
利用者のベッドの下には見守り支援システム「眠りスキャン」のセンサーシートが敷かれ、心拍、呼吸、体動を感知して、パソコンやタブレットでリアルタイムに詳細な情報を映し出します(下の図参照)。居室の天井には、転倒などのリスクに備え利用者の行動を把握・分析するセンサー「HitomeQ(ひとめく) ケアサポート(下の写真参照)」も。これらのセンサー機器や、膀胱の拡張状態をモニタリングすることで尿の溜まり具合がスマホに伝達されるシステム「DFree(下の写真参照)」などを連携してセンサーを複合的に活用することで、利用者が起きている適切な時間にトイレ誘導を行うことも可能になっています。

【画像】「眠りSCAN」のリアルタイムモニター画像サンプル(提供:パラマウントベッド株式会社)

【画像】壁に設置している見守りセンサー「HitomeQケアサポート」(提供:コニカミノルタQOLソリューションズ株式会社)

【画像】膀胱の拡張具合を把握して排泄を予測する装着型デバイス「Dfree」(提供:トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社)
こうしたセンサー機器の採用を機に、職員らの負担になっていた無駄な巡回が減り、見守り業務にかける時間は約1/2※2になりました。数年前からは夜間巡回の必要がなくなったことで、夜勤のシフトも大幅に減りました。特養などの人員配置基準は現在3対1ですが、全国平均は2対1とも言われる中、善光会ではこうしたDX化と業務改善を徹底し、現在では2.8対1の配置を実現させています。
※2:令和2年度「介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム構築業務一式・報告書別冊モデル事業」(厚生労働省)
センサー機器の導入効果は単なる省力化にとどまりません。「眠りSCAN」により、利用者の睡眠の状態をリアルタイムで把握し、熟睡時にはできる限りおむつ交換を避けることで、利用者の睡眠の質や生活リズムもより良好に変化したといいます。さらに、「HitomeQケアサポート」では、離床や転倒・転落に関する注意行動を、スマートフォンの通知で察知して映像で迅速に状態を確認できるので、無駄なく効果的な駆けつけ対応が可能となりました。
このように、「多用な機能の機器を連携させて活用している点が善光会のDXの一番の特徴」だと宮本さんは話します。「介護現場では、見守りをしながら食事や排泄を介助するなど、複数の業務が複雑に関わり合います。一つの業務だけを取り出して機械化しても生産性向上にはなかなかつながりません。入浴、排泄、食事、就寝準備・見守り、コミュニケーションなどの業務全体を対象に、それぞれの時間や内容について業務分析をまず行った上で、見守り・巡回などの必ずしも人が行わなくてもいい業務についてはテクノロジーに代替させるなど、オペレーションを根本的に見直していくことが重要です」。
外販を前提に現場の使いやすさにこだわったSCOP
見守り・巡回のほかに宮本さんが業務改善のターゲットとしたのが、様々な記録の記載業務や申し送りでした。それを解決した仕組みが、冒頭でも紹介したスマート介護プラットフォーム「Smart Care Operating Platform(略称SCOP)」です。業務分析の結果、現場の職員は記録業務の際、手元でのメモや電子カルテへの転記など同じ作業を2度3度繰り返しており、職員間での情報共有にも時間がかかっていたことがわかっていました。この課題を解決すべく、「1度記録すれば転記しなくてもいいように、また、複数のICT機器を束ねて様々なバイタル情報を可視化でき、情報を一元化できるようなプラットフォームを作ろうと考えました」と宮本さんは開発の狙いを語ります。
これまで様々な機器を評価してきた宮本さん曰く、当時、世に出ていた介護システムはフルパッケージで重装備になりがちな側面があるにも関わらず、請求と介護サービスの連動性が不十分かつ、現場の職員にとってユーザーインターフェースが使いづらい面があったと話します。そこで、SCOPでは、画面のビジュアルも、IT機器に慣れない一般職員でも直観的に操作できるようにとの視点で設計されました(下の画面参照)。
SCOPには、食事や服薬、口腔ケア、排泄、体温などの介護記録の入力や閲覧ができるiPad用アプリ「SCOP Home」と、センサー類の情報を集約し、必要な情報を職員がいつでも手元でチェックできるiPhone用アプリ「SCOP Now」などがあります。

【画像】SCOP Homeのサマリーボード画面サンプル(提供:善光会)。赤く表示されたアラート部分をタップすると申し送り事項を確認できる。
導入後は1日4回行っていた申し送りミーティングがゼロに
SCOP Home(iPad)のサマリーボード画面では、利用者のバイタル情報に何等かの異常があればアラートのため赤く表示されるので、重要な情報を一目で把握できます。iPadのタブレットは各ユニットの入り口に1台置き、持ち歩かずにその場で入力します。SCOP導入後、善光会では複数回行っていた申し送りがゼロに。電子カルテへの転記がなくなったことで記載ミスや記入漏れも減り、導入後は記録業務、申し送り・伝達業務が約75%削減できたといいます。
SCOPはもともと他の施設への外販を前提に開発されたものですが、気になるのが導入コストです。さぞかし高額になるのかと思いきや、導入費は意外や1利用者当たりHomeの月額で100円、Nowは同50円と低額(初期導入費を除く)。「うちの本業はあくまで施設運営。ですので、SCOPはかなり低コストで提供できています」と宮本さん。利用者側に立った設計と価格設定の手頃さで、「SCOP Home」の導入実績は既に100法人超に上ります。
SCOPでは、AI機能によって、利用者ごとの転倒発生の確率や褥瘡発生率などを予測したり、ケアマネジャーがプランを考えたい対象者の方に類似したデータを検索・参照したりして、ケアプラン作りを支援する機能の追加も検討しています。「こうしたAIの機能を高めることで、いずれはすべての介護業務に対して『次はこんな業務をするといい』といったリコメンドができるようにしたい」というのが宮本さんの構想です。
介護ロボットを使いこなせる専門人材「スマート介護士」育成も
もう一つ、善光会の取り組みで特徴的なのが、介護ロボット全般を使いこなすことができる専門人材の育成です。介護の質と生産性向上につながる最先端技術を扱える介護士の資格として、2019年から「スマート介護士」制度をスタートしました。施設の管理職層やベンダーの研究開発者・販売担当者などからの受験が相次いでいます。
現在、この資格を取得している方は3500人以上。これまでは対面での試験のみでしたが、2021年12月からオンライン試験に切り替えたため、今後は地方在住の方でも受験しやすい環境が整い、さらなる受験数増加が見込まれそうです。
DX化を検討している経営者に今、伝えたいこと
厚生労働省は社会保障費の増加、人手不足が深刻化する2030年、2040年に向けて、「令和時代の社会保障や働き方のあり方はDXを前提として考える必要がある」※3と明言しています。宮本さんも来る2030年までには、「機械でもできる業務、介護職員が本当に注力すべき業務などを見極め、何が“いい介護”なのかを定義づけして、日本式介護の標準をきちんと作っていくことが必要」と指摘します。その上で、事業者側の心構えとしては、「どれだけ自らのマインドを変えていけるのか、その姿勢を現場にもきちんと示していけるか」が非常に重要だといいます。
DXを推進することで職員がしっかり利用者に向き合う時間を確保しつつ、非効率的な要素をまだまだ抱える従来型の介護経営からの脱却も目指す──。その両立こそが、これからの日本式介護の標準になっていくのかもしれません。
宮本隆史(みやもと・たかし)
社会福祉法人善光会 理事、最高執行責任者、統括施設局長、特別養護老人ホームフロース東糀谷施設長。介護職に従事し、特別養護老人ホームの立ち上げを行い、現職に至る。2009年ごろより介護ロボットの導入やサイバーダイン社のHALの監修に関わり、2013年に「介護ロボット研究室」、2017年に「サンタフェ総合研究所」を設立。介護ロボット機器のプラットフォーム「SCOP」や介護ロボット運用資格「スマート介護士」事業を創設。2021年に第5回日本医療研究開発大賞AMED理事長賞を受賞。関係省庁や関連団体の委員、セミナー・講演等幅広い活動を行う。