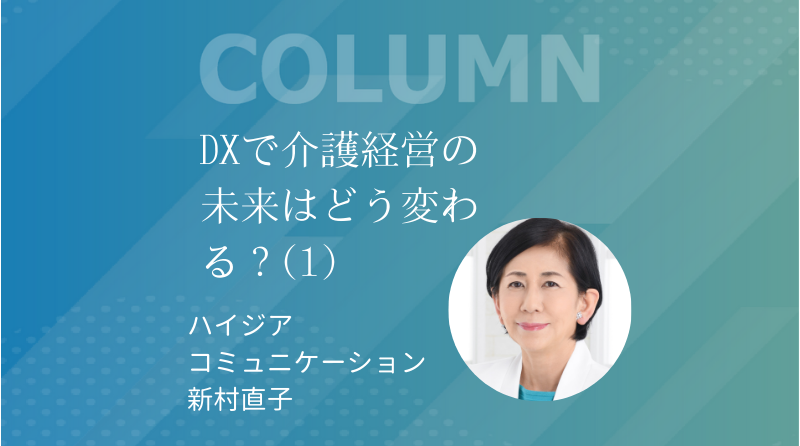昨年から、介護業界でもよく聞かれるようになってきた「デジタルトランスフォーメーション(DX)」。労働集約型の介護業界において、事業所、大手ベンダーがDX化を急ぎ出した背景にはどんなことがあるのでしょうか。介護業界のDX化を推進するキーパーソンたちに取材し、DX化によって介護経営がどう変わるのか、介護事業所でDXを成功させるためのポイント、注意すべき落とし穴についてご紹介していきます。
連載第一回目に登場いただくのは、介護現場でのテクノロジー普及を目指す一般社団法人日本ケアテック協会代表理事を務める鹿野佑介さんです。
2025年問題に向け、DX化への対応が迫られている

【画像】鹿野佑介氏
介護業界の大きな課題と指摘されているのが担い手不足です。団塊世代が後期高齢者に達する、いわゆる2025年問題が迫る介護現場の状況について、日本ケアテック協会代表理事で、ケアプラン作成支援AIなどを手掛けるウェルモの代表取締役CEOも務める鹿野佑介さんはこう指摘します。
「介護業界の人材不足は待ったなしです。少子高齢化の需要増により、2025年度には約243万人(+約32万人※1)、2040年度には約280万人(+約69万人)の人材が必要という厚生労働省の推計が出ていますが、それだけでなく、介護職員の高齢化も大きな問題です。平均年齢50歳※2の方々に、いわゆる“抱え上げの介護”のような力仕事を求め続けていくのは無理。今後は在宅介護が増えていきますが、一般住宅にはリフトなどの機材もありません。このまま気合と根性だけで立ち向かう“竹槍介護”では到底立ち行きません」。
※1:( )内は、2019年度の必要数211万人に加えて確保が必要と見込まれる人数
※2:介護労働安定センターの令和2年度「介護労働実態調査」によると、平均年齢は年々上昇、現状は49.4歳(2020年)。介護労働者全体の23.8%が60歳以上。
全産業中、最もICT化が進んでいないという報告も
こうした背景から、介護業界でのDX化は急務となっています。DX化を考える際に欠かせないのが業務のICT化ですが、現状はどの程度進んでいるのでしょうか。少し古い調査になりますが、「総務省の『平成24年版 情報通信白書』の報告では、介護事業所が含まれる『保健・医療・福祉関連』領域の中小企業のICT化は、全産業中で残念ながら最も進んでいないという結果でした」(鹿野さん)。

それだけではありません。令和2年度「介護労働実態調査」によると、「給与計算、シフト管理、勤怠管理を一元化したシステム」を利用している事業所はわずか17.9%(下の表参照)。「グループウエア等のシステムで事業所内の報告・連絡・相談を行っている」事業所も16.1%。パソコンで利用者情報を共有しているという事業所でさえも50.4%に過ぎませんでした。

【画像】令和2年度介護労働実態調査・事業所における介護労働実態調査結果報告書より抜粋(以下・同様)
「勤怠管理などの経営の基盤とも言える業務においてもまだICT化が進まず、従業員数が多い介護現場では欠かせないホウレンソウ、“報告・相談・連絡”業務ですら、電話のみに頼っている例が多いということでしょう。大企業であれば、大抵チャットツールなどを導入されていると思いますが、こうしたツールも近年は無料や低コストで導入が可能にもかかわらず、介護現場ではまだ浸透していないのではないでしょうか」。
ICT化が進みにくい理由に、介護のカルチャーも関連?
なぜ、ここまで介護業界にはICT技術が導入されにくいのでしょう。「私はその理由の一つに、介護や福祉の文化的側面が影響しているのかもしれないと感じています。介護は人が人のケアをする、人の心を扱う仕事でもあります。一般企業では、製品など無機質なものを取り扱うことが多いですが、この領域では、時間がかかっても利用者さんの心に寄り添おうという優しさを持つ方が多く、業務の合理化やICT化に関心を持つ人材がそもそも集まりにくい傾向にあるのかもしれません」。
もともとプログラミングに詳しくITベンダーで働いていた経験を持つ鹿野さんは、こうした課題に着目し、2020年11月に日本ケアテック※3協会を設立。介護事業者とベンダー間の懸け橋となり、介護現場のデータの利活用を進め、現場に即したテクノロジーの社会実装を推進しようとしています。その中で、「DX化に悩む事業者さん向けに支援を進めていきたい」と話します。
※3:ケアテックとは、「Care(介護)」と「Technology(テクノロジー)」を掛け合わせた、同協会による造語。
介護事業所の経営者がDX化を考える上で、何を一番重視すべきなのでしょうか。
まず、「DX化とICT化は異なります」と鹿野さん。業務の一部をITに置き換えるのがICT化だとすると、DX化は業務フローを根本から見直し、業務や経営を改革していくこと。「例えば、夜間の見守りにしても、一人一人の部屋を人海戦術で訪問して確認する従来の方法に対して、室内にセンサーシステムを導入することで、管理者は中央管理室にいながらにして何人もの方々の見守りができるようになります」。
センサーの記録データや録画された画像データがあれば、仮に転倒などの事故が起きたときには、その原因を確認することもできるので、裁判沙汰になるような経営上のリスクを減らすことにもつながるのです。
コストのみならず、製品選びや研修などの壁も
とはいえ、前述の令和2年度「介護労働実態調査」によると、実際に現場でICT機器の導入や利用にあたり大きな壁となっているのが「導入コスト」です(下の表参照)。さらに、「技術的に使いこなせるか心配」、「どのような介護ロボットやICT機器・介護ソフトがあるかわからない」といった不安を抱える事業所も少なくありません。

「コストのみならず、数ある製品のなかでどれを選ぶのか、それをどう業務に載せていくのか、また、オペレーションをどう構築し、研修にどう落とし込むのか、こうしたコンサルティングができる会社がまだ少ないことも業界の大きな課題。機器だけ入れても、事業所の従業員が使いこなせるようになるとは限りません」と鹿野さんも認めます。
そのため、協会としては、2022年から介護機器の認証制度を新たに立ち上げる方針だと言います。「まずは検討委員会をつくり、ユーザーにとっての機器選択の際の助けとなるような制度にするための議論を始めていきたい」と鹿野さん。
ケアテック市場の創出に向け、国に提言
鹿野さんは2021年12月10日、自由民主党ケアテック活用推進議員連盟会議において、会長を務める丸川珠代氏に、ケアテック普及促進に向けての法的整備や市場創出を推進する対策についての要望書を提出しました。その文書では、ICT投資が介護保険法に織り込まれていないことが一つの問題であるとの認識を明らかにしています。
「医療機器のMRIなどは高額にもかかわらず日本で導入が進んでいる背景の一つに、診療報酬がつくということがあります。ところが、介護機器や介護ロボットは介護保険に組み込まれておらず、報酬はつきません。そのほか、介護事業所にICTやDXへの投資をする余力がない面もあります。今後はこうした点を改善し、ケアテック機器の保険収載などにより、ケアテック市場を創出・育成していく方向性が必要です」。
さらに、介護事業者から入力負担が大きいとの指摘もある科学的介護情報システム(LIFE)のデータ収集方法についても、「センシングによるデータの自動収集など、現場の負担を減らす工夫を検討していく必要がある旨を提言しました」。
“道具”をどう使うかは経営者の腕次第
ただし、ICTはあくまで道具に過ぎません。「例えば、前述のような物理的な訪問の代替や記録の自動化などの観点からDX化を進めることで、限界まで省力化を実現しながらも、利用者さんのQOL向上や重度化予防など、介護ケアの“質”はむしろ向上させつつ、現場の働き手の疲弊や負担を減らすことを両立できるはずです。ICT技術をどう使いこなすかは経営者の腕次第。DX化を考える上で、よりよいケアと働き手の環境改善という、大きな2つの目的を忘れないでほしい」と鹿野さんは強調します。
さらには、ベンダー、介護事業所でタッグを組んで、ICTを使った介護のあるべき姿について議論を深めた上で、国にICT投資が必要だという“声”を届けていくことも必要だとも。「日本は高齢化率が世界ナンバー1の国。世界に先駆けて介護業界のDX化を進め、その仕組みを海外に輸出できるようになっていかないといけない。そのためにも、協会メンバーも増やし、官民一体となってDX化を推進していきたいですね」。
鹿野佑介(かの・ゆうすけ)
一般社団法人日本ケアテック協会 代表理事。東京大学 高齢社会総合研究機構 共同研究員。大阪府豊中市出身。ワークスアプリケーションズにて人事領域のITコンサルタントとして勤務後、東証一部上場企業人事部へ。その後8か月間にわたり、仙台から福岡まで、約400法人超の介護事業所にてボランティアやインタビューを実施し、福祉現場の働きがいに課題を感じて2013年ウェルモを創業。 厚生労働省、経済産業省、総務省、文部科学省等にて講師を務める。Forbes JAPAN 2018 NEW INNOVATOR 日本の担い手99選出。経済産業省主催ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト2019にて最多受賞。