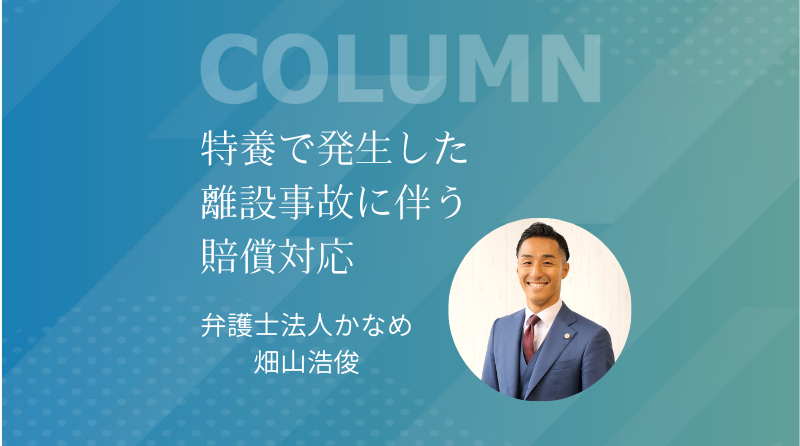介護事業所は、常に介護事故の危険と隣り合わせです。人が生活する場所ですから、それはある意味当然です。
介護事故の中には、必要な注意を尽くしていたにもかかわらず、発生してしまったものもありますが、介護事業所側に「過失」が認められる事故もあります。その場合、介護事業所は、利用者に生じた損害を賠償する必要があります。そして、通常は、介護事業所では、法律の専門知識を有していない管理者や施設長が、事故後の対応を担当することになります。中には、「いざという時のために賠償責任保険に加入しているから、対応は保険会社に任せておけば良いのだろう」と考える人がいますが、これは大きな勘違いです。
以下、介護施設側に過失が認められる場合の賠償対応について詳しく解説しますので、管理者や施設長等、事故対応の窓口を担当される方は是非チェックしてください。
1.特別養護老人ホームで生じた介護事故事例
<相談内容>
私は特別養護老人ホームの施設長です。
去年、利用者(男性)が特養の2階の非常階段から誤って足を滑らし、階段の踊り場まで転げ落ちるという事故が発生しました。この利用者は認知症を患っており、施設から出ていこうとする離設行動が頻繁に見られており、非常階段から出ていこうとする姿も何度か目撃されていました。
施設内では、職員に対し、「非常階段を開けっ放しにしないように」と注意喚起を行っていたのですが、職員が清掃作業を行う際に、非常階段の扉にストッパーをかけ、開けたままの状態にしており、職員が目を離した隙に利用者が非常階段から出て行ってしまったようです。
利用者は足を骨折する重傷を負い、現在、入院中です。
ご家族側との話合いをしなければならないのですが、賠償対応の点についてどのように進めて行けば良いのか、皆目見当がつきません。 どのように対応すれば良いのでしょうか。2. 施設長が行うべき介護事故発生後の動き
介護事故後の流れを確認しましょう。
①利用者の救護措置を迅速に行う
②ご家族へ速やかに事故報告を行う
③事故報告書を作成し、行政へ報告を行う
④保険会社へ速やかに事故報告を行う
※重大事故発生時は警察が現場に捜査に来ることがありますが、本稿では警察対応は紙面の都合上割愛します。
という流れです。
本来は、もっと細かく対応すべきことがあるのですが、あくまで全体の流れのイメージを掴んで頂くための概括的な記載にしています。
特に重要な場面は、②です。ご家族に対しては、速やかに事故報告を行うことが大切です。
事故報告の際には、なるべく事前に事故調査を行った上で、事故が発生した経緯、原因をありのまま伝達できるようにしましょう。とは言え、事故直後の場面では、必要な調査を行う余裕が無い場合があります。その際は、「原因を調査の上、改めてご報告させて頂きます。」と伝えた上、次にご家族と面談する日時まで、その場で決めることが大切です。明確に期限を切ることで誠意が伝わりますし、ご家族側にとっても先の見通しが立つからです。
また、事故直後の場面では、共感を示す謝罪、道義的責任を認める謝罪は忘れずに行うようにしましょう。「当施設でお預かりしているにもかかわらず、このような重大な事故が発生したことについて、心から謝罪申し上げます。」というように心を込めて謝罪を行うことは、人として当然の振舞です。
なお、事故直後に行う上記のような謝罪は、法的責任を認める謝罪ではありません。
ご家族側から「治療費や慰謝料等の賠償は、今後どのようになるのでしょうか。」と聞かれた際はどう対応するのかについては、後述「3.保険会社は示談代行をしない」で詳しく解説します。
3.保険会社は示談代行をしない
まず、大切なことは、介護事故の賠償対応では、保険会社の担当者が介護施設の代わりに示談交渉の窓口になることは無い、ということです。交通事故では、自身が入っている損害保険の事故担当者が、加害者本人に代わって窓口対応、賠償対応の交渉を全て代行してくれます。これを示談代行といいます。示談代行については、交通事故に限って認められている特別ルールであって、介護事故の賠償対応では認められていません(弁護士法の規制が理由なのですが、詳細の理由は割愛します)。
そうすると、介護施設側で介護事故における賠償対応を行う必要があり、施設長等の担当者の動きが非常に重要になります。
事故対応を行う施設長等の担当者は、介護事故発生後、保険会社とどのようなやり取りをするのか、以下に解説しますので、流れをしっかりと頭に入れておきましょう。
介護事故発生後に保険会社と実施する具体的なやり取り
(1)事故報告を行うまず、介護事故が発生したらなるべく速やかに保険会社に事故報告を行うようにしましょう。保険代理店を通して保険に入っている場合は、保険代理店の担当者に速やかに連絡すると良いでしょう。
(2)調査会社からの調査を受ける次に、保険会社の関連会社による現場検証が実施されます。多くの場合は、事故後1週間前後で調査会社の方が介護事故現場に来られ、事故状況の調査報告書を作成します。この調査報告書は、調査会社から保険会社に提供されることを目的とするものです。
(3)保険会社へ電話連絡を行う施設長は、調査会社の調査が終わった後、速やかに保険会社へ電話連絡し、「調査報告書を受け取った後、連絡をください。その後の見通し、検討結果が出るまでどの程度時間を要するのか等を教えて頂きたいです。」と伝えるようにしましょう。保険会社は数多くの事故対応を行っていますので、小まめに進捗確認の連絡を行うことで、事故対応の遅延を防止することができます(裏を返すと、調査報告書を受け取ったにもかかわらず、事故内容の分析検討に着手しないまま対応を忘れてしまう損害賠償担当者も中にはいるということです)。
(4)ご家族へも小まめに報告連絡を行う施設長の上記動きは、ご家族からは見えません。しっかりと動いていることを可視化することが大切です。小まめに進捗状況はご家族に報告連絡を行うようにしましょう。
例えば、「〇月〇日に調査会社が事故状況の調査に来ることになりました。」、「調査会社の調査が完了しました。調査報告書は1週間程度で出来上がるようで、その後、調査会社から保険会社に当該報告書が送付されるとのことです。今後の見通しが分かり次第、また共有させて頂きます。」といった具合に、小まめに進捗報告を行うことで、ご家族は「きちんと対応してくれているのだな。」と安心します。
(5)裁判例を調査し、保険会社へ意見を提出するこれは、「過失」がある事故の場合の対応です。
上記ケースのように、介護施設側に明らかに「過失」があると考えられるようなケースでは、今後の賠償額の提示が交渉において重要な鍵となります。
もちろん、治療が終了していなければ賠償額の確定は難しいのですが、なるべく保険会社内部での分析検討を早く進めて頂くために、介護施設側からも必要な情報提供を行うことが大切です。
これは我々介護施設の顧問弁護士が行うことですが、過失があると認められるケースでは、先んじて、我々顧問弁護士の方から類似の裁判例を調査し、おおよその賠償額の見込みを保険会社に伝えます。その目的は、ご家族側へ提示する賠償額の目安を保険会社内で決めて頂くためです。
保険会社が賠償対応を行う、と言っても、前述のとおり、保険会社による示談代行はありませんので、あくまで、介護施設側が施設長を通じて、家族に賠償額の提示を行う訳です。保険会社の了解を得ずに賠償額を提示することはできません。とは言え、保険会社がいつまで経っても賠償額の目安を教えてくれなければ、施設長としてはご家族へ具体的な話ができず、ご家族からすると、「対応を放置されているのではないか。」と介護施設の対応に疑問を持ちかねません。
介護施設に顧問弁護士がいれば類似の裁判例の調査を弁護士に依頼し、その情報を保険会社に伝達して頂くことができるのですが、仮に顧問弁護士がいない場合は、介護事故に関する裁判例をまとめている書籍を介護施設で購入し、類似裁判例をチェックしてみましょう。全く同じケースは無いのですが、類似する事例はあるはずです。そして、保険会社の担当者に参考となる裁判例の年月日や事案の概要、賠償額等を伝えることで、保険会社内部での賠償額の目安検討が進むはずです。
以上、介護事故の場面では、管理者・施設長が賠償対応の局面で様々な動きをする必要があります。本稿を参考に実践してみましょう。