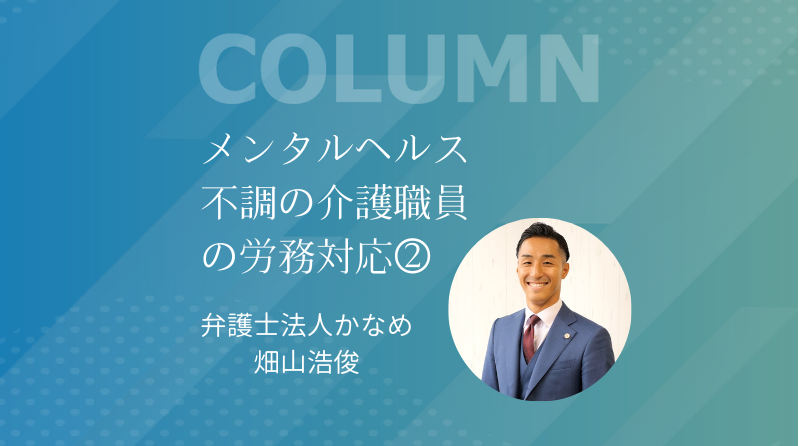みなさまの職場に
・遅刻早退や業務におけるミスを繰りかえす
・業務時間中に気分の落ち込みが激しく、仕事が手についていない
・時に、異常な言動が見られる
客観的に見て、このような状態が単なる怠慢ではなく、メンタルヘルス不調が原因と思われる職員がいて、対応に困ったことはありませんか。
今回は、職員の労務提供が不完全になっている背景にメンタルヘルス不調があると思われる場合、職場としてどう対応すれば良いのかという点について法的な観点から解説していきます。
なお、『休職制度』についてはこちらの記事を参考にして下さい。
今回のポイントは次の3つです。
1.労務の不完全提供は原則として注意指導の対象
2.明らかにメンタルヘルス不調に陥っている職員へは医師の意見を踏まえた対応を
3.産業医と連携しよう
1.労務不提供は原則として注意指導の対象
頻繁な遅刻早退や業務におけるミスを繰り返すなどというような労務不提供がある場合、原則として注意指導(書面での指導・懲戒処分等)することが必要になります。
雇用契約では、職員は法人に対して労務提供義務を負っています。
ですから、遅刻早退や業務におけるミスの繰り返しは、満足に労務提供ができていない点で債務不履行なのです。
適時適切な指導が重要になることは言うまでもありません。
2.明らかにメンタルヘルス不調に陥っている職員へは医師の意見を踏まえた対応を
もっとも、それが単なる怠慢ではなく、客観的に見て明らかにメンタルヘルス不調が原因と考えられるような場合は要注意です。
たしかに労務不提供ではあるのですが、注意指導ではなく、休職手続きで対応するべきかどうかを医師の意見を踏まえて検討する必要があります。
(ただし、医師の意見が絶対という訳ではありません。)
このように休職処分を検討すべき状況で休職を検討せず懲戒処分の措置を行ったことが不適切であるとして懲戒処分が無効になった事案として、一つ裁判例を紹介します。
それが、日本HP事件(最高裁平成24年4月27日判決)です。
この事件で懲戒処分された従業員Aは、次のような被害事実を会社に伝えて有給休暇を取得し、有給休暇を全て取得した後は、40日間欠勤を続けました。
従業員Aのいう被害事実とは以下のようなものでした。
「メイド喫茶のウェイトレスとの間でトラブルになったことがきっかけで、約3年間にわたり、加害者集団が雇った専門業者や協力者らにより日常生活を子細に監視されるようになった。盗撮や盗聴等の監視行為によって蓄積された情報は、インターネットの掲示板やメーリングリスト等を通じてAの見えないところで加害者集団に共有されており、ずっと嫌がらせを受けている」
会社の調査の結果、この被害事実の存在は認められず、従業員の何らかの精神的な不調による被害妄想だということがわかりました。
この従業員に対し、会社は欠勤に正当な理由は無いとして諭旨退職という懲戒処分に処したのです。
つまり、労務不提供の背景に何らかの精神不調があると思われるケースで、懲戒処分を実施したということです。
これに対して、裁判所は以下のようにジャッジし、会社の対応を不適切としました。
「精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対しては、精神的な不調が解消されない限り引き続き出勤しないことが予想されるところであるから、使用人であるY社としては、その欠勤の原因や経緯が上記のとおりである以上、精神科医による健康診断を実施するなどした上で(記録によれば、Y社の就業規則には、必要と認めるときに従業員に対し臨時に健康診断を行うことができる旨の定めがあることがうかがわれる)、その診断結果等に応じて、必要な場合は治療を勧めた上で休職等の処分を検討し、その後の経過を見るなどの対応を採るべきであり、このような対応を採ることなく、Aの出勤しない理由が存在しない事実に基づくものであることから直ちにその欠勤を正当な理由なく無断でされたものとして諭旨退職の懲戒処分の措置をとることは、精神的な不調を抱える労働者に対する使用者の対応として適切なものとはいい難い。」
3.産業医と連携しよう
このように、労務不提供の原因が客観的に見てメンタルヘルス不調が原因だと考えられる場合には医師の意見を踏まえた対応が必要であることは分かって頂けたかと思いますが、問題は医師との連携方法です。
例えば、職員に主治医がいる場合、主治医の意見を踏まえた対応をすることも一つの方法です。
もっとも、主治医が非協力的である場合は、そもそも意見を参考にすることすらできません。
また、主治医の意見を得られたとしても、患者のみの言い分に依拠した意見であって、法人の状況や職務内容を踏まえたものになっていない場合もあり得ます。
さらには、法人が受診を勧めても「自分は病気ではありません」と受診を拒否して、主治医からの意見すら得られないこともあります。
そこで、有効だと考えられるのが産業医との連携です。
産業医とは、事業所において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう専門的立場から指導・助言を行う医師です。
もっとも、労働安全衛生法上、産業医の選任義務があるのは50人を超える事業所です。
介護事業などの福祉現場では、一つの事業所で50人未満であることも多く、産業医とのパイプを持っていないも多くあります。
また、実際に私が経験した事例ですが、法人が産業医との繋がりを持っていても、その産業医が「メンタルヘルス不調のことは詳しくないから他を当たって欲しい」と非協力であったり、職員の主治医と産業医が同一人物であり、協力が得られないようなケースもありました。
さらに、地方の事業所ではそもそも近くに産業医が存在しないこともあります。
裁判例では、よく「産業医等の意見を聞くべきであった」という指摘がされることがありますが、日本の福祉現場の実情を見ると、連携できる産業医が中々見つからないという根本的な問題があります。このような状況で、現場でメンタルヘルス不調職員に直接対応している管理者の苦悩は計り知れません。
そこで筆者が最近注目しているサービスは、オンラインで実施できる産業医面談サービスです。
既に複数の事業者がオンライン産業医面談のサービスを実施しているので、是非一度読者の皆様もリサーチして下さい。
地方に産業医とのつながりが無い場合や、繋がりのある産業医の先生がメンタルヘルス不調対応をしていないケース等、産業医とうまく繋がれない問題を一挙に解決することが可能になります。
我々としても、オンライン産業医面談サービスがあることで、「産業医面談の実施」という手段が実践可能なアドバイスになったと実感しています。
メンタルヘルス不調の問題は、今後も益々日本社会で増えていく問題ですので、オンラインで産業医面談が実施できるサービスは需要が拡大していくと思います。
産業医との連携で悩んでいる事業者は是非チェックして下さい。