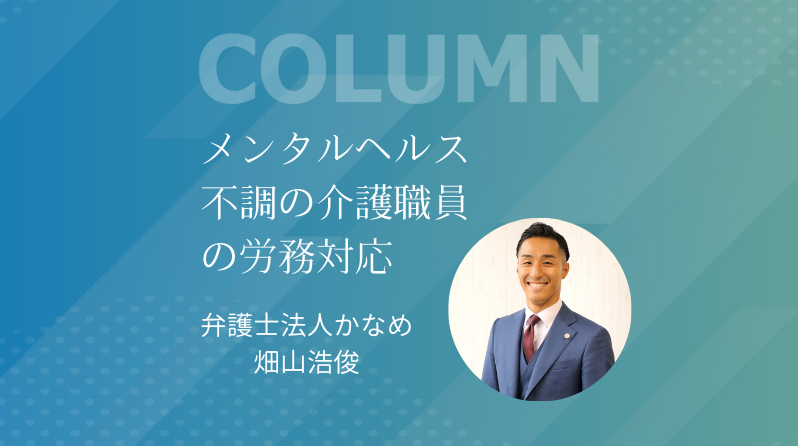0.はじめに
弁護士法人かなめでは、福祉事業者に特化してリーガルサービスを提供していますが、最近特に増加している法律相談はうつ病などのメンタルヘルス不調の職員への労務対応です。
うつ病とは、精神的ストレスや身体的ストレスなどを背景に、脳がうまく働かなくなる気分障害です。例えば、一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないといった精神症状とともに、眠れない、食欲がない、疲れやすいといった身体症状が現れ、日常生活に大きな支障が生じている場合、うつ病の可能性があります。
うつ病などの精神疾患は年々増加傾向にあります。
長期化するコロナ禍や様々な社会情勢の不安など、ストレスフルな社会ですからメンタルヘルスの不調による問題は他人事ではありません。
令和の時代においては、職員がメンタルヘルス不調に陥った場合に就業規則に基づいて適切な労務管理を実践できることが管理者などのマネジメント層に求められる能力になりますので、一緒に学んでいきましょう。
メンタルヘルス不調に関する法的論点は多岐にわたりますが、今回は以下の3つを解説します。
①本来「病気で働けない」は解雇事由
②休職制度を知ろう
③うつ病などの精神疾患に対応した規程にしよう
1.①本来「病気で働けない」は解雇事由
そもそも、「病気で働けない」という状態は、簡単に言うと法人に対する「債務不履行」になります。
雇用契約では、雇い主側は、従業員に対して、給料支払義務と安全配慮義務を負っています。従業員は雇い主に対して労務提供義務、つまり働く義務を負っています。
例えば、1日8時間、週40時間働くことが雇用契約で定められている従業員は、当然、決められた時間、決められた労務を提供することが義務です。
うつ病が原因で、勤務時間中に仕事が手につかず、度々休憩室に入って休んだり、遅刻や早退や欠勤が生じたりすると、雇用契約で決められた労務を満足に提供できていないことになります。
そうすると、債務不履行ですから、本来、雇用契約は解除されることになるはずです。労働法の世界では、雇用契約を雇用主から一方的に解除することを「解雇」と呼んでいます。
もっとも、簡単に解雇が認められてしまうと、従業員の生活に重大な影響が出てしまいます。
従って、労働法の世界では、「解雇権濫用法理」が存在します。解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできません
2.②休職制度を知ろう
このように、業務外の傷病を理由に労働者が労務を提供できない場合、それは労働者の債務不履行ですので、本来であれば雇用契約の違反を理由に解雇になり得ます。しかしながら、休職制度は、労働者が労務を提供しないことを、一定期間「債務不履行」と扱わず、労務への従事を免除するのです。
具体的に、休職とは、ある従業員を労務に従事させることが不能または不適当な事由が生じた場合に、使用者がその従業員に対し、雇用契約関係そのものは維持させながら、労務への従事を免除すること、または禁止することです。
法人側からすると、解雇猶予の意味合いの制度になり、従業員側からすると、治療に専念できるため福利厚生の意味合い帯びた制度と言えるでしょう。
3.③うつ病などの精神疾患に対応した規程にしよう
休職制度は、就業規則で定め、それに基づいて法人が発令する形で運用しますので、休職の条件の定め方が非常に重要になります。
まず、法人がもっとも気を付けなければならないことは、就業規則に、うつ病などの精神疾患を原因とする労務提供不能・不十分な場面を想定した休職事由を設けているかどうか、という点です。
以下のような規定になっている法人は要注意です。
業務外の傷病及び通勤災害により欠勤1カ月を超えた場合、又は、欠勤が2カ月間に通算して30日を超えたとき
休職の発令の事由として上記の規定しか無い場合の問題点は、うつ病などの精神疾患では、通常、上記のような長期間の欠勤が連続して続くことは無く、結果として休職の発令が困難になってしまうという点にあります。
うつ病に罹患した労働者は、もちろん2、3日連続して欠勤することもありますが、遅刻や早退はするものの一応出勤してくるケースが目立ちます。
また、遅刻や早退はなくても、業務時間中、集中力を欠きケアレスミスが増えたり、気分が悪くなり休憩室で休む時間が増え現場を離脱することが増えるなど、通常の労務提供が不十分な状態になることがあります。
法人としては、通常の労務提供が不十分な状態がうつ病などの精神疾患が原因である場合、しばらくは治療に専念させるために休職を発令したいと考えますが、上記のような「欠勤1カ月を超えた場合」や「欠勤が2カ月間に通算して30日を超えたとき」のように「欠勤」を条件とする規定しか存在しない場合、休職命令を出す条件を満たしていないため休職を発令できないのです。
もとより、このような長期間の欠勤を前提とした休職事由は、歴史的には交通事故による長期間の欠勤や肺結核による長期間の欠勤を想定して設けられた規定であり、現代社会にマッチしていません。
そこで、以下のような規定にすることをお勧めします
職員が、次の各号のいずれかに該当したときは、休職とする。職員が、次の各号のいずれかに該当したときは、休職とする。
(1)業務外の傷病により欠勤が、継続、断続を問わず日常業務に支障をきたす程度(おおむね1カ月程度を目安とする。)に続くと認められるとき。
(2)精神又は身体上の疾患により労務提供が不完全なとき。
精神疾患の場合は、勤怠状況等(断続的な欠勤・早退・遅刻がありかつ業務遂行に明らかに支障をきたしている場合)を判断し、当該職員とも協議のうえ欠勤が1カ月等継続しない場合でも休職を命ずることがある。その場合、当該職員は、協議の前提となる情報の提供、必要に応じ専門家による相談又は医師による受診等について、同意・協力するものとする。
このようにうつ病などのメンタルヘルス不調の状態を想定した規定を設けることが大切です。 メンタルヘルス不調の問題に関する法的論点は枚挙に暇がありませんので、今後も重要なトピックごとに解説していきます。