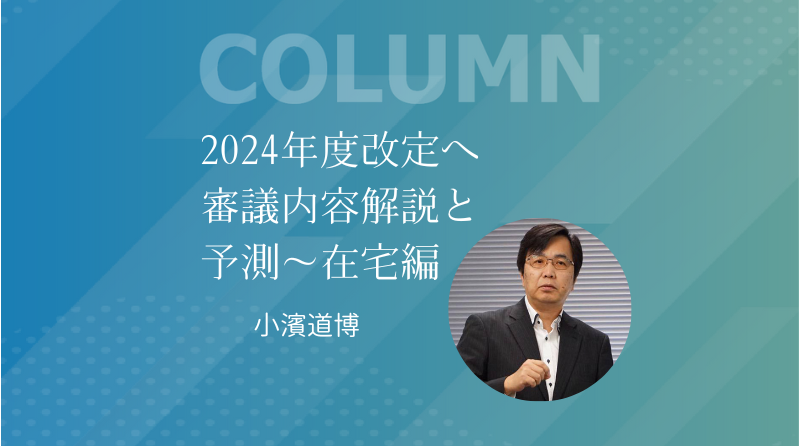令和6年介護報酬改定審議は、第一ラウンドの審議を終え、業界団体がそれぞれ5―10分程度のスピーチを行う業界団体ヒヤリングというイベントが終了した。今、第二ラウンドの介護報酬改定審議に移行している。第一ラウンドの審議では、各サービスの論点が出揃った。しかし、具体的な改定の方向性は、2巡目に持ち越された印象が強い。今週から始まった定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護についての審議では、近い将来の統合に向け、両サービスの一体的実施についての議論が始まったところだ。
今回は、これから2巡目に入る検討にあたり在宅サービスに関する注目ポイントをみていきたい。
1.介護報酬の改定率はプラスになるか?経営環境を左右する不確定要素
令和6年度改定は6年に一度の、医療、介護、障害のトリプル改定となる。
3年弱続いたコロナ禍の影響や、ウクライナ戦争を起因とした物価高騰など、経営環境が悪化していることから、プラス改定を望む声が増している。問題は、国の政策の中心が少子化対策に大きく舵を取ったことだ。現内閣の重要政策である「異次元の少子化対策」での3.5兆円の財源確保には、社会保障費用の抑制が不可欠とも言われている。すなわち、今後の財政予算の動向に令和6年度介護報酬改定が委ねられているのだ。そして、その結論はまだ見通せない。
現実的には、過去2回と同様に1%に届かないプラス改定となることを予想している。
たとえプラス改定となったとしても、介護職員処遇改善3加算の一本化と加算率の引き上げ、さらには居宅介護支援事業所への処遇改善加算創設の可能性がある中で、これらの増額部分もプラスの改定率と見なされる。そのため、実質的にはマイナス改定となる可能性も高いだろう。
さらに、事業者にとって見過ごせないもう一つの不確定要素が、自己負担2割の対象者の引き上げである。この可否も大きく影響するだろう。
2.通所サービス事業者も多機能型の審議動向に注目を
小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護については、第9期介護事業計画においても、国の重点化サービスである。今回の審議においても、その普及促進策が重要な論点となっている。
また、令和6年度介護保険法において、看護小規模多機能型が機能訓練の場であることが明記された。今後は、機能訓練関連の加算や算定要件の強化が期待される。しかし、小多機と看多機は介護厚生労働省の最重点サービスとして位置づけられているに関わらず、未だに経営が安定しない状況が続いているのも現実だ。その原因のひとつが施設ケアマネジャーの存在とされる。
居宅介護支援事業所のケアマネジャーが利用者を多機能型サービスに紹介する場合、結果として自らの利用者を手放す事になる。そのため、ケアマネジャーは紹介多機能サービスを紹介しづらい構造になっている。
過去の介護報酬改定審議においても、多機能型のケアマネジメントを居宅介護支援事業所に移すことが論点になったが、その結論は出ていない。管理不能となるからだ。未だに多機能型は、“使い放題のサービスである”というイメージが強い。しかし、その契約定員は29人であり、通いサービスの定員は18人が上限となっている。
仮に、多機能型のケアマネジメントを居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担うこととした場合、29人全員が毎日通いサービスを使うケアプランを立ててしまったら、定員18人の通いサービスはパンクしてしまう。
しかし、今回の審議においてもケアマネジメントを居宅介護支援事業所へ移行するよう求める声が多い。施設ケアマネジャーと居宅介護支援のケアマネジャーを利用者が選択できる「選択制」を提案する声も出ている。多機能型のケアマネジメントを居宅介護支援事業所が担当できるとすれば、ケアマネジャーにとっては、介護サービスの選択肢として多機能型を位置づけやすくなり、今まで以上に利用が進むことが期待出来る。そして、今回の介護報酬改定でその可能性が高いと見ている。その場合、通所介護にとっては今まで以上の競合サービスとなり、確実に脅威となる。ケアマネジャーの担当事業所の選択肢に、多機能型が入った場合、これまでケアプランに位置づけてきた訪問介護、通所介護が切られる事になるからだ。
3.通所サービスやケアマネジメントにおけるLIFE活用の促進
通所介護と通所リハビリテーションについては、LIFEの活用と共に自立支援への取組が更に求められる。成功報酬の導入も促進されるだろう。また、令和3年度介護報酬改定で設けられた入浴介助加算の区分Ⅱにおける算定率が10%以下と低すぎることから、この区分創設は「単に報酬を引き下げただけ」だという批判が出ている。令和6年度改定で何らかの対策が取られるだろう。また、大規模減算は、介護事業の大規模化推進の方向に逆行するため、廃止となる公算が強い。
通所リハビリテーションにおいては、前回の令和3年度介護報酬改定において提示された月額包括報酬への移行が導入の可否が注目ポイントになる。3年前に厚労省から提示された原案では、アウトカムの評価指標が設けられて、リハビリテーションの成果が問われる事になっていた。

(第193回社会保障審議会介護給付費分科会で示された資料※令和2年11月16日より)
在宅サービスの介護報酬における成功報酬の導入を検討する上での問題は、在宅サービスは複数の介護サービスによる協働で成立していることにある。
介護施設内で実施されるリハビリには、複数の介護サービスが絡むことは無く、リハビリの成果は、その介護施設の実績であることは間違いない。しかし、在宅での介護は複数の事業者が分業体制で担当するため、その改善の成果を通所リハビリテーションだけに特定することは困難である。そのため、「通所リハビリテーションだけに成功報酬を支給するのはいかがなものか」という意見が出てくるのは当然だ。これは、前回の介護報酬改定審議で、ADL維持等加算を検討する際に出た意見である。厚労省はLIFEによるエビデンスを元にして成功報酬を構築したいと思われるが、その論点が蒸し返された場合、どうまとめて行くのか興味深い。その対応策として、ケアマネジャーによるサービス担当者会議をひとつのチームとして位置づけ、改善や維持をそのチーム全体の評価として成功報酬を設けるなどの工夫も一案だろう。
ケアマネジャーの法定研修は、令和6年度のカリキュラムの見直しが行われる。その中で、多くのカリキュラムに盛り込まれる「根拠ある支援の組み立て」の基盤となる視点として、科学的介護(LIFE)等が重要なエビデンスとなる。
今後はケアマネジメントにおいても、LIFEとの関わりが強く求められることは間違いない。在宅サービス事業者は、一層のLIFEへの対応が急務となる。そして、LIFEの論点にアウトカム評価が盛り込まれた。従来のLIFE関連加算では、プロセス評価に終始し、アウトカムは求められていない。今回の報酬改定で、どのような形でLIFE加算にアウトカムを求めるのか。第2ラウンドの審議に注目である。
4.訪問サービスは人材確保と大規模化がポイント
訪問介護は、有効求人倍率が15.5倍となり、介護職員の確保策が重大な課題だ。これに関連して、外国人研修生の活用を認める等の対策が焦点となってくる。
その審議の中で、訪問介護に外国人研修生の配置を認めるか否かの検討も進められている。現状、多くの意見は反対に傾いている。その理由が、外国人を密室状態でのサービス提供となる訪問介護に認めた場合、「事件事故が起こった場合誰が責任を取るのか」という事だ。しかし、これは明らかに外国人への偏見であり、差別である。今、多くの事件や事故を起こしているのは日本人の介護者である。その折衷案として、まずは有る程度の視野の効く高齢者住宅に限定して認め、その状況によって一般住宅への適用を検討するという意見である。
訪問看護は、「地域包括ケアシステムの更なる深化」という方向性の中で在宅介護における医療行為や看取りを担う重要な位置づけとなる。同時に24時間、365日体制が求められ、看護職員数が20人以上の大規模化策が取られていくだろう。また、これまで同様にリハビリ専門職による訪問リハビリへの規制強化が行われるかも注目される。
5. LIFE加算創設にケアプランデータ連携システムの活用…注目点の多い居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所については、令和6年度から介護予防支援の許認可が可能となった事から、その報酬引き上げが実現するかが注目される。また、令和3年度介護報酬改定審議から引き続き、ケアマネジャーへの処遇改善加算の適用を求める声も強く、その実現が期待される。4月20日からスタートしたものの普及が進まないケアプランデータ連携システムへの加算等での後押しや、LIFE加算の創設なども期待出来る。訪問サービスと居宅介護支援事業所へのLIFE加算の創設は、予算枠の問題もあり、まだ流動的であるとの話も聞くが、令和6年度に改正される法定研修カリキュラムに置いてLIFEに関する項目が相当数、加わることも勘案して、居宅介護支援事業所においてはLIFE加算が創設される可能性が高いと考える。
いずれにしても、令和6年度介護報酬改定審議は折り返し点を過ぎてラストスパートの段階になっている。その審議経過をしっかりと追っていきたい。