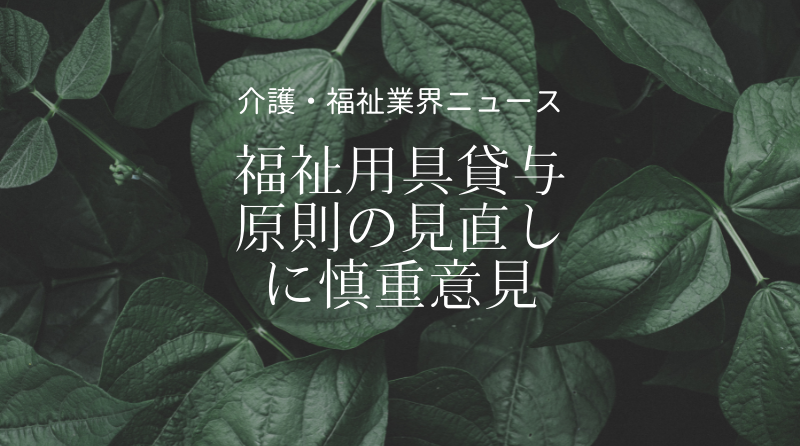【4月22日追記】記事中で紹介した構成員の発言について、誤解を招く表現があったため、記事の内容を修正しました。 立教大学経済学部安藤道人氏の発言(お名前)を削除しています。
厚生労働省は3月31日、第2回となる「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」を開きました。本検討会では「貸与」を基本原則とする介護保険制度上の福祉用具の扱い等が議題となっています。
2月の初会合での議論を踏まえ、厚労省は、「現行制度における福祉用具貸与と特定福祉用具販売の考え方の再整理の必要性」や在宅で生活する要介護者が福祉用具を利用する際の「介護支援専門員による支援」など5つの論点を「着目すべき」ものとして、専門家に意見を求めました。
*関連記事:福祉用具貸与のみのケアプランなどを対象に集中的に検討、厚労省
「福祉用具貸与・販売種目のあり方」議論、これまでの経緯と論点
この検討会は、以下の3点を検討する場として2月に新たに立ち上げられました。
①福祉用具貸与・特定福祉用具販売の現状と課題を踏まえたあり方の検討
②福祉用具貸与・特定福祉用具販売に係る適正化の方策
③福祉用具貸与・販売に関する安全な利用の促進、サービスに質の向上等への対応

【画像】第2回介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会に関する資料(資料2)より
これらの論点は、2021年度の介護報酬改定に関する審議報告でも「今後の課題」として積み残されてきたものです。
今回は、1つ目の議題「福祉用具貸与・特定福祉用具販売の現状と課題を踏まえたあり方の検討」について、前回の意見を踏まえたうえで厚労省が5つの論点を提示。各専門家がこれに沿って意見を述べました。
<今回の論点>
1.現行制度における福祉用具貸与と特定福祉用具販売の考え方の再整理の必要性
2.利用者の状態を踏まえた対応
3.福祉用具の使用に関するモニタリング・メンテナンス等
4.介護支援専門員による支援(ケアプラン作成、モニタリング、サービス担当者会議等)
5.経済的な負担
本稿では上記の5つの論点のうち、論点1および論点4に焦点をあて専門家による意見などをご紹介していきます。
福祉用具「貸与」品目の販売への移行、専門家は安全性に懸念
まずは論点1「現行制度における貸与・販売の考え方の再整理の必要性」についてみていきましょう。
介護保険制度における福祉用具については、「貸与」を原則とし、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、および使用によってもとの形態・品質が変化するものは「販売」とされています。
これは、利用者の身体状況や要介護度の変化や福祉用具の機能に応じて、適時・適切に利用者に提供するための考え方ですが、介護保険制度開始時より変更されていません。この枠組みについて、財政制度等審議会(財務相の諮問機関)の財政制度等分科会は、「要介護度に関係なく給付対象となっている廉価な品目(歩行補助杖、歩行器、手すり等)について、貸与ではなく販売とすべき」と提言してきました。
実際、”廉価な品目”について、2年以上の長期利用者が全体の3割程度おり、その割合が上昇傾向であるデータも示されています。

【画像】第2回介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会に関する資料(参考資料1)より
しかし、日本福祉用具・生活支援用具協会から出席した松永茂之氏(花岡徹構成員の代理で出席)は、廉価な品目として示された移動補助具について、「経年劣化による不具合はケガに直結する」ことに触れ、貸与が安全面の維持に寄与している点を強調しました。さらに、貸与から販売に移行することで、コストカットが重視された安全性の劣る商品開発を促進する可能性にも言及。他の複数の専門家からも、安全面を懸念する声や、販売後のアフターフォローの縮小を危惧する意見が目立ちました。
また、現行で販売種目に指定されている入浴・排泄関連用具について、公共トイレや温浴施設と同様に消毒管理を徹底することで貸与へ移行できるのでは、との意見も聞かれ、これを踏まえた制度の再整理の提案もなされました(東畠弘子・国際医療福祉大学大学院福祉支援工学分野教授)。
介護支援専門員による福祉用具利用者の支援は”貸与でも自己負担でも同程度とすべき”との声も
次に論点4「介護支援専門員による支援」についてです。現行では、福祉用具購入費の支給対象者は居宅介護支援(介護予防支援)の対象外であり、他の介護保険サービスを受けていない場合は 、ケアプラン作成の対象外となっています。
また、財政審は、「ケアマネジメントのうち、福祉用具の貸与のみを行うケースについては、報酬の引き下げを行うなどサービス内容に応じた報酬体系とすることを、2024年度報酬改定において実現すべき」と提言しています。
当日は、介護支援専門員が介護保険サービスの利用を福祉用具貸与のみと判断する要因として、「他のサービスの必要性がない」、「利用者や介助者の希望」、「介護拒否等がある」とのデータが提示されました。

これについて、一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会理事長の岩元文雄氏は「利用者の中には、人との関わりや交流、他のサービスの利用を嫌う人もいる。孤立しがちな利用者も福祉用具の貸与がケアプランにあるからケアマネによる支援ができている」と指摘し、福祉用具の在り方を見直す際に利用者や介助者にとって不利益になるべきではないと主張しました。
また、健康保険組合連合会理事の幸野庄司氏らはそもそもの現行制度に対して疑問を呈したほか、貸与でも販売(自己負担)でも、介護支援専門員による同程度の支援を実現していくべきであるとの見解を示しました。
制度の見直しに慎重な議論を求める声が大多数、次回も検討継続
本稿では論点1、論点4を中心とした議論内容を紹介しましたが、他の論点とも複雑に絡み合う5つの論点全般に関して、変更には慎重な議論を求める声が大多数を占めました。
次回は、4月21日に第3回同検討会の開催が予定されています。今回の議論では多くの課題に道筋が立っていないことを踏まえ、次回会合にて継続議論される予定です。