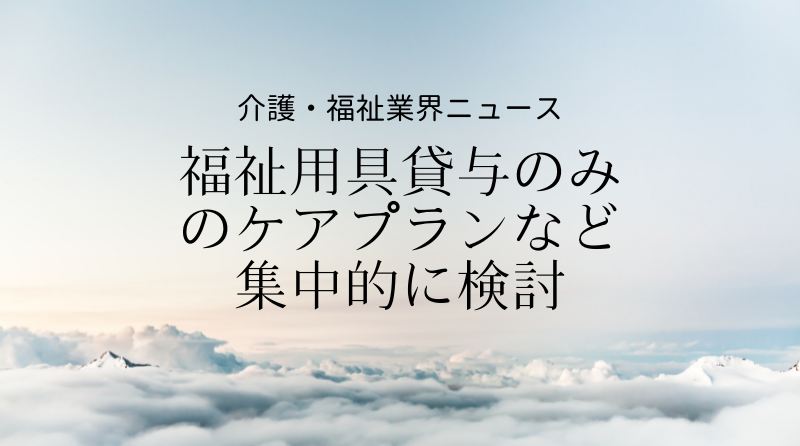厚生労働省は2月、介護保険の給付対象である福祉用具の在り方について検討を始めました。新たに設置された検討会では、「貸与」を基本原則とする介護保険制度上の福祉用具の扱いについて議論するほか、財務相の諮問機関が介護報酬の引き下げを求めている福祉用具貸与のみを位置付けるケアプランの扱いも議題となっています。
「福祉用具貸与・販売種目のあり方」が議論の俎上に上がった背景と経緯
厚労省は今回、介護保険制度における福祉用具の貸与・販売種目に関する課題や現状について検討し、根本的な「あり方」を検討する場を設けました。それが、2月17日に初会合が開かれた「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」です。
この検討会が開かれた背景には、財務相の諮問機関・財政制度等審議会が社会保障費を抑制するために、介護や福祉・医療サービスの提供側の視点とは異なった立場から介護保険制度の改革について提言を続けていることがあります。
近年の提言では、以下のように福祉用具の在り方についても踏み込んだ検討や対応を求めています。
・杖や歩行器、手すりなど要介護度に関係なく給付対象となっている品目を貸与ではなく販売とすべき。また、それによって毎月ケアプラン作成時にかかる費用を不要とすることが考えられる。(令和2年11月25日・令和3年度予算の編成等に関する建議)
・ケアマネジメントのうち、福祉用具の貸与のみを行うケースについては、報酬の引き下げを行うなどサービス内容に応じた報酬体系とすることを、2024年度報酬改定において実現すべき(令和3年5月21日・財政健全化に向けた建議)
また、財制審の提言の中では、ケアマネジャーはインフォーマルサービスの調整を行うだけでは報酬を受け取れないことから、「介護報酬算定のため、必要のない福祉用具貸与等によりプランを作成した」ケアマネジャーが一定数存在したという調査結果が出ていることについても指摘があり、これが問題視されています。


【画像】財政審で示された資料(上、2020年11月2日:下、2021年4月15日開催分より抜粋)
財制審の指摘を受け、2021年度介護報酬改定に向けた検討の場でも保険給付対象となる福祉用具を貸与から利用者による購入への運用の切り替えなどについて、対応が話し合われました。しかし、この議論を進めるには福祉用具の利用者の状態に応じた、”適時・適切な利用”や”安全性の確保”など考慮すべき要素が多く、今後の継続検討事項として持ち越されていました。
今回の検討会では、福祉用具の利用実態をしっかりと把握しながら、現行制度(貸与原則)の在り方や対応について改めて検討を進めていく方針です。
福祉用具の「販売制度導入」含めた適正化に向け、軽度者の利用状況など共有
厚労省は初回の主な論点として
・福祉用具貸与と特定福祉用具販売の整理について、介護保険法施行時と現在の状況などのちがいを踏まえ、どのように考えるべきか。また、福祉用具貸与を利用している者に対するケアマネジメントについて、どのように考えるべきか。
・福祉用具貸与等における販売制度導入を含めた適正化方策について、どのような取組が考えられるか。
・福祉用具貸与等における安全な利用の促進、サービスの質の向上について、どのように取り組んでいくか。特に、事故発生情報の活用や福祉用具貸与事業所等における連携、福祉用具専門相談員の質の向上、事業所におけるサービスの質の向上に向けた取り組みについて、どのような事が考えられるか
の3つを示しました。
その中には、
・在宅系サービスのうち、福祉用具貸与の利用者は居宅介護支援に次いで多く、給付者の約6割以下が要介護2以下である
・手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえの4種目は、軽度者(要支援1〜要介護1)による利用が多い種目となっている。
といった、軽度者の利用状況に着目したデータが含まれています(※以下の画像)。




【画像】第1回介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会に関する資料(資料2及び参考資料1より
福祉用具貸与の効果はマクロでの評価が必要、専門家からは慎重な検討論
福祉用具貸与にかかる給付費用を抑えるという点を優先して考える場合、先に紹介した財政審の指摘のように
・貸与から販売(自己負担)に切り替える
・ケアマネジメントに対する評価を引き下げる
といった方法は一見すると有効な手法として考えられます。
しかし、これは福祉用具の利用に直接かかっている費用だけを個別に取り上げて考えた場合で、介護保険サービス全体でかかる費用を考えると、福祉用具のみの利用者が多く存在しているということは、財政面でも、「大きな効果をはたしているのではないか」(小野木孝二一般社団法人 日本福祉用具供給協会理事長)という見方もあります。
福祉用具の適切な利用によって多くの高齢者がより重度の状態へ移行するのを防ぎ、在宅介護などそのほかの人的サービスを使わずに自立した生活を継続できているという主張です。
実際、当日は福祉用具の長期利用者のうち、1種類の品目だけを使い続けている利用者の半数以上が、要支援・要介護度を「維持」できているというデータも示されました。

【画像】第1回介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会に関する資料・参考資料1より
このほかにも、現在貸与が原則となっている福祉用具の制度を抜本的に見直すのであれば、利用者の多くを占める「要支援2要介護1の状態像について議論が必要」といった指摘などがありました(岡田進一・大阪市立大学大学院生活科学部教授)。
この層の多くはMCI(軽度認知障害)や骨粗鬆症の問題を抱えていて、制度変更があればその状態にも変化が起こってくる可能性があり、今後も後期高齢者人口が増えてくるというトレンドは変わらないことを考えると、慎重に議論する必要があるという見方です。
さらに、濱田和則構成員(一般社団法人日本介護支援専門員協会副会長)は一見、「福祉用具貸与のみを内容とするケアプラン」であっても、実際には基礎疾患のある利用者のための医療機関との連携や行政機関や金融機関における手続きの支援、入退院時の支援など、ケアプラン(特に第2表)には記載されていなくても複数・複雑な支援が行われている場合があるなどと指摘しています。まとめられたケアプランの内容だけを判断材料にして、報酬について一律に線引きをする施策に対しては明確な懸念を示しました。
本検討会の今後の予定としては、今年夏にも中間的な整理を行い、その内容を介護保険法や制度改正について話し合う社会保障審議会・介護保険部会などに示す方向で調整が進められているところです。