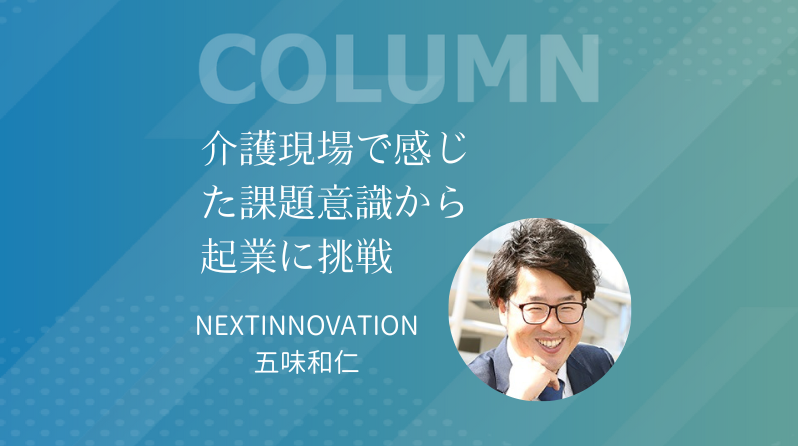私は、介護現場で働いてきた経験を元に、“企業と職員・その家族をサポートする総合介護サービス”をコンセプトとした事業を展開しています。具体的には、望まない介護離職を減らすための個別相談や実態調査、セミナー企画などを展開する事業を手掛けています。「介護に希望が持てるような支援をしたい」という思いを足掛かりとして2019年に起業しました。
介護現場出身・駆け出し起業家の立場から、事業構築や営業活動の実体験や現場の視点が生きた経験をお伝えします。
介護に希望が持てるような支援を目指して起業の道へ
私と介護業界との関わりは、介護保険制度が創設された2000年に遡ります。「成長分野で働こう」と専門学校に通い、知識や技術を学びました。その後、老人保健施設や特別養護老人ホーム、デイサービスなどの現場で働くなかで、やりがいや楽しさを感じると同時に問題点も数多く見えてきました。
介護サービスは人を相手にする事業であり、そのニーズは無限に広がります。
しかし、大きい施設に所属していると、そのルールに縛られて柔軟な対応が難しくなり、いいアイデアや改善点が浮かんでも実践できるまでに時間がかかることもあります。こうしたとき、もやもやした気持ちを抱く従事者は多いのではないでしょうか。
私の場合、「現場で生じる課題を一つずつ解決していくだけでなく、介護に関係する人や社会を俯瞰的に見て、幅広いニーズに応えられる事業を展開したい」という思いが日々強くなっていきました。特に、介護が必要になるとたいていの方がネガティブな気持ちになることに強く課題意識を感じています。今までの経験を活かしつつ、「諦めでなく希望がもてるような支援をしたい」という想いを形にするには、起業するしかないと決断しました。
老人ホーム紹介事業を始めた矢先のコロナ禍
起業して最初に始めたのは老人ホームの紹介事業でした。介護を必要とする本人やご家族の多くは、ニーズに合った施設を探すのに苦労されます。
彼らにとって初めての経験で、「どこに何があるのか分からない」、「様々な施設の種類があるが、違いが分からない」といった不安が大きいようです。また、親戚や知り合いからの紹介で入居された場合、紹介してもらった手前、ニーズに合わなくても断れないということもあります。
さらに、「介護」や「老人ホーム」といった言葉にネガティブなイメージを持ち、身内の困りごとを相談しにくいと感じる方も多くいます。
そこで私は、こうした課題を解消し、ご利用者、ご家族のニーズに合った老人ホームを紹介する、コンシェルジュのようなサービスを設計しました。
しかし、滑り出しは順調だったのですが新型コロナウイルスの感染拡大で多くのホームが新規入居をストップしてしまいました。起業後まもなく迎えた予想外の展開に、どうしようもなく不安だったことを鮮明に覚えています。
“家族の支え”というニーズに着目「介護離職の予防」を新たな中心事業に
介護業界で働いた経験しか持たない私は、超高齢社会として抱える課題から事業創出に繋がるものはないか模索を続けました。過去の利用者との関わりを振り返る過程で、介護されるご本人だけでなくその家族も様々な課題や不安を抱えていることに気づきました。
突然介護が必要になることで、本人だけでなくその家族の生活も一変し、先の見えない不安に包まれるのです。
介護保険制度が始まり23年経ちさまざまな支援体制を構築してきましたが、介護を担う家族の相談ができる場所は未だほとんど無いように感じます。家族の相談ができる場所はあるものの「身内の介護の話は他者に話しにくい」という感情から一人で抱え込んでいる方も多くいらっしゃいます。その結果、精神的に病んでしまう家族をたくさん見てきました。
そこで、こうした困りごとを抱える家族の相談先を作り、介護への備えをサポートすることを新たな事業の一環とすることに決めました。
この事業を考えるにあたりもう一つ思い当たったのが、急増している介護離職という社会課題です。福利厚生の一環として、職員の介護離職防止を弊社が支援することに価値を感じてくれる企業も多いのではないかと考えました。
しかし、一般企業との繋がりが薄かった私は、どうやってその繋がりを構築していけばいいのか悩みました。そこで、地元の中小企業が集まるコミュニティに顔を出し、事業を知ってもらうために幅広い企業の経営者と会うことから始めました。その後、知り合いの経営者を紹介してもらったり、直接企業に連絡したりするなど、様々な方法を使いアプローチを続けました。
“介護離職ゼロ”―国のスローガンと経営者の認識の間にあるギャップ
さまざまな企業の経営者と接点を持った後はそのうち10社ほどを訪問し、経営者や総務の方からヒアリングを行いました。スーパーマーケットや製造業、警備会社などジャンルや規模を問わずに介護離職への認識や対策を伺いましたが、その全ての会社で職員の介護離職を防止する対策や、実際に介護の問題を抱える従業員の支援はできていませんでした。
その多くに共通していたのは、
- 今までに親の介護が原因で退職された方がいること
- 備えは必要だとは分かっているが、従業員任せになっていること
- 実態調査は行っておらず現状従業員が介護に不安を持っている人が何人いるかも分からない
ということでした。
経営者は従業員の介護リスクを“身近な問題”と捉えていても、どこか他人事で危機感は薄いように感じました。そして、この結果こそ、国が掲げる「介護離職ゼロ」というスローガンと現実のギャップが生まれる理由であると感じました。
ヒアリングの過程では、企業が従業員の介護問題について触れない理由も伺っています。
それは、従業員が抱える問題の実態を把握したり、実際に悩みや相談を受けたりしたところで介護に精通した人間が社内にいないため、「どう対応したらいいか分からない」、「結果として不安を煽り、逆効果になってしまう」ということでした。
また、「介護は個人の悩みだから、会社はそこまで対応できない」とはっきり話されるところもありました。
介護保険制度の正しい理解が離職を防いで初契約に
その後もめげずに企業訪問を続ける中で、ついに契約につながる出来事がありました。
ご縁をいただいた企業から、「従業員でまさに今介護に悩んでいる方がいるから、一緒に話を聞きに行って欲しい」とご依頼を受け、同行させて頂いたのです。
当日は、総務部長にも同席して頂き、私が従業員から相談に応じる姿を見てもらいました。
従業員の状況は以下の通りです。
- 要介護状態にある母親の退院が決まり、自宅で受け入れる必要があるが、何から手を付けていいのか分からない
- 現状、自分たちが介護するしかない
- 介護保険でベッドをレンタルできることを知らず購入した
- 退勤後の負担が大きく、仕事との両立が難しい
この従業員は、当時退職を考えていました。
しかし、介護保険制度は家族の負担軽減も担っています。うまくサービスを使えば、その方に合った働き方も考えていけるはずです。
この事例のように、介護保険制度を利用したことがない方は、具体的なイメージが湧かずに一人で悩みを抱え込んで「退職」を検討することがあります。しかし、知識を身につければ具体的な対応も考えることができます。
このときは、企業側にも従業員向けの相談窓口の必要性を理解してもらうことができ、契約をいただきました。そして、弊社の事業モデルは山梨県で唯一の事業形態ということもあり、この時の様子は地元の新聞にも掲載して頂きました。
次回は、ここまで手探りだった自社のサービス内容や方針を明確に定めていくまでの過程や今後の展望についてお伝えします。