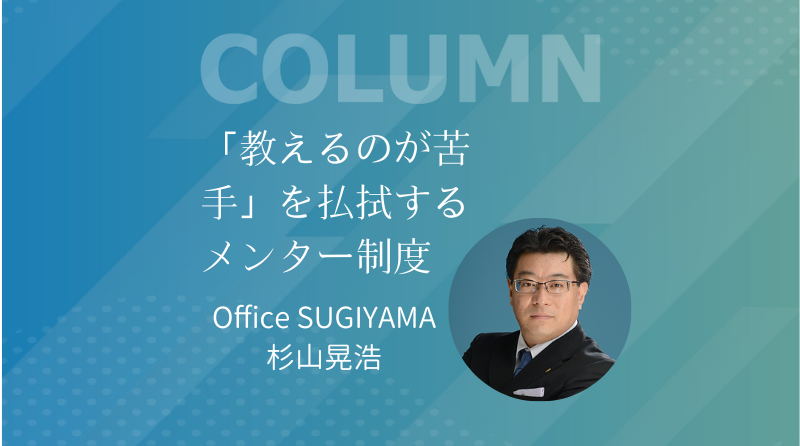策定の義務化が2024年に迫っているBCP。作成手順などの情報はあふれていますが、いざとなったときに誰もが見て動くことができる現場マニュアルはできていますか?
これまで各所からBCPとは別に、こうした実用のためのマニュアル作りに困っているという相談を頂いています。そこで、今回は、災害などが起きた時、誰が見ても実践に移せる”シンプルなマニュアル”をどうやって作成するか、考え方をお伝えします!
BCP作成に向けて陥りがちな失敗パターンとは
- BCPの作成に取り組まれた皆様は、以下のようなお困りごとに直面したのではないでしょうか。
- ・計画に記載している文章量が多すぎて分かりづらい
- ・策定している内容が複雑すぎて実際には使えない
- ・重要業務などの優先順位が付けられていない
このような要素が1つでも該当している計画は現場での運用が困難です。
BCP作成で優先すべきことは「必要な人が、必要な内容を、必要な時に使えるようにすること」です。
それでは、この目的を達成するための考え方と作成方法について紹介していきます。
原因事象アプローチと結果事象アプローチという考え方
原因事象アプローチとは
原因事象アプローチとは、「感染症」「地震」「火災」「風水害」などの業務継続を困難にする要因に対して、個別に対策(マニュアル)を記載する方法です。
現在厚労省や全国訪問看護事業協会が示しているBCPの作成方法やマニュアルはこの方法を採用しています。全体を網羅しており、抜けがないという利点はありますが、マニュアルの数が原因の数だけ膨らみ、膨大な資料になってしまうという欠点があります。
マニュアルの数が増えれば作成する側はもちろん内容を覚える側にも負担がかかります。訓練する内容も増え、1年以内に全部行う事はできなくなります。 そして、こうしたアプローチのリスクとしてしっかり認識しておかなければいけない事は、マニュアルにない「想定外」の出来事に対し、対応が取りづらいことです。
災害下では、想定外の出来事が連続して起こります。
結果事象アプローチとは
これに対して、結果事象アプローチとは、業務継続が困難となる原因の違いに関わらず、起こる結果は共通しているという観点からマニュアルを作成することです。
災害にしろ、感染症にしろ、事業困難となる出来事は結果として以下の3つに集約されます。
- ・社員が出社不能になる(人員不足)
- ・事業所と設備が利用不能になる
- ・情報システムが利用不能になる
有事のリスクはこの3つに集約されると考えれば、最小限のマニュアル・対策で済みます! 表1は結果事象とその対応例です。

【表1】
シンプルなマニュアルを作る意義
シンプルなマニュアルが必要な理由
これまでに何度か、阪神・淡路大震災や東日本大震災のような大災害を経験された方とお話させて頂きました。彼らが共通しておっしゃる事は
「マニュアルなんて見る時間がなかった」「マニュアルは、災害が落ち着いた後になって対応がちゃんとできていたかチェック程度にしか使わなかった」
「何か起きたときはこれを見て対応すればいい」という認識では想定が甘いのです。それでもマニュアル必要ならば、可能な限りシンプルにすべき、という考え方が大切です。
シンプルなマニュアルの要素とは
BCPに最低限必要な要素は以下の3つです!
- 基本方針(全部門・全社共通)
- 基本手順(全部門・全社共通)
- 個別マニュアル
あとは従業員や職場環境に応じて必要な内容を追加して作っていきましょう
1.基本方針と2.基本手順については、以前ご紹介した超簡易版BCPでほぼ対応できます。
まだ読んでいない方はこちらもお目通しください。
訪問看護BCP策定の手順解説~初めの一歩のハードルを下げる便利ツール~
- 社員の不足で起きる問題
- 事業所や設備が使えずに起きる問題
- 情報システムの利用が出来ずに起きる問題
への対策です。
まずはこの3つの問題に対するマニュアル作りから早めに着手していきましょう。
その他追加で作るとすれば、感染症ごとの出社基準や予防方法などのガイドラインや既存であるマニュアル内容を組み込むと良いでしょう。
BCPの策定完全義務化を前に意識したい「最も大切なこと」
BCP作成までの猶予期間はもう少しで終わります。
計画の作成において一番大切なことは「完璧なマニュアルを作ること」ではなく、「皆が活用できるマニュアル」を用意することです。
作成しながらスタッフに共有してみる、皆が興味を持ちそうな内容から研修を開催する、といったイメージで皆が参加したいと思える工夫を取り入れ、修正を加えながら作成を進めて下さい!