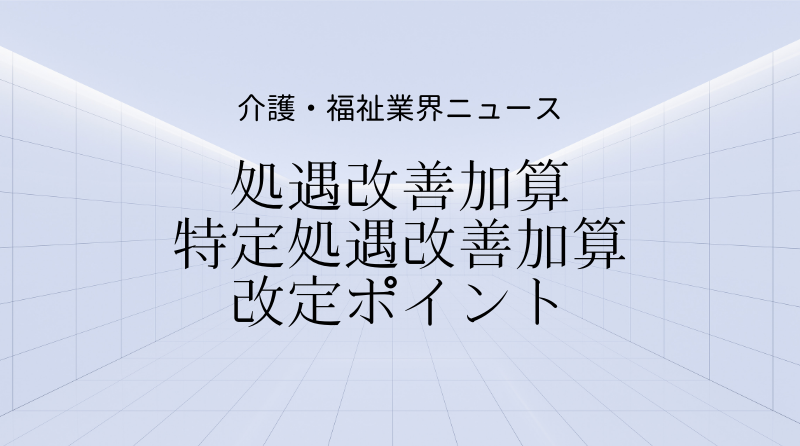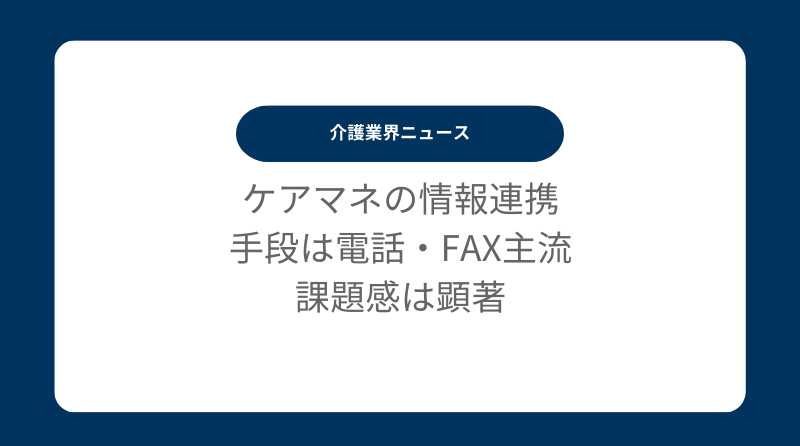2021年度の介護報酬改定で、介護職員処遇改善加算(以下、処遇改善加算)と介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定処遇改善加算)について、配分ルールや職場環境等要件等に関する見直しが実施されました。2021年3月までの内容と、2021年4月からの改定後の内容を比較して、変更点を整理しておきましょう。
*22年度アップデート情報:介護職員等ベースアップ等支援加算と処遇改善加算、特定処遇改善加算の違いを比較
2021年度報酬改定の変更ポイント
①特定処遇改善加算の配分において、経験や技能のある職員をその他の職員の「2倍以上」とする配分ルールを、「より高くする」に弾力化
②職場環境等要件の施策内容がアップデート。処遇改善加算、特定処遇改善加算のどちらも、施策の実施を強化
③処遇改善加算Ⅳ・Ⅴは廃止へ。今後の新規取得は不可、取得している事業所のみ2022年3月まで継続可能で、2022年度に完全廃止
関連記事:介護保険最新情報Vol.935「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(2021年3月16日通知)
特定処遇改善加算の配分ルールの弾力化
事業所内でのより柔軟な配分を可能とする観点から、平均の賃金改善額の配分ルールについて、介護職員間の配分ルールが一部弾力化されました。
賃金改善の対象となるグループ
・「経験・技能のある介護職員」:介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者(※)
・「他の介護職員」:「経験・技能のある介護職員」を除く介護職員
・「その他の職種」:介護職員以外の職員
※勤続年数10年以上の介護職員を基本としつつ、現場での業務を勘案して、事業所の裁量で設定
2021年3月までの配分ルール(変更点は下線)
下記の規程内にて、一人ひとりの賃金改善額は、柔軟な設定が可能。
①「経験・技能のある介護職員」のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額平均8万円以上、または年額440万円以上であること
②「経験・技能のある介護職員」の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、「他の介護職員」と比較し、2倍以上であること
③「他の介護職員」の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、「その他の職種」の2倍以上であること
④「その他の職種」の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと
2021年4月からの配分ルール(変更点は下線)
下記の規程内にて、一人ひとりの賃金改善額は、柔軟な設定が可能。
①「経験・技能のある介護職員」のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額平均8万円以上、または年額440万円以上であること
②「経験・技能のある介護職員」の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、「他の介護職員」と比較し、より高くすること
③「他の介護職員」の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、「その他の職種」の2倍以上であること。ただし、「その他の職種」の平均賃金額が「他の介護職員」の平均賃金額の見込額を上回らない場合はこの限りでない(記事下部に関連Q&Aあり)
④「その他の職種」の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと

「経験・技能のある介護職員」が「その他の介護職員」と比較して「2倍以上」という制限がなくなり、「より高くすること」に弾力化されたことで、事業者の裁量に応じた、より柔軟な配分が可能となりました。
職場環境等要件の施策実施の強化
職場環境改善の取組みをより実効性の高いものとする観点から、「職場環境等要件」として求められる取組み事項が更新されました。また、2021年3月までは、事業所における過去の取組みを含められましたが、4月以降は年度ごとの実施が求められます。
2021年3月までの「職場環境等要件」
●処遇改善加算
賃金改善以外の処遇改善の取り組みを実施すること。加算Ⅰ・Ⅱについては2015年4月から現在まで、加算Ⅲ・Ⅳについては2008年10月から現在までに実施した事項について、全ての介護職員に周知していること(加算Ⅴは職場環境等要件なし)。
●特定処遇改善加算
「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の各区分について、1つ以上の取り組みを行っていること。
| 資質の向上 | ●働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む) ●研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 ●小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 ●キャリアパス要件に該当する事項(キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る) ●その他 |
| 職場環境・処遇の改善 | ●新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等導入 ●雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実 ●ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化 ●介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入 ●子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備 ●ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 ●事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化 ●健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備 ●その他 |
| その他 | ●介護サービス情報公表制度の活用による経営 ●人材育成理念の見える化 ●中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等) ●障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮 ●地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上 ●非正規職員から正規職員への転換 ●職員の増員による業務負担の軽減 ●その他 |
2021年4月からの「職場環境等要件」
●処遇改善加算
職場環境等要件の施策の中から、いずれか1つ以上の取組みを実施すること。年度ごとに実施が必要。特定処遇改善加算の施策と重複可。
●特定処遇改善加算
「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性向上のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの醸成」の6区分について、それぞれ1つ以上の取り組みを実施すること。(2021年度は6区分から3区分を選び、それぞれ1以上の実施で算定可能となる特例あり)
年度ごとに異なる新たな取組みを行う必要はなく、前年度と同様の取組みを当該年度に行うことで、要件を満たすことが可能。(介護保険最新情報のVol.941 Q&Aより)
| 区分 | 内容 |
| 入職促進に向けた取組 | ●法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 ●事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 ●他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 ●職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 |
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ●働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 ●研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 ●エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 ●上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 |
| 両立支援・多様な働き方の推進 | ●子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 ●職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 ●有給休暇が取得しやすい環境の整備 ●業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 |
| 腰痛を含む心身の健康管理 | ●介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施 ●短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 ●雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施 ●事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 |
| 生産性向上のための業務改善の取組 | ●タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 ●高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 ●5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 ●業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 |
| やりがい・働きがいの醸成 | ●ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 ●地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 ●利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 ●ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
計画書・報告書の様式ダウンロード(厚労省ホームページ)
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(入力用)
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(記入例)
介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(入力用)
介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(記入例)
処遇改善加算Ⅳ・Ⅴの廃止
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、2021年3月31日で廃止となりました。2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業所については、1年の経過措置期間が設けられます。2022年度には完全廃止となります。
関連Q&A(介護保険最新情報Vol.941、946、952)
Q.事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の介護職員」を設定せず、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。
事業所ごとに、「経験・技能のある介護職員」のグループを設定することが必要であるが、介護職員の定着が進み、勤続年数が長くなったこと等により、当該事業所で働く介護職員全てが、「経験・技能のある介護職員」であると認められる場合には、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることも想定される。
この場合における配分ルールについては、当該事業所における「経験・技能のある介護職員」の平均賃金改善額が、「その他の職種」の平均賃金改善額の2倍より高いことが必要である。
Q.事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の賃金改善額を上回らない場合等はこの限りでないこと。」とは、どのような意味か。
その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合においては、柔軟な取扱いを認め、両グループの平均賃金改善額が等しくなる(1:1)までの改善を可能とするものである。
なお、その他の職種全体では他の介護職員の平均賃金額を上回る場合であっても、その他の職種のうち、他の介護職員の平均賃金額を上回らない職種については、当該職種に限り、他の介護職員と平均賃金改善額が等しくなるまでの改善を行うことも可能である。
Q.介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、月額8万円の改善又は年収440万円となる者を2人設定する必要があるのか。 また、その場合の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額1:1:0.5)はどのような取扱いとなるのか。
事業所において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に行っており、同一の就業規則等が適用される等労務管理が同一と考えられる場合は、法人単位の取扱いを適用するのではなく、同一事業所とみなし、下記により特定処遇改善加算の算定が可能である(介護給付のサービスと予防給付のサービスについても同様)。
・ 月額8万円の改善又は年収440万円となる者を1人以上設定すること
・ 配分ルールを適用すること
また、特別養護老人ホーム等と併設されている又は空所利用型である短期入所生活介護、介護老人保健施設等と短期入所療養介護についても、同様に判断することが可能であるとともに、これらについては、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設等が特定処遇改善加算を算定している場合において、短期入所生活介護等においても、同じ加算区分を算定することが可能である。
Q.職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善の内容を全ての職員に周知していることとあるが、毎年度新たな取組を行わなければならないのか。
計画期間における取組の実施が求められることとされたが、これは毎年度新たな取組を行うことまで求めるものではなく、前年度と同様の取組を当該年度に行うことで、当該要件を満たすことも可能である。
Q.新型コロナウイルス感染症への対応として、介護職員に対し、臨時的に慰労金や手当等を支給した場合、実績報告書や処遇改善計画書において、どのような取扱いとなるのか。
加算による収入額を上回る賃金改善を行うことを担保する仕組みとして、実績報告書及び処遇改善計画書の作成を求めており、職員に支払いを行った賃金については、実績報告書及び処遇改善計画書に記載することが必要である。
一方で、慰労金は賃金に該当しないものであり、実績報告書及び処遇改善計画書における賃金にも含める必要はない。
なお、事業所において、独自に新型コロナウイルス感染症への対応として、通常の昇給等による基本給の増加や手当の支給等とは別に、臨時的・特例的に慰労金と同趣旨の賃金の支払いを行っている場合、実績報告書及び処遇改善計画書における賃金に含まない取扱いとして差し支えない。通常の賃金増とは明確に区別を行う必要があるとともに、職員から当該取扱いに係る質問があった場合は、丁寧に説明を行う必要がある。
Q.共生型介護保険サービス事業所についても、算定要件を満たせば算定可能か。
算定可能。
Q.共生型介護保険サービスを提供する障害福祉サービス事業所においては、人員配置基準上、介護職員の配置は求められていない。加算算定にあたり、当該障害福祉サービス事業所のホームヘルパーや生活支援員等の「福祉・介護職員」を介護職員とみなすこととして差し支えないか。
差し支えない。
Q.職場環境等要件に基づく取組として「介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施」が設けられたが、 新たに取組みを行うにあたり参考にできるものはあるか。
介護職員の腰痛予防対策の観点から、「職場における腰痛予防対策指針」(平成25年6月18日付基発0618第3号)参考2別添を公表しているので、参考にされたい。
関連記事
Vol.941 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1(令和3年3月19日)」の送付について
Vol.946 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)
Vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3(令和3年3月26日)」の送付について
図引用:第199回社保審・介護給付費分科会「資料1令和3年度介護報酬改定の主な事項」より