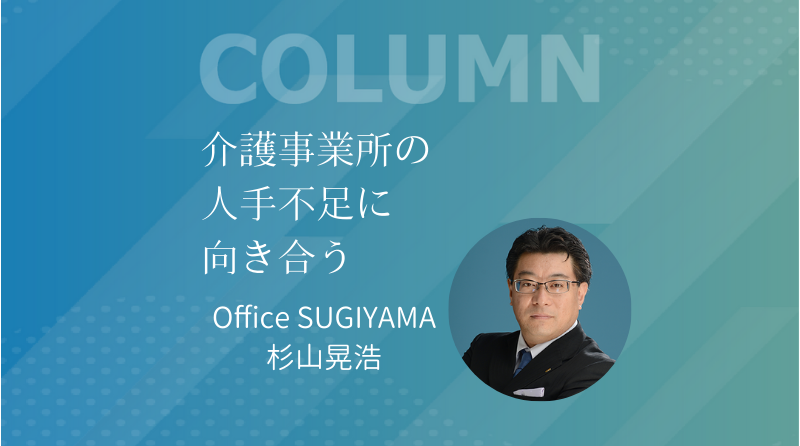1.人材争奪戦の介護業界、積極的な採用戦略を
介護事業所から、「ハローワークに求人を出しているけど応募がない」、「人材紹介会社にお願いしているけど良い人が来ない」といった相談が後を絶ちません。
公益財団法人介護労働安定センターが行った『令和2年度介護労働実態調査 介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書』のデータを参考に、介護事業所の実態を数値化してみます。
『不足感の推移(職種別)』(図1)のグラフを見ていくと、訪問介護員、介護職員、事業所全体の全てにおいて、不足感は前年より改善方向にあることが読み取れます。しかしながら、介護業界としては、訪問介護員で8割、介護事業所全体で6割の人手不足が顕在化しています。
そして、人手不足を感じている多くの介護事業所が、良質な介護労働者を巡って争奪戦をしています。この争奪戦に巻き込まれているために、「採用が困難である」と感じているのです。
裏を返せば、訪問介護員では2割、介護事業所全体では4割で、必要な人員の確保ができているのです。これらの介護事業所は、人材争奪戦に巻き込まれることなく採用が上手くできているといえます。

ところで、人手不足の理由として、86%が「採用が困難である」と回答しています。さらに「採用が困難である」と判断した理由を掘り下げると、「他産業に比べて労働条件が良くない」が53%、「同業他社との人材獲得競争が厳しい」も同じく53%の回答となっています。
ここで考えてみたいことは、介護事業経営者のみなさまが、採用が困難になってしまう原因について、その原因を解消すべくアクションを起こしているかどうかです。
もしかしたら、「当社で他の産業以上の給与を支払うことなんて考えられない」、「当社は他の施設のように財政が豊かじゃないから…」などと、採用についてネガティブになってしまってはいませんか。その結果、採用について考えることを止めてしまっているのではないでしょうか。採用を諦めた瞬間に、企業力は一気に下がります。人手不足スパイラルが加速し、廃業や倒産がグッと近づくと理解してください。
2.人的資源への考え方を明確にして求人に反映する
経営には「ヒト」「モノ」「カネ」が必要だと言われます。
言い換えれば、経営とは、これらの3つを上手に活用して利益を生み出すことです。
この枠組みの中における採用とは、自社の経営に必要な「ヒト」という資源を仕入れることだと考えられます。
わかりやすいように「モノ」を仕入れる場合に置き換えて考えてみましょう。
「モノ」の仕入れでは、良質な原材料を仕入れることができれば、良質な商品を生み出すことにつながります。良質な商品であれば、高い値でもよく売れ、利益が多く残せるようになります。
それでは貴社では「ヒト」という資源に対してどのようにお考えでしょうか。次のA~Dの資源について、仕入価格を決めてみましょう。
A いつでも替えがきく、単なる労働力
B 欠員がでたら(でそうなら)補充すべき労働力
C 欠員とならないように定着してほしい労働力
D 会社の理念・ビジョンに共感し、会社の中期的な計画目標を理解し、将来長期間にわたって活躍してほしい労働力
値段と内容を勘案し、どの程度の労働力を、どのくらい経営資源として仕入れたいのかを考えてください。
その答えが求人内容となり、貴社の採用戦略を練る上でのベースとなります。
3.3年後の”未来組織図”をつくる
戦略とは、目標を達成するためのアクションプランです。目標がなければ戦略が作れません。採用戦略を練る上でも同様です。ここでは「ヒト」という資源に関する目標を作ってみます。
「ヒト」に関することですから、まず最初に現在の組織図を作成してください。組織図には、部署部門ごとにスタッフの氏名と年齢も書き入れておきましょう。
次に、3年後の貴社の事業がどのようなものになっているべきなのか、全ての目標を達成していることを前提として頭の中でイメージしてください。そのイメージを基に、3年後の未来組織図を作成してください。現在の組織図と同様に、部署部門ごとにスタッフの氏名と年齢を書き入れます。
例えば、3年後に施設が新たに1つ増えているとイメージするならば、そこでは何人のスタッフが必要でしょうか。そのうち有資格者は資格ごとに何人必要でしょうか。管理職は何名必要でしょうか。バックヤードの体制はどのようになっていますか。今いるスタッフのうち、新たな施設に関わるのは誰ですか。3年間のうちに新たに有資格者となるスタッフは誰ですか。3年間のうちに定年を迎えるスタッフはいませんか。3年経たずに退職しそうなスタッフはいませんか。
作り上げた3年後の未来組織図に記載されている名前の横には、現在より3歳年齢を重ねたスタッフの年齢が書かれています。つまり、組織が3歳年老いたことになります。「ヒト」は、年齢を重ねると成長しますし、衰えもします。未来組織図に氏名と年齢を書きこむことで、未来の職場の状況がはっきりと頭の中に浮かびませんか?
3年後の未来組織図には、多くの空欄も存在しています。新しい施設ができれば、現状よりも多くのスタッフが必要になります。これらの空欄を埋めるために、採用戦略が必要となるのです。
4.”未来組織図”を実現するための3つのステップ
3年後の未来を現実のものとするためには、次のことを計画立てて実行しなければなりません。
1.今いるスタッフが離職しないための環境づくり
2.今いるスタッフが成長するための教育
3.新しい施設を運営するために必要なスキルをもった人材の採用
例えば、今いるスタッフが離職しないための環境づくりをするのであれば、何をしなければいけないかを考えることから始まります。「処遇改善加算、特定事業所加算を活用して報酬を上げる」、「人事評価制度を導入して仕事内容と報酬に納得感を得てもらう」、「年次有給休暇を利用しやすい雰囲気をつくる」、「スタッフの声を聞くために従業員満足度調査を行う」など、やるべきことは山ほどあります。これらのアクションプランを全て文字化し、見える化しておきます。
次に、全てのアクションプランを、緊急性と重要性の2軸で分けます。さらに優先順位をつけます。ここまでたどり着けたら、あとは実行あるのみです。実行に際しては、緊急性と重要性が高いものを最優先に着手し、その後緊急性が低く重要性が高いものを実行してください。実行してみたもののうまくいかなかったものでも、PDCAを回して試行錯誤しながら、必ず実行してください。
PDCAが回せない状態に陥った場合は、しっかりと伴走してくれるコンサルタントをつけ、実行力を補完することをお勧めします。コンサルタントの費用は決して安いものではありません。しかし、せっかく実行計画まで作っても実行しなければ、未来は何も変わりません。
最後に、次のAかBのうち、どちらの選択をするかは経営者が決めなければならないことをお伝えします。
A 人手不足の課題に対して、解決するために第一歩を踏み出しますか?
B 人手不足の課題を抱えて悩み続けますか?
今すぐ決断し、実行することをお勧めします。