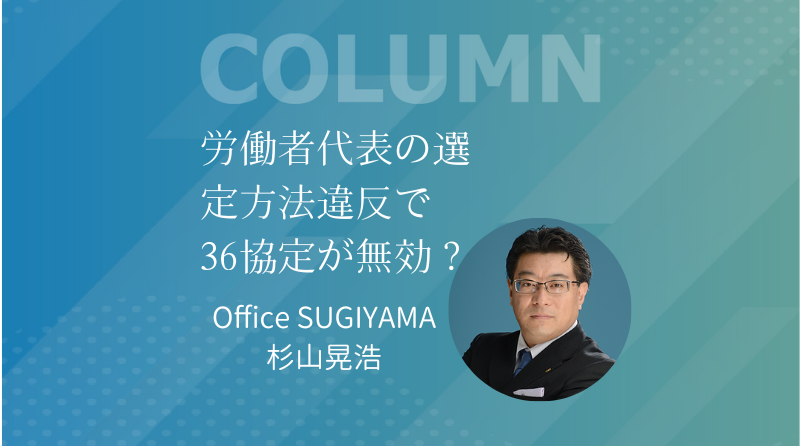毎年、年度初めに「時間外労働・休日労働に関する協定(以降、「36協定」という)」などの締結をしている介護事業所は多いでしょう。これを締結する労働者の過半数代表者が適切な方法で選ばれていないとこの協定が無効と見なされます。
最近の事例ではこの代表者が適切に決められていなかったために1,000万円を超える割増賃金の支払いを命じられた事業所や、違法な残業などをさせたとみなされ書類送検された事業所が存在しています。
このようなリスクとそれを回避するためのプロセスについて解説します。
1.36協定を結ぶことで得られる免罰効果と注意点とは?
36協定がその名で呼ばれるのは、労働基準法第36条に時間外及び休日の労働の取り扱いについて規定されているからです。同法第36条第1項には次のように書かれています。
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」
ここで定められているのは、スタッフに時間外労働(残業や法定外休日に出勤させること)や休日出勤(法定休日に出勤させること)をさせる可能性がある場合には、36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届出なければならないということです。なお、36協定書を締結し、労基署に提出することで得られる法律的効果は免罰効果と呼ばれます。つまり、36協定書の範囲内の時間外労働や休日労働をスタッフに命じたとしても、違法に働かせたことにはならないということです。
したがって、36協定書を締結せずにスタッフに残業させた場合には、違法残業ということになります。
また、36協定書の締結をしたけれども、その内容に不備があれば、協定書は無効となります。この場合に、既にスタッフに残業をさせていた場合には、違法残業をスタッフに強いたことになります。
同時に覚えておいていただきたいのは、36協定を労働基準監督署に届け出たけれども、その内容をスタッフに周知していなければ、30万円以下の罰金刑が課される可能性があるということです。
2.労働者の過半数代表者を選出する基本的な流れ
みなさんの事業場の中では、労働者の過半数代表者を選定する必要がある場合とそうでない場合があります。その違いは、以下の流れで判断します。

手順としては、まず最初に労働組合の存在有無を確かめます。
労働組合がある場合には、パートタイマーやアルバイトを含むすべての労働者を分母とし、労働組合員数を分子として計算した結果が、50%を超えている組織率であれば、労働組合が過半数代表者となります。
労働組合の組織率が50%以下、もしくは、労働組合がない事業所の場合には、過半数代表者の選出が必要です。
選出に当たっては、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなどを含めたすべての労働者が参加して、民主的な方法で決定する必要があります。
ちなみに、社長が代表者を指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合などは、民主的な方法で選出されていないとみなされてしまい、労働者の過半数代表としての地位を得ることはできません。さらに、管理監督者は労働者の過半数代表になれないことにも注意してください。
3.労働者の過半数代表者を適切に選ばなかったことによる悲劇とは?
労働者の過半数代表者が不適切に決定されると36協定書が無効になり、違法残業が発生すると先述しました。
しかしながら、事業者にとってもっと恐ろしいのは、選定プロセスが不適切な場合、1カ月変形労働時間制などの労使協定も無効となるということです。
変形労働時間制のメリットは、1日8時間、1週40時間を超えて、所定労働時間を設定できることです。例えば16時間勤務の夜勤シフトが必要な場合を考えてみます。通常の労働時間であれば、1日8時間が上限となりますので、8時間の残業が発生します。
でも、1カ月変形労働時間制を適法に採用していれば、16時間の夜勤シフトでは残業は発生しません。つまり、割増賃金が発生しないということです。
私の住んでいる宮崎県では、労働者の過半数代表者が適切に決定されていなかったことから、変形労働時間協定が無効とされ、約1,400万円もの割増賃金が発生した事案があります。適切な選任がなされていれば、このような大金が一瞬で消えてしまうことはありませんでした。
2023年5月8日に愛媛県の八幡浜労働基準監督署から送検された事例も紹介します。
外国人技能実習生10人に違法な時間外・休日労働を行わせたとして、縫製業のK社と同社取締役が、労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで松山地検に書類送検された事例です。
その根拠はまさに、同社が届け出ていた36協定は、締結当事者となる労働者の過半数代表者の選出が適法でなく、無効だったということです。
同労基署によると、労働者の過半数代表者は選挙などの方法で選出されたものではなくて「使用者の意向に沿う形で選出されていた」ということです。
同社に向けられた疑いは、有効な36協定がない状態で、令和4年1月1日~6月30日の期間に、週40時間を超えて1週当たり最大36時間、1カ月で最大156時間50分の時間外労働を行わせたことです。
事業所が書類送検されれば、当然マスコミの記事になり、ブランドが低下してしまいます。その結果、スタッフは退職し、新規の採用も難しくなるでしょう。
正しい労働者の過半数代表者の選任方法を知らないだけで、大きなリスクにさらされてしまうことが伝わったのではないでしょうか。
4.正しい労働者の過半数代表者の選ぶための3つの条件
正しい労働者の過半数代表者の選び方は、次の3つの条件を満たす必要があります。
①管理監督者でないこと
②労使協定の締結者、就業規則意見者としての過半数代表者選出であることが明らかにされていること
③民主的な方法で選任されること
ここで、「民主的な方法」にはどのようなものがあるのかを挙げてみます。
① 投票による選挙
② 挙手による選挙
③ 投票による信任
④ 挙手による信任
⑤ 回覧による信任
⑥ 2労働組合の話し合い(2労働組合の組合員の合計は、全労働者の過半数)
⑦ 各職場ごとに職場の代表者を選出し、これらの者の過半数の賛成を得て選出過半数代表者を選出
近頃では、労働局や労働基準監督署から労働者の過半数代表者の選任方法を尋ねられることが増えてきたように感じます。また、選挙等を実施した証拠を求められることもあります。丁寧に選任したいものです。
5.労働者の過半数代表者を合法的に選出するための具体的な手順
労働者の過半数代表者を合法的に選出するための具体的な手順を考えてみました。
以下のとおりすすめていただければ、民主的な方法で合法的に選出できます。
これで、労基署等への対策も万全です。
【投票による選挙を実施する具体的な手順】
1.告知と意見募集:スタッフ全員に対して過半数代表者選出の目的、プロセス、および候補者の資格要件を説明する通知を行います。
その後スタッフからの候補者推薦や自己推薦を募集します。
2.候補者の確定:推薦された候補者が資格要件を満たしているか確認します。
そして資格要件を満たす候補者を公示し、全スタッフに周知します。
3.選挙の実施:秘密投票による選挙を実施します。投票方法、場所、時間を事前に明確に告知します。
また全スタッフが投票に参加できるよう、適切な支援と環境を提供します。
4.投票結果の集計と発表:投票を受け付けた後、公正な方法で票数を集計します。
選出された過半数代表者を全スタッフに対して公表します。
5.記録と確認:選挙プロセスの全ての段階を文書化し、透明性を確保します。
労働局等の求めに応じて、記録文書の開示を行います。
◆今回の読者プレゼント:選挙と36協定締結をスムーズに行うためのツール◆
最後までお読みいただきありがとうございました。
今回は、投票による選挙をスムーズに行うための『全体会議における過半数代表者の選出について』とする従業員向け文書を作成しました。
また、『従業員代表の対応事項一覧表』として労基法における過半数労働者代表が行うべき業務をまとめたシートを作成しました。
特に、
①従業員向け文書をどのように作成したらよいかわからない
②労働者の過半数代表がすべき業務を確認しておきたい
③労働者の過半数代表者の選任について不安がある
といった方は、お気軽に下記からお申し込みください。