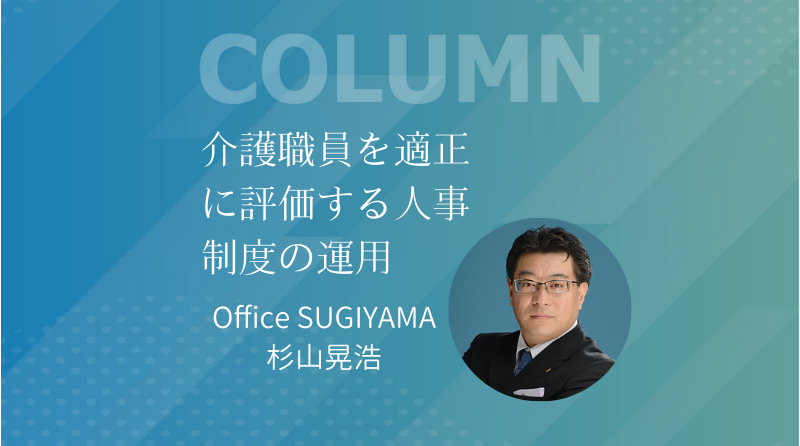1.適正な人事制度が実現する7つのメリット
介護職員処遇改善加算を取るために、「経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み、または一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」として人事制度を導入している介護事業所は確実に増加しています。
これらの人事制度の中には、単純に毎年賃金が上がるだけのものや、実務に使用していない資格に対して手当などを支給するものなど、将来的に課題を生みだす可能性が高い制度も含まれています。人事制度は、一度構築してしまうと長期間変えることはありません。つまり、間違いがあったとしても正されずに運用され続けていくことになります。実際に間違いに気づいた企業の人事担当責任者から、相談を受けたことは私も一度や二度ではありません。
人事制度が適正に構築され、運用されると7つのメリットが得られます。
(1)なすべきことの優先順位が明確になるため、緊急かつ重要な項目が実行され業績がアップします。
(2)業務に必要な能力と能力を発揮したときの賃金が明確化されるので求職者へのピンポイントのアピールができるようになり、優秀な人材を獲得できるようになります。
(3)評価結果に納得できるスタッフが増えるため、離職率の軽減につながります。
(4)定着率が高まるため、人材紹介や採用広告を利用しなくてもよくなり、採用コストが削減されます。
(5)評価項目が明確化されるため、スタッフが無駄な行動をしなくなるため、既存社員のパフォーマンスが向上します。
(6)上司が部下の評価を高めるサポートをするため、管理職のマネジメント能力が向上します。
(7)金融機関などのステークホルダーにPRすることで信用が増します。
人事制度を理解し、正しく運用することで、組織の成長を促進させてみませんか。
2.人事制度の基となる3つの制度~等級・評価・賃金の仕組み化~
人事制度は、次の3つの制度から成り立っています。
(1)等級制度
(2)評価制度
(3)賃金制度
育成制度を併せて、4つの制度を運用している組織もあります。
育成制度がなかったとしても、上司が評価制度を利用して部下の教育をすることで、自然と部下が育ちますから安心してください。
ところで、人事制度を構築するときは、必ずこの3つの制度を連携させるようにしてください。それぞれが独立していると、せっかく構築した人事制度の効果が半減してしまいます。
助成金受給を目的に作成された評価制度では、スキル評価のみに特化している制度や評価項目を達成しても昇給原資が確保できない制度も散見されます。
不安になった方は、今一度、何のために人事制度を導入しているのか、何のために人事制度の導入を目指すのかを明確にしてください。そうすれば、現状のままで良いのか、制度の中に足りないものがあるのかが判断できます。
3.等級制度の概要と代表的な4つのモデル―職員の何を評価するのか明確にする
等級制度は、人事制度の根幹となる最も重要な制度です。
等級制度を設計するうえで大切なことは、「形式」ではなく、「何を価値と判断して差を設けるのか」ということを熟考したうえで意思決定することです。
等級制度は、基本的に次の4つの制度に分類されます。いずれの制度も、メリットとデメリットがあるため、これまでの自社の歴史、現在の人材運用などを多角的に考慮し、最も組織にふさわしい制度を選択してください。
職階制度
課⻑・部⻑など、「役職を価値」として処遇する等級制度です。
【メリット】日本人にとって、単純で基準がわかりやすい。
【デメリット】専門性が高いスタッフの処遇ができないことやポストが空かなければ昇進させられないことなど。
職能資格制度
「職能(職務遂行能力)を価値」として処遇する等級制度です。【メリット】等級内の異動が容易に行えるため、柔軟な人事異動ができる。
【デメリット】過去の実績が重視されるため降格が難しいことなど。
職務等級制度
「職務(ジョブ)を価値」として処遇する等級制度です。
【メリット】職務レベルと賃金レベルが同一となるため合理的に処遇が決められる。
【デメリット】空きポストがなければ、昇格も異動もできないことや職務ごとにジョブディスクリプション(職務記述書)の作成が必要なことなど。
役割等級制度
職能的な等級の価値」と「役割ごとの差異の価値」を両立させる日本と欧米系の折衷といえる等級制度です。
【メリット】現在価値の役割で合理的に等級を区分できる。
【デメリット】現在基準で区分されるため、過去の功績の蓄積が等級には反映されない。
4.評価制度の概要と運用のポイント
スタッフの貢献度や能力を、自社の基準に照らして数値化するのが評価制度です。
数値化された評価の結果が賃金制度に反映され、給与などの処遇が決定します。
評価制度には、次の3つの種類があります。
目標管理制度(MBO)
組織目標に繋がる個人目標を達成するために、スタッフが自主的に目標を決定し、自己評価する制度です。上司の役割は、部下の目標設定と達成のサポートとなります。スタッフ自身が個人目標の設定をするため、努力しなくても達成できるような甘い目標を設定されてしまったときには、上司がしっかりとフォローして目標の再設定をする必要があります。
コンピテンシー評価
職務ごとに決められた行動特性から生み出された結果を評価します(※編集注:コンピテンシー:職務や役割において優秀な成果を発揮する行動特性)。高い業績や成果を出す人を分析し、自社組織に合った行動特性を定義して評価基準にします。なお、部署、職種、レベルなどに合わせて細かくコンピテンシーを定義する必要があるため、導入までに多くの手順が必要となります。また、選択したコンピテンシーが適正であるとは限らないこともデメリットのひとつです。
360度評価
被評価者に対して、上司、同僚、部下など複数の者が評価するため、公平で客観的な評価が可能です。半面、被評価者全員に考課者研修を実施したり、評価シートの集計作業が膨大になるなど、運用面での工夫が必要になります。
一般的な評価シートには、次の3つの評価基準が利用されています。これらの組み合わせやウエイトの設定は事業者次第です。最近では、成績評価を基本給を中心とした処遇を決める評価項目としては扱わず、賞与での評価とする企業も増えてきています。
●情意評価…日常の勤務態度や仕事への取り組み姿勢などを評価します。
●能力評価…職務遂行に必要なスキルや知識・能力の発揮度を評価します。
●成績評価…行動プロセスや目標達成度などの実績を評価します。
これらの評価基準から評価項目を導き出し、評価シートに記載します。評価シートに記載する評価の判断基準は、誰でも理解できるように明確化してください。
明確化とは、判断基準を具体的に数値化(定量化)することです。なお、情意評価に属する評価項目は定性的なものが多いため、数値化する代わりに達成条件を明確にしておくことで代用が可能になります。
介護事業所では評価シートの作成に際し、厚生労働省の職業能力評価シートを利用することも多いと感じています。確かに公表されている評価シートをそのまま流用してしまえばすぐに評価制度の形が出来上がります。
しかしながら、評価項目が自社の現状に合っているのか、ひとつひとつ再吟味しなければ、運用に堪えない評価シートになってしまいます。判断する人によって異なる評価になってしまう評価項目が入っていることもあり、注意が必要です。
実際に「通所介護サービス レベル2(中級)」の評価シートに記載されている次の2つの項目を例に取り上げて、誰が判断してもブレがないのかを検証してみます。
例1
常に利用者の安全に気を配りながら、サービスを実施している。
この項目が達成できているか、達成できていないかの判断基準はどこにあるか考えてみてください。
「常に」とはどの程度の頻度なのでしょうか。
「気を配る」とはどのような状態なのでしょうか。
「サービスの実施」とはどのレベルのサービス提供なのでしょうか。
これら3つの質問をスタッフにして下さい。全く同じ回答になることはないでしょう。人によって解釈が異なる判断基準を使用してしまうと、公平な評価ができず評価者と被評価者の間のトラブルになるおそれがあります。
例2
ミーティングやカンファレンス、上司への報告・連絡・相談等の機会を利用して、提供したサービスの内容や、ケアのやり方について検証し、自身の介護サービスの質を高めようと努めている。
この項目には「努めている」とのキーワードが入っています。努めているという言葉は、努力しているか、努力していないかの判断基準が人によって異なっています。
すなわち、スタッフ本人が「努力しているからできている」と判断し、上司が「否。努力不足である」と判断したときにどのような未来が待っているでしょうか。
これらの例からわかるように、判断基準を明確化するためには、判断する人の主観が判断基準に影響を与えてしまう「常に」や「努めている」といった表現を使わないことが大切です。
とはいえ、介護事業所において判断基準が定量化された明確な評価項目の作成はとても難しいものです。
今回は、「介護事業所向けの定量化された評価項目別の判断基準サンプル」をプレゼントします。ご興味のある方はお申し込みください。
5.賃金制度の概要とトレンド
日本で多く見られる賃金制度は月例賃金、賞与・一時金、退職金から成り立っています。
一般的に評価制度と連動させる賃金は、基本給です。
どのような基準で基本給を構成するかは、企業が自由に決めることができます。
介護事業所では、年齢給や勤続給がベースとなっていることが多いです。
単一の基準を採用するのではなく、年齢給と職能給のように複数の考え方を用いた給与の合計を基本給とすることもできます。
なお、職能給は職能資格制度、職務給は職務等級制度、役割給は役割等級制度にそれぞれ紐づきます。
最近では、評価制度の成績評価はプロセス評価のみ賃金に反映させ、成果は賞与に反映させる企業が増えてきています。たまたま良い成績を挙げたスタッフの給与が高くなってしまい、翌期以降に全く成績が挙がらなくても給与がなかなか下げられないといったリスクを回避するための方策です。
介護事業所では個人の営業成績を成果として設定することは稀です。介護事業所に応用するときは、個人の営業成績を経営計画の利益目標に置き換えて運用します。経営計画をベースとすれば、全てのスタッフが関係してくるので、利益分配を目的とした成果主義的賞与制度の導入ができることになります。この方法であれば、全社一丸となって大きな目標に向かって行動し易くなります。
ちなみに、賞与制度や退職金制度を作ることは義務ではありませんので、これらの制度が存在しない会社も世の中には存在しています。
諸手当については、同一労働同一賃金の考えの下、均等待遇や均衡待遇に留意する必要があります。

◎お知らせ
『介護事業所向けの定量化された評価項目別の判断基準サンプル』が必要な方は、無料でプレゼントします。
お申込みはこちらから ⇓
https://forms.gle/t7srjo6xhiecb4B48
『人事賃金制度診断』を希望される方は、無料で10ページ程度の診断レポートをプレゼントします。
お申込みはこちらから ⇓
https://forms.gle/MhQ7ZG9wHgks4EjH9