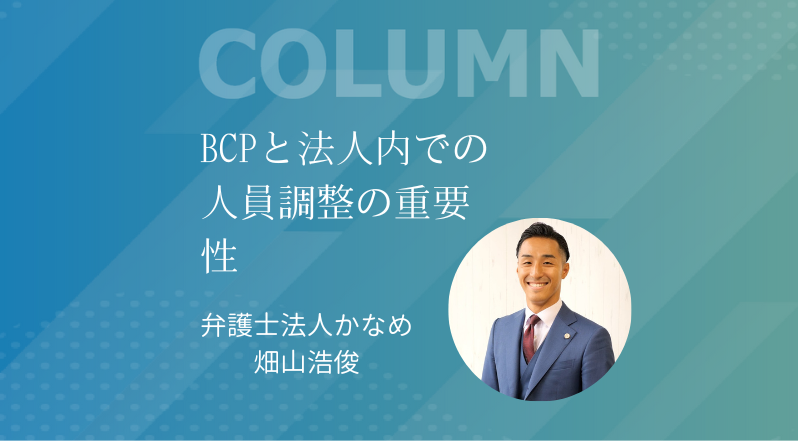1.BCPで手薄になりがちなポイント
皆様も既にご存知のとおり、2021年度介護報酬改定で、21年4月から全ての介護事業者を対象にBCP(業務継続計画)の策定が義務付けられました。完全義務化は24年4月以降ですが、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっている状況下で、同感染症発生時のBCP策定を先んじて策定した介護事業者も多いのではないかと思います。
筆者が代表を務める弁護士法人かなめでは、日本全国の介護事業者の方々にオンラインですぐに法律相談ができる顧問弁護士サービス『かなめねっと』を提供しており、日々、様々な法律相談を受けています。本稿では、コロナ陽性者が発生した介護事業所からの相談で見えてきたBCPで手薄になりがちなポイントのうち、筆者が特に重要であると考えるポイントの1つを解説したいと思います。
そのポイントとは、ズバリ、「同一法人内における人員調整の仕組みが構築されていない」ということです。以下、詳しく解説します。
2.BCPは策定しただけでは意味が無い
新型コロナウイルス感染症BCPの最重要ポイントは、「人員をどう確保するか」です。
感染疑い・感染者が発覚した場合、ゾーニングやコホーティング、徹底した消毒作業等、業務量が急激に増大します。そして、職員からコロナ陽性者が発生した場合には、さらに人員も減り、当該事業所の職員一人ひとりの業務量が急増します。この観点から、「人員をどう確保するか」が、新型コロナウイルス感染症BCPの最重要ポイントになるのです。
ここで、例えば、グループホーム、デイサービス、特養、ヘルパーステーションの4事業を運営しているA法人において、グループホーム内でコロナ陽性者が多数発生して、人員確保が難しくなった状況を考えてみます。
この場合、グループホームにおいて人員を確保する手段としては、A法人が運営する他の介護事業所から人員を派遣する方法が最も効率的かつ実効的です。
他方、BCPは、介護事業所ごとに策定が求められていることから、A法人で1つではなく、A法人が運営する4つの事業所ごとにBCPを策定する必要があります。その結果、BCPの内容が、一つの事業所内部の職員調整に終始するか、同一法人内での職員調整について抽象的に規定されるにとどまり、実際に感染(疑い)者が発生した場合に、同一法人内の別の事業所から職員を調整することが後手後手になり、事態が急迫する傾向があります。
3.同一法人内の職員の調整を具体的にルール化しよう
事業所ごとに策定したBCPが有事の際に更に有機的に活用することができるように、同一法人内の職員調整に関するルールを具体的に策定するようにしましょう。
最低限決めておくべき事項は以下の2点です。想定する法人は上記のA法人、すなわちグループホーム、デイサービス、特養、ヘルパーステーションの4事業所を運営している法人で、グループホーム内でコロナ陽性者が発生した場合です。
【1】コロナ陽性者が発生した際に、同一法人内で応援を要請する際の内容を予め制定しておく。具体的には、応援時に担当する業務の内容、応援を求める期間などを明記し、なるべく協力してくれるメンバーを多く募れるような工夫をした文書を、事前に作成しておく。
【2】コロナ応援要請時における職員への処遇を予め制定しておく。具体的には、応援先の距離や、応援日が所定労働時間か、それとも休日か、などによって、職員間に不平等が生じないよう、社労士や弁護士との間で、事前に労働条件を決めておく。
皆様の介護事業所でも、ぜひ一度BCPを見直し、「法人内での人員確保」という項目がない、または、あったとしても概略の記載しかない場合には、是非上記【1】【2】を参考に、具体的なアクションプランを立ててみてください。
4.外部サービスの活用も視野に入れよう
もちろん、同一法人内での職員の調整もできないほどコロナ対応が逼迫する場合もありますので、その際の対応も検討しておく必要があります。同一法人内での調整が難しいほどコロナ対応が逼迫している状況の場合、当該法人だけでなく周辺地域においてもコロナ対応が逼迫している可能性が高く、その場合、当然のことながら保健所も十分に機能しなくなる場合がほとんどですし、医療体制も逼迫しています。そうなれば、公的な支援は期待できなくなりますし、保健所としてもコロナ罹患者の入院調整が不可能になってしまうケースもあります。
都道府県が実施する緊急時における人材応援派遣の仕組みもありますが、コロナ対応逼迫時は、どの法人も似たような状況に陥っているため、応援派遣を要請しても、肝心の人材が来てくれないという問題も多数発生しています。
こうなると、最終的には、各事業者が自力で外部サービスを活用して人員を確保するしかありません。外部サービスとは、例えば、看護師や介護士等の専門職を手配してくれるサービスです。インターネットで検索すると、様々なサービスが出てきますので、一度調べてみましょう。費用は決して安くありませんが、業務継続の観点から、背に腹は代えられません。
BCP策定時の段階で外部サービスを事前に調査し、選定している介護事業者はほぼ皆無です。したがって、いざ、法人内部での職員調整に逼迫する段階になって初めて外部サービスを調べることがほとんどです。これでは、時間も費用も余分にかかってしまいます。活用できる外部サービスを予め調査し、パンフレットを取り寄せたり、サービス内容の説明を受けたりしておくことで、どのように緊急時に活用できるのかを十分に検討しておくようにしましょう。