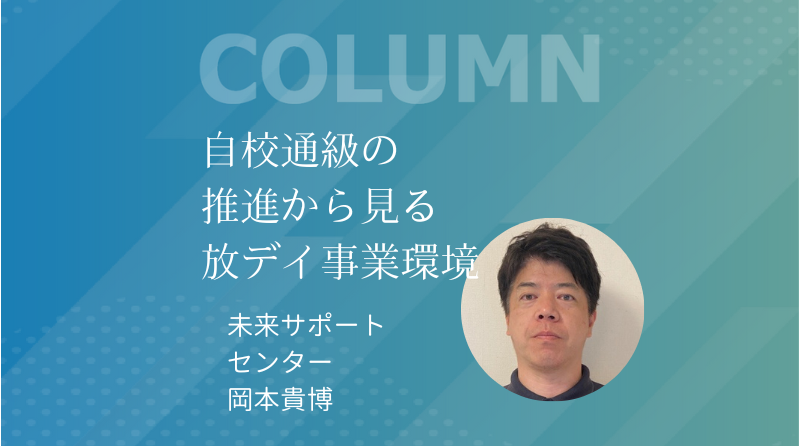障害福祉の分野に携わっていると、「インクルーシブ教育」という言葉を耳にする機会は少なくないでしょう。
障害者の権利に関する条約によればその定義は、「人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的および身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能にするという目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み」となっています。
このインクルーシブ教育を推進する取り組みには様々なものがありますが、今回はこのうち、「自校通級」に関する動向と放課後等デイサービス事業への影響、事業者がとっていくべき対応について考察します。
各自治体が充実を図る自校通級とは
障害のある子供のための学びの場に、「通級による指導」(通級指導教室)があります。これは、小・中・高等学校等において、通常の学級に在籍しているものの、一部特別な指導を必要とする児童や生徒に対する指導形態です。
対象となるのは、学習障害(LD)、自閉症、ADHDなどの発達障害と診断された子供、または言語障害、弱視、難聴、肢体不自由、病弱といった、特定の困難を抱える子供達です。
「自校通級」とはこのうち、子供達が通っている学校で実施する指導を言います。
指導は、通級指導教室の担当の教員が担任の先生や特別支援教育コーディネーターと協力しながら行います。
23年5月には、「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議」報告が公表され、現在、各自治体が自校通級に積極的に取り組んでいます。
(【参考 】文部科学省 通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議報告)
例えば、大阪市では26年度までに市内の小中学校の全校に自校通級教室を開設する予定です。(24年度小中学校合わせて147校)
自校通級の充実が放課後等デイサービスに及ぼす影響
自校通級の目的
通級は、通常学級での授業に困難を感じている子供に提供されますが、学習の遅れを取り戻すためのものではありません。障害の状況に応じた「自立活動」を行い、自分なりにできる方法を見つけたり、自分の特性を理解して効果的に練習したり、環境にうまく働きかけたりするなど、自分の力を可能な限り発揮して主体的に取り組もうとする力や態度を育てることを目的としています。
自校通級の実施時間等
学校によって違いはありますが、学校教育活動時間内または放課後の時間帯に月1回から週8回の範囲で実施されます。
個別教育支援計画の作成
自校通級では、個別教育支援計画や個別の指導計画が作成されます。
自校通級の充足が放課後等デイサービス事業に及ぼす影響
ここまでご覧いただき、ピンときた方は多いのではないでしょうか。通級の目的は、放課後等デイサービスの事業目的と変わりはありません。
これから自校通級が大きく拡充された場合、放デイ事業の脅威になりえると私は考えています。
「学校で個別の療育が受けられるのであれば、放課後等デイサービスに通所させる理由がない」「週5回放課後等デイサービスを利用していたけど、自校通級に週2回通う」といった状況が今後生まれてくるでしょう。
放課後等デイサービス事業所の自校通級との向き合い方
それでは、放デイ事業所はどのように対応したら良いのでしょうか。
学校としっかりコミュニケーションを取る
学校として把握している子供の特性・ニーズと、放課後等デイサービスが把握している内容を共有しましょう。それぞれが全く違う考えに基づく支援をすると、子供が戸惑い、成長を阻害します。
また、自校通級の支援内容を把握することで切れ目のない支援が期待できます。
学校と良好な関係を構築できれば、保護者からも安心感を得られるでしょう。「あそこの事業所は学校と良好な関係だから安心」と口コミを広げてくれるかもしれません。
同じ学校から複数の子供が通所することは、送迎等、事業所運営上のメリットになりますし、「地域に密着している事業所」であることは強みとなります。
個別支援計画書をきちんと作成する
保護者が自校通級での支援方法や自校通級で作成される個別教育支援計画書を知ることで、放デイにおける支援方法や個別支援計画と見比べることができるようになります。
そのとき、保護者が安心できるような支援を実施し、個別支援計画書の作成を行いましょう。
自校通級には無い強みを持つ
繰り返しになりますが、放デイ事業所にとっては、子供が通いなれた学校での自校通級は強力なライバルとなります。
そこで、保護者や子供が、放課後等デイサービスに通わせるための明確な理由と必要性が求められるでしょう。
放デイの強みは、保護者からすると「自宅まで送迎する」「遅くまで預かってくれる」ことであると思っていらっしゃる事業所はないでしょうか。
しかし、送迎は本来、介護タクシーの役割です。預かり目的であれば、それは日中一時支援や学童保育の役割です。いずれも放課後等デイサービスの役割でありません。
自校通級が拡大する前に、事業所の強みを整理してください。
おすすめは、現在通所している子供や保護者に「なぜ、当事業所を利用しているのか」というアンケートをとることです。強みが“見える化”できて今後の運営のヒントが生まれるかもしれません。
事業所が必要とされ続ける存在であるために
ここまでお伝えしてきたように、自校通級は放デイ事業にとって脅威になることが予想される一方で、正しく向き合うことができれば、サービスの質の向上に繋がり、子供や保護者の安心を生み出せるでしょう。
近年は自校通級だけではなく、障害児を受け入れる学童保育も増加しています。また、発達障害児向けの塾やプログラム教室、フリースクールなども増加しており、一般の習い事教室でも障害児を受け入れるようになってきています。
背景には発達障害児が増加しており、放課後等デイサービスの制度を使わなくても民間事業者が十分、収益が見込める状況にあるということもありますし、国がインクルーシブ教育を推進した結果、市民の障害への理解や障害児を支援する支援者が増加した影響もあるでしょう。
2012年に放課後等デイサービスの制度が出来て以降、放デイの存在はインクルーシブ教育に大きく貢献してきたのは事実です。
これからも、引き続き家庭・学校・地域ときちんと連携し、共生社会の一翼を担うことが、活路となるでしょう。