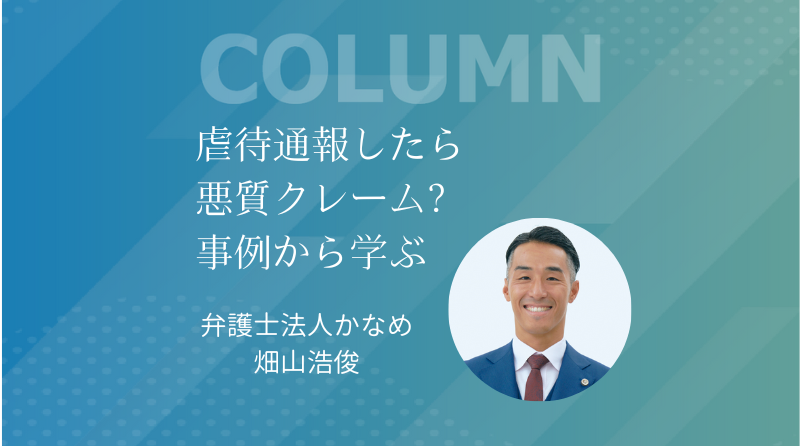2021年度介護報酬改定ではハラスメント対策の強化、そして、24年度からは高齢者虐待防止の推進といったように、介護事業者にとって対応しなければならないルールが制度改正のたびに増えています。
そのような中、今回は、虐待通報をしたら、その対象である利用者の家族から悪質なカスタマーハラスメントを受けてしまう、という何とも悩ましい事例がありました。この事例を元に、事業所ではどのような対応をとるべきなのかポイントを解説します。
1.虐待を通報したケアマネジャーに利用者の家族が激高!:ケース紹介
【ケース】
私がケアマネとして関わっている利用者のことでとても困っています。
ある日、その利用者が通っているデイサービスの職員から慌てた様子で電話がありました。
「利用者の顔に痣ができています。話を聞くと、どうやら息子さんに殴られたようで・・・」
私は驚き、すぐにそのデイに行きました。その利用者の左目の周りが赤紫色になって腫れていたので、家族の虐待を疑い、すぐに地域包括支援センターに虐待通報をしました。 通報から数日後、モニタリング実施日でしたので、私は、利用者宅を訪問しました。
インターホンを鳴らして待っていると、私の後ろに市の職員がやってきたのです。
どうやらモニタリングと虐待通報に基づく調査の日が重なっていたのでしょう。
家族は私の後ろに行政職員がいるのを見て、「お前が通報したのか!個人情報を漏らしやがって!」と激怒し、それ以降、毎日事業所に「個人情報を漏らしたケアマネを解雇させろ!賠償しろ!謝りに来い!」と電話がかかってきます。
私はケアマネとして何か間違ったことをしたのでしょうか。どのように対応すれば良いのでしょうか。
2.今回の事例における3つのポイント
今回の事例のポイントは3つです。
- 高齢者虐待防止法に基づく通報は個人情報の漏洩には該当しない
- 行政調査の実施日を予め把握しておこう
- カスハラ要求には「組織」で「No」を伝えよう
順に解説します。
(1) 高齢者虐待防止法の通報は個人情報の漏洩には該当しない
今回のケアマネさんの地域包括への通報は、高齢者虐待防止法上、正しい行動です。 高齢者虐待防止法第7条1項には次のとおり定められています。
高齢者虐待防止法第7条1項
養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
つまり、相談者であるケアマネさんは高齢者虐待防止法上の通報義務を果たした訳ですから、何ら責められることは無いのです。
それでは、「個人情報を漏洩しているではないか」との家族の訴えについてはどう反論すれば良いでしょうか。
たしかに、ケアマネ事業所は個人情報保護法上、利用者の個人情報については厳重に管理する義務を負っていますから、本人の同意が無ければ個人情報を第三者に提供してはいけません(個人情報保護法第27条1項本文)。
もっとも、虐待通報の場面では事前に同意を得るなど悠長なことを言っている時間はありません。そこで、高齢者虐待防止法第7条3項は、虐待通報の場合には、例外的に通報しても守秘義務に違反しないことを定めています。ですから事前に本人から同意を得ていないとしても、個人情報保護法違反にはなりません(個人情報保護法第27条1項第1号)。
この点をしっかりと理解しておくようにしましょう。
(2)行政調査の実施日を予め把握しておこう
虐待通報を受けた市町村は、速やかに事実の確認を行う必要があります(高齢者虐待防止法第9条1項)。その一環で利用者の自宅を訪問して家族にヒアリングを実施することがあります。
今回の相談事例は、行政調査のタイミングが悪いと言わざるを得ません。行政側の配慮不足です。
もし、自分が虐待通報をしたことが相手にわかってしまうとすれば、報復や不利益な扱いを受けることをおそれ、通報をためらうのが自然です。
そこで、高齢者虐待防止法では、市町村の職員は通報した人が誰かを特定できるような情報を漏らしてはいけないと定められているのです(高齢者虐待防止法第8条)。
行政担当者は、意図的にケアマネさんが通報したことを漏らした訳ではありませんが、モニタリングのために訪れたケアマネさんと行政職員が同じタイミングで自宅を訪問すれば、家族側から見たときに「このケアマネが通報したのか!」と勘繰るのも当然です。
ケアマネさんは行政担当者に対し、通報後の行政の利用者宅訪問調査の実施日を予め聞いておき、その日とモニタリング実施日が重ならないように注意するようにしましょう。
(3) カスハラ要求には「組織」でNoを伝えよう
これまで解説してきたように、虐待通報したケアマネさんは何ら責められるべきではありません。家族側の「個人情報を漏らしたケアマネを解雇させろ!賠償しろ!謝りに来い!」という要求は、全て不当要求であり、カスタマーハラスメントです。
解雇するかどうかは法人が決めることです。人事権への不当介入ですから聞く必要はありません。
賠償対応も不要です。今回のケアマネさんの対応に違法性は皆無です。
謝りに来い、との謝罪要求ですが、事情説明を行う際の冒頭に「ご心配をお掛けして申し訳ございません」という程度の共感言葉・クッション言葉としての言葉掛けで十分でしょう。
共感言葉・クッション言葉を冒頭で用いつつも、事情説明としては毅然とした説明を行うことが大切です。担当ケアマネの行動は高齢者虐待防止法上、必要なものであり、業務として遂行しなければならないものであったこと、個人情報保護法ついても違反していないこと、賠償についても検討したが、違法性が無い以上、賠償対応は難しいことを丁寧に説明するようにしましょう。
また、担当していたケアマネさんが窓口対応することは避けましょう。個人攻撃されることは目に見えているからです。あくまでケアマネさんの上長が対応するようにしましょう。
口頭でのやり取りでは埒が明かないことは明白ですから、最終的には書面で、法人としての見解を示すことが大切だと思います。高齢者虐待防止法や個人情報保護法等の法令が絡む問題ですので、事前に弁護士へ相談することをお勧めします。
3.今回のまとめ
以上、今回は虐待通報したら個人情報の漏洩だと家族から激怒された事例の対処法を解説しました。行政との連携がうまくできていなかったことで発生した不幸な事例ですが、虐待通報をする場面に遭遇しやすいケアマネの皆様が意外と遭遇してしまいがちな場面です。是非ご参考にしてください。
*以下の記事でもカスタマーハラスメントや利用者家族への対応について事例の紹介とその対応策について解説しています。
介護現場における利用者家族からのハードクレーム(過剰要求)への対応
夫からのDVを受けている利用者の訴え―訪問看護事業所としてどう動くべき?
利用者の骨折で虐待が疑われ通報?原因不明事故への対応の重要性
うつ病などの労災認定基準に「カスタマーハラスメント」が追加に~介護現場への影響を弁護士が考察