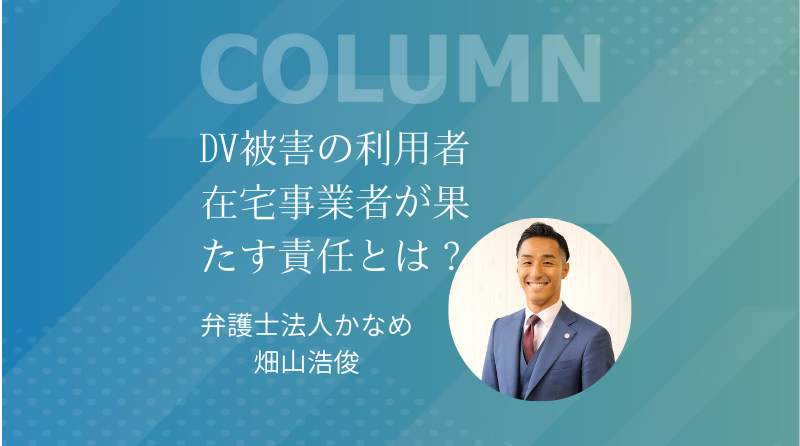今回は、外部との連携によって利用者の生活を支える在宅サービス提供者の責任の在り方について実際にあった裁判例の事案(アレンジしたもの)を基に考察します。
夫からのDV被害を受けている利用者に対するサービス提供をする中で起こった事例です。介入していた訪問看護事業所の責任が認められるかどうかなどが争点となりました。
虐待が疑われる場面にあった際に在宅サービスの従事者はどのように動くべきか、ぜひ考えながら読み進めてみてください。
1.訪問看護事業所で生じたトラブル事例
<相談内容>
私は訪問看護事業所の代表取締役で、私自身も看護師として現場に出ています。
利用者であるBさんに対しては、医師から担当ケアマネに対し、「血糖値管理と精神的な不安解消を図るべく、訪問看護の導入をお願いしたい」と依頼があったため、サービス提供を行なうことになりました。
Bさんは、夫から酷いDVを受けているようで、顔に痣があったり、「夜になると叩かれる」などと発言したり、家庭内での生活環境に非常に問題のある利用者でした。 ある日、私は、訪問看護のためにBさんの自宅を訪れました。
その際、Bさんはベッド横の手すりにしがみついて、「立てない」と繰り返し訴え、点滴後にトイレに行く際の介助にも「歩けない」と何度も訴え、手引き介助によってようやく歩けるような状態でした。訪問を終え、私は事業所に戻って来たのですが、その夕方、担当ケアマネから「夕方にヘルパーがBさんを訪問したら、痛がって動かない様子だった」と報告を受けたので、再度、私もBさんを訪問しました。
Bさんは左足の付け根付近の痛みを訴えましたが、屈伸もできますし、外内転可、立位も可能という状態でした。 私は、「きっと、後日、控えている精神科へ行きたくないだけで、詐病だろう」と思い、紹介元の医師に対しても「異常はなさそうです」と伝えました。
しかし、数日後、Bさんは左大腿骨頸部骨折と診断されたようで、そのまま病院へ搬送され、約2か月後、亡くなってしまいました。
Bさんが死亡した後、DV夫から、「うちの妻が痛がっている様子を見ていたのだろう!何で医師に対して骨折の疑いがあるから診断した方が良いと言わなかったのだ!詐病と決めつけたことには大きな問題がある。看護師として必要なことをしなかったのだから責任を取れ」と怒りの電話がありました。
私の対応は間違っていたのでしょうか。
2.訪問看護事業所から医師に対する報告が法的責任に問われるのか
上記の相談内容を見て、皆様はどう感じましたか。
「看護師として、利用者の状態を詳細に観察し、それを医師へ報告することは行っているのだから、やるべきことはやっているはず。これで責任を負うことになるのはおかしい」と考える人もいると思います。
かたや、「詐病と勝手に決めつけてしまい、その内容を医師に報告したことで、医師の判断が遅れた可能性があるのだから、看護師としての責任は免れないのではないか」、と考える人もいるはずです。
相談内容は、実際の裁判例の事案をアレンジして筆者が作成しました。
ベースとなった裁判例は、大阪地裁令和3年2月17日判決です。
夫からのDV被害を受けている利用者を医療者・介護事業者が連携してサポートしている中で起こった事例です。
骨折の原因になった事象ははっきり分かりませんが、もしかしたら夫のDVかもしれません。
いずれにしても、利用者の生活環境を少しでも改善するために一生懸命関わってきた医療者や介護事業者が、利用者の死後、問題の原因となったDV夫から訴えられることになるとは、なんとも皮肉な話です。
この裁判で争点は複数ありましたが、ここでは、訪問看護事業所の責任が認められたかどうか、という点に絞って解説します。
裁判所は、以下のとおり判示して、訪問看護事業所の責任を否定しました。
判決文は難解ですので、先に簡単に要約すると、「看護師として行うべき報告はきちんと行っているので問題無し。仮に看護師なりの評価を加えていたとしても、医師はそれに拘束されないし、医師として判断することが求められる訳だから、看護師が評価を入れていたとしても、責任の当否には影響しない」という理由で責任を否定しました。これを踏まえて以下の判決文を精読してみましょう。
本件事業所(筆者注:訪問看護事業所のこと)は、Bに対してした訪問看護の内容等について、「訪問看護記録」を作成し、これを毎日夕刻に被告Y2(筆者注:紹介元の医師のこと、以下「本件医師」と言い換えます)に宛ててファクシミリ送信していたことが認められるところ、9月11日分から19日分までにかけて作成された訪問看護記録中には、訪問時点でのBの状況、左下肢の痛みの訴えの内容や程度、トイレ又は朝食介助の過程におけるBの言動等が個別具体的に記載されているとみてよい。
しかも、被告Y4(筆者注:本件事業所の運営法人の代表取締役兼看護師のこと、以下「本件看護師」と言い換えます)は、9月11日には、予定されていた訪問看護に当たってBの訴えに接した際及びケアマネからの通報を受けて急遽再訪した際の2度にわたって本件医師に電話で連絡し、所見とともに本件看護師の見立てを伝えたというのである。
そうであれば、9月11日から同月19日までの本件看護師から本件医師に対する訪問看護をめぐる報告に足らざる点はなかったものというべく、本件看護師には原告らが主張するような故意行為や注意義務違反があったとはいえない。
なお、本件看護師が9月11日に本件医師にした電話連絡中には、Bの左下肢痛や歩行困難の訴えは、精神科への受診に対する回避のための自作自演である旨の見立てを前提とした本件看護師の評価が含まれる。もっとも、看護師から何らかの評価を伴った報告に接した医師が常に当該報告に拘束されるべきいわれはなく、むしろ、必要に応じて医師としての再評価をすることが求められる筋合いであるから、本件看護師の本件医師に対する報告の過程で上記の見立てが含まれていたとしても、上記判断を異にしない(太字下線は筆者)。
3.在宅における虐待案件の対応は「連携」が重要
以上のとおり、上記裁判では、訪問看護事業所として行うべき報告を行っていれば問題がないという結論が出た訳ですが、やはり「詐病だ」との決め付けで報告をすることは宜しくないのではないかと思います。医師も人ですから、訪問看護事業所の看護師を信頼するにあたり、報告を鵜呑みにする可能性もゼロではありません。経験豊かである人であればあるほど、利用者の状態を見て「●●に違いない」と思い込むことがあり、それがかえってトラブルの原因になる場合があります。報告はあくまで事実に留め、思い込みの発言は控えることが無難ですね。
さて、相談内容のように、医師から紹介を受けて訪問看護事業所として利用者に関わるケースでは、利用者へのケアの在り方を主導的に考えることを医師やケアマネに委ねてしまい、訪問看護事業所は一歩後ろに引いて物事を考えてしまう場合があります。
ただ、相談内容は、家庭内で夫から深刻なDVを受けている可能性のある事案であり、高齢者虐待防止法の観点から積極的に行政が介入すべき案件(介護施設への措置入所等)であったのではないかと思います。
訪問看護事業所の立場でも積極的に行政へ虐待通報を行う等、関係各所との連携が重要であると筆者は考えます。
実際の介護現場では、対応に悩むケースも多くあると思います。
今回の記事を読んで、現場の職員の皆様で「自分たちだったらどう動くか」を議論してみて下さい。皆様で意見を出し合うことが関係各所との連携の第一歩になるはずです。