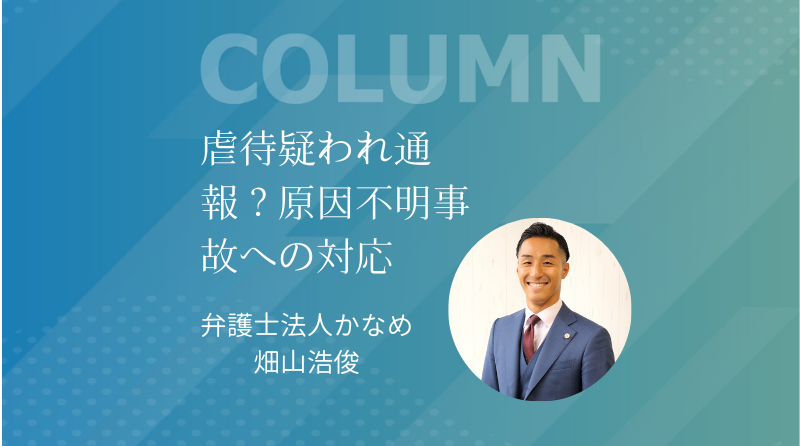介護施設では、日常的なケアを提供する中で利用者にいつのまにかあざや内出血などができていることに気が付くというのは、よくある出来事かもしれません。
しかし、利用者側の立場に立つと、例えば自身の親を預けていた施設の職員からその怪我についてあいまいな説明を受けたらどう思うでしょうか。「施設で虐待を受けているのではないか」という不信感にもつながりかねません。
今回は、原因不明の負傷事故が起きた際の適切な対応について取り上げます。
1.原因不明の骨折事故と虐待通報
<相談内容>
私は特別養護老人ホームの施設長です。
先日、利用者の右の脇腹部分に内出血があることの報告がありました。
現場の職員からの報告によると、その内出血があることは数日前からわかっていたようですが、最初は深く気に留めず、放置していたようです。
数日経つ内に内出血の範囲が広がっており、一目見ても酷い状態になっているように見えてきたから報告をしたとのことです。
急いで病院に行ったところ、「これは肋骨が折れていますね」と医師に診断され、骨折事故として処理することになりました。
利用者の家族に報告したところ、「何故骨折したのですか?どこかにぶつけたのでしょうか?」と質問されました。事前にこの利用者の介助に当たった職員に簡単なヒアリングを実施すると、「多分オムツ交換の際の体位変換の際に強く体をひねったことが原因だと思う」と言っていたことからそのまま家族に伝えました。
すると、家族は「そんな中途半端なヒアリングだけで事を済ませようとしているのか。これは虐待ではないのか。」と激怒し、市に虐待通報し、さらに警察にも相談に行くという騒ぎに発展してしまいました。
どうすれば家族に納得して頂けるのでしょうか。
上記の相談内容のように施設内で原因不明の負傷事故があった場合、事後対応の在り方次第でご家族との信頼関係が壊れてしまう場面があります。
我々弁護士法人かなめでは、実際に原因不明の負傷に伴う事故後の対応について、介護施設から数多くの法律相談をいただき、対応してきました。
事後対応が不適切な場合、ご家族との信頼関係は壊れ、上記の事例の通り、虐待通報に繋がってしまうケースになりかねません。また、関係性の悪化から、損害賠償請求をめぐって訴訟にまで発展することもあります。
かたや、施設側の言い分は、「本当に原因が分からないのでどう説明すれば良いかわからない」というものです。たとえモニターを設置していたとしても、死角になって映っていないことがありますし、映像の解像度が低く、うまく判別できないこともあります。また、モニターを設置していない施設も数多くあり、その場合は、職員あるいは利用者からのヒアリング以外に事実を知る方法はありません。
どうしても調査方法に限りがあるので、真実を解明しようとしても難しいことが多いのです。
ここで押さえておくべきことは、ご家族側の感情・気持ちです。
施設のことを信頼して大切な利用者を預けているご家族側の気持ちとしては、「何故このような原因不明の事故が起こっているのか、その理由を詳しく知りたい」という一点に尽きます。
ここから考えると、事故後の家族への説明の場面では、「いかに家族が納得する説明ができるか」が大切になってくることが自ずとわかるはずです。
では、「納得感を与える説明とは何か」を分析検討する必要があります。以下、詳しく解説します。
2.原因不明の負傷発生時の対応法:重要なのは「納得感の提供」
(1)ご家族の同じ温度感で調査しているか?
上記のとおり、ご家族からすると信頼しているはずの施設で原因不明の事故が発生している訳ですから、不安な気持ちがとても大きくなっています。人は、マイナス方向へのイメージは加速度的に大きくなってしまう傾向がありますので、良くない想像をたくさんしてしまいます。
「何故、骨折したのだろう」、「詳しい事故原因が分からないってどういうことだろう」、「隠ぺいされているのだろうか」、「もしかしたら、虐待を受けているのだろうか」と不安は増大する一方です。
原因不明の負傷が生じ、ご家族がそれを知った場合、多くのご家族が上記のとおりの気持ちを抱くということをまず理解しましょう。
一方で、正直なところを申し上げますと、介護施設では原因不明のあざ、内出血、負傷は日常茶飯事に起こります。ですから、現場職員の感覚では、ご家族が抱くような「重大な出来事だ!」というような焦燥感・不安感・切迫感はありません。「またいつものことか。」と言った具合でしょうか。
この温度差こそが調査の本気度合いに影響を与えるのです。ご家族が納得するための前提条件としては、「ご家族が本気で心配している気持ちに寄り添い、介護現場からすれば大袈裟に感じるほどの温度感で本気で調査に乗り出す姿勢を見せること」が必要不可欠な条件であることを心得て下さい。
(2)調査報告書の作成と提示
要は、「大袈裟に調査を行いましょう」ということなのですが、内容はいたって当たり前のことです。何度も繰り返しますが、「大袈裟に」というのは、介護現場で働く職員から見ると「大袈裟に感じる」という意味合いであって、世間的に見ればごく当たり前の対応です。
まずフォーマットとしては「調査報告書」という題をつけた報告書を作成することを心掛けて下さい。「きちんと調査しています」という本気度の高い姿勢を示す上で、「形を整える」ことは重要です。
調査方法としては、以下のポイントを押さえましょう。
ア 原因不明の負傷事故がいつ発生したのか、なるべくその時間帯を推定する。
⇒負傷が発見された時間を特定し、そこから遡って、負傷が無かったことが確認されている最後の終点を特定する。これにはケース記録、入浴介助時の記録等、利用者本人の身体の状況を確認した時の記録が役立つ。日頃からこの記録をこまめに記録していない介護施設は記録の付け方を見直す必要がある。
イ 推定された時間帯に利用者の介助に関わった職員を全てピックアップする。
ウ ピックアップされた職員に利用者の介助を再現し、記録に残す。
⇒職員には「犯人捜しをしている訳ではない」ことを事前に告知すること。
⇒日々のケアの在り方を見直し、きちんとした原因分析を行い、再発防止に努めるとともに、結果としてその取組みを通じて介護の質を向上させることが目的であることをきちんと説明した上で行うこと。
⇒再現記録を作成する際は、写真や動画を添付することも検討する。
「伝わる報告書」であることが重要である。
エ 利用者の特性を分析検討し、記載すること
⇒体動の多い利用者かそうでない利用者かによって、受傷原因が変わり得る。
⇒体動が多い利用者である場合は、自身でベッド柵に体をぶつけることがあり得るのではないか、等の検討が必要になる。
オ 負傷状況を医師に診てもらい、医師の見解を報告書に記載すること
⇒負傷状況を単純に医師に診てもらうだけでは不十分。医師にも前提情報の共有が必要。少なくともウとエは医師に共有した上で、医師の見解を仰ぐこと
カ ウ・エ・オを総合考慮し、介護施設の見解を記載すること
これらのポイントを押さえた上で、報告書を作成し、それをご家族に示し、丁寧に説明することを心掛けて下さい。
この方法で報告を受けたご家族としては、「そこまでして下さったのですね」と安心され、納得されるケースが多いです。これがご家族の不安な気持ちに寄り添った対応であると言えるでしょう。たとえ、真実が解明されなかったとしても、介護施設側がご家族と同じ温度感で動いてくれた、という事実こそがご家族が納得感を得るポイントなのです。