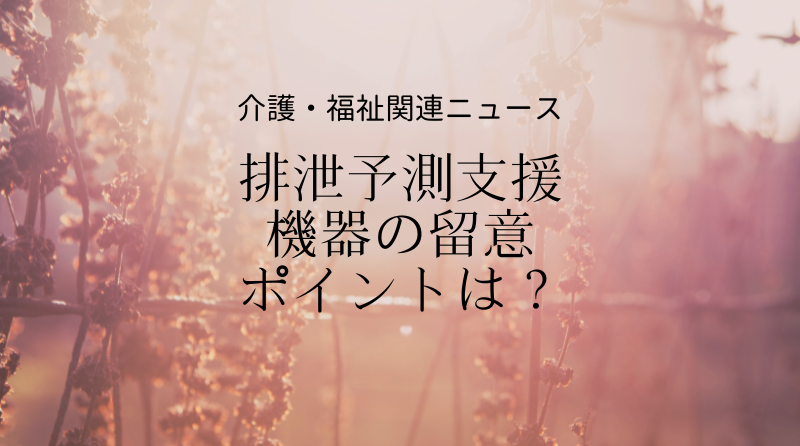2022年4月1日より「排泄予測支援機器」が介護保険の特定福祉用具販売の対象種目として新たに追加されました。3月31日に厚生労働省より通知が発出され、現場で実際に活用する際の取扱いに関する留意事項等が明らかとなりましたので、本稿にて詳細を整理します。
「排泄予測支援機器」が対象種目に追加されるまで
介護保険の給付対象となる福祉用具の品目への「排泄予測支援機器」の追加については、厚労省の「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」で年度をまたいで話し合われてきました。
この機器は超音波等を利用して膀胱内の尿の溜まり具合を可視化するものです。排尿の機会を本人や介護者に通知することで自立した排泄を支援し、トイレ誘導にかかる負担の軽減も期待されています。
検討会では、機器が適用される利用者像や適用可否を判断するフローの明確化など、実用に向けてまだ検討すべきといえる課題も一部で指摘されていました。今回の通知では、こうした懸念なども踏まえ、留意事項および取扱いの方針が明文化されました。
*関連記事:福祉用具の介護保険給付対象に「排泄予測支援機器」が追加へ
給付対象は「トイレでの排尿が見込める人」
今回発出された通知にて、「排泄予測支援機器」の給付対象となる具体的な定義と判断基準が示されました。
「排泄予測支援機器」はあくまでトイレでの自立した排尿を支援するものです。給付対象は「トイレでの自立した排尿が困難となっている居宅要介護者等であって、排尿の機会の予測が可能となることで、失禁を回避し、トイレで排尿をすることが見込める者」と定義付けています。
この通知では、Q&A形式で「対象者」についての厚労省の見解がいくつか示されましたので、整理しましょう。
独居でも給付対象となるか
排泄予測支援機器の使用方法については以下の2パターンが想定されます。1.利用者本人が装着し排尿の機会を知らせることで、適時にトイレに移動し排泄する。
2.介助者が通知により、排泄の声かけやトイレへの誘導を行い、本人の排泄を促す。
上記1のケースも考えられるため、独居者は「必ずしも給付対象外になるものではない」とされています。そのうえで、適切な使用によってトイレでの自立した排泄が期待できるのか、十分に検討するよう求めています。
おむつ等を使用していても、自分で準備から後始末まで行っている人は?
十分に検討の上、適切に使用することによりトイレでの自立した排泄が期待できる場合は給付対象となります。
常時失禁の状態の利用者に対して、おむつ交換時期等の把握を目的とした使用は?
あくまでトイレでの自立に向けた排泄を促すことを目的としたものであるため、給付対象にはなりません。
「自動排泄処理装置」を貸与されている利用者は?
自動排泄処理装置を貸与されていることのみをもって、排泄予測支援機器が給付対象外になることはありません。ただし、要介護者等の状態や目的を充分に聴取したうえでの慎重な検討が必要です。
要支援者、要介護4・5の利用者は?
利用者の状態、および排泄予測支援機器の使用によって自立した排尿が期待できる場合は、介護度に関わらず対象となります。
特定福祉用具販売事業者に求められる確認事項について
特定福祉用具販売事業者がこの機器を販売するに当たっては、利用者の身体状況や自立への意思や膀胱機能等の医学的な所見等を事前に確認することが求められています。
利用希望者に対しては、下記の3点の事前確認が必要です。
1.利用の目的を理解して、トイレでの自立した排尿を目指す意志があるか
2.装着することが可能か
3.利用者やその介助者等が通知を理解でき、トイレまでの移動や誘導が可能か
上記3点の確認事項について、注意すべきポイントは下記の通りです。
(1)排泄予測支援機器はトイレでの自立した排泄を促すことを目的としており、失禁をなくすものではないことを理解していること。
(2)製品によっては体型や体質により装着が困難な者もいるとされていることから、製品の特徴等を十分に説明した上で、装着後の状況等を聴取すること。
(3)通知を受信するスマートフォン等の使用に慣れており、通知を確認・理解することができるか。また、使用前の介助状況を確認し、利用者等が主に過ごしている居室等からトイレまでの介助方法や時間等を確認すること。
「利用者の膀胱機能等の確認」については以下のいずれかの方法での確認を求めています。
・介護認定審査における主治医の意見書
・サービス担当者会議等における医師の所見
・介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
・個別に取得した医師の診断書
さらに、市町村に対しては、必要に応じて利用者に試用状況の確認調書を提出させるよう促しています。
 【画像】介護保険最新情報vol.1059「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の改正についてより
【画像】介護保険最新情報vol.1059「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の改正についてより