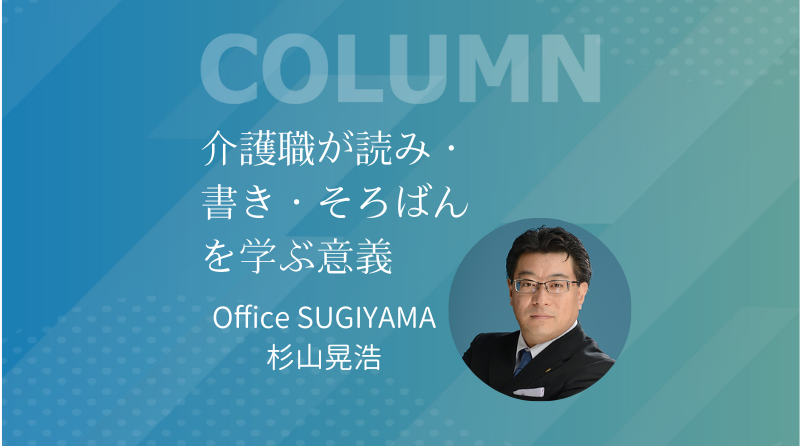長年の課題である介護職員の離職率の高さ。私は、これを解消するには、介護職員が、介護の専門スキルや知識を身に着けるだけでなく、社会人としての基礎能力「読み・書き」、「考える」能力を向上させることが大切だと考えています。
あまり、現代社会では聞くことがなくなった言葉ですが現代版「読み・書き・そろばん」能力といっていいでしょう。
介護現場では、利用者さんやそのご家族、同僚との円滑なコミュニケーションが求められます。その土台となるのがこうした基礎能力ではないでしょうか。
しかしながら、介護職員向けの研修では専門的なスキルに関するプログラムは充実していても、こうした社会人としての基礎能力を開発する機会に恵まれていない場合が多いのが現状です。
そこで、今回は、現代版「読み・書き・そろばん」を能力として身に着けていくためのトレーニングを提案します。ぜひあなたの職場に導入できないか、真似できる部分はないか、検討してみてください。
1.共感力と傾聴力を育む ~利用者さんの心に寄り添う「読む」力~
介護における「読み」の力とは、利用者さんの言葉だけでなく、表情や仕草、行動の変化から、その真意や感情を読み解く力です。この「読み」の土台となるのが、共感力と傾聴力です。利用者さん一人ひとりの個性や人生の物語を尊重し、共感的に関わることができれば、深い信頼関係を築くことができます。
例えば、認知症の方とのコミュニケーションでは、言葉の奥にある本当の気持ちを「読む」ことが重要です。不安や戸惑いを言葉で表現できない利用者さんに対し、表情や行動の変化を注意深く観察し、何に困っているのか、何を求めているのかを察知する力が求められます。
この「読み」の力を高めるためには、日々の業務の中で、利用者さんを注意深く観察し、その言動の背景にある思いを想像する習慣をつけることが大切です。また、傾聴のトレーニングとして、相手の目を見て、相槌を打ちながら、最後まで話をさえぎらずに聴く練習をしてみましょう。「聴いてもらえた」という安心感は、利用者さんの心の安定につながります。
さらに、他の職員と利用者さんに関する情報を共有し、多角的な視点から理解を深めることも重要です。
2.記録と報告の正確性を磨く ~信頼と連携を支える「書く」力~
介護現場における「書く」力とは、利用者さんの状態やケアの内容を正確に記録し、報告する力です。正確な記録は、適切なケアプランの作成、多職種連携、リスク管理の基盤となります。介護記録は、利用者さん一人ひとりの「生活の記録」であり、ケアの連続性を保証する重要な情報源です。
記録を書く上で大切なのは、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識し、具体的かつ客観的に記述することです。
例えば、「○○さん、興奮状態」と書くのではなく、「15時頃、居室にて、○○さんが『家に帰りたい』と繰り返し訴え、落ち着かない様子で室内を歩き回っていた」のように、具体的な状況を描写します。この際、専門用語の多用に注意し、できるだけ多くの人が理解できる、平易な言葉遣いを心がけるべきでしょう。
記録だけでなく、申し送りなど報告の正確性も重要です。口頭による報告は、情報が曖昧になりがちです。報告する際は、要点を整理し、簡潔明瞭に伝えることを意識しましょう。メモを取る、復唱確認するなど、正確な情報伝達のための工夫も必要です。
職員一人ひとりの書く力の向上が、チーム全体のケアの質を高め、利用者さんへ安心で安全なサービスを提供するための「信頼」という強い絆を築き上げるのです。
3.職場のコミュニケーションを革新!読み・書き・考える力のトレーニングと効用―「READ AND WRITE」活用法とその効果
ここまで「読み」や「書き」の能力について、介護職員にも教育機会を設けることをお薦めしてきました。
私達、オフィススギヤマでもスタッフの基礎能力向上のためのトレーニングを取り入れていて、その際のツールとして「READ AND WRITE」というテキストを活用しています。
読み書きのトレーニングの一例として、私の事務所で起こったスタッフの変化にも触れつつ紹介します。
「READ AND WRITE」とは
このテキストは、以下7つの大テーマに基づき、ビジネスの場面で使えるノウハウを1ページごとに簡潔にまとめたものです。75個のノウハウについて「読んで書く」プロセスを経ながら身に着けていくことができます。
①コミュニケーション力②問題解決力
③自己管理力
④チームワーク
⑤思考力
⑥対人関係力
⑦情報活用力
テキストのイメージをお伝えする動画をこちらに用意しました:「READ AND WRITE」(実際に書き込んだもの)。
ここに記載した7つのテーマは、社会人に共通して求められる能力であり、介護現場の業務にも関わってくるのではないでしょうか。
読み・書き・考える力を鍛えるための実践例:オフィススギヤマの場合
次に、スタッフの読み・書き、考える力を鍛えるために私の事務所での取り組みを紹介します。
私達の事務所では、先述の「READ AND WRITE」をテキストに使って、朝礼の始めの5分間に以下のトレーニングを取り入れています。
まず1~4を各メンバーが実施し、その後、当番が自分の考えや気づきをシェアしています。
1.読む (READ): 各テーマに沿ったテキストを、集中して読み込みます。
2.書く (WRITE): テキストの内容を、なぞり書きするか、書き写します。手を動かすことで、内容の理解が深まります。
3.考える : 今回のテーマについて、今日から行動に移すこと、気づき、感想などを自由に書き出し、思考をアウトプットします。これが思考力のトレーニングに繋がります。
4.自己評価: 自分の実践レベルと、テキスト内容の重要度を5段階で自己評価します。
さらに、毎週金曜日には各自が一週間を振り返り、その内容をチャットツールで共有しています。この継続的な取り組みが、スタッフ一人ひとりの成長を促進しています。
スタッフからシェアされた内容を一部公開します。
《スタッフA》
【今週の振り返り】建設的なフィードバック
「良い点と悪い点」を伝えるのではなく、「良い点と改善点」を伝えることが大切だと学びました。
悪い点ならただの批判だが、その改善点を伝えることで、チーム全体の成長だけでなく、自分の成長にも繋がると考えています。自分自身の行動についても「あー、あれは良くなかったな」と後悔するだけでなくて、「次はこうしよう」と改善点を考えることで前向きになれると気付きました。
【今週の振り返り】失敗から学ぶ力
失敗をしたら次がないように必ずメモをとり定期的に見返すようにしています。
また、事務所のみなさんが失敗したときにでも怒ったり責めたりせずに声をかけてくださるので次は迷惑をかけないように…!と頑張れています。同じ失敗を繰り返さないためには人間関係も大事だなぁと感じています。
《介護事業所C》
「READ AND WRITE」を上司と部下の1on1ミーティングのツールとして活用しています。
テキストの内容について質問し、確認することで、部下の知識レベル、事業所への理解、介護への理解などのレベル感を上司が把握し、適切なフォローができるようになってきたとのフィードバックをいただいています。
《介護事業所D》
「毎月の部門会議(デイサービス会議)で『READ AND WRITE』にある『チームワーク』について全体で深堀して、サービスの質の強化を目指しています。スタッフ全員が使用しているテキストは、部門内の共通認識を築く、自社の教科書になっています。
実際に、このトレーニングに参加しているスタッフからは、「コミュニケーションについての項目に特に影響を受け、話し言葉に気を付け、相手の話をよく聞くようになるなど、行動変化を実感している」という声が届いています。
◆『READ AND WRITE(抜粋バージョン)』プレゼント◆
最後までお読みいただきありがとうございます。
今月は、介護スタッフの成長に寄り添うための『READ AND WRITE(抜粋バージョン)』を希望者全員に無料プレゼントします。
介護経営者、管理職、部門長、リーダー職にもぜひおすすめします。
お気軽に下記からお申し込みください。