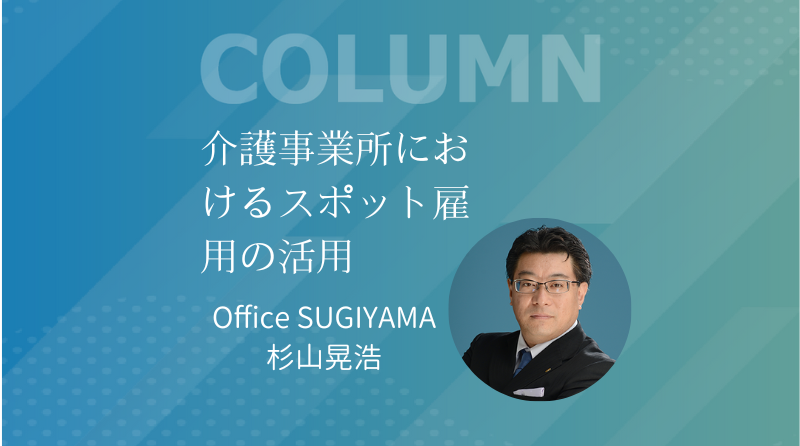先日、オフィススギヤマが関与している介護事業者様が、”スキマバイト”や”スポットワーカー”のような臨時雇用のマッチングサービスを活用して、スタッフ不足を補う取り組みをしていました。この介護事業所はもともと、さまざまな新しいチャレンジにも積極的で、今回のサービス活用もその一環です。
スポットでの雇用やそのマッチングサービスについては、「専門職の集まりである介護事業所で活用することは困難ではないか」という考えがあります。しかし、私は工夫次第で十分対応できると考えています。
スタッフ不足で悩んでいる事業所にはぜひ、今回のコラムを読んでいただき、選択肢として検討いただきたいと思います。
1.介護業界でも注目が集まる”スキマバイト”や”スポットワーカー”
深刻な介護業界の人手不足。少子高齢社会という構造的な要因があるため、すぐには改善が見込めません。職員の確保は事業運営の継続において最も重要な課題となっており、そのための新たな手段として先述したようなスポット雇用サービスが注目されています。
これは、短期間や単発で働きたい人と、急な人手不足に対応したい事業者をマッチングするサービスです。介護事業所では急な欠員があっても繁忙期であっても、サービスに穴を開けることなく運営を続けることが可能になります。
2.スポット労働者の受け入れは業務の切り分けが鍵
介護事業所でこうしたサービスを活用する際に最も重要となるのが、専門職が担うべき業務と非専門職が担う業務を明確に切り分けることです。これは、サービスの質を維持しつつ、効率的な人材活用を行うための基盤となります。
専門職業務は、介護福祉士や看護師などの専門資格を持つ職員が担当すべき業務です。これには、利用者の身体介護、医療ケア、緊急時の対応など、専門知識や技能が必要な業務が含まれます。これらの業務は、利用者の生命や健康に直接関わるため、経験の浅いスポット雇用者に任せることはリスクが伴います。
一方で非専門職業務は、資格や特別な訓練を必要とせず、短期間のトレーニングで対応可能な業務です。これには、施設内の清掃、食事の配膳、備品の管理、レクリエーションのサポートなどが含まれます。これらの業務をスポットで働く労働者に任せることで、専門職が利用者のケアに集中する環境を整えることができます。まさに、非専門職業務を切り出し、スポット雇用者に担当してもらうことが今回のポイントとなります。
3.業務切り分けの具体的な手順とスポットワーカーが働きやすい環境づくり
業務の切り分け方には、さまざまな方法があると思います。それぞれの事業所の業態、組織に合った方法で実施していただければよいでしょう。以下は、事例としてご紹介します。
(1) 業務のマッピングと分類
まず、事業所内の全業務をリストアップし、各業務について専門職の対応が求められる内容かどうかを評価します。このプロセスを通じて、業務を「専門職が担当すべき業務」と「非専門職でも担当可能な業務」に分類します。たとえば、利用者の入浴介助や服薬管理は専門職が担当すべき業務に分類できますが、食事の配膳や清掃業務は非専門職に任せることができます。
※記事の最後で業務リストのフォーム例をプレゼントしていますので、必要な方はお申し込みください。
(2) スポット雇用者専用マニュアルと業務手順の整備
スポットで配属される労働者が効率的に業務を遂行できるよう、わかり易く、短時間で理解できるマニュアルや業務手順書を整備します。
このマニュアルは文字だけでなく、画像や図解を活用し、一目で理解できるようにしましょう。
これを準備することにより、スポット雇用者が短期間で業務に慣れ、一定の品質でサービスを提供できるようになります。
また、業務の標準化を進めることで、誰が担当してもスムーズに業務が進む環境を作り出すことが可能です。
(3) 研修と教育の実施
非専門職業務を担当するスポットの労働者には、就業前に必要最低限の研修を行います。この研修では、基本的な介護業務の知識や、利用者とのコミュニケーション方法、施設内のルールなどを学びます。これにより、利用者とのトラブルを防ぎ、安心して業務に取り組めるようになります。
スポットで働く労働者を受け入れる際に有効な準備やツールとしては次のようなものも考えられます。
- ポスターや標識の設置
介護事業所内の要所に「安全第一」や「ここに注意」といったポスターや標識を設置します。目立つ場所に配置することで、安全意識を高める効果があります。
- クイックリファレンスカード
ポケットに入るサイズの「クイックリファレンスカード」を作成し、いつでも業務チェックができるようにします。
4.スポットワーカー活用における労務管理のポイント
スポットで働く労働者の労務管理について、注意が必要なポイントを解説します。
(1) 労働契約の明確化
スポット雇用者に対しても労働契約を明確にし、契約書に業務内容や労働条件を詳細に記載することが重要です。必ず、労働条件通知書をスポットで働く雇用者に交付し、業務内容等を確認させた後で、了承したことを明確にするサインをさせておきます。これにより、労働者と事業所の双方が権利と義務を理解し、トラブルを未然に防ぐことができます。
(2) 労災保険の適用
スポット雇用者も業務中に事故や怪我が発生する可能性があります。当然のことですが、労災事故が発生したときは、労災保険を活用して事故の補償をしてください。また、万が一の際に迅速に対応できるよう、事前に手続きを確認しておくことが重要です。ここで重要となるのが、労災保険より高度な補償を福利厚生で設けている事業所については、同一労働同一賃金ガイドラインに沿った補償となるよう対応が必要であるということです。
同一労働同一賃金ガイドラインは、雇用形態にかかわらずに均等・均衡の待遇を確保し、同一労働同一賃金を実現するために策定されています。
具体的な対応がわからないときは、所轄の都道府県労働局均等室を訪ねてください。細かく教えてくれます。
(3) 適切な管理体制の構築
スポット雇用者を管理するための体制を整備します。例えば、スポット雇用者が初めて介護現場の業務に就く際には、経験豊富なスタッフがサポートし、業務の進捗をチェックします。これにより、業務の遅延やサービスの質の低下を防ぐことができます。
管理体制を明確にするための手段としては、名札と組織図を活用することをおすすめします。
これでスポット雇用者が困ったときに、どこの誰に聞けばよいのか一目でわかります。シフトによってベテランスタッフがサポートできないときには、組織図が威力を発揮します。
5.長期的な人材戦略としてのスポット雇用サービスの活用方法と事例
スポット雇用サービスは、単なる人材の穴埋めの手段にとどまらず、長期的な人材戦略にも寄与する可能性があります。その理由や切り口について整理してみました。
(1) 人材発掘の場としての活用
スポット雇用サービスを通じて短期的に働いた労働者の中に、適性やスキルが高い人材が見つかることがあります。こうした労働者に対して長期雇用を提案することで、介護事業所の人材確保に役立てることができるでしょう。
実際に事業所の業務に従事してもらうことで、通常の採用プロセスでは見えにくい、実際の仕事ぶりや適応力を確認することができます。
(2) 労働者との信頼関係の構築
スポット雇用サービスの労働者が事業所に馴染み、「長期的に働きたい」と感じるような環境を提供することが重要です。これは、単に仕事を提供するだけでなく、働きやすい環境や成長の機会を提供することで実現できます。これにより、事業所は質の高い人材を維持し、育成することが可能になります。
実際に、私が知る、ある中規模の介護施設では、清掃やレクリエーションのサポート業務でこうした労働者を活用し、大きな成果を上げています。
この施設では、前述したように、事前に業務マニュアルを整備し、各業務の担当者がスポット雇用サービスの労働者をサポートする体制を構築しました。その結果、専門職がより重要なケア業務に集中できるようになっただけでなく、利用者満足度も向上しています。
さらに、同サービスを通じて優秀な人材が見つかり、その後長期雇用に切り替わった例もあります。スポット雇用から始まったスタッフが、適応力や人柄を評価され、常勤スタッフとして活躍している事例は、人材確保の新たな手段として注目されています。
6.スポット雇用サービスの効果的な活用は有効な人材戦略に
いかがでしたでしょうか。
スポット雇用サービスを効果的に活用すれば、事業所の人手不足を解消するだけでなく、業務の効率化やサービスの質向上にも寄与します。しかし、その成功には、専門職と非専門職の業務を明確に切り分け、効果的に人材を活用するための仕組み作りが欠かせません。
また、スポット雇用サービスを単なる労働力の補充手段としてだけでなく、長期的な人材戦略の一環として捉えることで、事業所の持続の可能な運営を支える力となるでしょう。
スタッフ充足のための新しい手段として、試してみてはいかがでしょうか。
◆『介護事業所向け業務リストフォーム例』プレゼント◆
最後までお読みいただきありがとうございます。
今月は、専門職と非専門職に業務を振り分ける時に使うことで業務効率を向上させる『介護事業所向け業務リストフォーム例』を希望者全員に無料プレゼントします。
お気軽に下記からお申し込みください。