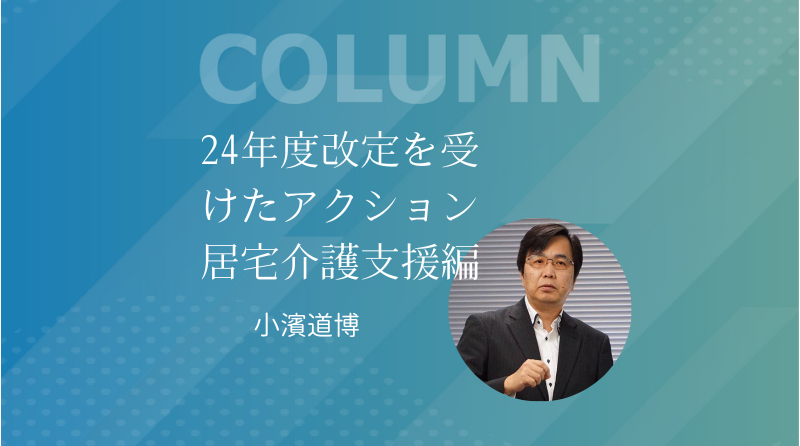2024年度介護報酬改定では、訪問介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護など一部のサービスの基本報酬がマイナスとなった。この2つのサービスは、11月に公表された介護事業経営実態調査においてそれぞれ、7.8%、11%と非常に高い収支差率が示されていたため、ある程度のマイナスは想定できた。
居宅介護支援も4.9%と決して低くは無い収支差率だったので、全体の改定率(0.61%)を超えたことは評価出来る。その分岐点となったのは、賃金アップの考え方である。訪問介護は介護職員だけで構成されるため、介護職員等処遇改善加算もすべてが介護職員の賃上げにまわる。しかし、居宅介護支援には処遇改善加算は存在しない。
1,在宅サービスで最大のプラス改定となった居宅介護支援―増収分はケアマネジャーの賃上げ原資?
居宅介護支援は在宅サービスでは最も大幅な0.9%弱の基本報酬アップだった。しかし、介護職員等処遇改善加算の対象ではないために、事業者は経営努力の中でケアマネジャーの賃上げを実施する必要がある。国も実際に、“引き上げた基本報酬を処遇改善に充てて欲しい”という考えを示している。こうした対応まで視野に入れると、かなり厳しい改定率である。
逓減制が緩和されて担当件数が44件となったことも、収入の増加分をケアマネジャーの処遇改善の原資とする意図がある事は間違いないだろう。もちろん、賃上げは義務では無い。しかし、圧倒的なケアマネジャー不足を勘案すると、その処遇改善は急務であり、大きな経営課題である。
また、既存加算の算定要件の多くも変更となった。新たに同一建物減算も創設され、激変の改定となっている。
2,小規模事業所には対応が難しいターミナルケアマネジメント加算と特定事業所医療連携加算
居宅介護支援では、ターミナルケアマネジメント加算の対象疾患に制限がなくなった。これまでは末期ガンのみだったので算定対象が大きく拡大したことになる。
同時に特定事業所医療連携加算の算定要件において、ターミナルケアマネジメント加算の算定回数が、これまでの5回以上から、15回以上と一気にハードルが上がった。いくら対象疾患が緩和されたとは言え、年間15回の算定は非常に厳しいと言える。特に、小規模事業者の算定は確実に困難となった。
もともと、ターミナルケアマネジメント加算の算定要件である“死亡日及びその前後数日の居宅訪問”は現実的には厳しい算定要件だ。看取り期に入った利用者のケアプランの見直しは、ほとんど必要無い。ただ静かに旅立ちを見守るだけである。居宅訪問の理由が無く、死亡日に訪問する理由も示しにくい。そもそも、死亡日は家族も多忙で、ケアマネジャーの訪問は歓迎されない。
年に15回の加算算定は、ケアマネジャーの在籍人数が多い大規模事業所でない限りは難しい。とは言え、ターミナルケアマネジメント加算は400単位、特定事業所医療連携加算は 月125単位である。可能な限り、死亡日の訪問を出来る体制を仕組みとして構築して算定を目指すべきである。
3,要件緩和の入院時情報連携加算は当日の情報提供で(Ⅰ)の算定を
今回改定は、6年に一度の医療と介護の同時改定だ。その趣旨から、情報連携に関連する加算にも変更が加えられた。入院時情報連携加算はこれまで、情報提供期日が3日以内(200単位)と7日以内(100単位)であったものを、当日中(Ⅰ、250単位)と3日以内(Ⅱ、200単位)に短縮された。7日も経ったらすでに病院は準備を終えている、つまり、情報提供のタイミングとしては遅すぎることがその理由である。
では、新たな報酬区分はどちらを算定すべきか。これは当日中の情報提供が算定要件となっている(Ⅰ、250単位)だと断言できる。報酬単位が増えているというだけでなく、算定しやすくなっているからだ。これまでは、入院日以前の情報提供は認められていなかったが、今回の改定によって同加算では入院日以前の情報提供が可能になっている。
利用者の入院時のシチュエーションをイメージすると、体調急変による緊急搬送の場合を除けば、通常は持病関連による入院だ。それなら一週間前以上は前に入院日が設定される。情報提供は入院日が決まった日に実施すれば良いのだから、余裕を持った対応ができる。
居宅介護支援事業所の基本的スタンスとしては入院日当日に必要な情報を提供することを目指し、何らかの理由で入院日前の情報提供が出来なかった場合は3日以内に切り替えれば良い。
Q&Aでは「入院日以前の情報提供の期日に制限はなく、常識の範囲である」とされた。ただ、現場サイドの声としては、入院日前に情報提供しても受け取って貰えない病院も多いという事だ。医療機関との関係性の強化も必要である。
4,ケアプランに口腔ケアを位置付けることの重要性が組み込まれた通院時情報連携加算及び訪問系サービス
情報連携に関する加算の見直しには、通院時情報連携加算もある。この加算は前回改定で創設された。利用者が病院に通院するときにケアマネジャーが同行訪問し、主治医師と情報交換することで50単位が算定できる。この通院対象に歯科医師が追加された。
来年度からはケアマネジャーの法定研修カリキュラムが変更となり、ここでも誤嚥性肺炎マネジメントが大きく取り上げられる。高齢者の死亡要因で誤嚥性肺炎は高い割合を占め、その予防においては口腔ケアが重要である。しっかりとケアプランに口腔ケアを位置づけることが求められ、歯科医師との連携も重要であることが示された一例である。
このように、加算の算定を検討するときはその意味を理解することが大切な要素となる。
口腔ケアに関しては、訪問系サービスに口腔連携強化加算が創設された。この加算は、事業所の職員が利用者の口腔の健康状態を評価して、その結果を歯科医師と担当のケアマネジャーに報告することで月に一回、50単位を算定できる。これによってケアマネジャーは毎月の利用者の状況を把握して、適切に口腔ケアをケアプランに位置づけることとなる。
5,業務継続計画未策定減算と高齢者虐待防止措置未実施減算は小規模事業所でも例外なく対応が必要
2024年4月より、BCP作成と高齢者虐待防止措置への未対応事業所には減算が適用される。BCPは特例措置があり、居宅介護支援は制限無く一律に2025年4月からの減算適用となるが、虐待防止措置は今年4月から適用されている。業務継続計画未策定減算は1%。高齢者虐待防止措置未実施減算も1%である。注意すべきは、BCPの義務化は24年4月であることには変わりはないという事だ。減算とならなくても、運営指導で運営基準違反として指導対象となる。やはり、BCPの作成と高齢者虐待防止措置は年度内に完了しておくことが必要だ。また、業務継続計画未策定減算の算定要件に、「当該業務継続計画に伴い必要な措置を講ずること」が示されている。
高齢者虐待防止措置未実施減算は、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、専任の担当者の設置の4つを実施して居ない場合に減算となる。こちらの特別措置は福祉用具関連だけであり、居宅介護支援事業所では24年4月からの減算適用となる。また、Q&Aにおいて、委員会、研修、訓練は、少人数の事業所も免れないとされた。1人ケアマネジャーの事業者や少人数の事業所は、他の事業所との共同開催などを模索することが求められる。
6,居宅介護支援へ導入された同一建物減算は今後も引き下げ続く予想
同一建物減算が居宅介護支援に創設された。5%の減算である。
事業所の所在する建物と同一敷地内、または隣接する建物に居住する利用者は、1名から減算。同一建物に居住する利用者が20人以上である場合に適用となる。5%の減算率は、段階的に引き上げられると思われる。次回の改定で訪問介護同様に10%に引き上げられる可能性が高いだろう。
7,身体拘束廃止措置への居宅介護支援事業所における対応
訪問サービス、通所サービス、福祉用具、居宅介護支援については、身体拘束等の適正化のための措置の未実施によって減算にはならないが、緊急やむを得ない場合の身体拘束について、記録の作成が義務化された。求められる内容は、身体拘束の態様、拘束時間、その間の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由である。この四点を、拘束を行う度に、利用者毎に記載しなければならない。また、今回、減算から外されたこれらのサービスも次回改定で減算となる可能性が高い。
居宅介護支援について、どのような身体拘束に該当するケースがあるのかという質問も多い。これに対して例を示すと、利用者の認知症が進行して行動心理症状を発症してケアマネジャーに危害を及ぼす危険があるとして、家族がモニタリング訪問時に拘束服を着せていたりするケースが実際にあった。この事例は、ケアマネジャー自身が拘束を行っている訳では無いが、その状況に関する記録を作成すべき事案だろう。