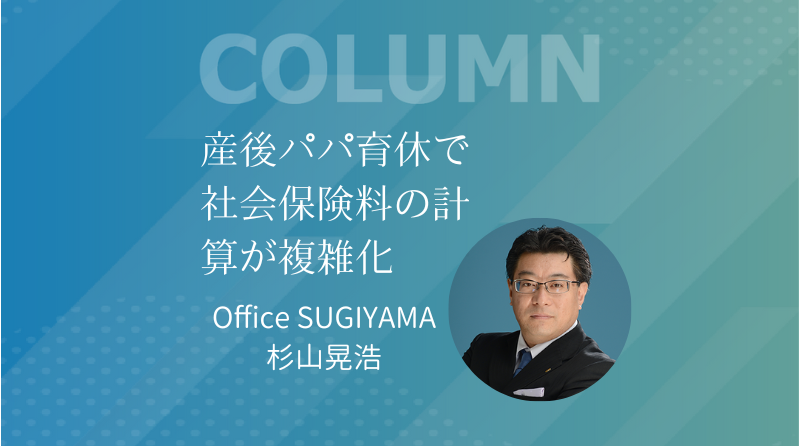事業者に広く関わる法改正に、育児・介護休業法があります。
2022年10月に始まる新制度と事業者に必ず覚えていただきたい対応について解説します。
1.改正育児・介護休業法は段階的に施行
法改正の内容
今回の育児・介護休業法改正の目的は、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするためとされています。
具体的には、2022年4月1日から、育児・介護休業法が3段階で施行されます。
1段階目は、22年4月1日より、次の2つの措置の義務化と取得要件の緩和が行われています。
【1】育児休業を取得しやすい雇用環境の整備以下のうちからいずれか一つ以上の措置を講じる義務
- 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
- 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
- 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
- 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を個別に行う義務
周知事項
- 育児休業・産後パパ育休に関する制度
- 育児休業・産後パパ育休の申し出先
- 育児休業給付に関すること
- 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
個別周知・意向確認の方法
- 面談 ※オンライン面談も可能
- 書面交付
- FAX ※労働者が希望したときのみ可能
- 電子メール ※労働者が希望したときのみ可能
有期雇用労働者のうち引き続き雇用された期間が1年以上の者は、育児休業も介護休業も取得できるようになります。
2段階目は、直前に迫る22年10月1日より、新たに産後パパ育休が創設されます。また、現状では育児休業の分割取得は原則としてできませんが、分割取得が可能となります。
3段階目は、23年4月から、従業員数1,000人超の企業に対して、育児休業等の取得状況を、年に1回公表することが義務付けられます。
産後パパ育休(出生時育児休業制度)はこれまでとは全く違う制度
ここからは、22年10月1日に適用される内容にフォーカスします。前述の通り、育児休業制度の内容が改正され、新たに始まるのが、産後パパ育休(出生時育児休業制度)です。
産後パパ育休とは、育児休業とは別に子の出生後8週間以内に4週間まで出生時育児休業(産後パパ育休)の権利を保障するものです。
厚生労働省が提供している産後パパ育休と育児休業の概要比較資料を見れば、産後パパ育休がこれまでの育児休業とは全く別物であることが容易に理解できます。休業中の就業の可否については、産後パパ育休と育児休業では全く異なりますから、労務管理上で特に注意が必要です。
| 産後パパ育休(R4.10.1 ~)
育休とは別に取得可能 |
育児休業制度
(R4.10.1 ~) |
育児休業制度
(~R4.9.30) |
|
| 対象期間
取得可能日数 |
子の出生後8週間以内に
4週間まで取得可能 |
原則子が1歳
(最長2歳)まで |
原則子が1歳
(最長2歳)まで |
| 申出期限 | 原則休業の2週間前まで | 原則1か月前まで | 原則1か月前まで |
| 分割取得 | 分割して2回取得可能
(初めにまとめて申し出ることが必要) |
分割して2回取得可能
(取得の際にそれぞれ申出) |
原則分割不可 |
| 休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 | 原則就業不可 | 原則就業不可 |
| 1歳以降の延長 | 育休開始日を柔軟化 | 育休開始日は1歳、
1歳半の時点に限定 |
|
| 1歳以降の再取得 | 特別な事情がある場合
に限り再取得可能 |
再取得不可 |
出典:厚生労働省 育児・介護休業法の改正について より
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf
2.育児期間中の社会保険料免除の仕組み
育児休業等期間中の社会保険料の免除とは?
育児休業等期間中の社会保険料の免除とは、被保険者から育児休業または育児休業に準ずる休業を取得することの申し出があった場合に事業主からの届出により、育児休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料が免除となる制度です。
育児・介護休業法が改正となる22年10月1日から、この社会保険料免除の要件が変更されます。
改正されるのは、月額保険料の免除要件と賞与保険料の免除要件の2つです。
厚生労働省の資料では、次のように図解されています。

出典:厚生労働省 令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件についての説明チラシ より
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyuumenjyo-ri-huretto.pdf
22年10月1日以降に社会保険料が免除されるのは、次の3つの場合だけですので、必ず覚えておいてください。月額保険料における14日以上と賞与保険料における1カ月超の期間は、今回の改正においてキモとなる重要な期間となります。

実は育児休業を何月何日から開始し、何日間取得するかによって、社会保険料の免除の可否が決まります。この可否判断ができなければ、育児休業取得者に対して「労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い」の正しい周知ができないこととなります。
社会保険料は労働者にとっては高額な負担です。例えば、人事担当者から育児休業取得予定者に対して、社会保険料が免除されると勘違いして説明してしまい、後日社会保険料の個人負担分を回収する際にトラブルに発展することも想像に難くありません。
3.育児休業中の休業と就労の考え方
休業の定義
休業とは、会社が定めた何らかの理由により、労働契約関係が存続したまま労働者の労務提供義務を消滅させることです。
育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。ただし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することは妨げられません。
ところが産後パパ育休では、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能とされています。またややこしいことに、産後パパ育休中に就労日とされた日に年次有給休暇を取得することもできます。
育児休業日数の計算方法
育児休業では、育児休業期間中は原則就業不可なので、一時的・臨時的な就労をしたとしても、育児休業取得日数に変化はありません。他方、産後パパ育休では、休業期間中に就労が可能なため、就業した日数は育児休業日数から差し引かれます。
すなわち、利用中の制度の種類によって育児休業日数の計算方法が変わってしまいます。その結果、社会保険料の免除要件となる14日や1カ月超の期間に影響を与えてしまい、社会保険料の計算にミスが発生する可能性が高くなるのです。
ちなみに、厚生労働省のQ&Aでは、『育児休業等日数の算定にあたり、休日は含めるのか?』との問いに次のように回答されています。
育児休業等日数は、ある育児休業等の開始日から終了予定日までの日数(当該育児休業等が出生時育児休業である場合、開始日から終了予定日までの日数から就業日数を除いた日数)をいい、その間に土日等の休日、有給休暇など労務に服さない日が含まれていても、育児休業等日数の算定に当たり差し引くことはしない(育児休業等日数に含まれる)。
例えば、産後パパ育休中に就労日とされた日に就労すれば、就労した日数だけ育児休業日数が減ることとなります。就労日に年次有給休暇を取得すれば、有給休暇の日は休業日数の算定にあたって差し引くことはしないため、有給休暇の日数も育児休業日数に含まれることとなります。
連続する育児休業の取り扱い
2022年9月30日までは原則分割不可の育児休業が、10月1日より分割して2回取得が可能となります。産後パパ育休も2回分割が可能です。ただし、分割の申出のタイミングが異なるため、複数のパターンが考えられます。
最初に産後パパ育休と育児休業が連続するケースが考えられます。これは、そのまま通算して計算されます。
次に、育児休業の分割取得は、取得の際に申出すればよいので、1回目の育児休業と2回目の育児休業が連続する可能性があります。この場合も、そのまま通算して計算されます。
ところが、産後パパ育休を分割するときは、最初に申し出ることが必要です。そうなると、産後パパ育休が連続することは考えにくいです。しかし、1回目の産後パパ育休と2回目の産後パパ育休の間が休日のみの場合は、連続しているとして、休日数も加算して計算されます。
連続する育児休業となるケースをいくつか例示しました。
みなさまの職場ではどのようなケースがあり得るのかシミュレーションしてみてはいかがでしょうか。ちょっとしたことで、月額社会保険料が免除になったり、賞与保険料が免除になるなど、とても興味深い考察になるはずです。
男性が育児休業を取得し易くするために、業務ともある程度調整しやすい柔軟で利用しやすい制度として、産後パパ育休が創設され、育児休業制度の見直しもされました。その一方で、人事担当者泣かせの制度になっていることは否めません。
人事担当者が、「労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い」について育児休業取得者に正しく周知するためにも、ケーススタディーはとても重要な意味を持ちます。
◆「育児休業と社会保険料に関する27個のケーススタディー解説動画」プレゼント
最後までお読みいただきありがとうございます。
みなさまが育児休業と社会保険料の関係のケーススタディーを考えるキッカケになれば幸いです。しかしながらケーススタディーを生み出す労力たるや簡単なものではありません。27個のケーススタディーについて杉山が解説した動画を作成しましたので希望者全員に無料プレゼントします。
お気軽に下記からお申し込みください。