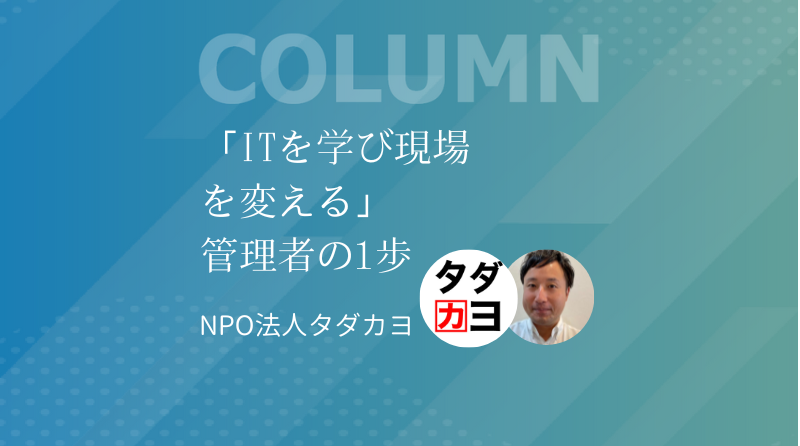はじめまして。わたしは、介護事業所のIT化を支援しているNPO法人タダカヨの本田康志と申します。
普段は介護ITフリーランサーとして、複数の介護の会社の介護DXについて取り組ませて頂いております。また、皆が完全テレワーク型で働く居宅介護支援事業所のDX担当役員という顔も持っています。
こんな私も元々は、特別ITに詳しい人ではありませんでした。
むしろ、現場で事務作業に苦しみ、IT化を進めようにもどうしていいか悩んできた経験があります。そして、この時の経験が現在のタダカヨでの活動の源泉となっています。
主な経歴として障がい者GHの世話人10年、デイサービス勤務7年間と、現場に17年間ほどいました。後に触れますが、デイでは管理者と現場スタッフの双方を経験しています。
今回は、このようなごく一般的な介護職員が、ITを専門として働くことになった経緯をお伝えします。
限界は必ずやって来る :現場業務と事務作業に忙殺される管理者時代
今から10年ほど前。
私はお泊り有りのデイサービスで、管理者として働いていました。
現場業務と事務作業のほか、スタッフ育成や営業など何でもしました。
きっとどこの管理者の方も同じだったと思います。
もしかすると10年たった今でも、介護現場の状況は変わっていないのかもしれません。
本来は、管理業務にもっと専念したいと思っていました。
しかし、介護スタッフが足りていない状況でそれは叶いませんでした。
シフトを組む時は、送迎、フロア、お風呂、夜勤業務がそれぞれ滞りなく回るよう頭を悩ませます。まるで難解なパズルを解くようでした。
それでも急なスタッフの休みでシフトに穴があいてしまうこともあります。
ほかにも現場では突然のトラブルに見舞われます。例えば、お泊り利用が急に入れば、即時に対応せねばなりません。
誰も入れる人がいなければ管理者がカバーします。
そのため、休みの日でも急な出勤となる事が有りました。
このような中で、鈍く重くのしかかっていたのは「事務作業」の負担でした。
記録や売上管理、シフト作成などパソコンと必死に格闘して日々を何とかやり過ごしておりました。しかし、ある日突然、限界が来ました。
「誰かが始めなければ」ITを学び、職場が変わった
負担の大きさについに耐えきれなくなった私は管理者を辞め、職場も変わることになりました。
それでもデイサービスの勤務が好きだったので、今度は一般のケアスタッフとして務めることにしました。
しかし、立場は変わっても毎日は相変わらず目まぐるしく、忙しいものでした。
パソコンに向き合う時間は減りましたが、それでも、計画書の作成や各種記録業務はありました。
このデイではこうした作業を主に手書きでやっていたため、非効率な転記作業などが多く、やはり消耗してしまいました。
「この苦しみは介護業界にいる限り逃れられないのか。いや、なんとかしないと」
これが、介護業界でITと向き合うことを決めたきっかけでした。
しかし、何から始めたらいいのか、どうしたら現状を変えていけるのか。周囲に相談できる人はいませんでした。
職場の上司や先輩、同僚に考えを伝えるだけでは、実際になにも動きません。
とはいえ、業務支援ソフトを購入して導入することも厳しい状況です。
日中はデイサービスで働いて、帰宅後はインターネットで現状を打開できそうな方法を調べる日々が続きました。
当時、現場で使うことができたツールは主にエクセルだけでした。
だから、そのエクセルで自分を苦しめた仕事の負担を減らすためのツールを作ろうと考えました。
情報収集を続けるうちに、プログラミングというものに出会います。
「これだ!」と感じてからは毎日、独学でプログラミングを学びました。
そして実際にいくつかツールを作り、上司にプレゼンを繰り返しました。
その結果、以下のようなツールが導入されるに至りました。
- マウス操作でほぼ入力が完了できて別の計画書からの転記も自動でできる機能を備えた「通所介護計画書」
- 処置の位置などを示す身体図を簡単に作ることができる「ナース処置管理システム」
このほかにも、無料で利用可能なGoogleスプレッドシートやGoogleフォームを利用して、ヒヤリハット報告集計システムを作りました。これによって各職員のスマートフォンなどからいつでも報告ができるようになり、劇的にヒヤリハット報告が増えました。利用者名も匿名であげていたので、個人情報の問題もありません。
また、集計のためのグラフなども自動で作成されるので、管理者の負担も増やしませんでした。
周囲の協力を得るために現場で体験を共有する大切さ
現場で感じた問題意識からツールを開発して、その使い方をサポートする。こうした働き掛けの結果、これらのツールは実際に使って頂けるものになりました。
全て、私の提案を聞いて協力して下さった当時の上司や同僚の皆さんのおかげです。
ただ、この経験から強調したいのは、ITの必要性だけを訴えていても何も進まなかったということです。
周りの方たちが協力的でいてくださったのは、このツールが実際に、現場の意見を起点に作り出されて、現場に合わせて最適化が繰り返されていたものであったことが大きいと思います。誰かが業務改善を始めて、それがちゃんと現場で運用できるものとして示さないと事態は何も好転しません。
この時の経験が、今のタダカヨでのITスキルアップを支援する無料オンラインスクール(タダスク)や無料で実施するITの導入などをサポートする活動(タダサポ)につながっています。
タダサポは、誰かに相談したかったけれども誰にも相談する事ができなかった自身の経験から始めた活動でした。
最初は私一人で行ってましたが、今は信頼できるメンバーみんなで実施しています。支援回数は延べ100回以上となりました。
IT食わず嫌いに「利用者様に喜ばれる体験」が効く
介護業界をITで効率化するための取り組みは大変なことが多いです。
介護従事者は、ITに触れられる機会がそう多くはありません。
その為、食わず嫌いのような苦手意識が自然と生まれているように思います。
まず必要なことは「体験」することだと思います。
現場スタッフの方たちに実際にツールを使って頂いて、実感を重ねていただく事です。
結果的に自分の作ったツールを使ってもらえた経験からそう感じています。
ITの便利さをより多くの介護従事者の方たちに知ってもらう為に実施しているタダカヨの活動に「タダレク」があります。
例えば、「無料のオンラインビデオ会議ツールでオンライン面会ができる」と言っても、ITを使うことに慣れていない方は、「すぐにそれを現場で始めよう」とはいきません。
「知らないこと」、「やったことがないこと」は、介護従事者にとってリスクが大きすぎるのです。
しかし、有名な歌手や芸能人がそのオンラインツールを通してレクリエーションを無料でしてくれるとなるとどうでしょうか?
「利用者様に喜んで頂ける事なので試してみよう」と受け止めてもらえるのではないでしょうか。
その証拠に、先日有名な歌手の方がご出演してくださったタダレクでは10万人以上の方がご参加くださいました。
このようにして、確かにITの便利さを体験する機会が拡がっていっている。と実感しています。
ITツールを上手に使ってより良い介護へ自ら踏み出す勇気を
介護業界でIT活用はこれからどんどん進んでいきます。
間違いなく効率化が望めるからです。
「知らない」「やったことがない」「わたしには出来ない」といった理由で踏み出さないままだと、ただ自身の限界がやってくるのを待つだけです。
それぞれの現場で、誰かが勇気を持って始めようと動くことが必要です。
もし分からない事が有っても大丈夫です。今ならタダサポがあります。
現場を変えようと思っても一人では厳しいこともあるかと思います。だからこそ協力者を少しずつ増やしましょう。ちゃんと具体的に動く仕組みや提案資料などを作って、伝わる様に何度でも改善していきましょう。
その様々な方法を無料で学べる場所がタダスクです。
この動きが日本全国の介護業界に拡がって行くものと確信しています。
まずは無料で利用する事ができる、素晴らしいITツールが数多く有るのですから。
これからのより良い介護業界のために、勇気を出して私達タダカヨと一緒に踏み出してまいりましょう。
「ITを上手に使って、お金をかけずにより良い介護へ」