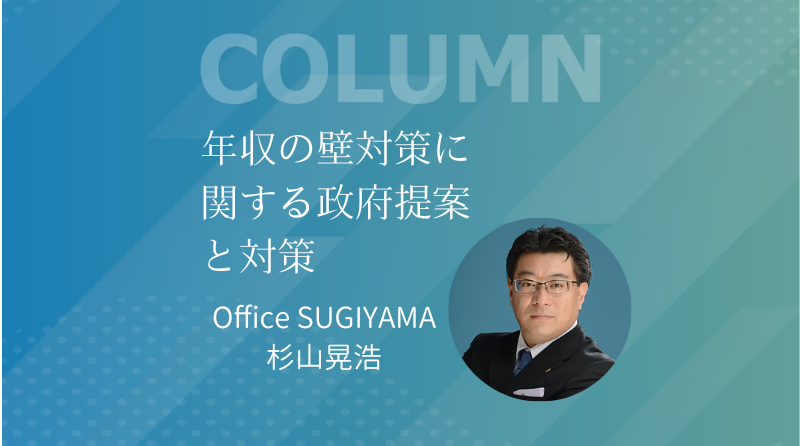政府は、経済成長と分配の好循環を目指し、賃上げや最低賃金の引き上げを推進しています。これにより、フルタイムだけでなく短時間労働者も賃上げの恩恵を受けることが重要とされています。また、2040年までに生産年齢人口が急減するため、労働力の確保が大きな課題となっています。
それらの解消に向けて、政府は「年収の壁」を意識せずに働ける環境の整備を目指し、「年収の壁・支援強化パッケージ」という対策を発表しました。
時期を同じくして、首相官邸主導で、年金事務所の調査が全国的にスタートしています。実態を調査し、雇用保険や所得税のデータと突合するようです。ですので担当官は、徹底的に調査しなければなりません。私が調査に立ち会ったときに担当官から得た情報です。
しかし、私が関与している介護事業者の方と話をしていると、「年収の壁・支援強化パッケージ」に関する情報が正しく伝わっておらず、間違った解釈をしていることも多いように見受けられます。
自社に有利な解釈をせず、しっかりと理解していきたいものです。
1.年収の壁・支援強化パッケージとは?有配偶パート女性の受け止め
現在、約40%の労働者が配偶者の扶養を理由に就業調整を行っています。その理由は、年収106万円または130万円を超えると社会保険料の負担や配偶者手当の減少に繋がるからです。
以下で紹介する野村総研が2023年10月に実施した「年収の壁」対策に関する調査の結果を参考にして、自社の取組みに活かしていくことをお勧めします。この調査では現在「就業調整」する有配偶パート女性の63.2%が、年収の壁対策を利用して、今より年収が多くなる働き方を希望しているという結果が示されています。
「年収の壁・支援強化パッケージ」がもたらす就業調整への影響
問.「年収の壁・支援強化パッケージ」によって、今年10月から年収の壁を超えて働いても手取額は減らなくなり、「年収の壁」を気にせず働くことができます。この制度が利用できるとしたら、あなたは今より年収が多くなるように働きたいと思いますか。

(【画像】野村総合研究所ウェブサイトより)
さらに踏み込んでヒアリングした結果、「今回の支援策を利用して増やしたい年収額」は次のような結果でした。なお、平均額は25.9万円で、中央値は34万円とのことです。
| 今回の支援策を利用して増やしたい年収額 | 月額換算額 | 割合 | |
| 1位 | 20~30万円 | 1.7~2.5万円 | 21.1% |
| 2位 | 50~60万円 | 4.2~5万円 | 16.9% |
| 3位 | 30~40万円 | 2.5~3.3万円 | 16.4% |
「年収の壁・支援強化パッケージ」がもたらす転職への影響◆
問.「年収の壁・支援強化パッケージ」によって「年収の壁」を超えても手取額が減らず「年収の壁」を意識しないで働けるようになった場合、あなたは今の仕事よりも時給が高い仕事に転職したいと思いますか。

(【画像】野村総合研究所ウェブサイトより
)これらの調査結果から、「年収の壁・支援強化パッケージ」の推進により、就業時間の延長や転職の促進に一定の効果をもたらすことが期待できるようです。
これを、自社の状況に当てはめてみた場合、どのような影響があるか考えてみましょう。
多くの介護事業所では人手不足が慢性化しています。短時間労働者の就業時間延長は喜ばしいものでしょう。人手不足解消にはプラスに働きます。
他方で、収入増を目指した転職の促進がすすむと、多くの介護事業所にとっては脅威になるのではないでしょうか。介護事業従事者の賃金が他産業と比較して低いことがその理由です。
要するに介護事業所は、自社の介護労働者の労働時間の延長を目指しながら、転職を防止するという2段構えの方策を実施しなければならないことになります。
2.「106万円の壁」と「130万円の壁」は具体的に何が問題?
「年収の壁・支援強化パッケージ」は、3つの支援策から成り立っています。ただし、今回の措置は2年後の年金制度改革で策定される抜本策までのつなぎ対策として位置づけられていることが大きなポイントです。
年収の壁は2つあります。106万円の壁と130万円の壁です。
いずれの壁も年金や健康保険の加入基準となっており、年収がそれぞれの壁を越えれば、社会保険料負担が発生するため、手取額が減少し、いわゆる働き損が発生することとなります。
106万円の壁の具体的な内容は、次の通りです。
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。さらに2024(令和6)年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。これらの企業等のことを「特定適用事業所」と呼びます。
特定適用事業所に勤務する以下の4つの条件すべてに該当すると、短時間労働者であっても厚生年金と健康保険の加入対象となります。
①週の所定労働時間が20時間以上
②所定内賃金が月額8.8万円以上 ⇒ 年収106万円
③2カ月を超える雇用見込がある
④学生ではない
つまり、年収106万円を超えると、社会保険料負担が発生するために給与手取り額が減少します。さらに配偶者の被扶養者から外れることとなります。その結果、配偶者の勤務先から支給されている扶養手当が不支給となり、世帯として可処分所得が減少することになります。
この対策として、手取り収入を減らさない取り組みを実施する企業に対して、キャリアアップ助成金で労働者1人あたり最大50万円を支援し、短時間労働者の厚生年金や健康保険の加入を促す仕組みを作りました。
130万円の壁の具体的な内容は、次の通りです。
短時間労働者が配偶者の社会保険の被扶養者となるには、収入要件があります。
つまり、短時間労働者の年間収入が130万円未満である必要があります。なお、60歳以上である場合または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者である場合は、年間収入が180万円未満とされています。
要するに、年収が130万円を超えてしまうと、配偶者の社会保険の被扶養者としての地位を失うこととなり、国民年金と国民健康保険に加入しなければならなくなります。社会保険の非扶養者であれば負担することのなかった保険料が発生することとなり、世帯としての可処分所得が減少することになります。
こうした状況の中、今回の政策では繁忙期に労働時間を延ばすなどして収入が一時的に増加しても、事業主が一時的な収入の増加であることを証明すれば、短時間労働者が被扶養者認定を外されずに、これまで通り配偶者の被扶養者のままでいることのできる仕組みが作られます。
3.キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」について
また、企業への支援策としてキャリアアップ助成金では、「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。
「社会保険適用時処遇改善コース」には、一人当たり最大50万円支給の「手当等支給メニュー」と一人当たり30万円支給の「労働時間延長メニュー」の2種があります。
手当等支給メニューでは、新しく社会保険適用促進手当が定義されました。
この手当は、短時間労働者への 社会保険の適用を促進するため、労働者が社会保険に加入するにあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものと定義されています。
特徴として、最大2年間に限り、給与・賞与とは別に支給され、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、社会保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないことができます。
また、事業所内でのバランスを考慮し、事業主が同一事業所内で同じ条件で働く他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合には、同様の取扱いとすることができます。
なお、この手当を導入する際には、就業規則の変更や給与計算ソフトの設定変更など、会社がしなければならない作業がいくつかあります。このあたりを怠ると助成金が不支給になることも考えられますので、労働局や助成金センターと話し合いながら進めるようにしましょう。
労働時間延長メニューは、所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。所定労働時間の延長時間数と賃金の増額割合によって助成金の対象の可否が決定しますので、あらかじめ十分検討したうえで労働時間や賃金額の変更を行ってください。
変更対象となる労働者には、労働条件変更通知書を交付するなど、労働基準法を遵守しながら進めてください。
4.「事業主の証明による被扶養者認定」について
通常、被扶養者が一定の条件に該当すれば、被扶養者ではなくなります。被扶養者でなくなるということは、本人が社会保険料負担をしなければならなくなるということです。
一般的に被扶養者でなくなるのは、つぎの2つのケースがあります。
①厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上の事業所で働く短時間労働者などの場合は、年収106万円以上となり、厚生年金保険・健康保険に加入したとき
②厚生年金保険の被保険者数が常時100人以下の事業所で働く短時間労働者などの場合は、年収130万円以上となり、国民年金・国民健康保険に加入したとき
そもそも被扶養者認定を申請する際には、過去の課税証明書 、 給与明細書 、 雇用契約書など、さまざまな証拠を確認して申請します。
なお、被扶養者認定を受けていても、実労働時間が長くなったり、給与額が高くなるなどしたときには、被扶養者を外れて社会保険料を負担することとなります。
年金事務所の調査では、パートタイマーについて重点的に調査されることがありますが、これは被扶養者に該当するレベルか否かをチェックしているのです。調査結果によっては、保険料時効の最大2年間を遡って社会保険加入を指導されることもあります。
ところが「事業主の証明による被扶養者認定」の仕組みを使って、事業主が『一時的に年収が130万円を超えているが、人手不足による労働時間延長に伴う一時的な収入変動である』と証明することで、被扶養者認定のままいられるようになります。この期間は、最大2年です。したがって、同様の状況が3年目も続いているようですと、当然に被扶養者から外され、本人が社会保険に加入しなければならなくなります。
残業発生により年収が130万円を超えることになるということがポイントです。

【画像】厚生労働省の説明資料より
ちなみに一時的に年収が130万円を超えてもよいという部分を、180万円まで許されると勘違いしている経営者に会ったことがあります。180万円というのは、60歳以上である場合または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者である場合のみです。何らかの資料を見て、130万円を超える数字が180万円だったので、単純に180万円までは大丈夫と判断されたのでしょう。
勘違いは誰にでもあることですが、この状況で労働条件通知書を作成してしまうと、被扶養者認定は100%受けられないと考えます。なぜなら、一時的に年収130万円を超えるということは、元々の労働条件では、130万円未満であることが前提だからです。このような点も注意しておかなければなりません。
5.「配偶者手当の見直し」について
短時間労働者の中には、配偶者手当があるから働き控えをするということがあります。
配偶者手当の支給基準を決定するには、社会保険の被扶養者になっていることが明確でわかりやすいため、社会保険の被扶養者から抜けたくないと考える短時間労働者は多いと推察されます。
諸手当の決定権限は企業が持っています。法律に抵触しない限り、企業はどのような手当でも創り出すことが可能です。
同一労働同一賃金が義務化されたことで、これまで支給されていなかった非正規従業員にも諸手当を支給するようになった会社も多いことでしょう。
さらにここにきて政府主導で、配偶者手当を見直すように促されるのは振り回され過ぎな感じも受けます。
ともあれ、今回政府が主導する配偶者手当の見直しは、次の3パターンを中心に議論が進みそうです。
①配偶者手当を基本給に追加する
②配偶者手当を子供手当に変える
③配偶者手当を資格手当に変える
①については、単純に基本給を増やすだけでは同一労働同一賃金の原則に反します。よって賃金体系の変更など、大掛かりな作業が発生するでしょう。
②については、過去にトヨタ自動車が実施しました。配偶者手当の受給対象者からすれば、不利益変更です。でも、配偶者から子供に対象を変えて若年世代の所得を増やして雇用を守るという大義名分のもとで、合理的な変更として労働組合と合意しています。つまり、不利益変更で訴えられない形で進める必要があります。
③については、配偶者の存在と業務上の資格はリンクしていません。従って単純に変更できるものではありません。
政府は、配偶者手当を支給する企業は減少傾向であるということを強調し、就業調整の一因となる配偶者手当をなくそうとしています。厚生労働省の資料には配偶者手当を支給する企業が減ってきていることを示すグラフが記載されています。
一方で、採用難の時代に配偶者手当があることをアピールして、採用力強化を目指している企業があることも事実です。
配偶者手当については、各社しっかりと考え抜いて対応する必要がありそうです。

【画像】厚生労働省の説明資料より
◆社会保険労務士による「年収の壁・支援パッケージ」に関するQ&A解説ビデオのプレゼント◆
最後までお読みいただきありがとうございます。
今月は、社会保険労務士による「年収の壁・支援パッケージ」に関するQ&A解説ビデオを希望者全員に無料プレゼントします。パンフレットを読むだけではうまくイメージできない、専門用語が多すぎて分かりにくいなどを解消するために、ぜひご覧いただきたい解説ビデオです。
お気軽に下記からお申し込みください。