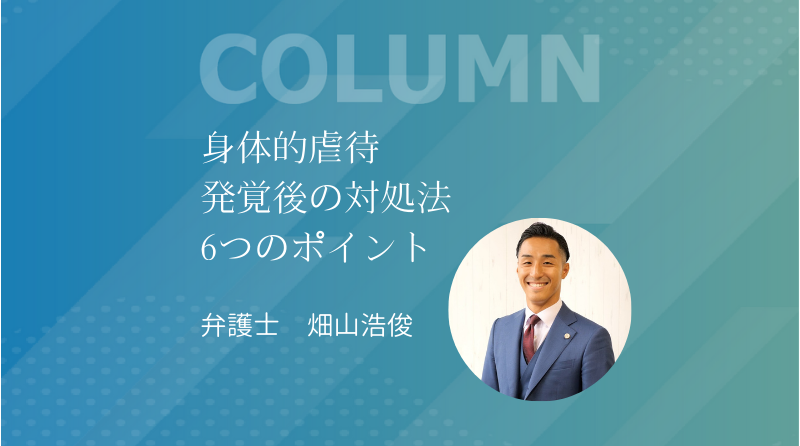1.初動を誤るな!
<ケース>
プルル・・・・
朝7時に施設長の電話が鳴った。
施設長:こんな朝早くに誰だろう。お、夜勤スタッフからだ。何かあったのかな。もしもし?
スタッフ:施設長、朝早くからすみません・・・!
スタッフは泣いており、パニックに陥っている様子だった。
施設長:どうしたのですか!?
スタッフ:実は、花子さん(仮名)を殴ってしまいました。なかなか言うことを聞いてくれなくて、ついカッとなってしまって・・・。大変なことをしてしまった。どうしよう!申し訳ありません。どうしよう・・。
施設長:とにかく落ち着いて下さい!私も今からすぐにそちらへ向かいます!
突然の報告を受けて施設長も混乱している。
一体これからどう対応すれば良いのだろうか・・・。不安な気持ちを抱えて、施設長は全速力で施設へと向かった。
皆様の施設で、仮にこのような身体的虐待事案が発覚したらどのように対応しますか。
「うちの施設では今まで虐待は発生していないから大丈夫だろう。」と安易に考えている介護施設は意外と多いのではないでしょうか。
しかし、「今まで発生していない」ということは、「今後も発生しない」ということを意味しません。発生を予期していない時こそ、職員はパニックに陥り、冷静な判断ができなくなります。
身体的虐待事案の発覚後に、介護施設にとって最も重要なのが初動対応です。
この初動対応を誤ることで、その後の利用者・家族対応や行政対応も難航する可能性が高くなります。
本稿を読んで頂き、初動対応を具体的にイメージすることで、対応する職員がパニック陥ることを防止し、組織全体で冷静かつ同一の対応ができるように、ここで得た知識を共有して下さい。
2.これだけは守ろう!6つのポイント
(1) 利用者の救護措置が最優先
当然のことながら利用者の安全確保が最も大切です。
利用者の状態を確認し、緊急処置の必要性が高いと判断したら迷わず救急車を要請して下さい。
緊急性が認められないと判断した場合でも、必ず医師の診察を受けるようにして下さい。
今回のケースでは、職員が利用者を「殴った」と申告している以上、すぐに医師の診察を受けさせ、怪我の状況を診てもらう必要性が高いです。
(2) 職員からの聴き取りはその日に!
利用者の安全が確保できたら、次に緊急性が高いのは、「殴った」と発言している職員からの事実関係の聴取りです。その職員からは、「殴った」と発言したその日のうちに、必ず聞き取りを行い、正確に記録を取って下さい。別の日に事情聴取を実施しようと思っていると、その職員が辞めてしまい、連絡が取れなくなり、正確な事実関係の把握が困難になってしまう可能性があるからです。
また、その職員に対しては、懲戒処分を検討する必要がありますが、介護事業所として、事実関係を正確に把握するまで、処分内容を確定することは困難です。しかしながら、自ら利用者を「殴った」と発言し、パニックに陥っている職員を、処分が決まるまでの間、漫然と業務を継続させることは絶対に避けるべきです。そこで、必要な調査が終わり、処分が決まるまでの間は、自宅待機命令を出して一旦業務から離れさせ、必要な調査に専念するようにして下さい。
(3) ご家族への報告
職員からの聴き取りができたら、ご家族へ速やかに報告して下さい。ここで重要なことは誠意ある対応です。
どのような虐待であったのか、事実関係を正確に報告し、利用者が今どのような状況にあるのか、どのような緊急対応を講じたのかを報告し、真摯に謝罪するようにしましょう。
ご家族への第一報は、まだ事実関係が全て明らかになっていない状況の中で、電話で行うことになります。
そのため、電話で報告をした後、調査が進んだ段階で、直接会った上で事実関係の報告を再度正確に行うことが望ましいです。電話だけで済ませる話ではありません。直接会って謝罪対応することこそが誠意ある対応に繋がると思います。
もっとも、第一報を受けたご家族も、突然の報告に驚き、ショックを受け、すぐには冷静な判断ができないこともあります。その場合に、執拗に面会を求めることは逆効果となる可能性もありますので、あくまでご家族の予定や気持ちに充分に配慮しながら、面会での報告を提案するようにしましょう。
(4) 警察への通報は必須ではない
「虐待が発覚したら、警察へ通報しないといけないのでしょうか」という質問を受けることがあります。
警察への通報義務は、法律上制定されていません。そのため、結論として、警察へ通報するかどうかは、ご家族とよく話し合った上で決めるようにして下さい。
仮に、介護事業所が、虐待の事実を、ご家族への報告の前に、警察へ通報してしまうと、介護事業所がご家族に虐待の事実を報告する前に、警察からマスコミに情報がリークされ、全国で報道されてしまい大騒ぎになってしまうという場合があります。
ご家族としては、「何で自分たちが知る前にこんな大騒ぎになっているんだ」と感情的に深く傷ついてしまい、もはや介護事業所との関係は修復不可能になってしまいます。
したがって、警察へ通報するか否かは、ご家族とよく話し合った上で決めるようにしましょう。日ごろからご家族との信頼関係が構築できている場合や、むしろそっとしておいて欲しいと考えるご家族の場合は、警察への通報を望まない可能性もあります。
(5) 行政への通報義務
警察への通報義務はありませんが、行政へは必ず虐待の事実について通報して下さい。
これは、高齢者虐待防止法が、養介護施設従事者等に対して、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した際には、速やかにこれを市町村に通報するという義務を課しているからです(高齢者虐待防止法第21条第1項)。通報後、行政調査が実施されますが、再発防止に向けて真摯に対応しましょう。
(6) 保険会社へ連絡
これらの対応が済んだ段階で、虐待の事実があったことは保険会社に連絡しておきましょう。保険会社の約款によりますが、職員の虐待により、利用者に対して損害賠償を負うケースでも、保険が適用される場合があります。
3.弁護士のサポートを受けよう
以上、6つのポイントに基づいて迅速に対応することが大切です。
虐待が発生すれば、どの施設でもパニックが生じ、対応方法に不安を覚えると思います。
しかし、「どうなってしまうのだろう」と恐れの気持ちから初動対応が遅れたり、誤ったりすれば、事態はより一層悪い方へ転がっていきます。
上記の6つのポイントを押さえ、事態を真正面から受け止め、迅速・的確に行動していきましょう。自分たちだけで対応していくことが不安である場合は、顧問弁護士に随時相談し、指示を仰ぎながら対応を進めていくようにしましょう。