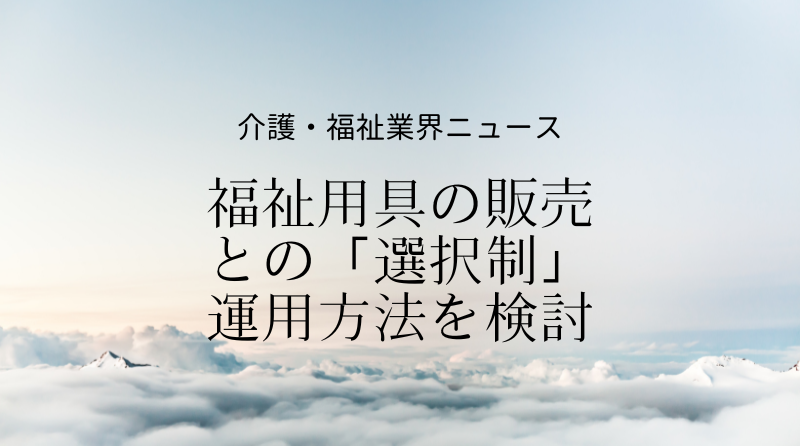介護保険給付の対象となる福祉用具について、厚生労働省は「貸与と販売の選択制」を導入した後の具体的な運用について提案しました。
選択制の対象として示されたのは、固定用スロープや歩行器、杖など、比較的"廉価”とされる5品目です。
ただし、そのプロセスについてはかなり煩雑なルールが提案されたため、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の業務負担増大を懸念する声が続出しました。
「貸与と販売の選択制」の導入と安全・適正利用に向けた今後の対策
「介護保険における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」ではこれまで、福祉用具貸与や特定福祉用具販売を巡る課題や今後の対応に向けた話し合いが重ねられてきました。
注目を集めてきたのが、杖やスロープなどの一部品目について、「福祉用具貸与」と「特定福祉用具販売」のいずれかを選択できるようにするかどうかについてです。
この新たなルールは、2024年度介護報酬改定へ反映することが念頭に置かれており、8月28日の会合では、厚労省が明確に「選択性の導入に向けて」意見を交わすことを求めました。
このほかに、福祉用具の利用安全に関する対策として、
- 福祉用具に関するヒヤリ・ハットに関する情報をインターネットで公表すること
- 介護予防福祉用具貸与の開始時とモニタリング実施時における福祉用具専門相談員の支援の実態や貸与期間設定の根拠などの検証を行い、モニタリングの実施時期を福祉用具貸与計画の記載事項として追加することを検討すること
- 自治体向けに制度の適正利用に関する点検マニュアルを作成すること
などを進めていくことも示され、おおむね了承されました。
「選択制の導入」で焦点となる3つの論点
選択制の導入を検討するにあたり、論点となったのは以下の3つです。
①選択制の対象とする種目・種類
②選択制の対象者の判断と判断体制・プロセス
③貸与又は販売後のモニタリングやメンテナンス等のあり方
杖や固定用スロープなど貸与期間長い品目では選択制を適用か
選択制の対象として提案された福祉用具は「固定用スロープ」「歩行器」「単点杖」「松葉杖」「多点杖」の5つです。
これらは販売価格が比較的廉価であり、購入することで利用者の自己負担が過度とならないことや、保険給付の適正化が図られる可能性のある種目・種類という観点からピックアップされたものです。
厚労省は検討材料として今回、品目ごとの利用期間やその時にかかる費用などのデータを示しています。このデータによると、例えば単点杖や多点杖の場合では、半数以上の利用者が購入によって最終的に自己負担を軽減できることが読み取れます。


(画像引用:介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第8回)資料2)
なお、松葉杖に関しては30カ月以上の長期利用者の割合が比較的少ないことがわかっています。構成員からも、選択制の対象には「不適切」との指摘がありました。
”選択制”の判断や運用についてはに合意形成進まず
次に、”選択制”をどのような場合に適用するかどうかについてです。
まず、対象者について、厚労省は、「一律に限定することは困難」との見方を示しており、”介護が必要になった原因”などで線引きすることは避ける方針を示しました。こちらについては構成員からの賛同が得られています。
一方で、判断のプロセスに関する提案については、意見が分かれました。
まず、たたき台として示されたのは以下の通りです。
- 介護支援専門員または福祉用具専門相談員が、サービス担当者会議等を通じて、利用者らに販売または貸与を提案し、合意に基づき方針を決定する。
- 提案の際、取得可能な「医学的な所見」や類似する「利用状況に関するデータ」などを活用し、利用者の身体状況や福祉用具の利用状況などの変化が想定される場合は、貸与を提案する。
- 「利用状況に関するデータ」については、今回示したデータに加え、状態別にみた福祉用具の貸与月数等に関する追加データについても、今後国が介護DB等を活用して整備し、これらのデータを国が関係者に提示する。
- 貸与を選択した場合においても、例えば6カ月ごとにサービス担当者会議等を通じ、必要に応じて貸与から販売への切り替えを検討する
この、厚労省の提案に対しては、「6カ月ごとのサービス担当者会議は負担が大きいのでは」「ケアマネジャーや福祉用具専門相談員等の業務負担が増えるのは明白」といった業務負担の増大を懸念する意見が事業者団体や専門職を代表する立場から示されています。また、安全性の面から「特に移動関連の福祉用具は、購入により使用方法の確認や保守点検が十分に行われなくなる可能性がある」という指摘もありました。さらには、選択制を導入することによる財政効果について疑問を呈する意見も出ています。
厚労省の提案内容に賛同する声もありましたが、全体としては反対意見が目立っていました。
次回の会合では提案を再整理したうえで、議論が深化されていく見込みです。