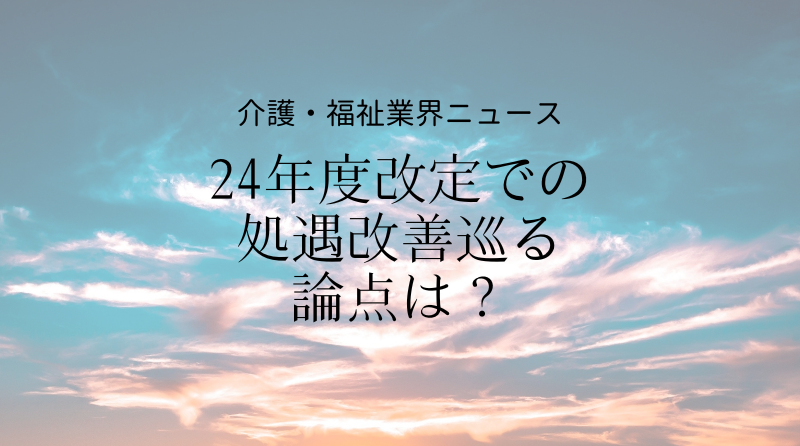2024年度介護報酬改定の気になる論点に、介護職員のさらなる処遇改善があります。5月の社会保障審議会・介護給付費分科会では、2024年に迫る介護・医療同時改定に向けた議論がスタートし、人材の確保を目的とした職員のさらなる処遇改善に関する意見が多くあがりました。
2024年度介護報酬改定に向けた中心的な検討テーマとしての人材確保
24年度の介護報酬改定でも、人材確保に関する施策は中心的なテーマに位置付けられています。生産性の向上という文脈とセットで、処遇改善関連加算の一本化についても検討される見通しです。
改定に向けた実質的なキックオフの回となった5月24日の社保審・介護給付費分科会でも様々な意見がありました。中でも多数の声が聞かれた「処遇改善」について焦点を当て、ご紹介します。
介護給付費分科会で注目の「処遇改善」を巡る3つの論点
人材確保に向けた「処遇改善」に関する今後の見通しと、専門家からあがった意見をまとめて整理します。主な意見・要望は以下の3つに分かれます。
- 処遇改善関連加算の一本化・事務負担軽減に関する要望
- 介護職員を対象にしたさらなる処遇改善策の有無
- 処遇改善加算の対象職種を拡大を求める声
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.処遇改善関連加算の一本化・事務負担軽減に関する要望
2022年度の臨時介護報酬改定で「介護職員等ベースアップ等支援加算」が新設され、処遇改善に関する加算は「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」との3本立てになっています。

【画像】厚生労働省「第217回社会保障審議会介護給付費分科会 資料1」より
これに対し、現場職員や業界団体などからは事務負担が大きく分かりにくいとの声があがっています。寺原朋裕参考人(全国知事会)は現場の事務負担だけでなく自治体による審査にも時間を要している現状に触れ、「加算額の更なる充実とともに、制度の簡素化による事務負担の軽減についても検討を」との意見を示しました。
2.人材確保につながるさらなる処遇改善策の有無
介護業界の「人材確保」に関する課題に触れ、さらなる処遇改善策の検討を求める意見も続出しました。
日本医師会の江澤和彦委員は「サービス提供体制の崩壊を危惧している」とし、「診療報酬も介護報酬も大半は人件費に使われており、抑制する状況には全くない。制度の安定性・持続可能性を確保するために財源の確保が不可欠。総力を挙げて取り組むべきだ」と意見を述べました。
日本労働組合総連合会の小林司委員は「ケアの質の向上を図るため、人材確保の後押しとなる取り組みを報酬改定でも強力に推し進めることが重要」と述べたうえで、「2023春闘での賃上げの流れを介護現場で働くすべての人に行き渡らせるよう、介護報酬体系の簡素化も意識しつつ更なる処遇改善を行うべき」と訴えました。
また、急激な物価高騰の影響を危惧する声も多く、全国老人福祉施設協議会の古谷忠之委員は「物価高騰が事業所運営に多大な影響を及ぼしており対応が不可欠。制度の安定性や持続可能性の確保の中でしっかり協議してほしい」と主張しました。
3.処遇改善加算の対象職種を拡大を求める声
審議会では処遇改善加算の対象外となっている職種への対策を求める声もありました。全国市長会(豊中市長)の長内繁樹委員は「人への投資」の必要性に言及し、「処遇改善加算の対象を拡充するなど、介護職員全体の賃金水準の底上げを行っていただきたい。またケアマネジャーの人材確保も難しいとの声があり、この点も踏まえて議論を進めて欲しい」と述べました。
日本介護支援専門員協会の濵田和則委員は「40歳未満のケアマネは介護職員の賃金を下回っているとの調査結果も出ている。例えば現行の処遇改善加算の対象に(居宅)介護支援を含めるなど、何らかの賃上げ策による人材確保難の改善を期待したい」と提言しました。
「すべての職員の処遇改善を必ず実施する必要がある」(古谷委員)などの追加的な処遇改善策を求める意見が出た一方で、健康保険組合連合会の伊藤悦郎委員は「今後は介護保険料率の大幅な引き上げが見込まれ、現役世代はこれ以上の負担増に耐えられない」と警鐘を鳴らし、メリハリをつけた制度実現を検討する必要性を訴えました。
診療報酬との同時改定:分野横断的な4つのテーマに注目
この日の会合は、処遇改善のほかにも2024年度介護報酬改定を巡って横断的な意見が交わされています。
厚労省からは今後の議論における分野横断的なテーマとして、以下の4つの柱が示されています。
- 地域包括ケアシステムの深化・推進
- 自立支援・重度化防止を重視した質の高い介護サービスの推進
- 介護人材の確保と介護現場の生産性の向上
- 制度の安定性・持続可能性の確保
また、24年度改定は診療報酬と介護報酬の同時改定となります。この日の会合では、診療報酬について議論する中央社会保険医療協議会総会と介護給付費分科会の委員の意見交換の内容についても共有されました。この日出席していた医療の専門家らからは看取りを含めた介護現場で提供される医療の在り方について、「医療介護連携に係る議論を深めるべき」との声があがりました。
今後、介護給付費分科会では、年内に「報酬・基準に関する基本的な考え方」の取りまとめに向け、議論を深めていく予定です。なお、次回の会合は6月28日に実施される予定です。