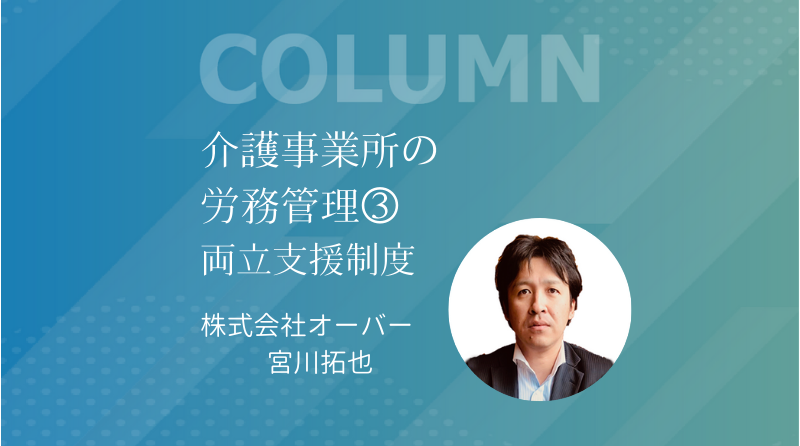前回の記事に続き、介護事業所における働き方改革を戦略的に実践するポイントについてお伝えします。第3回目は「両立支援制度と令和3年度助成金」について扱います。
両立支援に取り組む際に活用できる助成金
皆様は、「両立支援」という言葉を聞かれた事がありますでしょうか?
労務管理における両立支援とは通常、仕事と家庭の両立、具体的には「仕事と育児」「仕事と介護」「仕事と治療」などの両立を意味します。
少子高齢化に伴う労働力人口の減少、働く方々のニーズの多様化にともない、育児や介護、そして病気の治療や不妊治療と仕事の両立ができる職場環境の整備が重要となっております。
事業運営においては、この部分にどれだけ対応できるかによって、雇用定着や人材獲得等に影響が及びます。
「育児」「介護」「治療」と就労との両立支援については、“できれば対応した方が良い”という部分の他に、事業者が“必ず対応しなければならない”という部分があります。
両立支援に取り組む事業所に活用を検討頂きたいのが、「両立支援等助成金」です。
この助成金は、支援の内容によってコースが分かれており、「出生時両立支援コース」「介護離職防止支援コース」「育児休業等支援コース」については、育児・介護休業法の改正等も相まって「育児休業等制度」や「介護休業等制度」の周知が進んだことから活用される方が多くなられました。育児・介護休業制度の整備は法律で義務づけられている以上、事業所として対応しなければなりません。ぜひご活用を検討頂きたい内容です。
下記にその概要をご紹介します。
●出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業等を取得した男性労働者が生じた事業主に助成されます。
●介護離職防止支援コース
「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業事業主、または介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主に助成されます。
①介護休業:対象労働者が介護休業を合計5日以上取得し、復帰した場合
②介護両立支援制度:介護のための柔軟な就労形態の制度(*)を導入し、合計20日以上利用した場合
(*) 介護のための在宅勤務、法を上回る介護休暇、介護フレックスタイム制、介護サービス費用補助等)
③新型コロナウイルス感染症対応特例:新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護するために特別休暇を取得した場合
●育児休業等支援コース
①育休取得時
②職場復帰時:「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象労働者の円滑な育児休業の取得・復帰に取り組んだ場合に助成されます。
<職場支援加算>:育休取得者の業務を代替する職場の労働者に、業務代替手当等を支給するとともに残業
抑制のための業務見直しなどの職場支援の取組をした場合に助成されます。
③代替要員確保時:育児休業取得者が、育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員を確保し、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合に助成されます。
<有期雇用労働者加算>育児休業取得者が期間雇用者の場合に助成されます。
④職場復帰後支援:法を上回る子の看護休暇制度(A)や保育サービス費用補助制度(B)を導入し、労働者が職場
復帰後、6カ月以内に一定以上利用させた場合に助成されます。
⑤新型コロナウイルス感染症対応特例:小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために特別
休暇制度及び両立支援制度を導入し、特別休暇の利用者が出た場合に助成されます。
●不妊治療両立支援コース
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度について、次の①~⑥のいずれか又は複数の制度を組み合わせて導入し、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度を利用させた中小企業事業主への支援です。
① 不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、② 所定外労働制限制度、 ③ 時差出勤制度、④ 短時間勤務制度、⑤ フレックスタイム制、⑥テレワーク
●女性活躍加速化コース
女性労働者が、出産・育児等を理由として退職することなく、能力を高めつつ働き続けられる職場環境を整備するために、自社における女性の活躍に関する状況把握・課題分析を行った上で、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、課題解決に相応しい数値目標及び取組目標を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定・公表・届出を行い、取組目標を実施した結果、数値目標を達成した中小企業事業主に支給されます。
●新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主に助成されます。
※助成金額等の詳細は下記を参照ください。〈2021年度両立支援等助成金〉
助成金受給の目的化は事業運営に負担をかける場合も
助成金については、積極的な情報収集をおすすめしています。
申請するかどうかは別として、助成金の中では、「この内容だったら申請できたのに・・」という気付きを得ることは、今後の雇用の参考になります(知っていれば良かった・・という声も多く頂きます)。
助成金を申請する際には、注意すべき事があります。
まず、助成金の申請には、雇用保険等の適切な加入の他に当然ではありますが、法律で定められている労務管理をしている必要があります。就業規則等の規定においても、しかるべき内容が記載されている事が求められます。
また、助成金の種類によっては、雇入れ前後の6カ月間に事業主の都合で従業員を解雇や退職させた場合、受給できないケースがあります。
助成金を活用するポイントは、「助成金を受給するために経営をしない事」です。
助成金は事業運営において確かな支援となります。ただし、助成金を受給するにはそれぞれ取り組むべき事、達成すべき事が定められています。そのため、助成金を受給するための対応が負荷となり、自社の事業運営に影響を及ぼす可能性があります。
そのような事態を避けるため、法律や制度の改定等で定められているなど対応が必須でない場合は、自社にとって適切なタイミングで対応されることをおすすめします。
助成金を申請するために現場に負担をかけ、その運用に縛られた結果として事業運営が行き届かなくなる事態は避けなければなりません。
※この記事は、難しい用語を極力削減し、わかりやすさを重視しています。
この記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
第4回目は今回に続き、働きやすい職場づくりのための令和3年度の助成金の活用についてお届けします。