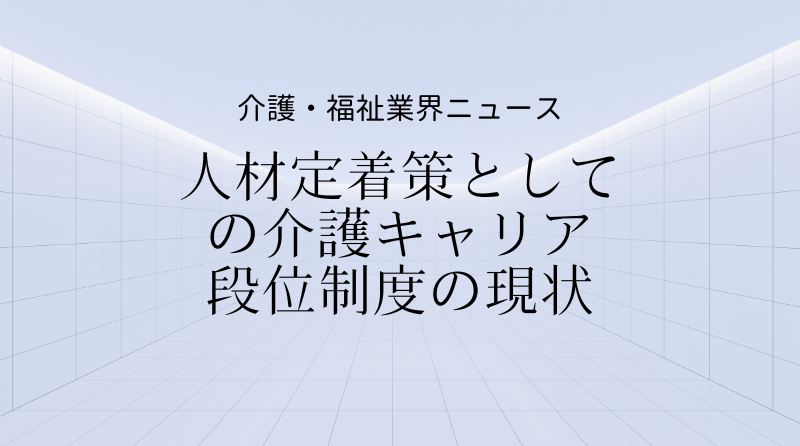厚生労働省はこのほど、介護職員の実践的なスキルの向上を後押しするための国による施策・介護プロフェッショナルキャリア段位制度(以下、介護キャリア段位制度)に関する調査結果を公表しました。介護職員の能力や事業所内での役割分担に応じたキャリアパスを構築するための仕組みとして国が活用を促進している仕組みです。
介護事業所の8割が制度を認知していて、その導入効果を実感する声もありますが、活用割合は低水準に留まっています。
本稿では、調査結果を基に、介護施設や事業所、自治体における介護職員のキャリア構築の取り組みについてお伝えします。
介護事業者・介護職の課題対応力強化に向けた調査の目的・概要
「介護事業者(介護職)における課題対応力強化に向けた調査研究」(2021年度老人保健健康増進等事業である)の目的は、2021年度介護報酬改定で積み残されていた課題を検討していくための材料を得ることです。
具体的には、「認知症への対応力向上に向けた取組の推進」、「中重度者・看取りへの対応や自立支援・重度化防止の取組の充実」など、現場での課題対応力強化に向けた取り組み実態や支援の在り方について手掛かりを集めています。
また、こうした項目について介護キャリア段位制度を用いて現場職員の資質向上につながった記録データを分析し、課題対応力強化につながる効果的・効率的な取り組みを探り、同制度の活用実態と課題も調べています。
調査方法・対象者・対象期間
「介護事業所」「都道府県」「介護職員」を対象にして、課題対応力強化に向けた取組みに関する調査(データ分析またはWebアンケート)を実施しました。
<介護事業所>
- 対象者:全国老人福祉施設協議会、老人保健施設協会、民間介護推進委員会の3団体
- 調査期間:2022年1月24日~2月22日
- 回収数:995事業所
<都道府県>
- 対象者:47都道府県の介護人材育成担当
- 調査期間:2022年2月16日~2022年3月11日
- 回収数:47都道府県
<介護職員>
- 課題対応力強化の取り組み前における資質実態データ分析
- 課題対応力強化の取り組みによる介護職員の行動・意識変化分析
介護プロフェッショナルキャリア段位制度とは
そもそも「介護キャリア段位制度」とは、2012年に内閣府が創設した制度です。役職や肩書ではなくキャリアや能力で評価される社会を目指すものであり、成長分野における新しい職業能力を「わかる(知識)」と「できる(実践的スキル)」の両面から評価することを目的とした仕組みです。
企業や事業所単位でバラつきのない“共通のものさし”によって人材育成を目指すものであり、2015年からは厚生労働省の補助事業となりました。
この制度では、スキルの向上を目指す職員が、レベル1からレベル4までの4段階の基準で認定を受けることができます。レベル4以上になると、「アセッサー(評価者)」として介護職員の「できる(実践的スキル)」の度合いを評価するとともに、スキルアップ支援(OJT=On the Job Traning)」を行う役割を担います。
 *画像引用:内閣府「キャリア段位制度についてのリーフレット」より
*画像引用:内閣府「キャリア段位制度についてのリーフレット」より
この制度の導入効果としては、評価基準を用いた評価・OJTを通じて介護職員の実践的スキルの向上を図り、学習のPDCAサイクルを介護職員だけでなく、事業所内にインソーシング(根付かせていく)することが期待されています。

画像引用:「介護事業者(介護職)の現場での課題対応力強化に向けた調査研究事業」報告書【概要版】より
しかし、こうした目的や役割とは裏腹に、今回の調査では「介護キャリア段位制度」が現場で十分に活用できていないという実態が明らかになっています。
「介護キャリア段位制度」実践活用は事業所・自治体ともに低水準
介護事業所に対する調査結果では、介護キャリア段位制度について「知っている」と回答した割合は8割を超えています。一方で、「知っているが、事業所内にレベル認定者やアセッサー(評価者)はいない」が53.9%、「知らない」が19.5%と、全体で73.4%もの事業所で十分な活用がなされていませんでした。

画像引用:「介護事業者(介護職)の現場での課題対応力強化に向けた調査研究事業」報告書より
また、介護サービス事業種別ごとに認知度や活用水準に開きがあり、認定者・アセッサーがいる割合は、介護老人保健施設が40.5%ある一方で、通所介護では8.4%に留まっています。

画像引用:「介護事業者(介護職)の現場での課題対応力強化に向けた調査研究事業」報告書より
都道府県を対象とした調査結果でも、44県(93.7%)が介護キャリア段位制度を認知しているものの、人材育成施策として反映させている自治体は13県(27.7%)のみ。20県(42.6%)が「人材育成施策への反映予定はない」と回答しています。


画像引用:「介護事業者(介護職)の現場での課題対応力強化に向けた調査研究事業」報告書【概要版】より
反映予定がない理由では「他の施策で支援している」「介護事業所等からの具体的な要望・ニーズがない」などの回答が集まりました。
「介護キャリア段位制度の導入と活用がはかられるために必要なこと」の設問に対しては、下記の回答が上位を占めています。
・取組みに対する介護報酬上の位置付けの明確化(68.1%)
・地域医療介護総合確保基金における施策の位置づけの明確化(34.0%)
・取り組み成果に対する事業所への助成・支援等の推進(34.0%)

画像引用:「介護事業者(介護職)の現場での課題対応力強化に向けた調査研究事業」報告書より
取組み事業所からはポジティブな評価・効果あり
介護キャリア段位制度に取り組む事業所からは、介護の課題対応力への効果について、「介護職員の介護技術について再認識できた」が77.5%、「自ら介護の内容を振り返り、気付きにつなげるようになった」が53.3%、「根拠(エビデンス)に基づく指導や助言ができるようになった」が51.7%と、効果を実感する声が多数を占めています。

画像引用:「介護事業者(介護職)の現場での課題対応力強化に向けた調査研究事業」報告書より
課題対応力強化を行う上での「他者による評価」の仕組みの必要性については、「必要」と回答した割合が77.3%にのぼり、8割近い事業所で他者評価の機会の必要性を認識する結果となっています。

画像引用:「介護事業者(介護職)の現場での課題対応力強化に向けた調査研究事業」報告書より
介護キャリア段位取り組み事業所と未取り組み事業所とを比較すると、「観察する力」、「多角的に検討したり、分析する力」、「多職種との連携、介護の専門職として発揮する力」、「根拠に基づく介護の指導力」について、育成認識に有意な差が生じていました。

画像引用:「介護事業者(介護職)の現場での課題対応力強化に向けた調査研究事業」報告書【概要版】より
課題対応力強化の取り組みによる介護職員の行動・意識変化分析結果でも多くの変化を実感する回答が多く、介護キャリア段位制度の取り組みには多くのメリットが期待されます。