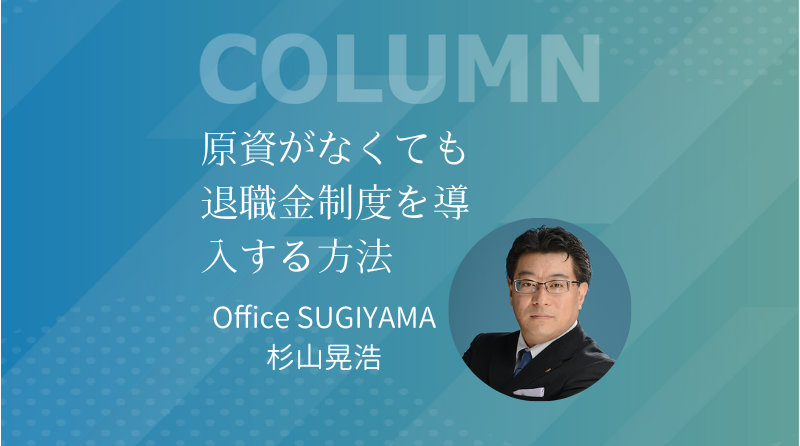1.退職金制度における会社の責任とは
法律で強制されていないため、退職金制度がない介護事業所は多く存在しています。
しかし、最近では、「退職金制度がないと退職されてしまう」、「退職金制度がないと求人への応募が来ない」といった理由から、制度を導入する介護事業所が増えてきています。
でも、いったん退職金制度を作ってしまうと、将来にわたってスタッフに退職金を支給することを約束することになります。この約束は、一般的に退職金規程という形でスタッフに周知されます。
それでは、退職金制度に対する会社の責任を考えてみましょう。
1.法令遵守
事業所は、退職金に関連する法律や規制を遵守する責任があります。
「退職手当の有無」を文書で明示する、退職金制度が存在するなら就業規則に記載する、といった労働基準法上の決まりです。退職金制度に基づき支払われる退職金は、賃金として扱われるため、恣意的に退職金を支給しない行為は賃金未払事案として訴えられる可能性があります。
なお、退職金は賃金の一部ではありますが、税金面の取り扱いは、給与所得ではなく退職所得となり、消滅時効は賃金債権が当面の間は3年であるのに対し、退職金債権は5年であるなどの違いがあります。
2.適切な情報提供
事業所は、スタッフに対して退職金制度に関する適切かつ明確な情報を提供する責任があります。これらの情報の中には、退職金制度の詳細や適用条件、退職金の算定方法、支給時期、制度の変更などについての情報が含まれます。適切な情報提供の下で、スタッフは将来の退職金に関する権利や手続きを理解し、安心して勤め続けることができるからです。
3.継続的な管理と運営
事業所は、退職金制度を継続的に管理し、適切に運営する責任があります。退職金原資の内部留保や掛社外積立を確実に実施することにより、退職金制度の継続性を担保することに繋がるからです。仮に退職金原資を確保できなくなったときでも、事業所には、資産を切り崩す、借入をするなどして、退職金を支払う義務があります。そうならないためにも、管理と運営はとても大事なことです。
4.公正な取り扱い
事業所は、退職金制度を公正かつ平等に運営する責任があります。同一労働同一賃金の考え方の下で、すべての身分のスタッフに対して公平な条件で退職金を提供することが求められます。
5.制度変更や廃止
事業所は、退職金制度の変更や廃止をするには、スタッフに対して適切な説明や同意を求める責任があります。スタッフの有利になるように退職金制度を変更することは容易にできます。一方で、不利益変更や廃止に対しては、丁寧な説明を実施し、スタッフの自由意思に基づく同意を得ることで無用なトラブルは避けられます。
以上のように、退職金制度を導入することで事業所には大きな責任が生じることを肝に銘じておかなければなりません。
2.確定給付型退職金制度と確定拠出型退職金制度のどちらがよいか?
◆確定給付型退職金制度(DB)のメリット・デメリット
| メリット | デメリット | |
| 事業主 |
|
|
| スタッフ |
|
|
◆確定拠出型退職金制度(DC)のメリット・デメリット
| メリット | デメリット | |
| 事業主 |
|
|
| スタッフ |
|
|
3.選択型確定拠出年金という選択肢
企業型確定拠出年金(DC)とは、企業が掛金を毎月拠出し、スタッフが自ら掛金の運用を行う制度です。スタッフは、掛金をもとに、金融商品の選択や資産配分の決定などを行います。そして定年退職を迎える60歳以降に、積み立て運用してきた掛金を一時金(退職金)、もしくは年金の形式で受け取ります。ただし、積み立てた年金資産は原則60歳まで引き出すことはできません。
原則として掛金は毎月5万5,000円が上限となります。一定の制約はあるものの、iDeCoに加入しているスタッフでも活用できるなど、制度自体がかなり整備されてきています。
DCは、掛金の負担方法によって3つのタイプが存在しています。
①全額企業型:掛金の全額を事業所が拠出します。一般的な退職金と変わりません。
②マッチング拠出型:事業所が掛金を負担し、事業所負担と同額までスタッフが掛け金を拠出できます。なおスタッフの掛金額には一定の制約があります。また、iDeCoとの併用ができない点がデメリットです。
③スタッフ選択型:スタッフが自身の給与や退職金などの一部を、掛金として拠出するか、これまで通り給与や退職金として受け取るか、自らの意志で選択することができるというものです。確定拠出年金への加入自体をスタッフが選ぶことができる制度です。掛金を拠出したくなければ、これまでと変わらず給与で受け取るだけなので、何ら影響も及びません。要は、老後生活資金を形成するために掛金を拠出して運用するか、今すぐ現金として受け取って、自身で使いみちを検討するのか、という選択を行うということです。
①~③の特徴を図式化すると以下のようになります。お気づきの方もいらっしゃるとは思いますが、③の選択型だけは、スタッフの給与と掛け金の総額が導入前の給与額30万円と同額になっています。さらに、企業掛金は存在していません。
これは、「スタッフ選択型」の企業型確定拠出年金が、スタッフ自らが給与として報酬を受け取るのか、掛金として老後資金積立をするのかを自由に選ぶ仕組みだからです。最低賃金を下回らない範囲で基本給等が設定されていれば、スタッフの掛金は月額3,000円から5万5,000円の間で1,000円刻みで自由に決めることができます。プランにもよりますが、運用商品は投資信託やリートが中心で、元本保証の預金も商品メニューにあります。資産運用に抵抗がある方でも預金であれば安心して利用できるのではないでしょうか。

4.経営者視点でみる企業型選択制確定拠出年金の魅力
スタッフにとって退職金制度は、福利厚生的満足度を高めるものです。
企業型選択制確定拠出年金は、スタッフのみならず経営者にとっても魅力満載の制度です。まだまだこのことを知らない経営者が多いので、そのポイントをお伝えします。
①経営者の退職金準備の手段として利用できる
掛金は全額損金で、スタッフが運用するのと同様に非課税特典が利用できます。ただし、あまりにも優遇されているため、月額5万5千円、年間66万円が利用できる上限額となっています。
②一人法人でも利用できる
条件が整っていれば、一人法人でも利用できます。
③相続対策、株価対策になる
ちょっと変わった見方をすると、企業型選択制確定拠出年金は法人資産を非課税で個人資産に移すことができる唯一の制度といえるのではないでしょうか。法人の資産が個人資産に移れば、株価評価が下がりますから、相続対策としても利用できます。
④所得税、住民税、社会保険料の対象外である
高額な報酬をもらっていると税金や社会保険料の高さに嫌気がさしている経営者も多いのではないでしょうか。経営者が企業型選択制確定拠出年金を利用するときは、役員報酬はそのままに、掛金を増やせます。すなわち、所得税、住民税、社会保険料が不要なお金を将来受け取ることになります。
⑤運用しながら退職金準備が可能
毎月の掛金を運用しながら積み立てることができます。
例えば40歳の社長が65歳の退職時に5,000万円の退職金をもらいたいと考えたとき、その方法は限られてきます。
仮に次の方法を考えたときに、あなたならどの方法が現実的だと考えますか。
a.7,500万円の利益から税金を2,500万円支払って5,000万円を確保する(毎年300万円の経常利益が必要)
b.会社を売却したお金で5,000万円確保する(会社が売却できる状況にあることが必要)
c.選択制選択確定拠出年金で運用し、5,000万円の退職金原資を確保する(8%で運用できることが必要)
⑥差押禁止財産
企業型選択制確定拠出年金で積み立てられた掛金は、差押禁止財産です。例え、会社に万が一のことがあっても、債権者に提供する必要がないのです。つまり、老後資金は完璧に守られることになります。
魅力が多く、説明が追いつきませんが、ぜひみなさんの事業所でも企業型選択制確定拠出年金を検討されてみてくさだい。
経営者にも、スタッフにも、メリットいっぱいの制度です。
◆「簡易版企業型選択制確定拠出年金シミュレーションシート」のプレゼント◆
最後までお読みいただきありがとうございます。
実際にどれぐらい税金や社会保険料に変化が起きるのか知りたい方にはシミュレーションシートを用意しています。
希望される方は無料でプレゼントしますので、下記フォームからアンケートにご回答ください。「簡易版企業型選択制確定拠出年金シミュレーションシート」プレゼント希望