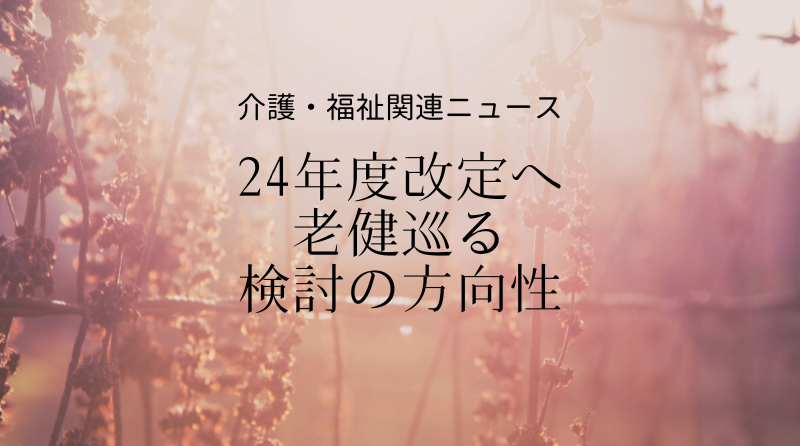2024年度介護報酬改定に向けた議論を実施している社会保障審議会・介護給付費分科会では、8月に入り、施設系サービスをテーマに取り上げました。
*関連記事:【2024年度介護報酬改定】介護老人福祉施設(特養)の配置医師や急変時の対応と評価が俎上に
このうち、介護老人保健施設(老健)については、過去最低を記録した収支差率に象徴される厳しい経営状況に注目が集まりました。
”在宅復帰・在宅療養支援機能の促進”は24年度改定でも主要なテーマとなりそうですが、そうした改革に取り組む施設の経営を安定させられるよう、基本報酬の見直しに関する要望が出ています。
この記事では、在宅復帰・在宅療養支援機能の促進に向けた現状の課題のほか、老健の看取り対応やポリファーマシーなど多岐に渡った議題を巡り、専門家の声をまとめます。
老健の機能強化は経営上のリスクも高い―「がんばっている施設が評価される仕組みを」
介護老人保健施設に関して、厚労省は以下の論点を提示しました。
2024年度介護報酬改定での対応の方向性とも言えるでしょう。
介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援機能の促進に向け、医療ニーズへの対応力の強化、看取りへの対応の充実、リハビリテーションの充実、適切な薬剤調整の推進等の観点からどのような方策が考えられるか。
老健については、2018年度介護報酬改定より、それまで3段階だった基本サービス費の類型が5段階評価に見直されました。見直し以降、超強化型(在宅復帰率やベッド回転率など10項目のポイントが70以上であることに加え、別に定められた算定要件を満たしている施設)の割合が増えており、直近では超強化型が約3割を占めています。

(【画像】第221回社会保障審議会介護給付費分科会 資料2より(以下同様))
ここで、老健の収支差率の推移に目を移すと、2020年度が2.4%、21年度が2.8%、22年度が1.9%と推移しています。特に22年度の数値は「過去最低」との指摘が出るほど、経営状況は厳しいものとなっています。

日本医師会の江澤和彦委員は、「(在宅復帰・在宅療養支援)機能を高めるために、人を要するすなわち人件費が高まり、それに伴って(=在宅復帰率の向上によって)稼働率も低下する」と指摘。経営を安定させるために「基本報酬の設定にはより詳細な検討が必要」と述べました。
全国老人保健施設協会の東憲太郎委員も「がんばっている施設が報酬上でも評価されるよう、基本療養費の増額を含めた検討を」と同様の主張をしています。
また、東委員は、老健の看取りに関する評価についても以下のような切り口から言及しました。
- 医療費が基本報酬に含まれており、看取り期の点滴等の医療提供が施設負担になっている
- 医師、看護師、リハ職等の多職種が連携して看取りに取り組んでおり、看取り期におけるリハビリも提供している
こうした老健の報酬設計に触れたうえで、「老健施設のターミナル加算は特養の看取りと同様の報酬体系となっており、老健施設特有のターミナルケア対応が評価されているとはいえない。ぜひ老健施設の看取り期対応を評価してほしい」と要望しました。
老健のポリファーマシー対策の現状と課題
本分科会で厚労省は、老健におけるポリファーマシーへの対応についても意見を求めました。薬剤調整の取り組み状況などのデータを以下の通り示しています。
- 薬剤調整の必要性を高いと考える施設は、全体の95.5%であるものの、実際に積極的に取り組んでいる施設は約半数。
- 利用者のかかりつけ医と連携し、薬剤を減らす取り組みを評価するかかりつけ医連携加算(Ⅰ)~(Ⅲ)の算定率は1.6%〜5.8%と低迷。
- 算定が困難な理由として、「入所者の処方内容を変更する可能性があることについて、入所者の主事の医師からの合意を得ること」等の理由が挙げられている。


全国健康保険協会の吉森俊和委員はこの原因を「入所前のかかりつけ医(主治医)と老健の医師または薬剤師の間での意思疎通・情報連携が難しい現状であることに尽きる」と指摘。解決に向け、「テクノロジーおよびICTを利活用し、関係者間における薬剤情報連携の整備が不可欠である」と主張しています。
今回の介護給付費分科会で、サービスごとの論点整理はひと区切りとなります。今後は関係団体へのヒアリング等を実施した後、2024年介護報酬改定への具体案について検討が進められる見込みです。