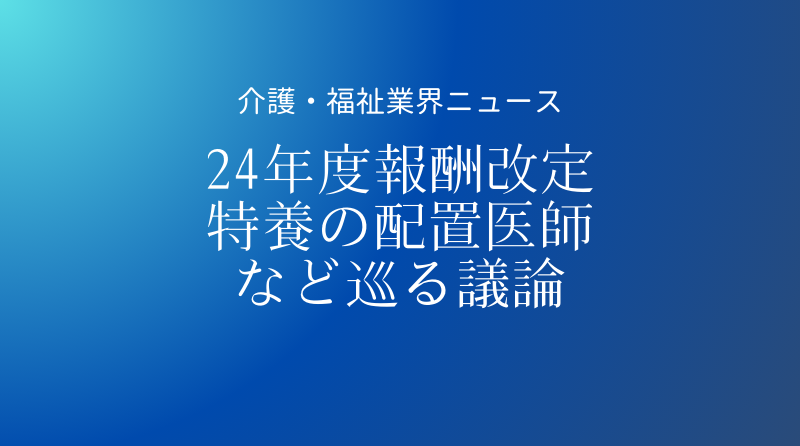8月7日の社会保障審議会・介護給付費分科会では、施設系サービスが議題にあがりました。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を巡っては、看取りを含む医療ニーズへの対応強化が俎上にあがりました。
特養には必ずしも常勤でないものの、医師の配置が義務づけられています。厚生労働省は特養の概況とともに「現行制度では特養入所者の医療ニーズに十分応えられていない」との指摘を紹介し、委員に意見を促しました。
本記事では、特養における看取りや緊急時の対応などを巡って示されたデータや検討状況をまとめます。
特養の概況:配置医師緊急時対応加算、算定は1割未満と低迷
厚労省が提示した論点は、
- 「介護老人福祉施設について、今後も中重度の高齢者が増加することが見込まれる中、入所者のニーズにこたえ、安定的にサービスを提供するためにどのような方策が考えられるか
- 小規模介護福祉施設等の基本報酬に関し、通常の基本報酬との統合に向けて引き続き検討していくべきとされていることについて、どのように対応することが適切か
です。
このページでは、前者に絞って紹介します。
厚労省は、中重度者への対応策について検討する前提データとして、特養の配置医師や緊急時の対応に関する状況を示しました。
全国の特養の配置医師の状況について(令和4年度老人保健健康増進等事業の調査研究データ)
- 配置医師数:「1人」が66.5%と最多
- 雇用形態:「雇用契約(嘱託等)」が62.9%
- 平均年齢:62.6歳
配置医師が施設にいない時間帯に生じた急変等の対応
配置医師が不在時の急変等への対応では、「配置医師によるオンコール対応(平日・日中で約63%、それ以外で約38%)」が最多ですが、「原則、救急搬送(平日・日中で約26%、それ以外で約38%)」が次いで多い結果となっています。

(【画像】第221回社会保障審議会介護給付費分科会 資料1より(以下・同様))
また、93.9%の特養が配置医師緊急時対応加算を申請しておらず、「配置医師が必ずしも駆けつけ対応ができない(45.3%)」、「緊急の場合はすべて救急搬送している(32.1%)」が算定しない理由の上位を占めています。

特養の看取りを含む医療ニーズ強化へ、評価の充実を求める声
こうしたデータに加え、厚労省は「現行制度では特養入所者の医療ニーズに十分応えられておらず、配置医師が行うこととされる『健康管理及び療養上の指導』の範囲の明確化や配置医師制度等の見直しなど所要の措置を検討すべき」との指摘(2022年6月7日閣議決定の規制改革実施計画)があることを説明。配置医師の制度上の在り方について意見を促しました。
大分県国民健康保険団体連合会の奥塚正典委員は、「看取りには常勤看護師を1名以上配置し、夜間もオンコール対応体制を整える必要がある。医師が常駐していない特養では、協力病院との密接な協力体制も必要」と指摘し、看取り体制の整備や医療分野との連携強化のためのさらなる評価の充実を求めました。
他にも複数の委員から、看護師の配置や医療ニーズへの対応などについて報酬上の評価について充実を求める意見が出ています。
日本医師会の江澤和彦委員は、「24時間365日を一人の医師で対応はできない。配置医師の仕組みは残しつつ、特養・配置医師・地域の中小病院等との顔の見える良好な関係構築が重要」と提言。入所者の医療提供に支障が出ない仕組みの重要性を強調し、「配置医師の対応が困難な場合に、(協力関係にある)中小病院がカバーをするバックアップサポート体制の構築」を要請しました。