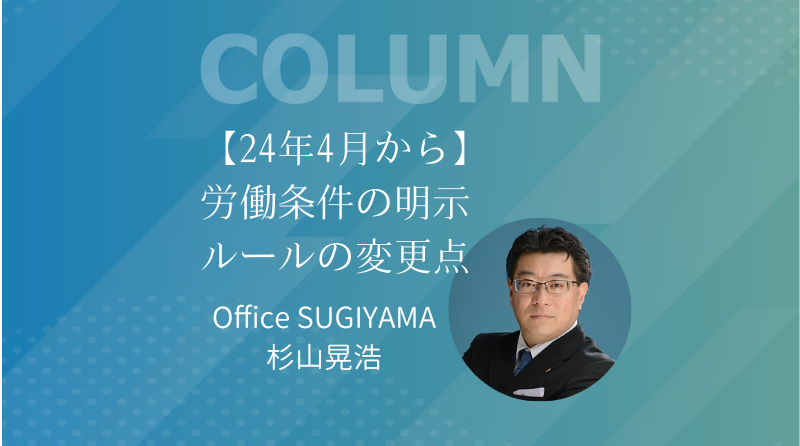2024年4月1日から、労働条件明示のルールが変更されます。
対象となる労働契約は、2024年4月1日以降に締結される労働契約です。まず、2024年3月31日までの取扱について、次の2点を理解しておいてください。
①既に雇用されている労働者に対して、改めて労働条件を明示する必要はないこと
②契約の始期が2024年4月1日以降であっても、2024年3月以前に契約の締結を行う場合には、改正前のルールが適用され、新たな明示ルールに基づく明示は不要であること
なお、厚生労働省の資料によれば、『もっとも、労働条件に関する労働者の理解を深めるため、令和6(2024)年3月以前から新たな明示ルールにより対応することは、望ましい取組と考えられる』とされています。つまり、早目にルール変更を適用しても構わないどころか、望ましいとされています。それならば、使用している労働契約書や労働条件通知書のひな形を見直して、早目にルール変更に対応しておきましょう。
変更される事項及び注意すべきポイントを以下に紹介します。
1.新たに追加された労働条件の3つの明示事項とは?
労働条件を正しく伝えないとどのようなリスクが考えられるでしょうか?スタッフが自分の労働条件をしっかり理解できていないと、スタッフと介護事業所の間で誤解が生じやすくなり、時にはトラブルに発展しかねません。
また、労働条件が明確でないと、働く人たちが自分たちの権利を守ることが難しくなります。例えば、どんな仕事をさせられるのか、有期労働契約の将来像がはっきりしないと、働く人は不安に感じるかもしれません。これが原因で、職場では不満が溜まりやすくなり、結局、スタッフが退職してしまうことに繋がりかねません。
つまり、労働条件をはっきりさせることは、働く人たちが安心して働ける環境を作るためにとても大切ということです。
2024年4月からの新しいルールは、このような問題を解決し、みんなが納得できる明るく公平な職場を作るためのものです。
このような前提の下で「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が改正されました。
これに伴い、次のとおり介護事業所でも、働く人に対して明示すべき事項が増えることとなりました。
| 対象 | 明示のタイミング | 新しく追加される3つの明示事項 |
| 全ての
労働者 |
労働契約の締結時と
有期労働契約の更新時 |
就業場所・業務の変更の範囲 |
| 有期契約
労働者 |
有期労働契約の締結時と
更新時 |
更新上限の有無と内容
(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限) |
| 無期転換ルールに基づく
無期転換申込権が発生する 契約の更新時 |
無期転換申込機会
無期転換後の労働条件 |
なお、明示事項に応じて有期契約労働者に対し、次の行動が求められています。
義務:更新上限を新設・短縮しようとする場合、その理由をあらかじめ説明すること
努力義務:無期転換後の労働条件を決定するに当たり、他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努めること
参考までに、義務とはしなければならないことです。説明は口頭でできますが、介護事業所が説明義務を確実に果たしたことを証明するためには、例えば「説明済み証明書」などの確認書類にスタッフのサインをもらっておくことがポイントとなります。労働局や労基署の調査の際に、実施した記録をペーパーで残しておくと義務を果たした証拠となります。
一方で、努力義務とは、例えしなかったとしても何ら罰則は問われないということです。しかしながら、努力義務違反により事故が発生したり、トラブルが発生した場合には、しなかったことを理由に損害賠償請求をされることも考えられます。つまり、努力義務のものでも、義務と同様に考えて、実行しておけば、将来的にトラブルに巻き込まれる確率は大きく減少すると考えられます。
2.介護事業所向け就業場所・業務の変更の範囲の記載例
「変更の範囲」の明示は、就業場所・業務がどの程度限定されるかにより記載内容が異なります。
ポイントは、雇入れ直後(ビフォー)と変更の範囲(アフター)を対比させて記載することです。
厚生労働省では、4つの状況を想定して記載例を公表しています。
その中から介護事業所で使われそうな記載例を、介護事業所向けにカスタマイズしてみました。貴社の状況に合わせてご活用いただければと考えています。
①就業場所・業務に限定がない場合
就業場所・業務に限定がない場合は、すべての就業場所・業務を含める必要があります。
■就業場所
| (雇入れ直後)訪問看護ステーション〇〇 | (変更の範囲)会社の定める介護事業所 |
■従事すべき業務
| (雇入れ直後)介護職 | (変更の範囲)会社の定める業務 |
| (雇入れ直後)経理業務 | (変更の範囲)全ての業務への配置転換あり |
②就業場所・業務の一部に限定がある場合
就業場所や業務の変更範囲が一定の範囲に限定されている場合は、その範囲を明確にしましょう。
■就業場所
| (雇入れ直後)都城市 | (変更の範囲)宮崎県内 |
■従事すべき業務
| (雇入れ直後)介護業務 | (変更の範囲)介護業務、介護事務
( 介護業務とは、入所者の着替え、食事、入浴及び排泄の介助等を行うものであり、介護事務とはレセプトの作成等介護業務に関連する事務作業一切をいう。) |
⓷完全に限定(就業場所や業務の変更が想定されない場合)
雇い入れ直後の就業場所・業務から変更がない場合は、その旨を変更の範囲で明確にしましょう。
■就業場所
| (雇入れ直後)デイサービスみやざき | (変更の範囲)変更なし |
■従事すべき業務
| (雇入れ直後)ケアマネージャー | (変更の範囲)雇入れ直後の従事すべき業務と同じ |
④一時的に限定がある場合(一時的に異動や業務が限定される場合)
就業規則の有無で記載内容が変わります。
■就業規則で詳細を定める場合
| 就業の場所 | (雇入れ直後)
グループホーム島根 |
(変更の範囲)会社の定める支店
(ただし会社の承認を受けた場合はAブロック内の支店。詳細は就業規則第2 5 、2 6 条参照) |
| 従事すべき業務 | (雇入れ直後)
管理業務 |
(変更の範囲)就業規則に規定する総合職の業務( ただし会社の承認を受けた場合は業務を限定する。詳細は就業規則第2 7 、2 8 条参照) |
| 就業規則 第25条 スタッフが希望し、承認された場合は、一時的に勤務地域を限定する。
第26条 勤務地域を限定する場合は地域を下記のブロック単位とする。
第27条 総合職は企画立案、折衝調整、営業、管理業務にわたる総合的な業務を行う。 第28条 労働者が希望し、承認された場合は、一時的に総合職の業務を一部限定する。 |
||
■就業規則以外で限定内容を明示する場合
| 就業の場所 | (雇入れ直後)
デイサービス みやざき |
(変更の範囲)会社の定める事業所
( 育児・介護による短時間勤務中は、原則、勤務地の変更を行わないこととする。ただし、労働者が勤務地の変更を申し出た場合はこの限りではない。) |
| 従事すべき業務 | (雇入れ直後)
看護業務 |
(変更の範囲)会社の定める業務
( 育児・介護による短時間勤務中は、原則、業務の変更を行わないこととする。ただし、労働者が業務の変更を申し出た場合はこの限りではない。) |
3.更新上限の書面明示の記載例
こちらの内容はパート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者が対象となります。いわゆる正職員は対象外です。
明示の態様ですが、スタッフと介護事業所の認識が一致するような明示となっていれば、どのような書き方でも差し支えないとされています。また、更新上限がない場合にその旨を明示することは必要ありません。
■更新上限の明示の例
| 契約期間は通算4年を上限とする |
| 契約の更新回数は3回まで |
通算契約期間または有期労働契約の更新回数について、上限を定めるかこれを引き下げようとする理由を労働者に説明することは、義務付けられています。しかしながら、当該理由の説明により、有期契約労働者が納得することまで求められているものではないということです。スタッフの中には、『納得がいかない』と言って詰め寄ってくる人がいるかもしれませんが、厚労省のQ&Aでは「納得するまで説明する義務」まではありません。この点がポイントになります。
理解しやすい図解事例を2つ厚生労働省パンフレットからご紹介します。
■事例1 : 契約当初から更新上限が定められていた場合

■事例2 : 契約当時は更新上限がなかったが、契約途中に更新上限を定める場合

4.無期転換申込機会の書面明示の記載例
こちらは無期転換申込権が発生する有期契約労働者のみが対象となります。
なお、「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに書面により明示することが必要です。
初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する場合は、更新の都度、上記の明示が必要になります。一度明示すればよいわけではないことに注意してください。
有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる
無期転換ルールの運用でトラブルにならないために、次の3つのことをしておきましょう。
①無期転換の意向確認
有期契約の更新時に正社員への転換が可能であることを働く人に知らせ、その転換を希望するかどうかを会話などを通じて確認することを意味します。この時、働く人の疑問や不明点にも答えます。要するに、働く人が契約を無期に変えたいかどうか、そしてそれについて質問があれば、その場で話し合い、解決策を見つける手続きです。
②無期転換に関する情報提供
契約更新の時に、正社員への転換を選んだ人の数や、もし今回転換せずにまた一時的な契約を更新する場合の労働条件について知らせることです。つまり、働く人が自分の将来についてより良い選択ができるように、役立つ情報を提供することを指します。なお、無期転換後のトラブルを回避するために、無期転換は正社員化でないことを伝えておく必要があります。
⓷無期転換ルールの周知
契約更新の前に、働く人たちに正社員への転換ができる制度について知らせることを意味します。具体的には、初めて契約を結ぶ時など、正社員になることができる権利が生じる前に、会社がこの制度について働く人たちに情報を提供することです。これは、働く人たちが自分の働き方について知り、将来について考える機会を持てるようにするためのものです。
労働力が急激に減少していく将来に向かって、無期雇用で労働力を確保しようとする動きが強まっています。また、労働力の確保という観点からは、正社員化した方が、スタッフの定着率を高めることができます。みなさまのおかれた現状において、より良い選択肢を提供するのが良いと考えます。
5.労働条件通知書の活用方法
労働条件の文書明示は、入社後のトラブルを防止するうえでとても大切なことです。
入社に際しては、労働契約書を取り交わしたり、労働条件通知書を交付して、労働条件の明示義務を果たします。
さらにパートタイマーや有期雇用労働者には、他にも書面明示すべき事柄が、パートタイム・有期雇用労働法に定められています。労働条件通知書に、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」もあらかじめ記載しておくことで、法令順守の抜け漏れを防ぐことができます。いわゆる、労基署調査対策のテクニックのひとつです。
厚生労働省から出されているひな形を、自社用にアレンジして4月に備えておきましょう。
◆杉山事務所使用新ルール対応型『労働条件通知書』のひな形プレゼント◆
最後までお読みいただきありがとうございます。
今月は、杉山事務所使用新ルール対応型『労働条件通知書』のひな形を希望者全員に無料プレゼントします。特に、以下に当てはまる場合はぜひご活用ください。
①パンフレットを読むだけでは、どのように労働条件通知書を変更すれば良いのかわからない方
②厚生労働省のひな形では、自社に合わない余分な情報が多いと考えている方
⓷労働条件通知書を最大限活用して、労基署や労働局の調査対策を実現したいと考えている方
お気軽に下記からお申し込みください。