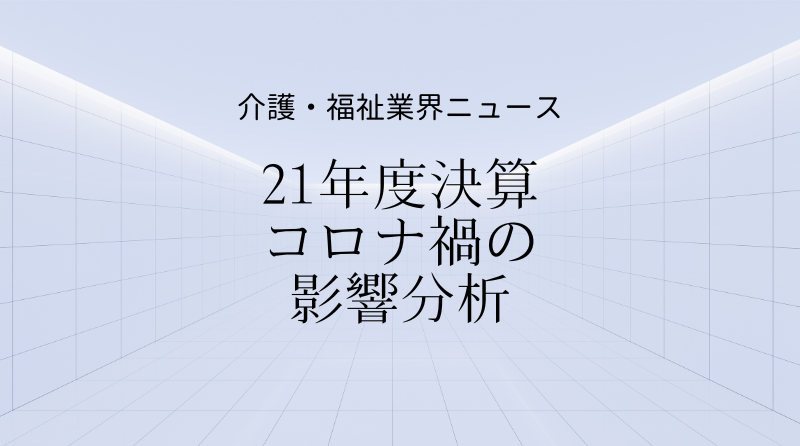このほど、厚生労働省から示された「介護事業経営概況調査」(20年度と21年度の決算の状況を調査したもの)の調査結果。このデータからは、収支差率(以下・利益率)や給与費率(以下・人件費率)など、介護事業の経営状況を把握する上で重要な指標を確認することができます。
多くのサービスで人件費率が増加し、利益率が悪化したことが話題になった本調査。今回は、新型コロナによる影響も分析されていて、サービス種別による違いが読み取れます。
複数サービスで人件費率が増加、利益率の悪化に影響
この調査は、介護報酬改定のあった2021年度とその前年度の介護事業者の決算の状況を明らかにし、次期介護保険制度改正や介護報酬改定の参考にするものです。
サービス別の利益率のほかに、介護事業の支出の大半を占める人件費率なども示されています。
それによると、21年度の決算で人件費率が高いサービスは「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」(78.5%。前年度比0.4ポイント増)、「居宅介護支援」(78.1%。同1.5ポイント減)、「訪問看護」(73.6%。同1.7%ポイント増)などの順、低いサービスは「福祉用具貸与」(38.5%。同0.6%減)、「特定施設入居者生活介護」(45.4%。同0.3%増)、「地域密着型特定施設入居者生活介護」(57.4%。前年度比0.4%増)などの順となりました(回答数の少ない夜間対応型訪問介護を除く)。
主な居宅系サービスの利益率と人件費率を比較すると以下のようになっています。
 (【画像】厚生労働省「令和4年度介護事業経営概況調査結果の概要」をもとに編集部で作成)
(【画像】厚生労働省「令和4年度介護事業経営概況調査結果の概要」をもとに編集部で作成)
21年度介護報酬改定後は、一部を除いた多くのサービスで利益率が悪化しました。21年度改定は原則として全てのサービスの基本報酬が引き上げられましたが、多くのサービスで人件費率が前年度から増えており、支出が膨らんでいることがわかります。
*関連記事: 21年度報酬改定後に居宅介護支援など一部除く事業収支が悪化
新型コロナウイルス感染症の影響は通所介護などで強く利益率減に
今回の調査では、新型コロナウイルスの感染拡大が経営に与えた影響も調査されていますので、主要サービスの状況を抜粋して比較します。なお、下記で紹介する利益率はいずれもコロナ補助金を含む税引前のものです。
新型コロナの陽性者の有無による利益率の違い
施設系サービスでは「介護老人福祉施設」と「介護老人保健施設」において、利用者か職員いずれかで陽性者もしくは濃厚接触の疑いが該当した際の利益率はそれぞれ1.2%(前年度比0.2ポイント減)、1.8%(同0.4ポイント減)でした。
居宅系サービスでは「訪問介護」6.2%(同0.3ポイント減)、「通所介護」0.7%(同3.1ポイント減)、「訪問看護 8.0%(同1.3ポイント減)」、「居宅介護支援 4.3%(同1.1ポイント増)」となっています。
発生者の有無による比較は以下の通りまとめられています。
 (【画像】令和4年度介護事業経営概況調査結果の概要より)
(【画像】令和4年度介護事業経営概況調査結果の概要より)
通所介護では、利用者か職員のいずれかで陽性者が発生した場合の利益率が0.7%となっており、発生しなかった場合(2.2%)に比べて大きく落ち込んでいます。
新型コロナに伴う施設・事業所運営への影響の有無による利益率の違い
新型コロナの感染拡大によって受けた具体的な影響としては、各サービスとも「行政からの要請によるサービスの一時休止」や「施設・事業所の判断による運営の縮小」が多くなっています。
このような具体的な影響を受けたとする施設・事業所の利益率について、主なサービスの状況をみると、「介護老人福祉施設」0.7%(前年度比0.5ポイント減)、「介護老人保健施設」1.5%(同0.1ポイント減)、「訪問介護」5.5%(同0.1ポイント減)、「通所介護」0.7%(同2.7ポイント減)、「訪問看護」6.8%(同0.7ポイント減)、「居宅介護支援」5.0%(同2.1ポイント増)となっています。

(【画像】令和4年度介護事業経営概況調査結果の概要より)
ほかのサービスと異なり、居宅介護支援では事業所の運営に新型コロナによる影響があった場合の方が利益率が高くなっています。これは、事業所が受けた影響として、「サービスの一時休止」や「運営の縮小」よりも「近隣事業所等からの利用者の受け入れ」が大きかった可能性があります。

(【画像】厚生労働省「令和4年度介護事業経営概況調査結果」をもとに編集部で作成)
24年4月に控える介護保険制度改正・介護報酬改定の方向性を検討するための前提情報となる今回の調査結果ですが、新型コロナウイルス感染症の影響をどう捉え次回改正や事業者支援に反映させていくか、今後の動向についても継続してお伝えしていきます。