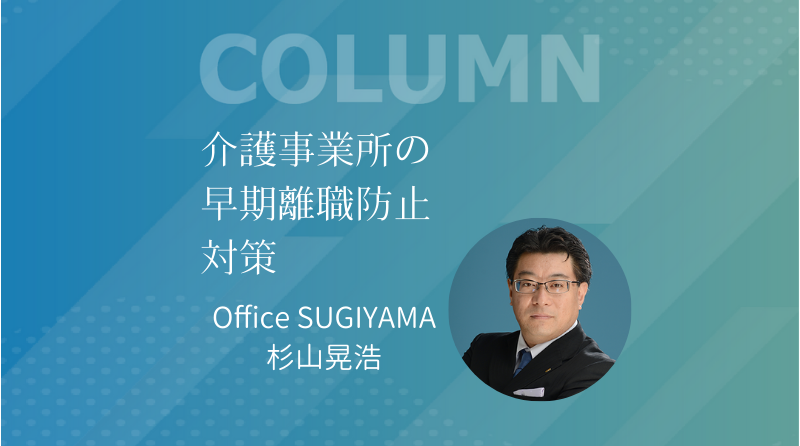1.早期離職が企業に与える損失・対策にかけられる費用を可視化する
公益財団法人介護労働安定センターが実施した令和2年度の「介護労働実態調査」によると、入職後3年の間に6割もの職員が離職しているという結果が出ました。
調査結果がわかり易く解説された「図表解説 介護労働の現状について」には、次のグラフとコメントが掲載されています。

*出典:令和2年度「表解説 介護労働の現状について」(公益財団法人介護労働安定センター)
また、この調査では、約2割の介護事業所が、離職率が高いことを人手不足の原因であると回答しています。すなわち、早期離職の傾向が改善されることで、人手不足感が薄らいでいくという仮説が成立します。

*出典:令和2年度「表解説 介護労働の現状について」(公益財団法人介護労働安定センター)
人手不足に悩む多くの介護事業所では、スタッフが頑張って利益を確保しても、その一方で早期離職に伴う損失が恒常的に発生し、経営を圧迫しています。その結果、給与は現状維持、賞与は雀の涙となり、スタッフが疲弊し、離職していく負のスパイラルからなかなか抜け出せません。
一度負のスパイラルに陥ってしまうと、経営にゆとりがなくなるため、現状改善にお金をかけることを放棄し、思考を停止してしまった経営者をたくさん見てきました。このような状況は組織運営にとって健全とは言えず、いずれは事業売却、事業縮小、廃業、倒産といった負の連鎖を引き起こしてしまいます。
早期離職の改善手法を考える前に、せっかく採用したスタッフが早期離職した場合の損失額を考えておきましょう。このプロセスが、早期離職防止対策を幅広く検討するうえでとても有効な手段となります。
あらかじめ早期離職における金銭的損失を明確化しておくことで、改善にかけられる自社の予算が見えてきます。採用広告の費用、人材紹介の手数料で多額の利益を失っている介護事業所ほど重要な作業ですので、ぜひ実践してみてください。
ところで、先日話をしたある病院は、看護職も介護職も常に不足している状態でした。
人手不足で困っているにもかかわらず、採用方法は無料でできるハローワーク求人のみです。そして、そのハローワーク求人を見て営業してくる人材紹介会社を使っている状況です。
慢性的に人手不足の状態なので、求人応募や人材紹介があればとりあえず入職させ、研修もないまま現場投入しているとのことでした。
「看護職と介護職のいずれも専門職なので、業務遂行には支障がないだろう」との判断です。また、「組織に合う、合わないは人それぞれなので、入職して、働いてもらえば分かるだろう」と話されていました。とはいうものの、早期離職される方が多いようで、定着率の向上に課題があると悩んでおられました。
このままの状態が続く限り、この病院の利益は増えません。利益を増やすためには、早期離職に伴う損失額を知ることから始まります。
早期離職に伴う損失は、次の計算式で算出することができます。それぞれのコストを自社ではいくら使っているか計算してみてください。
【早期離職に伴う損失額算出式】
採用コスト+教育コスト+支払給与+福利厚生費+退職者補充コスト
なお、マイナビが実施した「中途採用状況調査2020年版」では、採用者1人あたりの求人広告費が約53万円となっています。求人広告費用だけでこの金額ですから、人材紹介手数料を加味するととんでもない金額になることが容易に予想できます。

上記以外にも、目に見えないコストとして、時間コストがあります。退職者がでることで、組織の状態は過去に戻ります。でも、組織の年齢は若返りません。つまり、組織が退化、老化してしまう恐ろしいコストです。事業所規模が小さくなればなるほど、時間コストの影響を大きく受けることになります。
しかしながら、早期離職の防止ができれば、これらの損失は一切なくなります。
むしろ、損失となっていたコストが利益となり、経営に跳ね返ってきます。
利益が発生すれば、スタッフの給与や賞与として還元できます。
スタッフの処遇が改善され、定着率が上がることで、組織運営が安定してきます。
安定した組織となることで、採用力が上昇し、より良いスタッフが採用し易くなります。
先ずは、早期離職防止対策を実践することで、企業の収益力を向上させましょう。
2.早期離職防止対策としてのオンボーディング
日本企業では入社すると、オリエンテーションの後、すぐにOJTとなることが一般的です。組織規模が大きくなれば、新人研修が間に入ることがありますが、中小企業ではOJTを通じて仕事を覚えてもらうことが多いように感じています。10名未満の零細企業では、オリエンテーションもOJTもなく、いきなり現場投入なんてこともよくあります。
このような状況を別の切り口から見てみます。
例えば、介護ソフトを初めて導入したお客様に対して、そのソフトをフルに活用してその効果を実体験してもらうために、販売会社がどのようなことをしているか考えてみてください。
まず最初に、設定作業が必要となります。お客様の中にはITリテラシーがさほど高くないために、設定作業で躓いてしまうことも起きがちです。この場合に販売会社が採る手段は、代わりに設定作業を行うか、設定作業を教えるかのいずれかです。要するに、お客さまが最初に感じる『難しい』や『分からない』といったネガティブな感情を取り除くことで、介護ソフトの導入がスムーズに行われます。導入がスムーズにできなければ、お客さまは他社のソフトへの切替えを考えてしまいます。
更に、介護ソフトをフル活用し、『この介護ソフトを選んで良かった。』とお客さまに実感してもらうためには、使用法についての研修の実施やコールセンターによるサポートで、販売会社はお客さまに寄り添います。
介護事業所の採用でも、新たに採用するスタッフに対して、介護ソフト販売会社が、顧客に実施するような最大限のサポートを実施してみましょう。
新卒や中途入社のスタッフが入社した後に、早期離職を防ぎ、できる限り早く戦力化し、組織で活躍してもらうための一連の取り組みは、オンボーディングと呼ばれます。
3.オンボーディングスケジュールを創る
オンボーディングと一言でいっても、さまざまなアプローチがあります。自社で実施すべきオンボーディング施策は何なのかを考えるところからスタートします。
オンボーディングは、次の4つの期間に分けて考えると、効果的な対策が考え易くなります。
【オンボーディングスケジュール4つの期間】
①内定以前の期間
企業理念、ミッション・ビジョン・バリューに共感した人材を選別するための施策
②内定後から入社日までの期間
スムーズに入社初日を迎えられるように、内定者にストレスをかけず、入社日に期待を抱かせる施策
③試用期間終了までの期間
お客さまではなく、自律して考え、業務遂行ができる環境に慣れさせるための施策
④本採用後1年間
組織全員で寄り添い、定着させるための施策
これら4つの期間に実行すべき施策を当てはめ、オンボーディングスケジュールを作成します。
あらかじめ基本的なオンボーディング施策が記載されている『オンボーディングスケジューリングシート』を準備しておくと、スピーディーに作業が進められます。
なお、採用したスタッフには、翌年のオンボーディングに積極的に関わってもらうようにすることがこの取り組みのゴールとなります。そのスタッフは、自分がオンボーディングされて良かったことはそのまま実践し、実体験をもとに必要な改良が行える貴重な人材となっているからです。
施策を検討するためのもっとも簡単な方法は、今いるスタッフ全員からアンケートを取ることです。その後は、以下のような流れで施策を検討します。
(1)アンケートでは、前述の4つの期間のうち、ストレスを感じたことを箇条書きにしてもらいます。
(2) 箇条書きされたアンケートの回答をグルーピングし、課題を明確化します。
(3)明らかになった課題に対して有効と思える施策を検討します。
(4)施策を『オンボーディングスケジューリングシート』に書き込みます。
(5)経営者をはじめ全スタッフと『オンボーディングスケジューリングシート』を共有して、オンボーディングをスタートさせます。
ポイントは、最初は費用について深く考えず、できるだけ多くの施策を具体的に文字化することです。
施策を検討した結果、費用がかかることがわかったとしても、現状にプラスされるコストとして受け止めるのではなく、早期離職防止によりコストを利益に変えるための”投資”として考えてください。
なお、費用対効果を検証する際には、早期離職による損失と比較をしましょう。最初から、ベストな施策を選ぶことは難しいですが、新入スタッフへのインタビューを繰り返しながら、PDCAを回すことをお勧めしています。
ぜひこの機会に、早期離職を防ぎ、損失を利益に変えるオンボーディングを実践してください。組織が良くなることをお約束します。
◎お知らせ
『オンボーディングスケジューリングシート』が必要な方は、無料でプレゼントします。
お申込みはこちらから ⇓
『採用定着力診断』を希望される方は、無料で9ページ程度の診断レポートをプレゼントします。
お申込みはこちらから ⇓