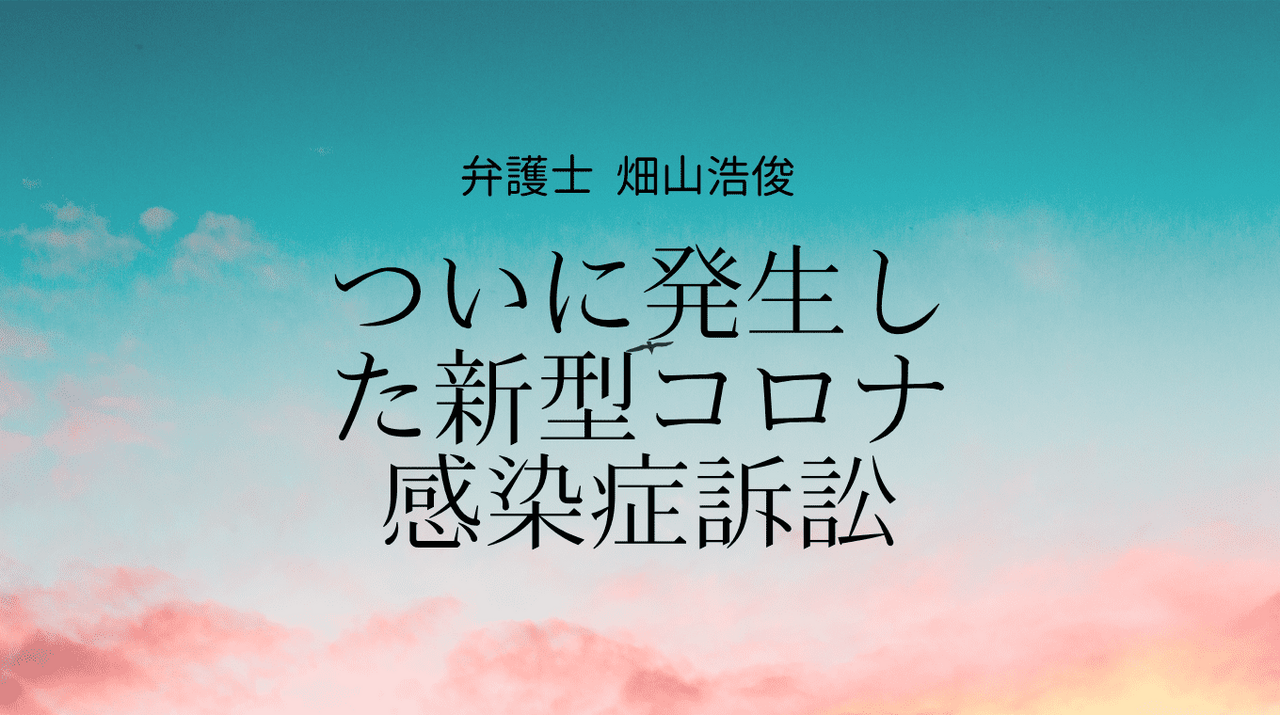新型コロナウイルス感染症が原因で82歳で亡くなった広島県三次市の女性の遺族が、同市の訪問介護事業所の運営会社に計4,400万円の損害賠償を求めて広島地裁に提訴したというニュースが2020年10月初旬、日本全国を駆け巡りました(なお、当該訴訟は、同年10月12日に和解が成立し、審理開始前に取り下げられています)。
訴状などによると、三次市で一人暮らしをしていた女性は、20年4月3日(以下日付は全て20年とします。)に新型コロナウイルス感染症を発症し、PCR検査の結果、9日に陽性と判明。その後、広島市内の病院に入院し、19日に新型コロナウイルスによる肺炎のために死亡しました。
何故遺族は、運営会社を訴えたのでしょうか。
担当ヘルパーの新型コロナ感染と亡くなった女性との接点
報道によると、以下のような経緯があったようです。
①3月23日、27日、30日
担当ヘルパーが女性宅を訪問して、介護サービスを提供。
②3月31日
担当ヘルパーが発熱と味覚・嗅覚異常を発症。但し翌日には一旦症状が改善。
③4月1日
担当ヘルパーの親族に感染が疑われる症状が確認される。
④4月2日、4月6日
担当ヘルパーが女性宅を訪問して、介護サービスを提供。
⑤4月10日
担当ヘルパーの新型コロナウイルス陽性とが判明。
これらの事実経過を踏まえ、遺族は「運営会社はヘルパーやその周辺の人に感染の兆候がある場合は報告を求め、出勤させない義務があるのに怠った。ヘルパーを交代させていれば母の命は奪われなかった。運営会社は責任を認めて謝罪してほしい」と主張したのです。
このニュースを見て「いよいよ恐れていたことが現実になった」と戦々恐々としている介護事業者が大勢いらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、今回は、介護事業者が利用者や遺族に対して損害賠償責任を負う場合の法的な理論の整理を行った上で、新型コロナウイルス対応で介護事業所に求められることについて、筆者の見解を述べたいと思います。
介護事業所と損害賠償責任の関係
損害賠償責任が認められるためには、
- 介護事業者に安全配慮義務違反があること
- その安全配慮義務違反と結果(コロナウイルス感染・死亡等)との間に因果関係があること
- 損害が発生していること
介護利用契約に基づく「安全配慮義務」とは
介護事業者と利用者は、介護利用契約を締結しています。簡単に言うと「利用計画に基づいて、利用者にはこのようなサービスを個別に提供しますね。サービス提供に対して、利用料を支払って下さいね」という内容の契約です。
しかし、介護事業者が利用者に対して負っている義務は、サービス提供義務だけではありません。介護事業者は、介護利用契約上、利用者の生命、身体、健康を危険から保護するよう配慮する義務、すなわち安全配慮義務を負っています。安全配慮義務を尽くしている中で発生した介護事故に関しては、介護事業者は損害賠償責任を負いません。
そして、安全配慮義務の内容は、個別具体的な事案によって具体的に特定する作業が必要です。
つまり、
①介護事故の発生が具体的に予見できたのか(予見可能性)
②予見できたとすると、その結果を回避できる可能性があったのか(結果回避可能性)
③その結果を回避するために具体的にどのようなことを行うべき義務(結果回避義務)があったのか
を考える必要があります。
例えば、立位の姿勢を保持することが困難で、移動の際に介護職員の支えが無ければ歩けない利用者を立たせた状態で放置し、転倒事故が発生したような場合で考えて見ましょう。①このような利用者を一人で立ちっぱなしにさせると、当然、転倒事故という結果を予見することができます(予見可能性有り)。②次に、移動の際は職員が付き添って歩行介助することが予定されていた利用者ですから、予定通りの介護を行っていれば転倒事故を回避することは可能でした(結果回避可能性有り)。そうすると、③転倒という結果を防ぐためには、予定通り付き添って歩行介助する義務、それができない場合には車いすを利用し転倒しない措置を講じる義務があったと言えます(結果回避義務の具体的内容)。それにも拘わらず、その結果回避義務を怠っているため、安全配慮義務違反があり、損害賠償責任を負うという結論になる訳です。
新型コロナウイルス対応においても、介護事業者は利用者との関係で安全配慮義務を負っています。例えば、介護事業者が、マスク着用や手指消毒等の感染経路を経つことを目的とした感染症対策を全く実施していなかった場合、利用者がコロナウイルスに罹患することを予見することができますし、このような感染症対策を実施することで「利用者がコロナウイルス感染する」という結果を回避できる可能性もあると言えます。そうすると、事前に感染症対策を実施しておくべき結果回避義務があるにも拘わらず、それを怠ったことになり、安全配慮義務違反がある、という結論になります。
新型コロナウイルス感染と「予見可能性」の問題について
では、感染症対策をどこまで徹底すれば安全配慮義務を尽くしたと言えるのでしょうか。広島県三次市の訴訟になった事例で考えてみましょう。
報道によると、問題となっているヘルパーは3月31日に発熱と味覚・嗅覚異常があったものの翌日に一旦症状が改善しています。このような状態のヘルパーを介護事業者としてはどのように扱うべきでしょうか。
予見可能性を検討する上で重要なことは「介護業界を取り巻く当時の状況」をしっかりと踏まえる必要があります。
2月24日、厚労省は事務連絡を出しており、訪問系サービスについて以下のような留意点を述べています。(https://www.mhlw.go.jp/content/000601686.pdf)
○ 社会福祉施設等(居宅を訪問してサービスを行う場合に限る。以下同じ。)の職員については、出勤前に各自で体温を計測し、発熱が認められる(37.5 度以上の発熱をいう。以下同じ。)場合には、出勤を行わないことを徹底する。
社会福祉施設等にあっては、該当する職員について、管理者への報告により確実な把握が行われるように努めること。
過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後 24 時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該職員等の健康状態に留意すること。
厚労省の目安に基づくと、仮に、このヘルパーに37.5度以上の発熱があれば、出勤を控え、解熱後24時間以上経過し、呼吸器症状が改善傾向になるまでは出勤させないよう配慮することが望ましいということになります。この配慮が出来ていたかどうか、が一つの争点になります。この配慮が出来ていたのであれば、ヘルパーが利用者にコロナウイルスを感染させるということにつき、具体的な予見可能性は無く、したがって安全配慮義務違反は認められない、という結論が出る可能性があります。
また、先ほど紹介した2月24日付事務連絡では、以下の記述があります。
○ 該当する職員については、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について」(2月17日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)を踏まえ、適切な相談及び受診を行うこととする。
要は、37.5度以上の発熱が認められた職員は、2月17日厚労省事務連絡記載の「相談・受診の目安」を踏まえた対応をして下さい、ということです。この「相談・受診の目安」では、以下のような場合には、帰国者・接触者相談センターに相談して下さい、とされています。
○ 以下のいずれかに該当する方は、帰国者・接触者相談センターに御相談ください。
・ 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く方(解熱剤を飲み続けなければならない方も同様です。)
・ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596978.pdf 参照)
これも報道からだけでは明確なことは分かりませんが、仮に、3月31日に発熱と味覚・嗅覚異常があったヘルパーが、それ以降、上記のような症状が無かったとすれば、そのような状況で出勤したとしても、利用者にコロナウイルスを感染させることにつき、具体的な予見可能性は無かったと言えそうです。
なお、厚労省は、5月8日に「37.5度以上の発熱が4日以上続く方」という目安を削除し、「息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合」に帰国者・接触者相談センターに相談して下さい、という表現に変更していますので、もし現時点において今回のヘルパーのような症状があった場合には、予見可能性は肯定される可能性が高くなります。
(5月8日付厚労省事務連絡本文:https://www.mhlw.go.jp/content/000628619.pdf)
(5月8日付厚労省事務連絡別紙:https://www.mhlw.go.jp/content/000628620.pdf)
新型コロナウイルス感染と「安全配慮義務」
仮に、予見可能性があったとすると、どこまで具体的に感染対策を実施していれば安全配慮義務を尽くしたと言えるのでしょうか。
安全配慮義務違反が認められるためには、予見可能性に加えて、結果回避可能性があり、結果回避義務に違反している必要があります。今回、介護事業者が感染症対策を行っていれば、利用者にコロナウイルスを感染させることを防ぐことが出来た可能性が高いことから、結果回避可能性はあるものと考えられます。
では、本件ではどのような結果回避義務があったといえるでしょうか。
一般的に、介護事業者が感染対策において踏まえるべき基準は、厚労省が公表している高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版です。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index_00003.html)
その上で、当時の状況に照らして、具体的に求められていた感染症対策を実施する必要があります。広島県三次市の訴訟事案で言うと、ヘルパーが発熱と味覚・嗅覚異常を訴えた3月31日前後に、具体的に求められていた感染症対策を検討することになります。
2月24日、厚労省は事務連絡を出しており、訪問系サービスについて以下のような留意点を述べています。(https://www.mhlw.go.jp/content/000601686.pdf)
○ 社会福祉施設等(居宅を訪問してサービスを行う場合に限る。以下同じ。)の職員については、出勤前に各自で体温を計測し、発熱が認められる(37.5 度以上の発熱をいう。以下同じ。)場合には、出勤を行わないことを徹底する。
社会福祉施設等にあっては、該当する職員について、管理者への報告により確実な把握が行われるように努めること。
過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後 24 時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該職員等の健康状態に留意すること。
上記のような対策を講じていれば、介護事業者としては十分な対応をしている、すなわち結果回避義務を果たしていたといえ、安全配慮義務違反は認められないことになります。
このように、介護事業者としては、行為当時において、厚労省が介護保険最新情報等の事務連絡において求める感染症対策をきちんと実施していれば、安全配慮義務違反は認められないと筆者は考えます。
訪問介護事業は、緊急事態宣言の根拠である改正新型インフルエンザ等対策特別措置法において、新型コロナウイルスがまん延している状況下においても事業継続すべき対象と考えられており(同法45条の使用制限等の対象事業から除外されている)、厚労省も訪問介護事業者は感染症対策を実施しながらも引き続き事業を継続すべき、と繰り返し喧伝しています。
安易に安全配慮義務違反を認めてしまうと、介護崩壊が起き、さらには医療崩壊を招く結果になりかねません。介護現場に求められる法的な安全配慮義務の内容の検討にあたってはこれらの視点も忘れてはならないと思います。
感染源の特定と因果関係
最後に、広島県三次市のケースでは、因果関係も議論の対象になり得ます。つまり、担当ヘルパーが利用者にコロナウイルスを感染させた、と法的に評価できるのか、という問題です。利用者は一人暮らしであり、遺族の主張によると担当ヘルパー以外に感染させる人は思い当たらないとのことです。しかし、実際には誰と接触していたかは分からない話であり、因果関係の立証はハードルが高いと考えています。
なお、報道によると、担当ヘルパーがコロナウイルスの陽性であると判明したのは、4月10日ですが、利用者が症状を発症したのは4月3日であり、コロナウイルスの陽性であると判明したのは4月9日です。利用者発症後の4月6日に担当ヘルパーが利用者を訪問していることからすると、担当ヘルパーと利用者のどちらが先にコロナウイルスに感染したのかは不明です。報道されている事実関係からだけでは明確なことは言えませんが、法的には因果関係の立証は相当難しいと考えます。
まとめ
広島県三次市のケースは、介護事業者には法的な責任は無いという内容で和解が成立しましたが、コロナウイルス感染を理由に介護事業者が訴えられたという事実は残りました。この訴訟により、介護事業者は、今後益々感染症対策に意識を注ぐことになると思います。もっとも、感染症対策を講ずるあまり、「日常生活の手助けをする」という介護の本質的役割が達成できない世の中になってはいけないと強い危惧感を覚えています。
安全配慮義務の内容は個別具体的な状況により変わりますが、厚労省が繰り返し公表しているスタンダードな感染症対策の実施をもって、安全配慮義務を尽くしていると考えてよいと思います。
介護事故は、交通事故や医療事故と異なり、まだまだ裁判例の蓄積がなされていない未開の分野です。
そうであるからこそ、日頃からの対策の徹底と、事故が発生した際の初期対応が問題解決には何より重要であり、対策・対応の構築にあたっては介護分野に詳しい弁護士等の法律の専門家と日頃から連携できる関係を構築しておくことが重要だと思います。