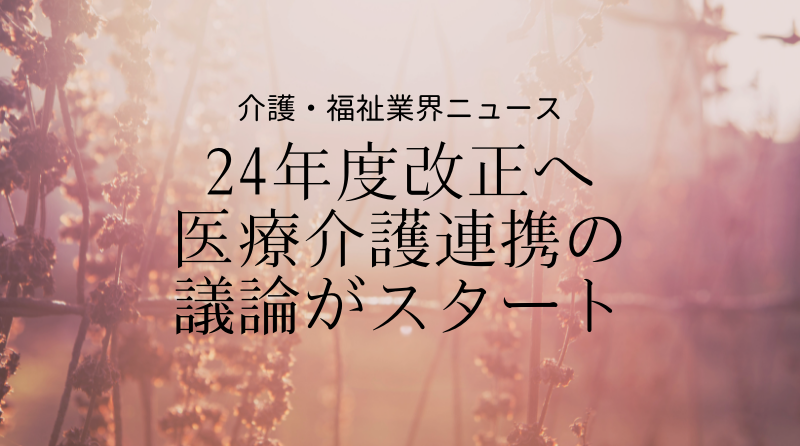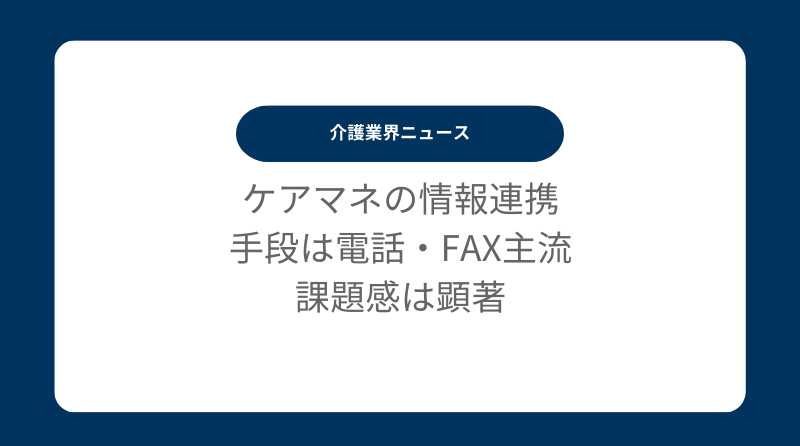2024年度には、都道府県や市区町村が介護サービスの整備目標などを記載する計画(第9期介護保険事業(支援)計画)が見直されます。
今回は、団塊の世代が75歳以上になる2025年度を控えた最後のタイミングです。
これに先立ち、厚生労働省は、「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」(都道府県の介護保険事業計画や医療計画などに位置付ける医療介護連携の在り方を定める方針。以下・総合確保方針)の改正に向けた検討を始めました。
ここでの決定は、介護報酬改定・診療報酬同時改定の方向性にも影響します。
2025年に向けた医療・介護の総合方針策のスケジュール
2024年度の第9期介護保険事業(支援)計画の同時改定は、6年に1度行われる都道府県の医療計画(第8次医療計画)との同時改正でもあります。
そのため、行政として医療介護連携を進めるには、このタイミングで両計画を定めるための方針に落とし込んで行く必要があります。
医療・介護に関わる法律(医療法・介護保険法)の整合性をとり、効果的な連携を進めるための指針である総合確保方針の改正に向けた検討が、厚労省保険局・医療介護連携政策課主催で開かれた会議(医療介護総合確保促進会議)で、10月11日に始まりました。2022年末までに会議としての結論をまとめます。
*会議のメンバー:第15回 医療介護総合確保促進会議 構成員
*関連記事:介護事業者へのICT導入支援、都道府県の補助事業に格差


【画像】第15回医療介護総合確保促進会議資料より(下の図の一部は編集部で加工)
医療介護の情報連携ではシステム入力への負担など懸念
厚生労働省はこの日、初回の論点として
・足下の感染症対策はもちろん、人口動態の変化への対応など、より長期的な事項について検討すべきではないか
・引き続き「地域包括ケアシステム」の構築を進め、一層の医療介護連携政策を推進していくことが重要ではないか
・介護・医療間の情報共有を可能にするための標準化など、より一層のデジタル化による医療・介護の情報連携の強化が重要ではないか
と提案し、構成員に2025年の先を見据えて総合確保方針に記載すべき事項について、意見を促しました。
これに対し各構成員からは、医療と介護の情報連携の基盤となるシステムの在り方についての要望や指摘が相次ぎました。
介護現場からも、LIFEへの入力の負担などが報告されていますが、医療現場でも新型コロナについて国への情報提供に伴う負担が大きかったことや、現在整備が進んでいるマイナンバーカードの保険証利用(オンライン資格確認/厚労省の説明資料P2-8参照)の仕組みについて、医療機関からの必要な機器の申請に対し、整備が圧倒的に遅れているといった状況が起こっています。
こうしたことから、システムの乱立や拙速な制度化による混乱や、それによって業務負担が拡大することなどを懸念したものです。
井上隆構成員 (日本経済団体連合会常務理事)は、介護と医療情報との連携について「地方自治体に任せるということではなく、国が基盤のところはしっかり整備をして行く」こと、9月に新設されたデジタル庁ともこの点について連携するよう求めました。
また、総合確保方針については、この先加速化する人口減少を考慮し、「給付の増加の幅を様々な工夫、ICTも含めて極力抑制する、適正化していく」方向で検討すべきだと主張しました。
総合確保方針に盛り込むべき検討事項としては、このほかに、「高齢者が入院して急性期を脱した後、地域に戻ることができるような連携・支援体制の構築を強化すべき」「地域共生社会の実現についても整理し、障害福祉計画との連動を反映するべき」といった趣旨の提案がされています。