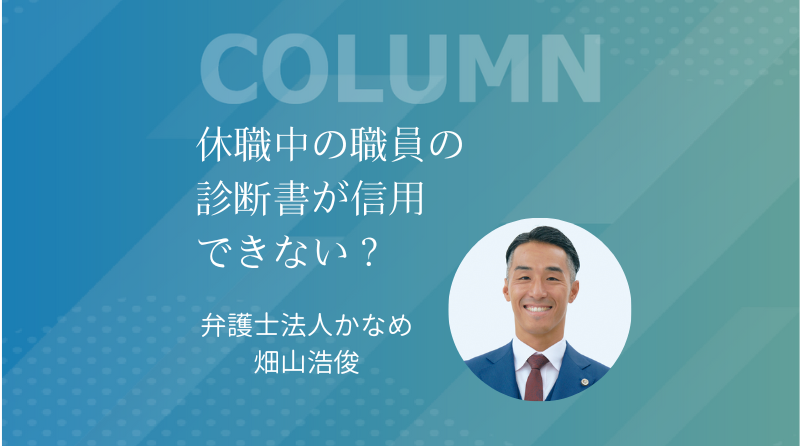弁護士法人かなめでは、福祉事業者に特化したリーガルサービスを提供していますが、うつ病などのメンタルヘルス不調に陥った職員への対応について、どうすれば良いか分からないという労務相談が多く寄せられています。
今回は、「職員から提出された診断書が信用できないのだが、どう対応すれば良いのだろう」という実際の相談事例を紹介し、対応方法を解説します。
1.うつ状態で2カ月休養必要なはずの職員が2週間で復帰?:ケース紹介
<相談内容>
私は、特別養護老人ホームの管理者です。
協調性が無く、自分勝手な行動ばかりする職員について悩んでいます。
周りの職員から「あの人は身勝手だから一緒に働くのが難しい」という声が私の元に寄せられたので、管理者として事実を確認した上で、問題行動を繰り返す職員に注意指導をしました。
指導の数日後、その職員から「注意指導に納得がいかない。注意を受けたことで精神的にしんどくなった」と申し出があり、それと合わせて「うつ状態、2カ月の休養を要する」と書かれた医師作成の診断書が提出されました。
私は「この程度の指導でうつ状態になるのか?」と疑心暗鬼だったのですが、就業規則に基づき、休職を言い渡したのです。
休職通知書には、「休職期間が満了した時点で、復職できる状態になっていなければ自然退職になります」という記載が入っています。これも就業規則で定められているルールです。
この休職通知書を問題の職員に交付したところ、「え?休職期間が終了した時に治っていなければ退職になるのですか?」との発言があり、納得のいかない様子で帰っていきました。
その2週間後です。
問題の職員が、新たな診断書を提出してきました。
その診断書には「うつ状態は寛解しており、職場復帰が可能と思われる」との医師による所見が記載されていました。問題職員は「医師は復帰して良いと言っているので明日から復帰しますね」と言います。
私としては、「2カ月の休養が必要だったのに、もう復帰できるの?」と混乱しており、どのように対応すれば良いか分かりません。医師の診断書の記載について、どのように判断し、どのように法人として対応していけば良いのでしょうか。
2.主治医面談の重要性とその理由
上記のケースでは、最初に提出された診断書に「2カ月の休養を要する」と記載されていたにもかかわらず、その2週間後には「職場復帰が可能」と記載されており、その内容を信用して良いのか分からなくなるのは当然です。
そもそも、診断書に記載されている主治医の意見は一言であることが多く、これだけで、職員がどのような状態にあるのかを正確に判断することはできません。診断書の記載のみを鵜呑みにして復帰させるか否かを判断してはいけないのです。
加えて、主治医は通常、職員本人の言い分しか聞いていません。
多くの場合、復職の判断に必要であるはずの職員の業務内容や業務量を正確に把握した上で診断書が作成されている訳ではありません。ですので、主治医の診断書のみをもって復職の可否を判断することは難しいのです。
厚生労働省が公開している『心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き』でも「主治医による診断は、日常生活における病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限りません」と説明されています。
法人側の対応として、主治医からの診断書を前提に、産業医に意見を求める、という手も考えられますが、「私が患者を診察したわけではなく、診断書の内容の当否は判断できません。まずは診断書を作成した主治医と面談してみてはいかでしょうか」と言われることもあります(そのような例として、平成26(ワ)4712号:横浜地裁平成29年6月6日判決参照)。
そのため、今回のケースのような場面では、主治医面談を実施することが重要になります。
3.主治医面談の手順と質問すべき項目
個人情報保護法上、主治医は、患者(ここでは休職している職員)の同意が無ければ職場に患者の情報を提供することはできません。したがって、まずは当該職員に、医療照会に関する同意書を提出してもらいましょう。
主治医面談では、以下の基本項目を質問します。
①発症から初診までの経過
②治療経過
③現在の状態(業務に影響を与える症状及び薬の副作用の可能性なども含めて)
④就業上の配慮に関する意見(疾患の再燃・再発防止のために必要な注意事項など)
これ以外にも、職場として知っておくべきと考える項目は遠慮せず主治医に質問することをお勧めします。
特にケースのような事例では、主治医に単刀直入に以下のような質問をすべきでしょう。
<ケースにおいて実際に相談すべき質問事項>
最初、うつ状態で2カ月の休養が必要であるとの診断書が出てきました。
それを受けて職場としては休職扱いにしたのですが、その2週間後に、今度は復帰が可能であるとの診断書が出てきています。
2カ月も休まないといけない程に健康状態が悪かったのに、たった2週間で寛解したというのが素人目線でも理解ができないのです。
何故このような診断内容になったのでしょうか。診断書の具体的な作成経緯を教えて下さい。
実際に筆者自身、ケースのような事例に関する相談を多くの法人から受けてきました。上記のように単刀直入に主治医に質問するよう法人の担当者にアドバイスしたところ、主治医が本音を吐露してくれることがありました。
主治医が漏らした本音とは、「実は医師としても復帰はまだ難しいと考えています。ただ、本人から『先生、復帰可能と診断書を書いてくれないと、職場復帰できず退職になってしまうのです。退職になると生活に困るから、何とか復帰可能と書いて欲しいのです』と懇願されましてね・・。そこまで言われたら書かざるを得なかったのです」といったものです。
裁判例でも、主治医が、復職は時期尚早であると考えていたにもかかわらず、休職中の職員から復職可能との診断をしてほしいと申し出を受け、復職可能との診断書を作成したという事実を認定したものがあります(J学園事件:東京地判平成22年3月24日判決)
実際には復帰が難しいにもかかわらず、患者の強い意向を受けて主治医が「復帰可能」との診断書を記載するケースは実は珍しくはありません。
主治医面談をしなければ、実際の主治医の本音を聴くことができません。ケースのような事例においては、診断書の記載を鵜呑みにせず、必ず主治医面談を実施するようにしましょう。
4.主治医面談を拒絶されたらどうする?
今回のような事案では、診断書を鵜呑みにして復帰の判断をすることはできません。法人として復職が可能かどうかを判断するための判断材料が足りていないので、その点を補完するために主治医面談の実施が必要です。
しかし、この主治医面談を拒絶されてしまうと、復職が可能かどうかを判断するための十分な材料がないままの状態になってしまいます。
休職中の職員には、「復職ができるかどうかを判断するための材料が無いので、このままでは復職させることができない」とはっきりと伝えましょう。
5.今回のまとめ
今回は、職員の主治医が作成した診断書の記載が信用できない場合の法人側の対応について具体的な事例に基づき解説しました。
メンタルヘルス不調の職員への対応は個別具体的な状況により異なりますので、どのように対応すれば良いか分からない時は、弁護士等の専門家に随時相談しながら対応するようにしましょう。