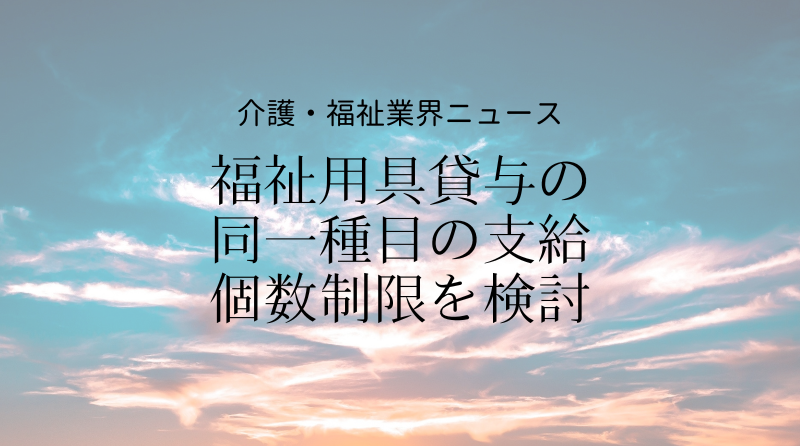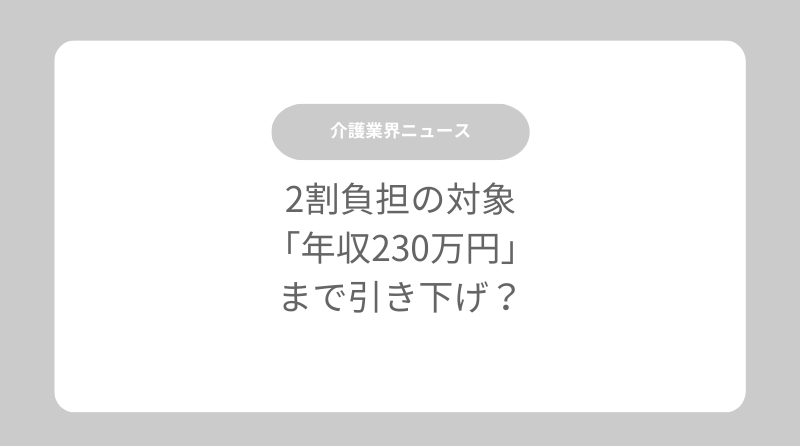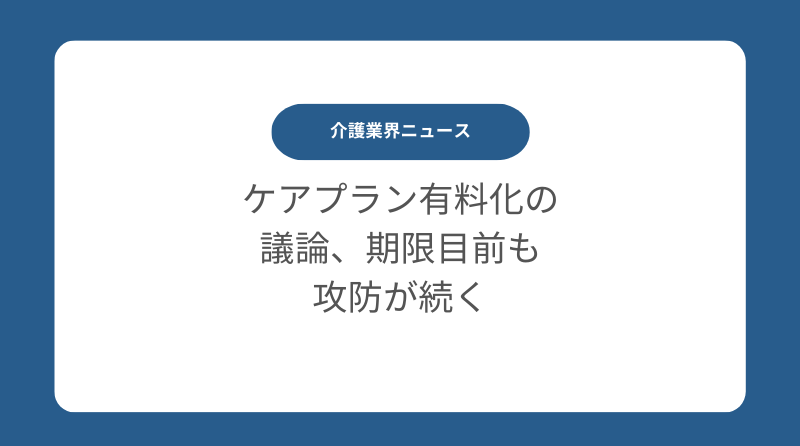厚生労働省は5月26日、第4回となる「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」を開催しました。
本会合ではこれまで、財政審からの提言を踏まえ、福祉用具の「貸与を原則」とするルールの見直しや福祉用具貸与のみを位置付けたケアプランの検討を巡って議論されてきました。今回は、「福祉用具貸与・販売に係る適正化」「安全な利用の促進とサービスの質の向上」に論点が移っています。
福祉用具貸与・販売の適正化・安全利用促進を図るのための2つの論点
2月に立ち上げられた本検討会は、以下の3点を検討する場としての役割を担っています。
<①福祉用具貸与・特定福祉用具販売の現状と課題を踏まえたあり方の検討
②福祉用具貸与・特定福祉用具販売に係る適正化の方策
③福祉用具貸与・販売に関する安全な利用の促進、サービスに質の向上等への対応

【画像】第4回介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会に関する資料(資料2)より
前回までは①について議論されてきましたが、今回はこれまでの意見を踏まえつつ、②③のテーマについて議論が進められました。
厚生労働省は、議論の方向性を以下の通り示しています。
<着目すべき論点(厚労省>
② 福祉用具貸与・特定福祉用具販売に係る適正化の方策
- 貸与時における福祉用具の適切な選定の促進・利用について
- 貸与決定後等における給付内容の検証の充実について
③ 福祉用具貸与・販売に関する安全な利用の促進、サービスの質の向上等への対応
- 福祉用具利用による事故を未然に防ぐ取組の促進、事故情報等の活用について
- サービスの質の向上に資する福祉用具専門相談員等に係る取組について
同一種目「手すり」の複数個支給、貸与数に上限をつける案も
まず、厚労省が示した論点のうち、
②2.「貸与決定後等における給付内容の検証の充実」
についてみていきます。
厚労省は同一種目における複数個支給について、現時点では制限等を設けていません。厚労省が示したデータでは、特に、手すりについて、利用者が活動する部屋や通路等など、複数設置されているケースが多いことなどが着目されています。
こうした現状は、参考として提示された2021年4月貸与分のデータベースによる調査結果からも読み取れます。
検討会では同一種目の支給個数に一定の制限を設ける案について意見が交わされましたが、その賛否は分かれました。


【画像】第4回介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会に関する資料(参考資料1)より
複数個支給の必要性に検討の余地あり
国際医療福祉大・大学院福祉支援工学分野教授の東畠弘子構成員は、「手すり」の支給個数状況に焦点を当て、利用者1人に対し10個以上の貸与を実施している事例を指摘。「上限や使用個数の設定も、ひとつの検討案としてあり得るのでは」と提言しました。
健康保険組合連合会理事の田河構成員は、車いすや歩行器等でも2個以上の複数支給がなされている点に触れ、利用者の状況を勘案したうえで一定の制限を設ける検討案の必要性を指摘しています。
「数」だけに着目したルール設定に懸念の声も
複数個支給の制限に、検討の余地があるとの指摘ががあがる一方で、一部の構成員は、住宅改修の給付を用いての手すり設置が叶わない事例や、複数個支給によって自立度が担保される具体的な事例を紹介しました(一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会理事長の岩元文雄構成員、一般社団法人日本福祉用具供給協会理事長の小野木孝二構成員)。
そのうえで、介護保険制度を用いた住宅改修には多くの手順やローカルルールが存在し、環境改修には一定の時間や事務的な負担が発生すること(岩元構成員)、介護保険における福祉用具の選定基準の創設当時には無かった新製品の活用が利用者の自立支援・重度化防止に寄与している可能性(小野木構成員)などにも触れ、一律で支給個数に上限を設けることについて、慎重な態度を示しました。
事故・ヒヤリハット事例を適切に収集・共有する仕組み化が重要
安全な利用の促進に関する論点についても、活発な意見交換がなされました。
福祉用具利用による事故を未然に防止するため、現状では福祉用具専門相談員等が貸与時に身体の状況等に応じた福祉用具の調整使用方法の指導等を行うとともに、貸与後も福祉用具の使用に関するモニタリングを実施しています。そして、万が一、利用によって事故が生じた場合は、福祉用具貸与事業所等から市町村に報告する流れとなっています。
一方で、現状の仕組みについて、以下の通りの課題も指摘されました。
・福祉用具製造事業者が事故情報やヒヤリハット情報を把握する仕組みが整っていない
・必要な情報が複数のメディアに分散して掲載され、情報収集に非効率
・報告された情報へのフィードバックまで踏まえた仕組みが不十分
このように、事故情報・ヒヤリハット情報を適切に収集し、把握し、共有する仕組みの検討を求める声が目立ちました。
福祉用具専門相談員の研修に追加項目や「更新制」を求める声も
重大事故を未然に防ぐための取組みの一環として、福祉用具専門相談員の研修内容に「リスクマネジメント」に関する項目を追加する案も、複数の構成員から示されました。
テクノエイド協会の五島清国構成員は「事故情報を報告しにくい現状から、むしろ情報を共有し、みんなで重大事故を無くしていく風潮をつくりあげていくことが重要」とし、福祉用具専門相談員やメーカーはもちろん、訪問介護者や家族まで含めてリスクを認識できるような情報発信の取組みの重要性を述べました。
福祉用具専門相談員を対象とした研修に関しては、岩元構成員から下記の提出も提出されています。
岩元構成員は、全国福祉用具専門相談員協会が福祉用具専門相談員に対して実施している研修について紹介するとともに、こうした取り組みを通じて定期的な研修機会の確保や更には更新制の導入についても検討するよう求めました。この要望に対し、目立った反対意見はあがっておらず、今後の論点の一つとなりそうです。
これまでの意見を踏まえ、次回中間的な取りまとめへ
全4回にわたって、福祉用具貸与・特定福祉用具販売に関する制度の見直しを検討してきた本検討会。議論の余地を残す論点もありますが、次回の検討会にて中間的な取りまとめがなされる予定です。