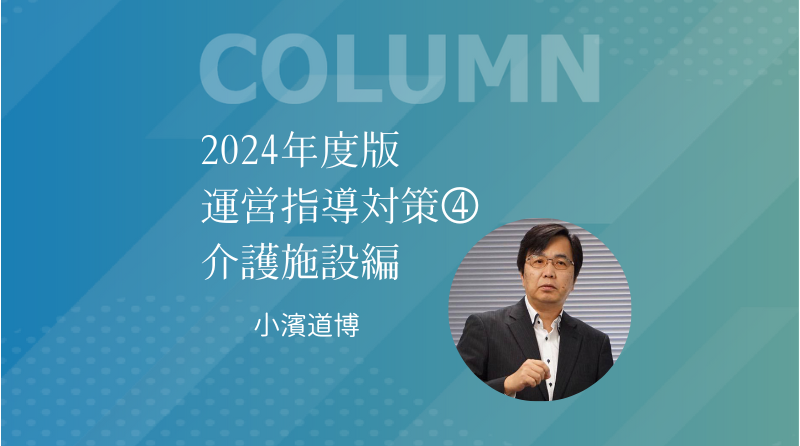既存加算における算定要件の見直しを含めると、変更点が過去最大クラスに多かった2024年度介護報酬改定。
ここまで主に人員基準、設備基準、運営基準に絞って、運営指導のチェックポイントを解説してきた(全サービス共通・概要編、通所介護編、居宅介護支援編)。
最終回の今回は、介護施設について改定の全体像を確認し、特別養護老人ホームと介護老人保健施設の運営基準上の変更点について点検していこう。
1,介護施設における2024年介護報酬改定の全体像
介護施設における24年度介護報酬改定への対応を点検するうえで、着目したいポイントは、生産性向上に向けた取り組みが広範囲に盛り込まれたことだ。まず、居住系サービスや多機能系サービス、短期入所系サービスとともに、3年間の経過措置付きで生産性向上委員会の設置が義務化された。
同時に、ICT化に取り組み、その改善効果に関するデータを提出することを評価する「生産性向上推進体制加算」が創設されている。介護施設では、生産性向上への取り組みが待ったなしの状況だ。
また、このほか介護施設に共通して、
- 介護施設の居住費の基準費用(負担限度)額を1日当たり60円引き上げ(24年8月から実施)
- 新興感染症(コロナに続く新たなウィルスのパンデミック)への準備
- 医療機関との協力体制構築の強化促進
2024年度介護報酬改定の全体像:特別養護老人ホーム
特養の基本報酬は、総じて2.8%程度のプラスだった。
特養単独の変更点として特筆すべきものはなかった。強いて目新しい点を上げるなら、施設職員による透析患者の病院への送迎を評価する「特別通院送迎加算」の創設がある。
月に12回以上の透析患者の送迎が要件だが、往復で1回のカウントなので注意が必要である。
「配置医師緊急時対応加算」では夜間、深夜、早朝に加えて、今回、日中であっても、配置医師が通常の勤務時間外に駆けつけて対応を行った場合の区分が創設された。
2024年度介護報酬改定の全体像:介護老人保健施設
介護老人保健施設は、報酬区分によって明暗が大きく分かれた。
在宅強化型が4.1%のプラスに対して、その他型が0.86%、基本型が1.1%と大きく差が開いた。中間の区分である加算型は、特養並みの改定率である。
老健の基本報酬ランクを決める評価指標のハードルが上がった。入所前後訪問指導割合、退所前後訪問指導割合の指標で基準が引き上げられたほか、支援相談員に社会福祉士の配置が無い場合は、点数が減額される。これによって、上位区分の基本報酬算定がこれまで以上に難しくなった。ギリギリの点数で強化型、超強化型を算定している施設でも、状況によってはランクダウンしたことが想定される。
また、老健では、療養型とその他型において先に挙げた多床室料の自己負担増が25年8月から始まっている。
加算に目を移すと、「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」では、入所者の居宅を訪問し生活環境を把握する要件が追加された。「短期集中リハビリテーション実施加算」では、入所時及び月1回以上ADL等の評価を行うことなどを要件とする上位区分が設けられている。また、「ターミナルケア加算」では、死亡日の前日及び前々日並びに死亡日の対応を高く評価する変更が行われた。
2,2024年度介護報酬改定で施設に対応が義務化された項目とチェックリスト
ここからは24年度改定で介護施設や居住系サービスにおいて義務化された。
(1)利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置
(2)口腔衛生管理の強化
(3)協力医療機関との連携体制の構築について、具体的に対応が必要となる内容を確認しよう。自施設でもぜひ点検してもらいたい。
※BCP減算、高齢者虐待防止減算、感染対策強化の義務化などについては、運営指導対策・サービス共通編の参照のこと。
⑴利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務化
※3年間の経過措置
※生産性向上推進体制加算を算定する場合は、進行期から実施が必要。
【委員会の開催要領】
委員会は、現場職員の意見が適切に反映されるよう、管理者だけでなく、 ケアを行う職員を含む幅広い職種やユニットリーダー等が参画するものとする。委員会では、次のアからエまでの事項について必要な検討を行い、また、委員会は三月に一回以上開催する必要がある。
ア 利用者の安全及びケアの質の確保
a、 見守り機器等から得られる離床の状況、睡眠状態やバイタルサイン等 の情報を基に、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種が連携して、見守り機器等の導入後の利用者等の状態が維持されているか確認すること。
b、 利用者の状態の変化等を踏まえた介護機器の活用方法の変更の必要性 の有無等を確認し、必要な対応を検討すること。
c、 見守り機器を活用する場合、安全面から特に留意すべき利用者につい ては、定時巡回の実施についても検討すること。
d、 介護機器の使用に起因する施設内で発生した介護事故又はヒヤリ・ハット事例の状況を把握し、その原因を分析して再発の防止策を検討すること。
イ 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
実際に勤務する職員に対して、アンケート調査やヒアリング等を行い、 介護機器等の導入後における次のaからcまでの内容をデータ等で確認し、適切な人員配置や処遇の改善の検討等が行われていること。
a ストレスや体調不安等、職員の心身の負担の増加の有無
b 職員の負担が過度に増えている時間帯の有無
c 休憩時間及び時間外勤務等の状況
ウ 介護機器の定期的な点検
次のa及びbの事項を行うこと。
a 日々の業務の中で、あらかじめ時間を定めて介護機器の不具合がないことを確認するなどの不具合のチェックを行う仕組みを設けること。
b 使用する介護機器の開発メーカー等と連携し、定期的に点検を行うこと。
エ 職員に対する研修
介護機器の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知その事例を通じた再発防止策の実習等を含む職員研修を定期的に行うこと。 また、生産性向上推進体制加算(Ⅰ)を算定するに当たっては、上記に加え、職員間の適切な役割分担による業務の効率化等を図るために必要な職員研修等を定期的に実施すること。
⑵介護保険施設サービスにおける口腔衛生管理の強化
すべての介護施設において、24年4月より義務化となったので、今後の運営指導にて確認されるため、注意が必要。
【基準要件】
- 施設の従業者または歯科医師もしくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設入所時および入所後の定期的な口腔の健康状態の評価を実施すること。
- 技術的助言および指導または口腔の健康状態の評価を行う歯科医師もしくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士においては、当該施設との連携について、実施事項等を文書等で取り決めを行うこと。
⑶協力医療機関との連携体制の構築
①協力医療機関を定める場合は、以下の要件を満たす協力医療機関を選定しなければならない。
※経過措置3年
ア 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している
イ 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保している
ウ 入所者等の病状が急変した場合等に、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
すなわち、夜間休日においても、相談や診察、入院が出来る24時間体制の病院を協力病院とすることを求めている。この要件は、創設された協力医療機関連携加算の算定要件である。
②1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等については、事業所の指定を行った自治体に提出しなければならない。
③利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快して退院が可能となった場合は、速やかに再入居させることができるように努めなければならない。
連携する医療機関は、地方厚生局ホームページの一覧のうち「受理番号」の欄に下記の受理番号がある医療機関が該当する医療機関となる。
在宅療養支援病院:(支援病1)、(支援病2)、(支援病3)
在宅療養支援診療所:(支援診1)、(支援診2)、(支援診3)
在宅療養後方支援病院:(在後病)
地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料):(地包ケア1)、(地包ケア2)、(地包ケア3)、(地包ケア4)
※地域包括ケア病棟については、相談対応や診療を行う医療機関として、特に 200床未満(主に地包ケア1及び3)の医療機関が連携の対象として想定される。
※24年度診療報酬改定で新設される「地域包括医療病棟」は、地域の救急患者等を受け入れる病棟であり、高齢者施設等が平時から連携する対象としては想定されない。
(4)ユニットケアでの変更点
ユニットケアの質の向上の観点から、個室ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければならないとされた。
また、ユニット型施設において、職員の主たる所属ユニットを明らかにした上で、必要に応じてユニット間の勤務が可能であることが明確化された。
3,特別養護老人ホーム特有の改定項目
続いて、特養で対応が義務化された項目について確認しよう。
緊急時の対応の義務化
入所者の病状の急変が生じた場合などのために、あらかじめ配置医師および協力医療機関との連携方法、その他の緊急時等における対策を、緊急時対応マニュアルに定めることが義務化された。
マニュアルは、配置医師および協力医療機関との協力を得て、年に一回以上、緊急時の対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時の対応方法を変更することが求められている。
緊急時対応マニュアルに定める規定としては、緊急時の注意事項や病状等についての情報共有の方法、曜日や時間帯ごとの医師および協力医療機関との連携方法や診察を依頼するタイミング等がある。同様に、職員研修での活用も問われる。利用者の急な体調不良などの場合、マニュアルに沿って適切に主治医に連絡して指示を受ける。その過程や主治医の指示の内容、対応状況などをサービス提供記録に記載する。
4,介護老人保健施設特有の項目
見守りセンサー等の導入による夜勤職員の配置の緩和
老健や(介護予防)短期入所療養介護では、全ての入所者に対して見守りセンサーを導入して夜勤職員全員がインカム等のICT を使用している場合に夜勤職員配置を2人以上から1.6人以上に緩和する措置が取られた。これは、前回の改定で特養に適用された内容と同等の措置である。
なお、定員が40人以下で、緊急時の安全体制を確保している場合の配置人数1人に変更はない。
見守りセンサー導入後、3カ月以上試行して、夜勤職員をはじめ実際にケアを行う多職種の職員が参加する委員会を設置して、安全対策やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で、届け出を行う。
※安全体制の確保の具体的な要件
①安全かつ有効活用するための委員会を設置
②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
③緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)
④機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
⑤職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施
⑥夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施
以上、介護施設については24年度介護報酬改定での変更点が多いため、運営基準の改定項目に絞って取り上げた。
24年度介護報酬改定では創設された加算だけでなく、既存加算の算定要件も変更点が多いため、各現場で改めて確認してほしい。